
旅の日記 福島・会津の旅(その②)~サルバドール・ダリと素敵な湯宿
(猪苗代湖から裏磐梯へ)
この旅は、必ずしも事前に綿密なプランを組むということをしなかった。会津若松駅の 観光案内所に日参して、気持ちのいいスタッフと度々、どこへいくか相談する。その結 果、古い町並みを残す「大内宿」行きは取りやめ、猪苗代湖方面へドライブすることに した。壮大な自然の中に身をおいて見たかったからである。
駅近くのマツダレンタカーで1300CCのデミオを借りた。ここの対応も、和やかな気 持ちになる。スカイアクティブは燃費がいいが、乗り心地はふつうのデミオがいい。軽 快に走る、また装着されているカーナ ビがとても使いやすい。いい気持ちで運転する 。30分強で猪苗代湖の長浜というところに到着。大きな湖を眼前にして爽快な気持ち になる。近くの<野口英世記念館>を訪れる。野口博士は、だれでもその名を知ってい るように苦学力行の末世界的に活躍した細菌学者で、とくに黄熱病の研究で有名。その 生家がここ猪苗代湖畔に残されている。 床柱には、19歳の野口が猪苗代を去るときに 刻んだことばが残されている。いささかの感動を覚える。

”志を得ざれば 再びこの地に踏まず”
その向かい側には、磐梯山を背にして<世界のガラス館>がある。クリスタルのアクセサリー、クリスタルのグラスウエアなどが所狭しと並んでいる。しかし、そんなものに は目が向かない。ここに「チーレン」という喫茶コーナーがある。ここはスイスの首都 ベルンから、老舗「チーレン」のチョコレートを直輸入しているのである。珈琲を頼むと、一粒のチョコがついてくる。その生チョコを口にいれると、さわやかな甘みが口中に広がる。神戸にはモロゾフというお店があり、珈琲に一粒のチョコを添えて味わうのが常であるが、それに負けずとも劣らぬ深い味わいである。持って帰りたくなった。
115号線に沿って、北上。左手に磐梯山1819メートル)を見ながら、裏磐梯方面 へ回りこむ。お目当ては五色沼である。五色沼自然探勝路というのがあって、毘沙門沼 、赤沼、弁天沼、青沼、柳沼が点在。それをつなぐ形で全長3.6キロの林間の道が走っている。最大の毘沙門沼では、ボートを借りて久々にオールを握った。しばし、エメラルド・グリーンの水と遊んだ。学生時代に帰ったような気分。

(諸橋近代美術館)少しながくなります。。美術に興味のない方は読み飛み飛ばしていただき、次の湯宿の記事へどうぞ。

すこし道を戻ると<諸橋近代美術館>がある。偶然、わがパートナーが直感で見つけ たのであるが、これが本日の大ヒットとは相成った。磐梯・朝日国立公園内という山間 の地に、こんな素晴らしい美術館が存在していたと は。まず、そのたたずまいに目を疑った。磐梯山(1816メートル)を望み、フロントには清冽な渓流が流れる。そこに展開するのは、かつて存在したパリのチュイルリー宮もさぞかしと思われる壮麗な建物である。聞くところによりと、この建物の設計は、郡山に居をおく清水公夫設計研究所と諸橋氏(悌造、スポーツ用品ゼビオの創始者)の共同の作品とか。中に入ると、広く、明るく天井は9メートルと高く、ゆったりして落ち着いて美術品を観賞できる。メインの所蔵品は、スペインのかのシュルレアリズムの権化、サルバドール・ダリの作品である。

この美術館を創ったた経緯を諸橋氏は次のように語っている。
”昭和51年、スペインのフィゲラスにあるダリ美術館で、サルバドール・ダリの作品に 出会いました。絵画鑑賞が趣味の私でしたが、ダリの作品を一堂に数百点規模で目前にしたのは初めてでした。
その作品は印象派等のリアリズムではなく、夢と幻覚を絵画にした、従来の常識を打ち破るものでした。以来ダリ・シュルレアリスムに興味を抱き、版画・画集等の収集をして おりました。
そして平成3年、NHK主催のダリ展が東京で催されました。その中にパリ・ストラットン財団所有の彫刻37点が出品されました。それは油絵・版画より迫力と夢があり感動でした。
その彫刻を展示終了後、ある事情から一括して譲り受けることが出来たのです。まさに 偶然の出会いでした。その瞬間ダリ美術館建設の夢が、私の頭の中に忽然と現れたのです。以来、作品収集、土地、建物の3つの具体的課題 を負うことになります。この10年、世界2大オークションの「サザビーズ」「クリスティーズ」への10数回の参加、欧米 の美術館視察、土地探し、建設の構想・・・・・と瞬間の10年でした。夢を追い、夢を実現 する労は時間を 忘 れさせました。思い込み、念じ続けると重大な課題が次々と解決していくのです。多くの協力して下さる方々とめぐり会い、そこから貴重な教えを得ることが出来ました。
ロンドン、ニューヨークのオークションでは、ダリ生涯の大作「テトゥアンの戦い」( タテ3メートル、ヨコ4メートル)、ユトリロの白の時代の名作「モンマルトルのサン・ヴァンサン通り」、セザンヌ30歳の力作「林間の 空地」を落札した時は会場から大きな拍手をいただいたのが感動の想い出でもあります。(写真は、「テトゥワンの戦い」)

当館の作品構成はダリがメインですが、ダリ以外にもルノワール、マチス、ピカソ、シャガール等19・20世紀巨匠20数人の作品を収蔵しております。これから10年、20年かけ て、1点1点良い作品を集め、諸橋近代美術館の充実
を図ることが責務であります。うるおいのある県の文化に貢献出来ればと念じております。”
諸橋氏の想いが伝わってきて、深い感銘を覚える。
(所蔵の作品)

よく知られているダリの”柔らかな時計”、それから諸橋氏のことばに出てくる「テトゥアンの戦い」などの彫刻や絵画をみることができ、一つ一つの作品の前で、ゆっくり立ち止まって観賞した。そして圧巻は、長編叙事詩「ダンテの神曲」(La Divina Comm edia)のリトグラフ。
イタリアが輩出した詩人ダンテ・アリギエーリ(1265-1321)の代表作であり、イタリア文学最高峰の古典作品として世界的に名高い「神曲」。地獄篇34 歌、煉獄篇33 歌、天国篇33 歌の計100 歌で構成されている。ダンテ自身が古代ローマの詩人ウェルギリウスの導きにより地獄、煉獄、そして天上界を巡るという内容で、カトリック的道徳観を吟じた文芸復興の先駆的作品であると共に、彼自身の半生をなぞらえた壮大な物語でもある。その根底にはダンテの永遠の淑女ベアトリーチェへの愛が存在している。
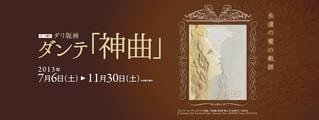
そのリトグラフ100点が、学芸員の方の詳しい解説とともに展示されていた。一枚、一枚ゆっくりとみる。初めて触れた「神曲」には感動を覚えた。
すこし脱線する。「神曲」なんてむずかしい、と思われているが、実はイタリアなどでは子供でも読むらしい。丸谷才一の『おっとりと論じよう』にそのエピソードが紹介さ れている。
(イタリアの読書運動)
(井上ひさし))それと子どもたちにはもっと本を読んで欲しいと思いますね。なにかそのための工夫をしないと。
また外国の例になりますけど。イギリスとイタリアでたまたま同じ読書運動をやって いましてね。たとえば、子供が、今度の春休みにダンテの『神曲』を読みます、と隣 近所のおじさん、おばさんに宣言するんです。じ ゃ、本当に読んだら百円あげるとか約束するわけですね。ここからが面白いんですが、休みが終わってその子が読んだかどうかを図書館の司書の人たち5人で面接するんです。その時面白い質問をするんですが、ともかく確かに読 んだと判断したら、証明書をくれるんです。子どもはその『神曲』を読んだという証明書を持って近所を回り、約束していたお金をもらう。そうして集めてお金の一割がその子のものになり、残りの9割は同じ年頃の病気の子ども たちの医療費に回るんです。
もう一つ脱線を。ダンテは、ベアトリーチェに導かれ、空へ上ってゆく。至高の天では、純白のバラを見て、この世を動かすものは神の愛であることを知る。いろんな翻訳が出ているが比較文学の泰斗である平川祐弘翻訳がいい(河出文庫)。なお日本では森鴎外の「即興詩人」(アンデルセン)でこの「神曲」が出てくる。
なおダリのコレクション以外にも、西洋近代絵画たとえばセザンヌ/ルノアール/ゴッホ/ヴイヤール/ブラマンク/シャガール/マリー・ローランサン(写真)などもあり、シュールに疲れた方は、こちらの展示室で目を休めることが
できる。

すっかり道がそれてしまったが、ダリの本物に触れ、この目で確かめることができ感動以外の何ものでなかった。鑑賞に疲れたら、入り口にある素敵なカフェで一服することをおすすめする。まさに至福の午後であった。
帰路はラーメンで有名な喜多方をまわり、「蔵(くら)」で珈琲を味わった。
(いろりの宿 芦名)
市内のレンタカー・オフィスに戻ると、素敵なクラシック・カー(トヨタ製)が出迎えてくれた。町から30分ほどで東山温泉に到着。

「芦名」は湯川沿いに立つ、わずか7室の小体な宿である。伝統的な木造建築の良さを残し、そのたたずまいに心が和む。
入り口をはいると帳場にでんと座っている大女将や若女将、スタッフが出迎えてくれる 。能登半島にある有名な某大旅館のように大勢の仲居さんがズラリと並び、荷物を奪うように持ってゆくのとは違う。べたべたしたところ がなく、いささか放りっぱなしというようなところがないでもない。しかし、目配りが行き届いて暖かさをも感じる。スリッパがないものきもちいい。畳敷きの館内を歩き、三階に上がってゆく。若女将には少々重い荷物を持ってもらい恐縮するが、スポーツレディのようだから、お許し乞う。部屋は「白樺」次の間つきの8畳である。夜も明るくて気持ちがいい。よく大ホテルだ照明が暗く旅の地図や案内書もろくに読めないところも多いが、ここはそんなこともない。部屋でのんびり読書も楽しめる。
こじんまりした湯は、いつもきちんと整理され、気配りを感じる。さらりとした湯である。湯あたりは、やわらかい。そして24時間、いつでも入れるところがいい。
さて夕食は、宿の入り口の奥にある蔵の中に切ってある囲炉裏のスペースでいただく。囲炉裏を囲んでのの食事。その夜の献立てを記しておこう。


先付け:自家農園のいんげん豆、会津産枝豆「湯上がり娘」(もずく酢)
造り:特上ロース桜刺し(特製辛子味噌だれ)
(いろり炭火焼)
厚揚げの味噌田楽
奥会津博士山渓流の手釣りイワナ・・・新鮮そのもので、ことのほか旨かった! 頭からバリバリ頂いた。
会津地鶏のつくね・地鶏卵黄をたっぷり絡めて
おなじく炭火焼き・会津山塩・・・・・炭火でじっくり、ていねいに焼いた地鶏ジューシーで美味極まりなし。
煮物:冬瓜と南瓜のあんかけ
造り:鯉の洗いを酢味噌で
食事:会津強清水産そば粉 十割蕎麦
デザート:雪ぶどう(スチューベン)

この地元の食材への信頼感があふれ、それにこだわるる姿勢がいい。飛び切りの素材 がていねいに調理されている。どれも美味しい。今回は見逃したが、会津牛の石焼もあ る。炭火焼きは、食事の進み方もみつつじっくり焼き 上げる。構わずどんどん料理を出 す大旅館とは全く違うのだ。そして酒は辛口の「風が吹く」 さわやかな風が吹き抜ける感じでどんどんすすんでしまう。隣り合わせて若い人たちは、これに加え「国権」 (秋あがり)も い いとご機嫌の様子。なおデザートに出たスチューベンは、関西ではめったに手に入らない。ジューシーで上品な甘さに舌鼓を打った。これを選んだ大女将の選球眼に感服した。
少しアルコールが醒めたところで、再び湯に浸かった。そして渓谷湯川の瀬音を聞きながら熟睡。
次の朝も湯につかる。いつの間にか風呂はきちんと整えられていて、気持ちがいい。 見えないところでの裏方さんの仕事に感謝する。朝食も、満足すべきもの。特A級の会津こしひかりで炊いたご飯は、つやつやと際立つ。炭 火で焼いた鮭、あさりの味噌汁、あつあつの卵焼き、農家に特別に頼んでいる納豆。タレが何かわからぬが、あまりの旨さに納豆好きのわがパートナーは感激。持って帰りたいと言い出す。冷やの「会津娘」が欲しいところ だ。
池波正太郎の書いた本の題名そのままに、”よい匂いする一夜”を過ごすことができ、会津若松の旅のいい思い出になった。気持ちのいい好青年H君がハンドルを握るレトロカーで会津若松の駅まで送ってくれ た。また来年の新緑の頃に、再訪することになるのではないか。
(余滴)わたしの日本旅館考
これまで日本各地を巡って旅をしてきた。いい宿に恵まれたこともあれば、大枚はたいて泊まっても裏切られた思いのすることも少なからずあった。それらの体験から、どんな宿が望ましいか、少し頭の中を整理してみた。旅の案 内人として、またグルメ通でもある山本益博氏の本『味な宿に泊まりたい』や京都のドクター柏井壽氏の『「極み」の日本旅館』などの名著がある。が、ここでは自ら旅をした体験から述べることにした。
私が旅の宿を選ぶ時の条件は次のようなものである。
①まず小規模な宿であること。もちろんコスパは重要。バカ高いところは失礼する。いいところに巡りあったことが余りない。(もちろんそうでないところもあるが)
②オーナーあるいは女将の顔が見えること。宿を案内するウエブサイトも馬鹿にならな い。”顔”が出ているところは、まず安心感を覚える。顔写真でなくても、なにか直接 語りかけていることが重要。ウエブデザイナーに丸 投げでは行けない。基本コンセプト は主人がまず考えて欲しい。余談になるが、最近知り合ったあるファンドマネージャー のFさんは、スタッフを動員して面白い企業分析をした。それは東京証券取引所に上場 している43 0社を調べあげるもので、成長企業・よい会社を見分ける判断基準として 会社のホームページで社長や役員の写真があるところ、ないところ、また「私」とか「 私たち」という主語の有無を調べあげた。そうすると面白いこと が分かった。リーマン ショック後も、またここ10年間というレンジでみても、写真あり主語ありが、ダント ツに株価が上昇しているのである。社長や役員の写真がなく、主語もないところは株価 指数が100以下に沈んで いるのである。このことは、株式投資でいい会社、だめな会社を見分けるにとどまらず、日本旅館の判断基準としても参考になるのである。
③次に朝食がうまいこと。これが意外にに出来ていないところが多い。”好きな作家、橋治の小説に『春朧』というのがある。長良川沿いにある老舗旅館に嫁いできた女性 (日野紗衣子)が、修善寺で知り合った彫刻家の剣 達之助が宿にたずねてきて、”日本 旅館の朝は空しいからね”と厳しい指摘を受ける。そして剣にすすめられて、山中温泉の故山亭を訪ねる。ここは、120室あった鉄筋のビルから、わずか10室の宿に立て替えたと聞か され、衝撃をうける。 注)これは間違いなく、山中温泉の<かよう亭>のことである。
④そしてホスピタリティ。マニュアルのごとき作られた笑顔でなく、自然ににじみ出てくるような笑顔と気遣い。なかなかないものである。
そういった目でみて、私自身が訪れて良かったA級の宿をいくつか挙げてみる。
・九州日田のホテル風早
・郡上八幡の中嶋屋・・・・宿のある町が楽しい
・北海道のマッカリーナ(オーベルジュ)
・飛騨高山のフォーシーズン(ビジネスホテル風だが、旅の宿としても好ましい)
・有馬温泉・御所坊・・・オーナーが温泉街全体の活性化に熱心だ。
・長野県・下諏訪のみなとや
今度お世話になった<芦名>は、Aランクの上の方に位置づけられるのではないか。
このブログ記事をお読みいただいた方のご意見も伺えれば幸いである。
まことに長文となりました。お付き合いいただき、ありがとうございました。
(余滴その2) 素晴らしい宿に、京都花瀬の<美山荘>、山中温泉の<かよう亭>そしてもちろん
京都の<俵屋>、それに九州は天草の<五足のくつ>などがあるが、高すぎるので、ここでは考察対象からは外した。
(猪苗代湖から裏磐梯へ)
この旅は、必ずしも事前に綿密なプランを組むということをしなかった。会津若松駅の 観光案内所に日参して、気持ちのいいスタッフと度々、どこへいくか相談する。その結 果、古い町並みを残す「大内宿」行きは取りやめ、猪苗代湖方面へドライブすることに した。壮大な自然の中に身をおいて見たかったからである。
駅近くのマツダレンタカーで1300CCのデミオを借りた。ここの対応も、和やかな気 持ちになる。スカイアクティブは燃費がいいが、乗り心地はふつうのデミオがいい。軽 快に走る、また装着されているカーナ ビがとても使いやすい。いい気持ちで運転する 。30分強で猪苗代湖の長浜というところに到着。大きな湖を眼前にして爽快な気持ち になる。近くの<野口英世記念館>を訪れる。野口博士は、だれでもその名を知ってい るように苦学力行の末世界的に活躍した細菌学者で、とくに黄熱病の研究で有名。その 生家がここ猪苗代湖畔に残されている。 床柱には、19歳の野口が猪苗代を去るときに 刻んだことばが残されている。いささかの感動を覚える。

”志を得ざれば 再びこの地に踏まず”
その向かい側には、磐梯山を背にして<世界のガラス館>がある。クリスタルのアクセサリー、クリスタルのグラスウエアなどが所狭しと並んでいる。しかし、そんなものに は目が向かない。ここに「チーレン」という喫茶コーナーがある。ここはスイスの首都 ベルンから、老舗「チーレン」のチョコレートを直輸入しているのである。珈琲を頼むと、一粒のチョコがついてくる。その生チョコを口にいれると、さわやかな甘みが口中に広がる。神戸にはモロゾフというお店があり、珈琲に一粒のチョコを添えて味わうのが常であるが、それに負けずとも劣らぬ深い味わいである。持って帰りたくなった。
115号線に沿って、北上。左手に磐梯山1819メートル)を見ながら、裏磐梯方面 へ回りこむ。お目当ては五色沼である。五色沼自然探勝路というのがあって、毘沙門沼 、赤沼、弁天沼、青沼、柳沼が点在。それをつなぐ形で全長3.6キロの林間の道が走っている。最大の毘沙門沼では、ボートを借りて久々にオールを握った。しばし、エメラルド・グリーンの水と遊んだ。学生時代に帰ったような気分。

(諸橋近代美術館)少しながくなります。。美術に興味のない方は読み飛み飛ばしていただき、次の湯宿の記事へどうぞ。

すこし道を戻ると<諸橋近代美術館>がある。偶然、わがパートナーが直感で見つけ たのであるが、これが本日の大ヒットとは相成った。磐梯・朝日国立公園内という山間 の地に、こんな素晴らしい美術館が存在していたと は。まず、そのたたずまいに目を疑った。磐梯山(1816メートル)を望み、フロントには清冽な渓流が流れる。そこに展開するのは、かつて存在したパリのチュイルリー宮もさぞかしと思われる壮麗な建物である。聞くところによりと、この建物の設計は、郡山に居をおく清水公夫設計研究所と諸橋氏(悌造、スポーツ用品ゼビオの創始者)の共同の作品とか。中に入ると、広く、明るく天井は9メートルと高く、ゆったりして落ち着いて美術品を観賞できる。メインの所蔵品は、スペインのかのシュルレアリズムの権化、サルバドール・ダリの作品である。

この美術館を創ったた経緯を諸橋氏は次のように語っている。
”昭和51年、スペインのフィゲラスにあるダリ美術館で、サルバドール・ダリの作品に 出会いました。絵画鑑賞が趣味の私でしたが、ダリの作品を一堂に数百点規模で目前にしたのは初めてでした。
その作品は印象派等のリアリズムではなく、夢と幻覚を絵画にした、従来の常識を打ち破るものでした。以来ダリ・シュルレアリスムに興味を抱き、版画・画集等の収集をして おりました。
そして平成3年、NHK主催のダリ展が東京で催されました。その中にパリ・ストラットン財団所有の彫刻37点が出品されました。それは油絵・版画より迫力と夢があり感動でした。
その彫刻を展示終了後、ある事情から一括して譲り受けることが出来たのです。まさに 偶然の出会いでした。その瞬間ダリ美術館建設の夢が、私の頭の中に忽然と現れたのです。以来、作品収集、土地、建物の3つの具体的課題 を負うことになります。この10年、世界2大オークションの「サザビーズ」「クリスティーズ」への10数回の参加、欧米 の美術館視察、土地探し、建設の構想・・・・・と瞬間の10年でした。夢を追い、夢を実現 する労は時間を 忘 れさせました。思い込み、念じ続けると重大な課題が次々と解決していくのです。多くの協力して下さる方々とめぐり会い、そこから貴重な教えを得ることが出来ました。
ロンドン、ニューヨークのオークションでは、ダリ生涯の大作「テトゥアンの戦い」( タテ3メートル、ヨコ4メートル)、ユトリロの白の時代の名作「モンマルトルのサン・ヴァンサン通り」、セザンヌ30歳の力作「林間の 空地」を落札した時は会場から大きな拍手をいただいたのが感動の想い出でもあります。(写真は、「テトゥワンの戦い」)

当館の作品構成はダリがメインですが、ダリ以外にもルノワール、マチス、ピカソ、シャガール等19・20世紀巨匠20数人の作品を収蔵しております。これから10年、20年かけ て、1点1点良い作品を集め、諸橋近代美術館の充実
を図ることが責務であります。うるおいのある県の文化に貢献出来ればと念じております。”
諸橋氏の想いが伝わってきて、深い感銘を覚える。
(所蔵の作品)

よく知られているダリの”柔らかな時計”、それから諸橋氏のことばに出てくる「テトゥアンの戦い」などの彫刻や絵画をみることができ、一つ一つの作品の前で、ゆっくり立ち止まって観賞した。そして圧巻は、長編叙事詩「ダンテの神曲」(La Divina Comm edia)のリトグラフ。
イタリアが輩出した詩人ダンテ・アリギエーリ(1265-1321)の代表作であり、イタリア文学最高峰の古典作品として世界的に名高い「神曲」。地獄篇34 歌、煉獄篇33 歌、天国篇33 歌の計100 歌で構成されている。ダンテ自身が古代ローマの詩人ウェルギリウスの導きにより地獄、煉獄、そして天上界を巡るという内容で、カトリック的道徳観を吟じた文芸復興の先駆的作品であると共に、彼自身の半生をなぞらえた壮大な物語でもある。その根底にはダンテの永遠の淑女ベアトリーチェへの愛が存在している。
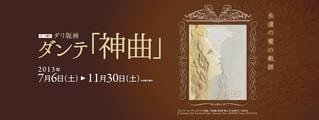
そのリトグラフ100点が、学芸員の方の詳しい解説とともに展示されていた。一枚、一枚ゆっくりとみる。初めて触れた「神曲」には感動を覚えた。
すこし脱線する。「神曲」なんてむずかしい、と思われているが、実はイタリアなどでは子供でも読むらしい。丸谷才一の『おっとりと論じよう』にそのエピソードが紹介さ れている。
(イタリアの読書運動)
(井上ひさし))それと子どもたちにはもっと本を読んで欲しいと思いますね。なにかそのための工夫をしないと。
また外国の例になりますけど。イギリスとイタリアでたまたま同じ読書運動をやって いましてね。たとえば、子供が、今度の春休みにダンテの『神曲』を読みます、と隣 近所のおじさん、おばさんに宣言するんです。じ ゃ、本当に読んだら百円あげるとか約束するわけですね。ここからが面白いんですが、休みが終わってその子が読んだかどうかを図書館の司書の人たち5人で面接するんです。その時面白い質問をするんですが、ともかく確かに読 んだと判断したら、証明書をくれるんです。子どもはその『神曲』を読んだという証明書を持って近所を回り、約束していたお金をもらう。そうして集めてお金の一割がその子のものになり、残りの9割は同じ年頃の病気の子ども たちの医療費に回るんです。
もう一つ脱線を。ダンテは、ベアトリーチェに導かれ、空へ上ってゆく。至高の天では、純白のバラを見て、この世を動かすものは神の愛であることを知る。いろんな翻訳が出ているが比較文学の泰斗である平川祐弘翻訳がいい(河出文庫)。なお日本では森鴎外の「即興詩人」(アンデルセン)でこの「神曲」が出てくる。
なおダリのコレクション以外にも、西洋近代絵画たとえばセザンヌ/ルノアール/ゴッホ/ヴイヤール/ブラマンク/シャガール/マリー・ローランサン(写真)などもあり、シュールに疲れた方は、こちらの展示室で目を休めることが
できる。

すっかり道がそれてしまったが、ダリの本物に触れ、この目で確かめることができ感動以外の何ものでなかった。鑑賞に疲れたら、入り口にある素敵なカフェで一服することをおすすめする。まさに至福の午後であった。
帰路はラーメンで有名な喜多方をまわり、「蔵(くら)」で珈琲を味わった。
(いろりの宿 芦名)
市内のレンタカー・オフィスに戻ると、素敵なクラシック・カー(トヨタ製)が出迎えてくれた。町から30分ほどで東山温泉に到着。

「芦名」は湯川沿いに立つ、わずか7室の小体な宿である。伝統的な木造建築の良さを残し、そのたたずまいに心が和む。
入り口をはいると帳場にでんと座っている大女将や若女将、スタッフが出迎えてくれる 。能登半島にある有名な某大旅館のように大勢の仲居さんがズラリと並び、荷物を奪うように持ってゆくのとは違う。べたべたしたところ がなく、いささか放りっぱなしというようなところがないでもない。しかし、目配りが行き届いて暖かさをも感じる。スリッパがないものきもちいい。畳敷きの館内を歩き、三階に上がってゆく。若女将には少々重い荷物を持ってもらい恐縮するが、スポーツレディのようだから、お許し乞う。部屋は「白樺」次の間つきの8畳である。夜も明るくて気持ちがいい。よく大ホテルだ照明が暗く旅の地図や案内書もろくに読めないところも多いが、ここはそんなこともない。部屋でのんびり読書も楽しめる。
こじんまりした湯は、いつもきちんと整理され、気配りを感じる。さらりとした湯である。湯あたりは、やわらかい。そして24時間、いつでも入れるところがいい。
さて夕食は、宿の入り口の奥にある蔵の中に切ってある囲炉裏のスペースでいただく。囲炉裏を囲んでのの食事。その夜の献立てを記しておこう。


先付け:自家農園のいんげん豆、会津産枝豆「湯上がり娘」(もずく酢)
造り:特上ロース桜刺し(特製辛子味噌だれ)
(いろり炭火焼)
厚揚げの味噌田楽
奥会津博士山渓流の手釣りイワナ・・・新鮮そのもので、ことのほか旨かった! 頭からバリバリ頂いた。
会津地鶏のつくね・地鶏卵黄をたっぷり絡めて
おなじく炭火焼き・会津山塩・・・・・炭火でじっくり、ていねいに焼いた地鶏ジューシーで美味極まりなし。
煮物:冬瓜と南瓜のあんかけ
造り:鯉の洗いを酢味噌で
食事:会津強清水産そば粉 十割蕎麦
デザート:雪ぶどう(スチューベン)

この地元の食材への信頼感があふれ、それにこだわるる姿勢がいい。飛び切りの素材 がていねいに調理されている。どれも美味しい。今回は見逃したが、会津牛の石焼もあ る。炭火焼きは、食事の進み方もみつつじっくり焼き 上げる。構わずどんどん料理を出 す大旅館とは全く違うのだ。そして酒は辛口の「風が吹く」 さわやかな風が吹き抜ける感じでどんどんすすんでしまう。隣り合わせて若い人たちは、これに加え「国権」 (秋あがり)も い いとご機嫌の様子。なおデザートに出たスチューベンは、関西ではめったに手に入らない。ジューシーで上品な甘さに舌鼓を打った。これを選んだ大女将の選球眼に感服した。
少しアルコールが醒めたところで、再び湯に浸かった。そして渓谷湯川の瀬音を聞きながら熟睡。
次の朝も湯につかる。いつの間にか風呂はきちんと整えられていて、気持ちがいい。 見えないところでの裏方さんの仕事に感謝する。朝食も、満足すべきもの。特A級の会津こしひかりで炊いたご飯は、つやつやと際立つ。炭 火で焼いた鮭、あさりの味噌汁、あつあつの卵焼き、農家に特別に頼んでいる納豆。タレが何かわからぬが、あまりの旨さに納豆好きのわがパートナーは感激。持って帰りたいと言い出す。冷やの「会津娘」が欲しいところ だ。
池波正太郎の書いた本の題名そのままに、”よい匂いする一夜”を過ごすことができ、会津若松の旅のいい思い出になった。気持ちのいい好青年H君がハンドルを握るレトロカーで会津若松の駅まで送ってくれ た。また来年の新緑の頃に、再訪することになるのではないか。
(余滴)わたしの日本旅館考
これまで日本各地を巡って旅をしてきた。いい宿に恵まれたこともあれば、大枚はたいて泊まっても裏切られた思いのすることも少なからずあった。それらの体験から、どんな宿が望ましいか、少し頭の中を整理してみた。旅の案 内人として、またグルメ通でもある山本益博氏の本『味な宿に泊まりたい』や京都のドクター柏井壽氏の『「極み」の日本旅館』などの名著がある。が、ここでは自ら旅をした体験から述べることにした。
私が旅の宿を選ぶ時の条件は次のようなものである。
①まず小規模な宿であること。もちろんコスパは重要。バカ高いところは失礼する。いいところに巡りあったことが余りない。(もちろんそうでないところもあるが)
②オーナーあるいは女将の顔が見えること。宿を案内するウエブサイトも馬鹿にならな い。”顔”が出ているところは、まず安心感を覚える。顔写真でなくても、なにか直接 語りかけていることが重要。ウエブデザイナーに丸 投げでは行けない。基本コンセプト は主人がまず考えて欲しい。余談になるが、最近知り合ったあるファンドマネージャー のFさんは、スタッフを動員して面白い企業分析をした。それは東京証券取引所に上場 している43 0社を調べあげるもので、成長企業・よい会社を見分ける判断基準として 会社のホームページで社長や役員の写真があるところ、ないところ、また「私」とか「 私たち」という主語の有無を調べあげた。そうすると面白いこと が分かった。リーマン ショック後も、またここ10年間というレンジでみても、写真あり主語ありが、ダント ツに株価が上昇しているのである。社長や役員の写真がなく、主語もないところは株価 指数が100以下に沈んで いるのである。このことは、株式投資でいい会社、だめな会社を見分けるにとどまらず、日本旅館の判断基準としても参考になるのである。
③次に朝食がうまいこと。これが意外にに出来ていないところが多い。”好きな作家、橋治の小説に『春朧』というのがある。長良川沿いにある老舗旅館に嫁いできた女性 (日野紗衣子)が、修善寺で知り合った彫刻家の剣 達之助が宿にたずねてきて、”日本 旅館の朝は空しいからね”と厳しい指摘を受ける。そして剣にすすめられて、山中温泉の故山亭を訪ねる。ここは、120室あった鉄筋のビルから、わずか10室の宿に立て替えたと聞か され、衝撃をうける。 注)これは間違いなく、山中温泉の<かよう亭>のことである。
④そしてホスピタリティ。マニュアルのごとき作られた笑顔でなく、自然ににじみ出てくるような笑顔と気遣い。なかなかないものである。
そういった目でみて、私自身が訪れて良かったA級の宿をいくつか挙げてみる。
・九州日田のホテル風早
・郡上八幡の中嶋屋・・・・宿のある町が楽しい
・北海道のマッカリーナ(オーベルジュ)
・飛騨高山のフォーシーズン(ビジネスホテル風だが、旅の宿としても好ましい)
・有馬温泉・御所坊・・・オーナーが温泉街全体の活性化に熱心だ。
・長野県・下諏訪のみなとや
今度お世話になった<芦名>は、Aランクの上の方に位置づけられるのではないか。
このブログ記事をお読みいただいた方のご意見も伺えれば幸いである。
まことに長文となりました。お付き合いいただき、ありがとうございました。
(余滴その2) 素晴らしい宿に、京都花瀬の<美山荘>、山中温泉の<かよう亭>そしてもちろん
京都の<俵屋>、それに九州は天草の<五足のくつ>などがあるが、高すぎるので、ここでは考察対象からは外した。

























お立ち寄りいただき、その上長文にお目通しいただきありがとうございます。写真がいいのは、カメラがいいからです(笑) 日本もいろいろ回ってみるといいところがありますね。さらに北上してみようと思っています。
会津は本当に山の中ですね。裏磐梯もいいし、猪苗代湖と磐梯山を望むのもいいですね。ゆらぎさんは更に素晴らしい宿と食が付加されています。人生何が大事か、あまり大上段に構えなくとも目の前のやりたいことをやることかもしれません。磐梯山は全部見えましたか。小生再三トライしましたが、いつも雲がかかっていてまだ見ておりません。
長文お目通しいただきありがとうございました。今回は天候に恵まれ、磐梯山は、表からも裏からも、その全容を見せてくれました。もう一度是非お出かけください。
スペイン旅行(平成22年4月)ダリ編
バルセロナ(Barcelona)からバスで約2時間半、北側のフランス国境近くのフィゲレス(Figures)、ダリの生誕地であり晩年を過ごした場所にあるダリ美術館を訪れる。
1935年~1975年のフランコ独裁政権崩壊後、カタールニア自治権を回復したこの地方はスペイン語とカタルーニア語のバイリンガルであって、後者が現在公用語になっているが若者中心にこの言葉は普及していない。
ダリは1904年5月11日、スペインのカタルーニャ地方フィゲラスで、裕福な公証人の息子として生まれた。母親も富裕な商家出身だった。ダリには幼くして死んだ兄がいて、同じ「サルバドール」という名が付けられた。このことは少年ダリに大きな心理的影響を与えた。少年時代から絵画に興味を持ち、画家ラモン・ピショット(ピカソの友人でもあった)から才能を認められた。1921年、マドリードのサンフェルナンド美術学校に入学し、フェデリコ・ガルシーア・ロルカ(詩人)、ルイス・ブニュエル(映画監督)と知り合った。ブニュエルとは、1928年にシュルレアリスムの代表的映画『アンダルシアの犬』を共同で制作した。1925年、マドリードのダルマウ画廊で最初の個展を開く。1927年、パリに赴き、パブロ・ピカソ、トリスタン・ツァラ、ポール・エリュアール、ルイ・アラゴン、アンドレ・ブルトンらの面識を得る。1929年夏、詩人ポール・エリュアールが家族とともにカダケスのダリを訪ねる。その妻が、後にダリ夫人となるガラ・エリュアールであった。ダリとガラは強く惹かれ合い、1932年に結婚した。
画学生時代には印象派やキュビスムの影響を受けていたダリは、シュルレアリスムに自分の進む道を見出し、1929年に正式にシュルレアリスト・グループに参加した。ダリは1938年にグループから除名されているが、その理由は彼の「ファシスト的思想」が、アンドレ・ブルトンの逆鱗に触れたからとされる。しかし彼の人気は非常に高かったため、そのあとも国際シュールレアリスム展などには必ず招待された。ダリは自分の制作方法を「偏執狂的批判的方法 (Paranoiac Critic)」と称し、写実的描法を用いながら、多重イメージなどを駆使して夢のような超現実的世界を描いた。第二次世界大戦後はカトリックに帰依し、ガラを聖母に見立てた宗教画を連作した。ガラはダリのミューズであり、支配者であり、またマネージャーでもあった。第二次世界大戦中は戦禍を避けてアメリカ合衆国に住んだが、1948年にスペインに帰国。ポルト・リガトに居を定めて制作活動を行った。1982年にガラが死去すると、「自分の人生の舵を失った」と激しく落胆し、ジローナのプボル城に引きこもった。最後に絵を描いたのは1983年5月である。1989年にフィゲラスのダリ劇場美術館に隣接するガラテアの塔で、心不全により85歳の生涯を閉じた。
この美術館はに入ると先ず驚くのは、アメリカ在住の際に買った大きな車の中に、ガラの蝋人形が傘をさして車の中にいる、外のあるボタンを押すと車の中で雨が降る、車の屋根の上には巨大且つ奇怪な女神が立っている。想像もつかないアートである。ダリには四つの顔がある、名人芸を持つ宝飾作家であること、小品であるが普通の写実的な美しい絵を描く画家であること、シューレアリズム的画家であること、奇怪な騙し絵や細工物を部屋の中で展示するアーティストであること。シューレアリスティックな絵を現物で見ると、写真では先ず見えない小さな細工を宝石で埋め込んでいたりする。まずは普通の人ではない事だけは確かである。ともかく、あっけにとたれて美術館を後にした。
長文にお目通しいただき恐縮です。ありがとうございました。この美術館は本当に素晴らしい。ロケーション、建築そのもの、コレクションも。ダリの絵の意味するところが少しわかった気がします。紀行文、拝読。絵や陳列物を見られた印象を写真と共に公開していただけるといいですね。もったいない。ブログは今更でしょうから、フェイスブックをやりましょう。とても簡単です。