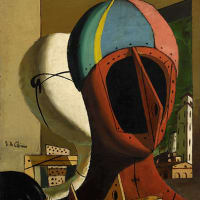(1)昔、1人の司祭が家政婦と住んでいた。飼われていた3羽の雄鶏が毎夜、真夜中と、明け方の3時と、6時に時を告げた。最初の雄鶏が歌った。「ここで起こっていることは・・・・・・」すると2番目の雄鶏が歌った。「とても辛抱できそうにない。」すると3番目の雄鶏が最後に歌った。「司祭は家政婦と寝ているよ。」
(2)司祭は怒った。そして司祭と家政婦は、そんな唄を歌っているのだと信じていた1羽の雄鶏を殺し、熱湯につけ食べてしまった。そしてもう誰も自分たちのしていることは知らないだろうと思った。
(3)ところがその真夜中と、明け方の3時と、6時に、雄鶏たちはまた歌った。最初の雄鶏が歌った。「ここで起こっていることは・・・・・・」すると2番目の雄鶏が歌った。「とても辛抱できそうにない。」その後、最初の雄鶏がもう1度、歌った。「司祭は家政婦と寝ているよ。」
(4)司祭と家政婦は、そんな唄を歌っていると信じたもう1羽の雄鶏を殺し、熱湯につけ、とてもおいしく食べてしまった。そして司祭は言った。「さあ、今こそ何の心配もない。もう1羽しか雄鶏は残っていない。そしてそんなことを歌う勇気はなかろう。」
(5)ただ1羽生き残った雄鶏は、事態をいろいろ考えた末、言った。「私は別の唄を歌おう。この世に生を全うしたいし、不幸な目にあいたくない。聞いたこと、見たことを、黙っていよう。」
(5)-2そして再び雄鶏は真夜中と、明け方の3時と、6時に歌った。「この世で、生活を楽しむためにゃ、聞いたこと、見たこと、黙ること。」
《感想》「君子、危うきに近寄らず」!(Cf. 正確な出典は不明だが『春秋公羊伝』には「君子不近刑人」とある。)日本の諺では「触(サワ)らぬ神に祟(タタ)りなし」だ。また「口は禍の元」、「雉も鳴かずば撃たれまい」、「物言えば唇寒し秋の風」。「火中の栗を拾う」ことはしない。安全第一主義だ。「石橋を叩いて渡る」、「転ばぬ先の杖」!
《参考》BBCパリ特派員のヒュー・スコフィールド記者の記事(BBC、2018/7/19)によると、フランス・アルペン地方の城で、床板の裏に大工が書き綴っていた秘密の日記が2018年に見つかった。「1880年、クロット村のJoachim Martin(ジョアシャン・マルタン)、38歳」と床板に署名されていた。(ジョアシャン・マルタンは、当時の城主の依頼で床板を張った大工。残された秘密の日記は、いつか人の目に触れることがあったとしても、自分はそのころとっくに死んでしまっているという前提で、書かれたものだ。)ジョアシャンが床板に本音を書き込んだ動機の一つは、地元の神父に対する怒りだったようだ。1880年代は急激な変化の時代だった。フランスでは王党派の最後の挑戦が終わり、第三共和政(1870-1940)が足場を固め、全国で教会権限を縮小する改革が導入されていた。ジョアシャンはこうした改革を歓迎していた。それは主に、村のラジェール神父への個人的な反感が理由らしかった。ジョアシャンは「神父が病的な女好きで、告解を悪用して女性との性行為に及んでいた」と非難している。ジョアシャンは床板にこう書いた。「まず、我が家の家庭事情に首を突っ込んでくるのだが、そのやり方がすごくおかしい。妻とどのように性交渉しているか聞くなど」(ジョアシャンは実際にはもっと下品な言葉を使っている)。神父は「月に何回しているか知りたがった」とジョアシャンは書き、体位について詳しく赤裸々につづった挙句、こう結論する。「この豚は絞首刑がふさわしい」。この日記では他にもこの神父のことを、「女たらし」と書いている。『ジョアシャンの床板』という本を出版したブドン教授によると、「ラジェール神父が告解室で村の女性たちに性生活について質問したのは、仕事を逸脱したわけではないかもしれない。むしろ、当時の司祭はよくこういう質問をしていた。夫婦でも子供の誕生につながらない性行為は慎むよう説得することは、宗教的に必要だとされていたからだ。」
(2)司祭は怒った。そして司祭と家政婦は、そんな唄を歌っているのだと信じていた1羽の雄鶏を殺し、熱湯につけ食べてしまった。そしてもう誰も自分たちのしていることは知らないだろうと思った。
(3)ところがその真夜中と、明け方の3時と、6時に、雄鶏たちはまた歌った。最初の雄鶏が歌った。「ここで起こっていることは・・・・・・」すると2番目の雄鶏が歌った。「とても辛抱できそうにない。」その後、最初の雄鶏がもう1度、歌った。「司祭は家政婦と寝ているよ。」
(4)司祭と家政婦は、そんな唄を歌っていると信じたもう1羽の雄鶏を殺し、熱湯につけ、とてもおいしく食べてしまった。そして司祭は言った。「さあ、今こそ何の心配もない。もう1羽しか雄鶏は残っていない。そしてそんなことを歌う勇気はなかろう。」
(5)ただ1羽生き残った雄鶏は、事態をいろいろ考えた末、言った。「私は別の唄を歌おう。この世に生を全うしたいし、不幸な目にあいたくない。聞いたこと、見たことを、黙っていよう。」
(5)-2そして再び雄鶏は真夜中と、明け方の3時と、6時に歌った。「この世で、生活を楽しむためにゃ、聞いたこと、見たこと、黙ること。」
《感想》「君子、危うきに近寄らず」!(Cf. 正確な出典は不明だが『春秋公羊伝』には「君子不近刑人」とある。)日本の諺では「触(サワ)らぬ神に祟(タタ)りなし」だ。また「口は禍の元」、「雉も鳴かずば撃たれまい」、「物言えば唇寒し秋の風」。「火中の栗を拾う」ことはしない。安全第一主義だ。「石橋を叩いて渡る」、「転ばぬ先の杖」!
《参考》BBCパリ特派員のヒュー・スコフィールド記者の記事(BBC、2018/7/19)によると、フランス・アルペン地方の城で、床板の裏に大工が書き綴っていた秘密の日記が2018年に見つかった。「1880年、クロット村のJoachim Martin(ジョアシャン・マルタン)、38歳」と床板に署名されていた。(ジョアシャン・マルタンは、当時の城主の依頼で床板を張った大工。残された秘密の日記は、いつか人の目に触れることがあったとしても、自分はそのころとっくに死んでしまっているという前提で、書かれたものだ。)ジョアシャンが床板に本音を書き込んだ動機の一つは、地元の神父に対する怒りだったようだ。1880年代は急激な変化の時代だった。フランスでは王党派の最後の挑戦が終わり、第三共和政(1870-1940)が足場を固め、全国で教会権限を縮小する改革が導入されていた。ジョアシャンはこうした改革を歓迎していた。それは主に、村のラジェール神父への個人的な反感が理由らしかった。ジョアシャンは「神父が病的な女好きで、告解を悪用して女性との性行為に及んでいた」と非難している。ジョアシャンは床板にこう書いた。「まず、我が家の家庭事情に首を突っ込んでくるのだが、そのやり方がすごくおかしい。妻とどのように性交渉しているか聞くなど」(ジョアシャンは実際にはもっと下品な言葉を使っている)。神父は「月に何回しているか知りたがった」とジョアシャンは書き、体位について詳しく赤裸々につづった挙句、こう結論する。「この豚は絞首刑がふさわしい」。この日記では他にもこの神父のことを、「女たらし」と書いている。『ジョアシャンの床板』という本を出版したブドン教授によると、「ラジェール神父が告解室で村の女性たちに性生活について質問したのは、仕事を逸脱したわけではないかもしれない。むしろ、当時の司祭はよくこういう質問をしていた。夫婦でも子供の誕生につながらない性行為は慎むよう説得することは、宗教的に必要だとされていたからだ。」