前作『酔ひもせず』に続く第2弾ですが、実はこちらの方が前作よりも10年ほど前のことが描かれてます。
絵師多賀朝湖=暁雲と俳諧師宝井其角との出会いからふたりの息の合った謎解きの顛末が色鮮やか。

『彩は匂へど』 田牧大和著 光文社時代小説文庫
暁雲三十一才、其角二十二才、深川にある芭蕉庵で出会ったふたり…、おりしも芭蕉庵になにやら怪しげな投げ文があって門人たちが揉めている最中のこと、芭蕉の口添えもあってその日のうちに酒を酌み交わす仲になる。
前作は其角の目を通して語られていましたが、今作は暁雲の目を通して語られています。
暁雲が見た其角は“息をするように”句を詠める才気溢れる俳諧師であり、人の心の裡や機微を感じ取ることには長けているのに相手に向ける言葉の選び方が極めて拙いからその差が面白い。
一方其角が見た暁雲は目の奥に闇を宿している……、その闇の元となっている出来事については前作の終盤で暁雲の口から語られるまで本作では其角には明かされません。
本作の謎解きには“琉球”が関わっていて、十一年という長い時をかけて一人の女の想いが昇華しますがそれに手を貸したのが芭蕉で、茶目っ気もあり深く秘めた思惑もあり、其角の論理的思考と暁雲の勘が見事に補い合って事の解決に至るというワケです
前作には紅葉太夫と花房太夫という花魁が登場しましたが、今作では紅花太夫という花魁が色を添えています…紅花という源氏名は彼女が好む紅掛花色という色からきているそうで、ちょっと検索してみたんですけど、キレイな青系の色でした。
“琉球の女”が纏っていた打掛の襟は緋色で山吹色の身頃には白や青や赤の鮮やかな蝶の柄、芭蕉庵の庭のバショウの鮮やかな緑、そして紅花太夫の紅掛花色、まさに“彩が匂ふ”ような印象です。
余談ですが紅花太夫は次作の『紅きゆめみし』にも登場してるみたい…、こちらは暁雲&其角コンビではないみたいですけど…。
絵師多賀朝湖=暁雲と俳諧師宝井其角との出会いからふたりの息の合った謎解きの顛末が色鮮やか。

『彩は匂へど』 田牧大和著 光文社時代小説文庫
暁雲三十一才、其角二十二才、深川にある芭蕉庵で出会ったふたり…、おりしも芭蕉庵になにやら怪しげな投げ文があって門人たちが揉めている最中のこと、芭蕉の口添えもあってその日のうちに酒を酌み交わす仲になる。
前作は其角の目を通して語られていましたが、今作は暁雲の目を通して語られています。
暁雲が見た其角は“息をするように”句を詠める才気溢れる俳諧師であり、人の心の裡や機微を感じ取ることには長けているのに相手に向ける言葉の選び方が極めて拙いからその差が面白い。
一方其角が見た暁雲は目の奥に闇を宿している……、その闇の元となっている出来事については前作の終盤で暁雲の口から語られるまで本作では其角には明かされません。
本作の謎解きには“琉球”が関わっていて、十一年という長い時をかけて一人の女の想いが昇華しますがそれに手を貸したのが芭蕉で、茶目っ気もあり深く秘めた思惑もあり、其角の論理的思考と暁雲の勘が見事に補い合って事の解決に至るというワケです

前作には紅葉太夫と花房太夫という花魁が登場しましたが、今作では紅花太夫という花魁が色を添えています…紅花という源氏名は彼女が好む紅掛花色という色からきているそうで、ちょっと検索してみたんですけど、キレイな青系の色でした。
“琉球の女”が纏っていた打掛の襟は緋色で山吹色の身頃には白や青や赤の鮮やかな蝶の柄、芭蕉庵の庭のバショウの鮮やかな緑、そして紅花太夫の紅掛花色、まさに“彩が匂ふ”ような印象です。
余談ですが紅花太夫は次作の『紅きゆめみし』にも登場してるみたい…、こちらは暁雲&其角コンビではないみたいですけど…。












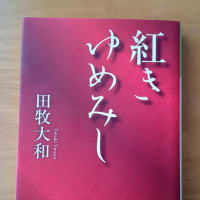













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます