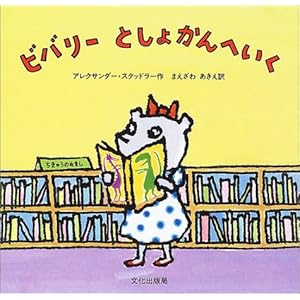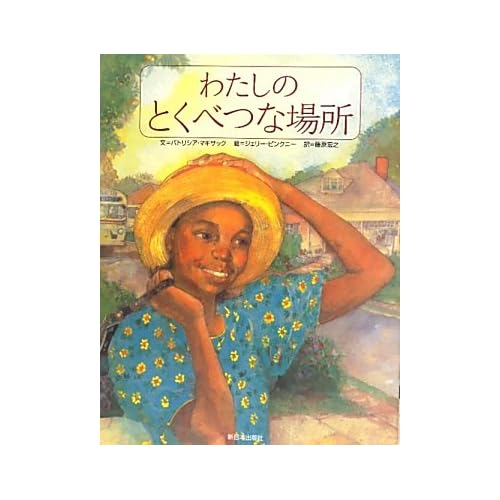今日4時から教育委員会あるそうです。HPで出ているか見てみましたが見つけられません。どこかに出ていました?
教育委員会は公開の場で、ということは委員さんたちも確認しているということですので、お時間のある方は傍聴にお出かけください。
三木の教育の大事なところは教育委員会で決められます。どのような議論の結果、結論が出されるのか、しっかり見ておきましょう。
といっても市民も暇ではありません。私も、合間を縫って出られるときにしか行けません。市民がそれぞれ合間を縫って傍聴したり、委員会参加したことを共有することで、市民にもようやく情報が届きます。
知る人ぞ知る、武雄市の図書館騒動、市民の議論も、教育委員会の議論もあまりないまま、すんなり決まってしまいました。
しかし、きちんと冷静な目で見ている市民もいらっしゃいます。
(ご報告)
武雄の市図書館指定管理者委託問題21日の議会最終日に市長提案通り可決されました。
7月下旬に予定されている臨時議会において委託先のツタヤへの委託料やサービス内容等が提案される
予定です。採決結果は17対8でこの数字がどのような問題に対しても変わらないのが市議会の現状です。
○賛成討論「公共図書館の多様性、発展性が向上する。」「運営経費を削減し、市民サービスの低下を招かないレベルでの制度導入だ」「行政の運営では人件費、委託費を切り詰めるのは限界」。
○反対討論「文化的、歴史的価値をどう保つか議論を尽くす必要があり、時期尚早」「改正は市長の権限を大きくするもので、公の図書館の理念を逸脱し、これまでの管理運営を無視するもの」
○採決後、樋渡市長は「全会一致にならなかったのは極めて残念。あくまで最大の関門は次の臨時議会。貸出履歴の扱いも、これから市個人情報審議会にかけ、臨時議会で報告したい」(佐賀新聞6月22日版)
突然、東京での記者会見で始まった図書館指定管理者問題、次は県庁で、私たち市民はマスコミ報道で知るのが精一杯でした。拙速に進めるのが彼の常套手段で、市民への周知時間や考える暇を与えることはありません。市議会はご用市議会で市長派と言われる人たちは、市長を載せる神輿を我先に担ぐような状況です。市民も内容が分からぬままに、一つの案件が終わればそれで終息(諦める)立ち止まって考える様子は今までありませんでした。
2006年3月に旧武雄市(34,603人)は、農村部の山内町(9,817人)と旧産炭地の北方町(8,648人)と理念無し(合併特例債ねらい)の合併で新武雄市になりました。現図書館歴史資料館は旧武雄市の施設で、山内町・北方町の人々には余り愛着が無いかもしれません。?
25日の月曜日に関係者と言われる人たちが集まり、今後の方向を議論する予定にしています。政治的なこと図書館そのもののこと、二つに分けながら結節点を探るようなフローになると思いますが、このような時代だからこそ、武雄の問題は全国的なテーマでもあると思っています。個人情報の取り扱いも市レベルの議論を超えるテーマかと思いますが、市レベルで治まる限り市長の独断で抑え込まれてしまうでしょう。今回の問題で市議会には最初から期待はしていませんでしたが、教育委員会がひと言もメッセージを発しないのには驚きました。そのことについても、危機感を抱いています。
ハード面では、ツタヤへの便宜供与と思われる図書館の増築、歴史資料館の移転改築、市庁舎の改築など玉突き的に建設事業が起こされ合併特例債が使われようとしています。市庁舎改築などは現庁舎耐震補強で十分ですし、旧山内町や旧北方町の庁舎建築は殆ど使われていません。
図書館を今まで通り運営すれば、逆に膨大な財政支出が避けられると思います。思いつき政策は、時間軸と空間軸で積み上げられてきた「まちづくりのバランス」を壊しています。
6月11日以降、みなさまの情報提供で図書館問題を学習してきましたが、図書館が民主主義や協働のまちづくりに直接リンクしていることが分かってきました。「新たな課題を抱え込むのか」と、思っていましたが、今ライフワークにしている「水環境」や「子育て・教育」「景観」等に包含して考えていきたいと思います。
少し長くなりましたが、取り急ぎご報告します。ありがとうございました。
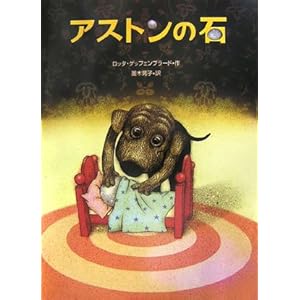 この絵本の表紙の犬、男の子?女の子?どちらだと思いますか?そしてそれはなぜですか?男の子の絵本、女の子の絵本という時、男の子と女の子には違った役割を与えてしまう絵本が多いように思います。
この絵本の表紙の犬、男の子?女の子?どちらだと思いますか?そしてそれはなぜですか?男の子の絵本、女の子の絵本という時、男の子と女の子には違った役割を与えてしまう絵本が多いように思います。