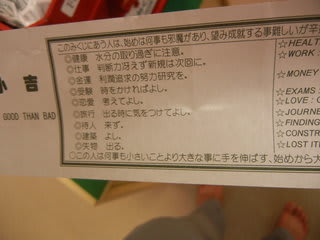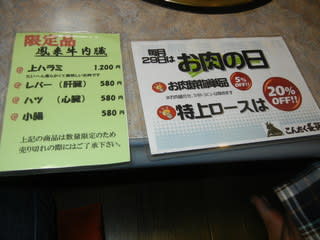一月以上経ってしまいましたが、あこがれの名護屋城のことを。

その昔、尾張名古屋に住んでいた小学生だった私は「なごやじょう」という巨城がもう一つあると聞いて妙な競争心を抱いた記憶があります。
まぁ、偏狭な郷土愛とも言うべきものでしょう。
その後、名護屋城は織豊系城郭の最高峰とも言うべき相当の城だと聞きつけ、行きたいと熱望する城へと変化する。しかし、なかなか馴染みの無い佐賀県にあるだけに、きっと定年後にでも行くのだろうと漠然と思っておりました。
が、案外とあっさりとその夢は叶いまして、本来は吉野ヶ里よりも名護屋城が、佐賀遠征の最大の目的でした。
憧れの名護屋城。
駐車場にとめるとこんな感じでお出迎え。

とにかくでかそう。
さすがに日本中の主要大名が渡海遠征のために集まっただけのことはある。
この城は豊臣秀吉が国内を統一し、海外出兵の拠点とした場所だけに錚々たるメンバーが集結しています。徳川家康、伊達政宗、小早川隆景、宇喜田秀家、上杉景勝・・・。まさに戦国の有名どころが全て。軍勢も多かっただけに、突然の巨大都市が出来上がったわけです。
その、中心となる拠点施設が名護屋城。
博物館から見た景色としてはこんな感じ。

周りに何も無く、青空の中にスカーンと聳えるのは見ていて壮観。
だいたい、城はその後の行政の中心地になるなどして、周囲に高層ビルなどが立ち並んでいることが多いのですが、なにぶんこの城は突如できあがり、そして目的終了とともに消えただけあって、周りが発展していない。だからなんとなく昔の感じが想像できるわけです。
さて、城へ侵入を開始。
入口を見た瞬間に「でかい。」

おなじ「なごやじょう」の名古屋城などは、石垣もでかいのですが郭も広々としているので石垣に近寄れずその巨大さをあまり感じないのですが、ここは際まで寄っていけるので大きさを身近に感じられます。

※唖然と見上げる一同。
石垣に上から下に向けて三角形のような形で柴が生えている部分があります。
「これが破城か!」
一同感動。
江戸時代に各大名は、一国一城令で城は原則一つまで、と、されたがために、国内の居城以外の城を壊さないといけなくなります。
そうした際に、全部を壊すのは大変なのと、いざというときにもう一度使えるようにするため、適当な壊し方をします。なので、外からよく見える部分の石垣の上部分だけを壊したりするわけです。どうやら名護屋城も破城の憂き目にあったようで、石垣がところどころ壊されています。
こうした点も、県庁所在地にある大名の居城から残ってきた城達と違う部分です。
まさに兵どもが夢のあと。
ところで、このときはお盆真っ盛り。
何でこんなクソ暑い時期に、と、いいながらも灼熱の日差しに焼かれながら登城する。
大手道がまっすぐと伸びてます。

その左側には石垣があるので、当然のことながら攻撃をされつづけることになりますが、名護屋城が敵襲を受けることは、さほど意識していないでしょう。どちらかというと安土城の大手道のような感じを受けました。
ちなみに、道の向かって右側はこんな感じ。

開発の手が入って無いだけに良い感じで朽ちてます。
さきほどのまっすぐの大手道の先の虎口を抜けると、ヘアピンカーブがお出迎え。

ここで180度、ぐいっと曲がる羽目に。
そして、やはり破城のときのものでしょう。壊された石垣の石が随所に。

本丸へどんどん近づいていきますが、階段の巨大なこと巨大なこと。

※宝塚のフィナーレで鈴を持った人達が並んでも大丈夫、という広さ。
そして、この城が良いのは木が少なく、見通しが利くことです。
なので、他の郭の状況がよくわかる。

※これは攻撃しやすい。

空と海が混ざり合う場所。カラッとして、本州にはない雰囲気です。
この鄙びた場所にこれだけのものが突如として現れれば、現地の人はさぞ驚いたことでしょう。
天守台には敷石まで。

どんだけ金かけとんじゃ、という感じがしますが、当時の日本は空前のゴールドラッシュ。
そりゃあ、金は唸ってるわな。さすが黄金関白。
石垣の補修工事なども行われておりました。

二の丸を巡っていると、より破城の跡がわかる場所も。

こうして色々と回ってきましたが、さすがに大きいのと暑いのとで、うっかり、山里丸を巡ってくるのを忘れてしまいました。無念。
とにかく巨大だった名護屋城。
巨大ながらも建物も無く、石垣は壊され、草が生い茂るのみ。
景色は遠く晴れ晴れと見渡せるのですが、侘しさを妙に感じさせる城です。
城好きがこんなことを言うのもなんですが、やっぱり平和が一番かと。

その昔、尾張名古屋に住んでいた小学生だった私は「なごやじょう」という巨城がもう一つあると聞いて妙な競争心を抱いた記憶があります。
まぁ、偏狭な郷土愛とも言うべきものでしょう。
その後、名護屋城は織豊系城郭の最高峰とも言うべき相当の城だと聞きつけ、行きたいと熱望する城へと変化する。しかし、なかなか馴染みの無い佐賀県にあるだけに、きっと定年後にでも行くのだろうと漠然と思っておりました。
が、案外とあっさりとその夢は叶いまして、本来は吉野ヶ里よりも名護屋城が、佐賀遠征の最大の目的でした。
憧れの名護屋城。
駐車場にとめるとこんな感じでお出迎え。

とにかくでかそう。
さすがに日本中の主要大名が渡海遠征のために集まっただけのことはある。
この城は豊臣秀吉が国内を統一し、海外出兵の拠点とした場所だけに錚々たるメンバーが集結しています。徳川家康、伊達政宗、小早川隆景、宇喜田秀家、上杉景勝・・・。まさに戦国の有名どころが全て。軍勢も多かっただけに、突然の巨大都市が出来上がったわけです。
その、中心となる拠点施設が名護屋城。
博物館から見た景色としてはこんな感じ。

周りに何も無く、青空の中にスカーンと聳えるのは見ていて壮観。
だいたい、城はその後の行政の中心地になるなどして、周囲に高層ビルなどが立ち並んでいることが多いのですが、なにぶんこの城は突如できあがり、そして目的終了とともに消えただけあって、周りが発展していない。だからなんとなく昔の感じが想像できるわけです。
さて、城へ侵入を開始。
入口を見た瞬間に「でかい。」

おなじ「なごやじょう」の名古屋城などは、石垣もでかいのですが郭も広々としているので石垣に近寄れずその巨大さをあまり感じないのですが、ここは際まで寄っていけるので大きさを身近に感じられます。

※唖然と見上げる一同。
石垣に上から下に向けて三角形のような形で柴が生えている部分があります。
「これが破城か!」
一同感動。
江戸時代に各大名は、一国一城令で城は原則一つまで、と、されたがために、国内の居城以外の城を壊さないといけなくなります。
そうした際に、全部を壊すのは大変なのと、いざというときにもう一度使えるようにするため、適当な壊し方をします。なので、外からよく見える部分の石垣の上部分だけを壊したりするわけです。どうやら名護屋城も破城の憂き目にあったようで、石垣がところどころ壊されています。
こうした点も、県庁所在地にある大名の居城から残ってきた城達と違う部分です。
まさに兵どもが夢のあと。
ところで、このときはお盆真っ盛り。
何でこんなクソ暑い時期に、と、いいながらも灼熱の日差しに焼かれながら登城する。
大手道がまっすぐと伸びてます。

その左側には石垣があるので、当然のことながら攻撃をされつづけることになりますが、名護屋城が敵襲を受けることは、さほど意識していないでしょう。どちらかというと安土城の大手道のような感じを受けました。
ちなみに、道の向かって右側はこんな感じ。

開発の手が入って無いだけに良い感じで朽ちてます。
さきほどのまっすぐの大手道の先の虎口を抜けると、ヘアピンカーブがお出迎え。

ここで180度、ぐいっと曲がる羽目に。
そして、やはり破城のときのものでしょう。壊された石垣の石が随所に。

本丸へどんどん近づいていきますが、階段の巨大なこと巨大なこと。

※宝塚のフィナーレで鈴を持った人達が並んでも大丈夫、という広さ。
そして、この城が良いのは木が少なく、見通しが利くことです。
なので、他の郭の状況がよくわかる。

※これは攻撃しやすい。

空と海が混ざり合う場所。カラッとして、本州にはない雰囲気です。
この鄙びた場所にこれだけのものが突如として現れれば、現地の人はさぞ驚いたことでしょう。
天守台には敷石まで。

どんだけ金かけとんじゃ、という感じがしますが、当時の日本は空前のゴールドラッシュ。
そりゃあ、金は唸ってるわな。さすが黄金関白。
石垣の補修工事なども行われておりました。

二の丸を巡っていると、より破城の跡がわかる場所も。

こうして色々と回ってきましたが、さすがに大きいのと暑いのとで、うっかり、山里丸を巡ってくるのを忘れてしまいました。無念。
とにかく巨大だった名護屋城。
巨大ながらも建物も無く、石垣は壊され、草が生い茂るのみ。
景色は遠く晴れ晴れと見渡せるのですが、侘しさを妙に感じさせる城です。
城好きがこんなことを言うのもなんですが、やっぱり平和が一番かと。