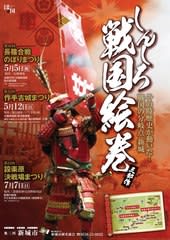古宮城が好きすぎて、作手地区を始めとする新城市が好きすぎて移住までしてしまった私です。
(現在は仕事の関係で名古屋に召還されてしまいましたが。)

※まだ下の息子がおらず、下の息子くらいの歳の娘と。
古宮城の関係である方と話をする機会が少し前にありまして、その際、尾張部で生まれ育った人の視点だと作手はどう?、といったことを聞かれまして、折角なので、ちょっと詳しく考えてみたいと思っておりました。
4月は生業がクソ忙しい状況となってしまい、なかなか考えることができなかったのですが、GWに入ったら考えたいと思っていたところでした。
あちこちの城や観光地を走り回って15万km。

※韮崎でぶつけられて今は無きフォレスター。

このようにあちこち運転してきた感覚から、
「名古屋起点で考えた場合、作手ってどこと一緒くらいだろうか。」
と、考えてみる。
ドライバーとしての感覚からすると、奥美濃、伊勢、掛川あたりを目的としたドライブを行うのと一緒くらいかな、と。
このカテゴリーは、当日思い付きでぷらっと出かける場所ではなく、少なくとも前夜までくらいに「あ、行こうかな。」と思いついて行く場所、という感覚です。できれば、朝8時台、最悪9時15分位までには出発したい日帰りスポット。
「ああ、遠出して楽しんで車も十分に運転してすっきりした。」
と、思える場所です。
京都だと行きすぎ、岐阜、知多、長浜だと近すぎ。この辺りだと、当日朝に「はっ。」と思いついて出発しても楽しめる、という日帰りスポット。岐阜、知多だと旅情が少し薄い。
実際、どんぴしゃで一致する場所、と、考えた場合、大津と松阪が該当しそう。
そんな分類を行った後、
「実際どうなんだ。」
と、思う。
幸い、最近ではネットで目的地と出発地を入力すると簡単に距離と時間が出る。
で、調べて見ました。
起点は、尾張名古屋は城で持つため名古屋城に。
すると、作手(高里)は『約80km。約1時間30分』との結果が。
では、私の中の同カテゴリーはどうなのか。
奥美濃 約100km、約1時間15分。※白鳥あたりです。
伊 勢 約133km、約1時間40分。
掛 川 約135km、約1時間45分。
と、いう結果となりました。
おお。
1時間半を挟んで15分前後の場所だったではないか。
では、注目の松阪、大津はどうなのかというと。
松 阪 約105km、約1時間25分。
大 津 約120km、約1時間30分。
おおおおお!
ほぼ一致。誤差は5分まで短縮されてますし、大津は時間で一致。
しかし、いずれも距離は100km。
作手の距離は80kmなので、距離の割には時間がかかる、ということがはっきりしました。
このあたりは、新東名高速道路の開通がなんとかしてくれる、というのが期待されます。
そうなってくると、知多、長浜、彦根と同じ「当日の朝『はっ』と」カテゴリーに入ってくることが考えられます。
まぁ、今日は、単純に時間感覚のみの話であり、行先の魅力としての分析まではしてないです。
人間の感覚って、案外、馬鹿にできないもんですね。
(現在は仕事の関係で名古屋に召還されてしまいましたが。)

※まだ下の息子がおらず、下の息子くらいの歳の娘と。
古宮城の関係である方と話をする機会が少し前にありまして、その際、尾張部で生まれ育った人の視点だと作手はどう?、といったことを聞かれまして、折角なので、ちょっと詳しく考えてみたいと思っておりました。
4月は生業がクソ忙しい状況となってしまい、なかなか考えることができなかったのですが、GWに入ったら考えたいと思っていたところでした。
あちこちの城や観光地を走り回って15万km。

※韮崎でぶつけられて今は無きフォレスター。

このようにあちこち運転してきた感覚から、
「名古屋起点で考えた場合、作手ってどこと一緒くらいだろうか。」
と、考えてみる。
ドライバーとしての感覚からすると、奥美濃、伊勢、掛川あたりを目的としたドライブを行うのと一緒くらいかな、と。
このカテゴリーは、当日思い付きでぷらっと出かける場所ではなく、少なくとも前夜までくらいに「あ、行こうかな。」と思いついて行く場所、という感覚です。できれば、朝8時台、最悪9時15分位までには出発したい日帰りスポット。
「ああ、遠出して楽しんで車も十分に運転してすっきりした。」
と、思える場所です。
京都だと行きすぎ、岐阜、知多、長浜だと近すぎ。この辺りだと、当日朝に「はっ。」と思いついて出発しても楽しめる、という日帰りスポット。岐阜、知多だと旅情が少し薄い。
実際、どんぴしゃで一致する場所、と、考えた場合、大津と松阪が該当しそう。
そんな分類を行った後、
「実際どうなんだ。」
と、思う。
幸い、最近ではネットで目的地と出発地を入力すると簡単に距離と時間が出る。
で、調べて見ました。
起点は、尾張名古屋は城で持つため名古屋城に。
すると、作手(高里)は『約80km。約1時間30分』との結果が。
では、私の中の同カテゴリーはどうなのか。
奥美濃 約100km、約1時間15分。※白鳥あたりです。
伊 勢 約133km、約1時間40分。
掛 川 約135km、約1時間45分。
と、いう結果となりました。
おお。
1時間半を挟んで15分前後の場所だったではないか。
では、注目の松阪、大津はどうなのかというと。
松 阪 約105km、約1時間25分。
大 津 約120km、約1時間30分。
おおおおお!
ほぼ一致。誤差は5分まで短縮されてますし、大津は時間で一致。
しかし、いずれも距離は100km。
作手の距離は80kmなので、距離の割には時間がかかる、ということがはっきりしました。
このあたりは、新東名高速道路の開通がなんとかしてくれる、というのが期待されます。
そうなってくると、知多、長浜、彦根と同じ「当日の朝『はっ』と」カテゴリーに入ってくることが考えられます。
まぁ、今日は、単純に時間感覚のみの話であり、行先の魅力としての分析まではしてないです。
人間の感覚って、案外、馬鹿にできないもんですね。