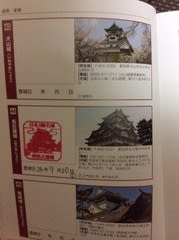今回の豊前征伐最大の目的『岩屋城』

時は天正14年(1568年)。
龍造隆信の首を取って勢力を拡大してきた島津軍。
九州北部の大友に攻めかかります。
5万の軍勢に包囲された大友方の岩屋城760名あまりは13日間の籠城の末、城主高橋紹運は切腹、そして全員が玉砕するというすさまじい結果になります。
しかし、この籠城により島津勢は足止めされてしまい、紹運の息子で立花道雪の養子になっていた立花宗茂が立花山城を島津軍が包囲している最中に豊臣勢が九州に上陸。島津勢は城の包囲を撤退。
(参考:『西日本文化』財団法人西日本文化協会 「岩屋城と戦国時代の山城」岡寺良)
結果的に九州に橋頭堡を確保した豊臣勢は九州を制圧。
そして、立花宗茂は「西の立花宗茂、東の本多忠勝」と並び称される大名として戦国時代を生き延びます。
そんなエピソード溢れる高橋紹運と岩屋城。
そして冒頭の迫力溢れすぎの石碑。
このダブルインパクトによって私達は岩屋城への訪問を心待ちにしていたのであった。
そして、大宰府を過ぎたところで発見した店。

大宰府で、伊達政宗と織田信長と真田幸村は無いだろう・・・。
大宰府ならば高橋紹運だろうがっ!!
て、いうか、菅原道真だろうがっ!!!
と、激怒する4名。
道真ショップ。イケメンに迫力満点で描かれた道真。雷神と化し復讐する道真。迫力ありすぎかも。
さて、この日、大宰府を過ぎた辺りから晴天になり、お盆としての暑さが戻ってきた。
そのため、なるべく歩きたくない。特に最終日だったこともあり、夜の10時まで新幹線に乗る予定。汗だくになってしまうと、その状況で夜まで、と、考えるとできる限り歩きたくなくなる。
と、いうことで限界ぎりぎりまで車で行く。

※今までサンダルで来たが、いよいよ靴に履き替え本気モードへ。
まずは、高橋紹運公と城兵の墓へ向かう。

大宰府市が一望できる場所。なるほど、ここに城を構えたくなるわな、と、納得の景色。

やっぱり夏は城めぐりに向かないなぁ、と、しみじみ思うこの道。

案内そって行くこと数分。
高橋紹運公の墓が現れました!

※写真を撮る前に敬意を表して少し墓前を掃除させていただいております。
700名の城兵が玉砕する、という指導力。すごい統率力です。
個人的には信長の野望で立花道雪と並びやたら強い武将として九州北部に登場する武将として気になっていた人。
憧れの武将の一人だけに、その墓に参れただけでも嬉しい。
なんか信長の野望では、赤い兜にマントみたいなのを羽織った渋い武将として登場していた印象が強すぎて、私の中の紹運はそのイメージで固定されています。
ところで、紹運が切腹した年齢は39歳。
これには一同驚く。
「俺、どう考えても紹運年上だと思ってた。」
と、4名全員が納得。
もう、そんな歳なんだな、俺ら、と、気持ちは20代の会社同期として飲み会やってた頃と変わらない面々だけに、若干狼狽する。そりゃそうだ。暑いから、と、いって車でぎりぎりまで向かうようにいつの間にかなっていたのだ。
結果的に息子の名将立花宗茂を送り出す捨て石になったのであれば、きっと、にっこり笑って死んでいったのではないか、と、思ってしまう40歳二人の子持ちの私。特に宗茂は相当その素質を見込まれていたようなので、安心して逝けたことでしょう。と、墓前でしんみりする。
現在では知る人ぞ知る、という渋すぎるオヤジ。それが高橋紹運なのです。
さて、そんな紹運が籠った岩屋城。
本丸を目指して歩きます。
ところどころで城郭遺構のようなものを発見する。
畝状竪堀に特徴があるのですが、まさにそれ。

あちこちに堀切が出てきて山城らしさが一気にUP!
迂回させる道とか、やっぱり土の城はいいですネェ。

主郭前に堀切があります。

そして、主郭に侵入するには主郭下を回りこんで入り込む。
山城の鉄則です。

※こういう造りに興奮しますね。
そして主郭に到着すると、素晴らしい眺望が!

風が一気に通って、暑いながらも涼しさを感じます。
そして、我々が目当てとしていた迫力ありすぎの石碑も発見!

佐渡守と私は大興奮していました。
やっぱこの字が迫力ありすぎだよね、と。
そして、この山からは300度近いビューが現れる。

大宰府が!

水城が!

※ 画面の緑の森がそれ。
この景色を見れば大宰府の全てが分かる。ここに陣取ったのもわかります。
しかし、この城を5万の軍勢が囲うのも一目瞭然。そんな中奮闘した一同って素晴らしい。

※ 思わず見とれる。
本丸下には腰曲輪登場。

山全体が要塞化されているこんな城を十七日間で落城させたということは、相当無理攻めを島津はしたのだろう、と、いうことが想像されます。実際、ここで消耗したことで島津軍のスピードが鈍ったわけですから、すさまじい力攻めだったのだろうと。あれだけの比高差があって、堀切や竪堀で防御した城を落とすって相当だと思います。
やっぱり紹運ってすごいな。
と、一同思う。
やっぱり紹運好きだわ、と、改めて思った城でした。

※スズメバチの巣を撮影する紀伊守。
さて、次回は最終回。
古代山城の「大野城」です。

時は天正14年(1568年)。
龍造隆信の首を取って勢力を拡大してきた島津軍。
九州北部の大友に攻めかかります。
5万の軍勢に包囲された大友方の岩屋城760名あまりは13日間の籠城の末、城主高橋紹運は切腹、そして全員が玉砕するというすさまじい結果になります。
しかし、この籠城により島津勢は足止めされてしまい、紹運の息子で立花道雪の養子になっていた立花宗茂が立花山城を島津軍が包囲している最中に豊臣勢が九州に上陸。島津勢は城の包囲を撤退。
(参考:『西日本文化』財団法人西日本文化協会 「岩屋城と戦国時代の山城」岡寺良)
結果的に九州に橋頭堡を確保した豊臣勢は九州を制圧。
そして、立花宗茂は「西の立花宗茂、東の本多忠勝」と並び称される大名として戦国時代を生き延びます。
そんなエピソード溢れる高橋紹運と岩屋城。
そして冒頭の迫力溢れすぎの石碑。
このダブルインパクトによって私達は岩屋城への訪問を心待ちにしていたのであった。
そして、大宰府を過ぎたところで発見した店。

大宰府で、伊達政宗と織田信長と真田幸村は無いだろう・・・。
大宰府ならば高橋紹運だろうがっ!!
て、いうか、菅原道真だろうがっ!!!
と、激怒する4名。
道真ショップ。イケメンに迫力満点で描かれた道真。雷神と化し復讐する道真。迫力ありすぎかも。
さて、この日、大宰府を過ぎた辺りから晴天になり、お盆としての暑さが戻ってきた。
そのため、なるべく歩きたくない。特に最終日だったこともあり、夜の10時まで新幹線に乗る予定。汗だくになってしまうと、その状況で夜まで、と、考えるとできる限り歩きたくなくなる。
と、いうことで限界ぎりぎりまで車で行く。

※今までサンダルで来たが、いよいよ靴に履き替え本気モードへ。
まずは、高橋紹運公と城兵の墓へ向かう。

大宰府市が一望できる場所。なるほど、ここに城を構えたくなるわな、と、納得の景色。

やっぱり夏は城めぐりに向かないなぁ、と、しみじみ思うこの道。

案内そって行くこと数分。
高橋紹運公の墓が現れました!

※写真を撮る前に敬意を表して少し墓前を掃除させていただいております。
700名の城兵が玉砕する、という指導力。すごい統率力です。
個人的には信長の野望で立花道雪と並びやたら強い武将として九州北部に登場する武将として気になっていた人。
憧れの武将の一人だけに、その墓に参れただけでも嬉しい。
なんか信長の野望では、赤い兜にマントみたいなのを羽織った渋い武将として登場していた印象が強すぎて、私の中の紹運はそのイメージで固定されています。
ところで、紹運が切腹した年齢は39歳。
これには一同驚く。
「俺、どう考えても紹運年上だと思ってた。」
と、4名全員が納得。
もう、そんな歳なんだな、俺ら、と、気持ちは20代の会社同期として飲み会やってた頃と変わらない面々だけに、若干狼狽する。そりゃそうだ。暑いから、と、いって車でぎりぎりまで向かうようにいつの間にかなっていたのだ。
結果的に息子の名将立花宗茂を送り出す捨て石になったのであれば、きっと、にっこり笑って死んでいったのではないか、と、思ってしまう40歳二人の子持ちの私。特に宗茂は相当その素質を見込まれていたようなので、安心して逝けたことでしょう。と、墓前でしんみりする。
現在では知る人ぞ知る、という渋すぎるオヤジ。それが高橋紹運なのです。
さて、そんな紹運が籠った岩屋城。
本丸を目指して歩きます。
ところどころで城郭遺構のようなものを発見する。
畝状竪堀に特徴があるのですが、まさにそれ。

あちこちに堀切が出てきて山城らしさが一気にUP!
迂回させる道とか、やっぱり土の城はいいですネェ。

主郭前に堀切があります。

そして、主郭に侵入するには主郭下を回りこんで入り込む。
山城の鉄則です。

※こういう造りに興奮しますね。
そして主郭に到着すると、素晴らしい眺望が!

風が一気に通って、暑いながらも涼しさを感じます。
そして、我々が目当てとしていた迫力ありすぎの石碑も発見!

佐渡守と私は大興奮していました。
やっぱこの字が迫力ありすぎだよね、と。
そして、この山からは300度近いビューが現れる。

大宰府が!

水城が!

※ 画面の緑の森がそれ。
この景色を見れば大宰府の全てが分かる。ここに陣取ったのもわかります。
しかし、この城を5万の軍勢が囲うのも一目瞭然。そんな中奮闘した一同って素晴らしい。

※ 思わず見とれる。
本丸下には腰曲輪登場。

山全体が要塞化されているこんな城を十七日間で落城させたということは、相当無理攻めを島津はしたのだろう、と、いうことが想像されます。実際、ここで消耗したことで島津軍のスピードが鈍ったわけですから、すさまじい力攻めだったのだろうと。あれだけの比高差があって、堀切や竪堀で防御した城を落とすって相当だと思います。
やっぱり紹運ってすごいな。
と、一同思う。
やっぱり紹運好きだわ、と、改めて思った城でした。

※スズメバチの巣を撮影する紀伊守。
さて、次回は最終回。
古代山城の「大野城」です。