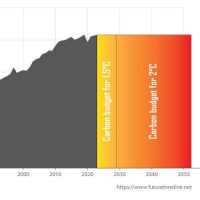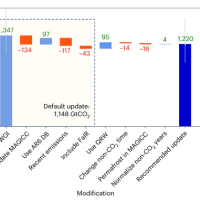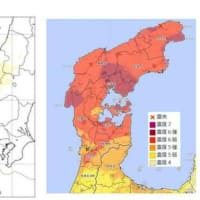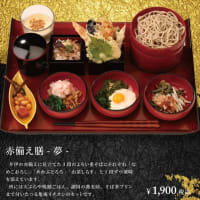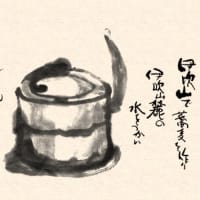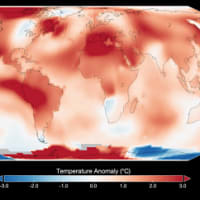☑ や
♗ 施薬院 全宗

☑生誕:1526年/近江国 甲賀郡
☑死没:1600年01月25日
☑宗派:天台宗
生憎の雨模様で天候不順で花見が危ぶまれる。ところ
で、近江は北は海津大崎、南は南郷洗堰の桜並木をは
じめとして、桜の名所に溢れている。そんな中、大津
市、比叡山延暦寺の東、琵琶湖に近い坂本には、56
ヶ所のの里坊(さとぼう)があり、10の里坊が名勝
指定されているが、薬樹院は里坊の一つで、かつては
比叡山の上にあったが、織田信長の焼討ちに会った後、
豊臣秀吉の侍医で信任が厚かった薬樹院全宗が、この
地に再建して住む。そんな由来をもつ薬樹院の太閤桜
は見事である。週末の土日に花見見物を計画する。
さて、施薬院全宗(やくいんぜんそう、大永6年(1526
年) - 慶長4年12月10日(1600年1月25日))は戦国時
代から安土桃山時代にかけての医者。豊臣秀吉の側近。
渡来系で多くの医者を輩出した丹波氏の出身。号は徳
運軒である。
☐大永6年(1526年)、平安時代に医心方を著した名医・
丹波康頼の二十世の末裔として生誕。祖父・宗清、父・
宗忠ともに権大僧都法印となる。幼少時に父を失い僧
籍となり、比叡山菜樹院の住持となる。織田信長によ
り比叡山焼き討ちに遭い、その時豊臣秀吉にもその意
図があると聞き及び、還俗して曲直瀬道三に入門し、
漢方医学を極め、豊臣秀吉の知遇を得て侍医となり合
わせ叡山の弁護にあたる。
☐秀吉が天下人になった後の天正13年(1585年)に大
飢饉と疫病の流行にみまわれると、廃絶していた祖先
よりの「施薬院」の復興を願い出て許された。この施
薬院は奈良時代・光明皇后による創建以来、800年の時
を経て完全に形骸化していた。全宗はこの復興に尽くし、
身分の上下を問わない施療を再開。天正年間に勅命を
受け、施薬院使に任命、従五位下に叙され昇殿を許さ
れる。
☐秀吉の信頼は厚く、秀吉の諱を与えられた息子の秀
隆とともに秀吉側近としても活躍し、伊達政宗・佐竹
義重との交渉役などを務める。天正15年(1587年)発
布の定(バテレン追放令)は全宗の筆による。豊臣氏
番医の筆頭として、番医制の運営につとめる。焼き討ち
後の荒廃した比叡山の再興にも尽力。天正18年(1590
年)に嫡男の秀隆が病没(外来の伝染病)のため、近
江の三雲資隆の子を養子とし、宗伯として継がせ、曲
直瀬氏嫡流を守り道三流医術の衰退を防止。豊臣秀次
の失脚事件を契機に曲直瀬一門の結束が全宗を頂点に
強化した。
☑ ま
♗ 曲直瀬道三

曲直瀬道三(まなせ どうさん、永正4年9月18日(1507
年10月23日) - 文禄3年1月4日(1594年2月23日))は、
戦国時代から安土桃山時代の日本の医師。道三は号。
諱は正盛(しょうせい)。字は一渓。他に雖知苦斎(
すいちくさい)、翠竹庵(すいちくあん)、啓迪庵(
けいてきあん)など。本姓は元は源氏、のち橘氏。今
大路家の祖。日本医学中興の祖として田代三喜・永田
徳本などと並んで「医聖」と称される。
父は近江源氏佐々木家庶流の堀部左兵衛親真、母は多
賀氏。母は自身を産んだ翌日に死去し、父もその年の
内に戦死している。なお、『近江栗太郡志』によれば
道三は近江国栗太郡勝部村(滋賀県守山市)の佐々木
氏一族勝部氏の一門の出とされ、母は目賀田攝津守綱
清の娘、諱を正慶とし、父母死別後伯母に育てられた
と記されている[2]。幼少時、守山の大光寺内吉祥院に
て学んだとされる。
【脚注及びリンク】
----------------------------------------------
- 2006年04月13日:春の比叡山麓坂本を訪ねる 薬
樹院の太閤桜 - 京、近江歳時記 薬樹院 太閤桜
- 2015年06月23日:薬樹院 | 滋賀県観光情報[公
式観光サイト]滋賀・びわ湖のすべてがわかる! - 施薬院全宗 Wikipedia
-------------------------;--------------------