
先日、ちらっとご紹介したホノホシ海岸。
奄美大島は、浜といえば白い砂浜、浜でなければ切り立った断崖というところが多いように思うのだが、ここは、海岸一面が玉石でいっぱい。そして、打ち寄せた波が引く際に「ゴロゴロ」という音を立てるので有名な海岸だ。「ゴロゴロ」「ガラガラ」「カラカラ」かな??
画像の中の三角をクリックすると動画になって音も入っています。この音は何と表現すればよいでしょう?↓
<script type="text/javascript" src="http://mooom.jp/JSPlayer?mid=69JAY7neT"></script>
さて、「ホノホシ海岸」。なぜホノホシ??
帆の干し?穂の星?と想像は膨らむが、今回は由来を探すのは簡単だった。
名前の由来は、この浜から大島海峡に抜ける陸の部分がひょうたんのくびれ状になっていて、昔、漁師が海路をショートカットして舟を担いで歩いたことから「船越」、なまって「ホノホシ」となったといわれています。
(奄美パークHPより)
ホノホシ海岸、漢字で書くと 船越海岸だったとは~。へー。
なるほど、このホノホシ海岸の面する伊須湾から大島海峡に渡るには、陸路の方が早そうだ。

この海岸の前は、ちゃんと整備された駐車場とトイレ(おむつ替えの台もあった!)があり、ちょっとした広場になっている。



このまーるい石たちが、ゴロゴロと。
こぶし大から、漬物石用まで、多彩なラインナップ。
白
s
s
トンネル岩(1枚目の写真)を挟んで、動画を撮った場所と反対側(下の写真)は、石がかなり上の方まで打ち寄せられていたので、この日、石の音は全然しなかった。

これは、台風の来る前日だったが、嵐のたびに、また潮の満ち引きによっても石の場所や量が変わるのだろう。
また違う時にも行って様子を見てみたいと思った。










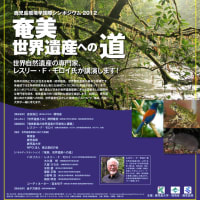









赤尾木と宇検の宇検。どのくらい昔か解りませんが、舟を担いだ・帆を担いだの説もありますね。時化とも関係があるようです。奄美は必ずといっていいほど風裏があるんですよね!?風の反対側に舟を出そうという魂胆なんでしょうね。「ダンプでどのくらい運んだのだろうね?」には私も噴出してしまいた。全て「ディズニイ」の発想。自然界にこんな場所があるって都会人には理解しにくいのかなあ?
なーるほど。確かに赤尾木も「船越」ですね。宇検の宇検、どこでしょう?(→地図を見てみました)
ひゃー!ほんと、なんとそこには「船越海水浴場」と書いてある!!
地図を見ると、くびれているところは結構ありますが、なおかつそこが平地、となると山がちな奄美には少ないのですね。
実際のところ、昔の人はどうやって船かついでいったんですか?公園のボートサイズですらかなりの重さですよね??私もダンプの人を笑えないです...
(追記)下にもう一つきさん宛てにメッセージいれました。
同じ海岸なのに、こんな風にコロコロ鳴ったり、どこぞの鳴き砂みたいにキュッキュッ言ったり。
自然のなせるワザって、おもしろいですねえ。
一枚目の写真は、岩がトンネルみたいになってるのですか?
なんだかこういう場所を見ると、探検してみたくなります。^^
改めて読み直してはたと気づきました。
「ダンプで石を運んだ」と思っていらした方がいたわけですねぇ!そうかそうか。
読解力不足ですみません。まさかそんな発想があるとは。
いやー、そんなの聞いたら噴出しちゃいます。で、「2ヶ月はかかったらしいよ。」っておっしゃいました?
★momongaさん★
確かに、ぐーっと寄せるとくっつきそうですよね。
瀬戸内町の海峡を挟んだ下の部分の島を加計呂麻(かけろま)島というのですが、これは「欠ケの島」か、「影の島」。すなわち、大島本島から「欠けた島」又は本島の「影になる島」ということだと瀬戸内町HPにありました。
名前の由来からも昔はくっついていたような感じですね~
そうです、トンネル岩です。
干潮の時は通り抜けられます。このときも、足が濡れるのを気にしなければ行けそうでした。行きませんでしたけど(^^;)
あ、中には入りましたよ!ちょっと探検気分で楽しかったです。
それにしても、そちらは停電大変でしたね。直接倒れる、濡れるなどの被害がなくてもライフラインが切れるだけでどれだけ不自由なことか...
ドキドキ・・。
FORTUNEさんのお人柄の良さや
奄美大島の澄んだ空気が伝わってくるようで
ページをめくりながら和んでいます。(*^_^*)
ようこそ!コメントありがとうございます。
「お人柄の良さ」とは、これを見たら私の友人は笑ってしまうと思いますが(^^;) 奄美の空気は本当に澄んでいますヨ!
まだまだ知らないことだらけの奄美での発見を綴っていきたいと思っていますので、また覗いていただけたら幸いです!
やっと解ってくれましたよ!(大笑)