 | 泡亭の一夜 (新潮文庫) 泡坂 妻夫 新潮社 このアイテムの詳細を見る |
☆
落語とマジック好きの、直木賞作家が創る落語のネタが15本と少しのエッセイ。
正直、落語としては、江戸調で書かれており、馴染み不足と相まって硬い感じがするが、
声を出して読んだり、一度、落語家の手に渡り、演者の味が加味されると
一段とおもしろくなるのだろう。
でも、マクラから吟味されたものが用意されており、
プロの文筆家の推敲の後が窺える。
あとがきに、吉川潮さんが、まとめて書いておられるので引用させて頂くと、
冒頭の「まくら」からして本寸法だ。「色色な酒のお癖がございまして」(狸の使い)
と、世間話のように始ることもあれば、「夏の盛り、長い石段を中年の夫婦が登って
まいります。(大黒漬)と、登場人物の行動を説明して噺に入る場合もある。時には
「富札の引き裂いてある首くくり」(千両弔い)、「彫物も遊女の作は金になり」(さま命)
と、定番である川柳を使い、「辰巳やよいとこ素足が歩く、羽織やお江戸の誇りもの」
(奥縞)と小唄の文句で始ることもある。また、「十人寄れば気はトイレ」(新内屋)と、
「気は十色}の駄洒落で入ったりする。この導入部を読んだだけで、作者の落語に
対する造詣の深さがわかる。
と、小説は出だしで決まるとか、「吾輩は猫である。名前はまだない」とか、
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」などと、
いまだ冒頭だけ覚えている小説は、多々ある。
この頃、まくらだけでは無く、落語に入る「こんにちは」とか、「定吉」、「植木屋はん」とか
これからはじまるでという、場面転換の、導入のテンションがいたって好きですな・・・・。
小説家の落語ネタだけに、一語一句、丁寧に作られたものだが、逆に窮屈さを感じる。
それだけに、上方の落語家の中で、このひとなら、上手に味付けされるんではないかと、
ごまめ流に、読みながら、頭に浮かんだ噺家さんを列挙致しました・・・ご参考に。
ごまめの泡亭
一、露の団姫・・・・・・・・・・・・「狸の使い」
二、桂吉の丞・・・・・・・・・・・・「大黒漬」
三、林家染太・・・・・・・・・・・・「千両弔い」
四、桂歌之助・・・・・・・・・・・・「さま命」
五、桂吉坊・・・・・・・・・・・・・・「奥縞」
六、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・「お島甲吉」
七、林家染雀・・・・・・・・・・・・「新内屋」
八、笑福亭生喬・・・・・・・・・・「三枚龍」
仲入り
九、桂文三・・・・・・・・・・・・・・「力石」
十、林家花丸・・・・・・・・・・・・「心中屋」
十一、月亭八天・・・・・・・・・・「そもそも」
十二、桂坊枝・・・・・・・・・・・・「勝券」
十三、笑福亭三喬・・・・・・・・「節分」
十四、笑福亭智之介・・・・・・「奇術」
十五、桂雀松・・・・・・・・・・・・「春色川船頭」














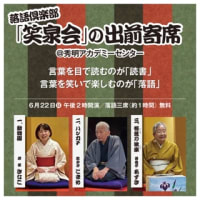











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます