○平林寺大門
4月15日に新河岸川右岸で水質測定をした帰りに、川越街道の「野火止大門」の交差点を通りますと、見た記憶のある石柱が建っていました。江戸名所図会の「平林寺大門」の絵の場所がどこか探そうと思っていたところだったので、探す手間が省けました。私は、最初にこの絵を見たとき、現在の平林寺境内の参詣路なのかなと思いましたが、実際は平林寺総門から「平林寺大門通り」を通って約1.5キロ離れています(平林寺総門の前、新座市役所前、新座警察署の前を通る道路が、「平林寺大門通り」です)。
当時はこのあたりまで、平林寺の寺領のようなものだったのでしょう。


左:市古夏生・鈴木健一校訂 ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会4』 筑摩書房p.313より転載
右:現在の「野火止大門」交差点 平林寺方向
この石柱が当時のものそのままなのか、あるいは、補修・復元し代がわりしたものかは分りませんが、「金鳳山平林禅寺」の面の裏には
「寛延三歳(次)庚午季夏之日
山本氏子(従)方(就)謹建」
と刻まれています。( )内は私には読めない文字。
年表をみると、寛延三年は、1750年のようです。

現在の交差点は、名所図会の感じと程遠いですが、現在の平林寺周辺で、この絵をイメージして写真を撮ってみました。


<左:新座市役所前。画面右が平林寺の林;
右:大門通りから平林寺の奥に走る「非常道路」。総門から150m離れたところにあります>
○野火止用水の資料さがし
●新座市歴史民俗資料館
平林寺に参詣する前に、新座市歴史民俗資料館に寄ってみました。
野火止用水について、職員(学芸員)の方から約1時間説明を聞きました。

<新座市のページでは、歴史民俗資料館の外観写真、案内地図がありません。さびしいので載せておきます。写真をクリックすると、敷地に立っている新座市文化財案内の地図が表示されます。>
伺った説明と、展示資料で、面白かった点をいくつかピックアップしてみます。
1.平林寺は、総門から奥に進むと次第に土地が高くなっていきます(ざっと見た感じで10-20mくらい上がっています)が、それは、この部分だけ、下末吉層が残っているためで、その分だけ周囲(下末吉層が残っていない)より高いのだそうです。
この高さは、平林寺西側の野火止用水散策路を通ると実感できます。また、境内の奥の方にある、業平塚の奥から、野火止用水散策路にむかって結構下り斜面になっているのがわかります。(ただしここから野火止用水は見えません)
2.平林寺のある野火止台地は、土地がやせていて、松平信綱の時代に野火止への入植が行われる以前には、アカマツやススキの原だったとのこと。また、入植後は、肥料源として雑木林が大切にされたとのこと。
現在の平林寺の境内林にもアカマツがけっこうあります。


<左:業平塚 右:業平塚の近くにひろがるアカマツ林>
ということで、名所図会「平林寺大門」に描かれている樹木の奥のほうはアカマツのようです。
3.野火止用水の昔の写真がいくつか展示されています。その中に「野火止用水その2」で述べた、街道(市場通り)の真中に用水が通っているものや、いろは樋の写真がありました。他に、昭和26年頃のものとして、志木駅近くを流れる用水などがありました。
●新座市立中央図書館
野火止用水の昔の写真として
・『志木市市制施行20周年記念 ふるさと写真集』志木市市制施行20周年記念事業市民実行委員会文化部会編
・『特別展 野火止用水 図録』東村山ふるさと歴史館 平成13年
などがありました。(図録は、現在東村山ふるさと歴史館で500円で頒布されています。)
清流復活事業については、
・『野火止用水清流対策調査報告書』新座市建設部昭和59年
・『野火止用水管理活用計画』新座市 新座市教育委員会 平成7年
などがありましたが、ざっと見たところ、流した水がどこに流れていくのかについての記載はありませんでした。
・『緑と清流 野火止用水の復活』埼玉県 埼玉県教育委員会 新座市 新座市教育委員会(記載内容は昭和62年度まで)というパンフレット中の地図に、唯一、「本流 流末処理 柳瀬川へ 平林寺堀 新河岸川へ」という記載がありました。
●新座市観光のページ
野火止用水散策マップがpdfファイルで入手できます。
http://www.niiza.net/pdf/nobidome_map01.pdf

<平林寺境内にある野火止塚>
4月15日に新河岸川右岸で水質測定をした帰りに、川越街道の「野火止大門」の交差点を通りますと、見た記憶のある石柱が建っていました。江戸名所図会の「平林寺大門」の絵の場所がどこか探そうと思っていたところだったので、探す手間が省けました。私は、最初にこの絵を見たとき、現在の平林寺境内の参詣路なのかなと思いましたが、実際は平林寺総門から「平林寺大門通り」を通って約1.5キロ離れています(平林寺総門の前、新座市役所前、新座警察署の前を通る道路が、「平林寺大門通り」です)。
当時はこのあたりまで、平林寺の寺領のようなものだったのでしょう。


左:市古夏生・鈴木健一校訂 ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会4』 筑摩書房p.313より転載
右:現在の「野火止大門」交差点 平林寺方向
この石柱が当時のものそのままなのか、あるいは、補修・復元し代がわりしたものかは分りませんが、「金鳳山平林禅寺」の面の裏には
「寛延三歳(次)庚午季夏之日
山本氏子(従)方(就)謹建」
と刻まれています。( )内は私には読めない文字。
年表をみると、寛延三年は、1750年のようです。

現在の交差点は、名所図会の感じと程遠いですが、現在の平林寺周辺で、この絵をイメージして写真を撮ってみました。


<左:新座市役所前。画面右が平林寺の林;
右:大門通りから平林寺の奥に走る「非常道路」。総門から150m離れたところにあります>
○野火止用水の資料さがし
●新座市歴史民俗資料館
平林寺に参詣する前に、新座市歴史民俗資料館に寄ってみました。
野火止用水について、職員(学芸員)の方から約1時間説明を聞きました。

<新座市のページでは、歴史民俗資料館の外観写真、案内地図がありません。さびしいので載せておきます。写真をクリックすると、敷地に立っている新座市文化財案内の地図が表示されます。>
伺った説明と、展示資料で、面白かった点をいくつかピックアップしてみます。
1.平林寺は、総門から奥に進むと次第に土地が高くなっていきます(ざっと見た感じで10-20mくらい上がっています)が、それは、この部分だけ、下末吉層が残っているためで、その分だけ周囲(下末吉層が残っていない)より高いのだそうです。
この高さは、平林寺西側の野火止用水散策路を通ると実感できます。また、境内の奥の方にある、業平塚の奥から、野火止用水散策路にむかって結構下り斜面になっているのがわかります。(ただしここから野火止用水は見えません)
2.平林寺のある野火止台地は、土地がやせていて、松平信綱の時代に野火止への入植が行われる以前には、アカマツやススキの原だったとのこと。また、入植後は、肥料源として雑木林が大切にされたとのこと。
現在の平林寺の境内林にもアカマツがけっこうあります。


<左:業平塚 右:業平塚の近くにひろがるアカマツ林>
ということで、名所図会「平林寺大門」に描かれている樹木の奥のほうはアカマツのようです。
3.野火止用水の昔の写真がいくつか展示されています。その中に「野火止用水その2」で述べた、街道(市場通り)の真中に用水が通っているものや、いろは樋の写真がありました。他に、昭和26年頃のものとして、志木駅近くを流れる用水などがありました。
●新座市立中央図書館
野火止用水の昔の写真として
・『志木市市制施行20周年記念 ふるさと写真集』志木市市制施行20周年記念事業市民実行委員会文化部会編
・『特別展 野火止用水 図録』東村山ふるさと歴史館 平成13年
などがありました。(図録は、現在東村山ふるさと歴史館で500円で頒布されています。)
清流復活事業については、
・『野火止用水清流対策調査報告書』新座市建設部昭和59年
・『野火止用水管理活用計画』新座市 新座市教育委員会 平成7年
などがありましたが、ざっと見たところ、流した水がどこに流れていくのかについての記載はありませんでした。
・『緑と清流 野火止用水の復活』埼玉県 埼玉県教育委員会 新座市 新座市教育委員会(記載内容は昭和62年度まで)というパンフレット中の地図に、唯一、「本流 流末処理 柳瀬川へ 平林寺堀 新河岸川へ」という記載がありました。
●新座市観光のページ
野火止用水散策マップがpdfファイルで入手できます。
http://www.niiza.net/pdf/nobidome_map01.pdf

<平林寺境内にある野火止塚>




















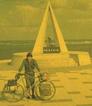





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます