江戸名所図会巻之三に「谷之口穴沢天神社」という絵があります。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.492-493

<三沢川の対岸から 撮影2006年11月>
右側の絵の中央部やや左に「巌窟」とあります。

この中をのぞくと、側壁から水がしたたっています。この部分の地質を真じかで観察できます。
「巌窟」の隣では湧水が汲めるようになっています。私が通るとき(土・日・休日)はいつもどなたかが水を汲んでいます。
今日(1/27)は、ここで簡単な水質測定をしてみました。
●測定結果(穴沢天神)●
測定時刻14時、水温14.6℃、気温10.5℃、pH6.6、電気伝導率200μS/cm(20mS/m)
丘陵の南側の吐玉水(白清水)でも同様な測定を行いました。
●測定結果(吐玉水)●
測定時刻14時30分、水温14.9℃、気温13.5℃、pH6.9、電気伝導率210μS/cm(21mS/m)
電気伝導率は結構面白い指標となるので、後日、その「面白さ」を紹介してみます。

ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会3』市古夏生・鈴木健一校訂 筑摩書房pp.492-493

<三沢川の対岸から 撮影2006年11月>
右側の絵の中央部やや左に「巌窟」とあります。

この中をのぞくと、側壁から水がしたたっています。この部分の地質を真じかで観察できます。
「巌窟」の隣では湧水が汲めるようになっています。私が通るとき(土・日・休日)はいつもどなたかが水を汲んでいます。
今日(1/27)は、ここで簡単な水質測定をしてみました。
●測定結果(穴沢天神)●
測定時刻14時、水温14.6℃、気温10.5℃、pH6.6、電気伝導率200μS/cm(20mS/m)
丘陵の南側の吐玉水(白清水)でも同様な測定を行いました。
●測定結果(吐玉水)●
測定時刻14時30分、水温14.9℃、気温13.5℃、pH6.9、電気伝導率210μS/cm(21mS/m)
電気伝導率は結構面白い指標となるので、後日、その「面白さ」を紹介してみます。




















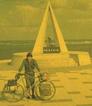





この二つの穴は、奥で繋がっています。
奥には確か、
弁天様が奉られていた記憶があります。
そういえば、近くに弁天洞窟がありますね。
>電気伝導率
面白そうな名前ですね。
興味しんしんです。
kampeitaさんが紹介してくれた、『大栗川と乞田川』小林宏一著p.100に「永山にあった湿地岩入りの池は、昭和43年・・・あっという間に埋め立てられてしまった。トキソウ、サギスゲ、モウセンゴケなどがあった。」という記述がありますが、このトキソウ、サギスゲ、モウセンゴケなどの生育条件に関係する話です。