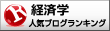足利フラワー・パーク
年若い中国人の妻と結婚し、埼玉県の地方都市に住まいを移して間もないころのことだった。いまから十数年前である。
彼女が外国人登録証の事務手続きのために市役所に行ったとき、そこのカウンターの片隅においてあった、外国人に日本語を教えるボランティア団体の案内のチラシがたまたま目に入り、それを持ち帰ってきた。行ったものかどうか迷っている様子だったので、私は、とにかくまあ行ってみたらいいんじゃないの、タダだしね、とアドバイスしたのだった。それでは、ということでその数日後、彼女は、市役所内で実施されている日本語講座に参加した。それから三年間ほどまじめにそこに通い続けたのではなかったか。
その講座を主催していたボランティア団体の女性リーダーのNさんは、なぜだか妻とウマが合ったらしく、実の娘のように妻を可愛がってくれた。親身になっていろいろと相談に乗ってくれたのだ。その分、妻はNさんの厳しい忠告を受けたこともあったようだ。日本人の常識感覚からはずれた振る舞いを率直に指摘されたこともあったのである。外国人である妻が日本で生きていくことを心底おもいやっているからこそできることであると私はそのとき思ったし、今でもそう思っている。
一つだけ、例をあげておこう。
市会議員を交えたある公的な集まりで、妻は周りの人たちに私の個人営業者としての名刺を少なからず配った。中国では当たり前の振る舞いらしい。ところが日本でそうすることは、若干ニュアンスが違ってくる。個人的な営利のために、そのボランティア組織に参加している、という意味合いになってしまうのだ。そこを妻は、普段は優しいNさんからキツく指摘されたのである。妻は、そういう「仕打ち」に対して、通常であれば決して耐えられない。耐えられないところを我慢するので、家に帰ってきてから私にキツく当たる。ところが、その時だけは妙にしおらしかったのだ。よほど、妻はNさんを信頼していたのだろう。そう判断するよりほかにない。
Nさんは、当時齢六十をとうに越えていたのではなかったか。お年を召されてはいるものの、若いころはさぞかし美人であったことだろうと思われた。色白で品のよい銀ぷち眼鏡をかけた、高価な和服のよく似合いそうな、どう見ても上流階級の女性だった。事実、Nさんの旦那さんは日本大使館職員として長らく旧ソ連に赴任していたという。妻が日本語講座に参加したときには、すでに退官して久しかった。妻によれば、旦那さんが言葉を発することはまれで、Nさんに影のように寄り添っている人だったという。二人は子宝にはあまり恵まれず、四十代の独身の一人息子が京都大学で教鞭をとっているとのことだった。
妻が日本語講座に参加しなくなってからは、年賀状のやり取りだけの付き合いになったのではあるが、Nさんの年賀状の走り書きに妻の身を案じる心使いが傍目にも感じられた。
ある年の年末、Nさんの旦那さんの差出名で、年賀状を差し控える旨のはがきが舞い込んだ。Nさんが急死したのだ。死因は、胃癌だという。妻に心配をかけないよう長らく病名を伏せていたのだろう。妻は大粒の涙をこぼしながらご自宅に電話をかけて、弔問の約束をした。
隣町の住宅街の一角にある故Nさんの瀟洒な一軒家を訪ねて、仏壇のある部屋でご焼香を済ませた後、妻はリビングに案内された。Nさんの妹さんと旦那さんが同席したらしい。庭先につつじの花が緑の地のなかに白、赤、ピンクときれいに咲いた晩春の穏やかな午後だった。Nさんの、おっとりとした感じの妹さんがおもむろに口を開いた。
「これは私たちみんなの前で起こったことなのよ。」
妹さんは、Nさんの臨終の様子を妻に話してくれたのだ。
病室には、病院関係者以外に、妹さんとNさんの旦那さんと一人息子の三人がいたという。臨終という抜き差しならない事態に固唾を飲む彼らの目の前で、Nさんの顔に著しい変化が生じはじめた。
穏やかなその顔がいつの間にか老衰してNさんの、すでに他界した祖母そっくりになったのだ。居合わせた人たちはあまりのことに声が出なかった。心のなかではみな「おばあちゃん」とつぶやいた。それだけではない。次に、小刻みな皺(しわ)がみるみるとれて母親そっくりになり、さらに、肌の色艶が輝くほどによくなって新婚時代のNさんの若々しくて美しい顔になり、今度はその顔がどんどん若返って、生まれてくる孫の幼い顔になり、最後にいまのNさんの顔に戻ってそのまま絶命したというのだ。居合わせた三人は、目を瞠って腰を抜かさんばかりだったという。普段はおとなしいNさんの旦那さんにいたっては、事の展開に頭がついていかず、気が動天して、やおらおいおい泣き出した。百面相の最後から二番目の顔が「生まれてくる孫」だと、なぜか居合わせたみんなが分かったそうだ。妻の話しっぷりから察するに、彼らが特別迷信深い人であるという感じはしない。
その半年後、今度はNさんの息子さんの差出名で、Nさんの旦那さんの訃報を知らせるはがきが舞いこんだ。Nさんに影のように寄り添っている人、という妻の人物評は的を射ていたのだった。旦那さんは、Nさんなしにこの世に生き続けていられるような人ではなかったのだろう。あの世からしょぼくれた旦那さんの姿を見るに見かねて早くおいでとNさんが手招きしたのに、旦那さんは微笑みながら黙って応じたのではないだろうか。
それから何年たっただろう。風の便りに、Nさんの一人息子が、ご両親の住まいを二人が生きていたときのままにしているらしいという噂を妻は耳にした。息子さんは仕事の関係でいまも京都に住んでいるので、ご両親の住まいの維持管理はNさんの妹さんに依頼しているという。いまだに、息子さんはご両親の死をどうしても受け入れることができないのだろう。特にNさんの臨終における言葉なき鮮烈なメッセージは、息子さんの心の最深部に届いたはずである。生命は、生きている者のさかしらを超えてどうしようもなく連続しようとするものなのだ、人はそれを避けようもなく志向してしまうのだ、というそれこそ命を賭けたメッセージが、である。息子さんは、相変わらず独身であると、これも風の便りに、耳に入ってきたのだった。物事は思うようには進まないものらしい。
あるとき、Nさんの臨終のありさまの話を思い出して、私が「それにしてもほんとうに不思議な話だね。」 と妻に言うと、彼女は「別に不思議でも何でもない。そういうものだ。」 と平然とした顔で言った。そうして、なぜそんな当たり前のことを不思議がるのだといわんばかりの怪訝な表情で私の顔をのぞきこむのだった。その妙にすっきりと納得した表情に、私は女なるものが抱え持っている薄気味悪さのようなものを、半ば畏敬の念をこめて感じた。子を孕む可能性を身体に生々しく織り込んだ性の、理不尽なものでさえ平然と飲み込んでしまう計測不能の懐の深さの所在がそこに示されているように感じられたのである。女どうしの了解の仕方には、男の私からすればどうにもわからないところがある。
私とNさんとは知人と呼べるほどのものでさえないあわあわした関係ではあったのだが、女の、この世に生きる思いの独特な奥深さを物語るエピソードとして忘れ得なかったので書き記すことにした。