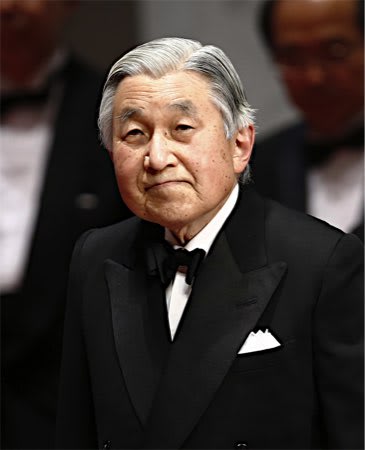今年の夏に公開された「シン・ゴジラ」と「君の名は。」の二作品は、既に社会現象と言える盛り上がりを見せている。
「シン・ゴジラ」は公開から一ヶ月ほどで興行収入は50億円を突破し、「君の名は。」も既に初動の興行収入だけで、12億円を超えている。
インターネットでは、多くの人間が、それら二作品について、この場面はこうではないか、あの結末はこういう意味があるのではないか、と言った具合で、考察し、議論を重ねている。
私は1999年生まれなので、「新世紀エヴァンゲリオン」放送当時、オタク達が行っていた、よく言えば真剣な、悪く言えば大袈裟な議論、考察についてはよく知らないが、当時もこういった雰囲気だったのだろうか。
「シン・ゴジラ」について言えば、東浩紀氏や石破茂氏、あるいは田原総一郎氏などが、その作品の持つ構造や、テーマ性に言及し、その議論の広がりは、いよいよ大規模なものになりつつある。
私自身、「シン・ゴジラ」については、その物語や、描写の数々に不思議な感動を覚え、興奮して鑑賞した。
既に多くの人々が指摘しているように「シン・ゴジラ」は、災害映画だと言える。自衛隊、官邸、米国、これらの組織、団体がいかに動き、そして、いかなる相関関係にあるのかを、ゴジラという究極のフィクションを用いて、鮮やかに描いている。「シン・ゴジラ」を観て、我々日本人はその内面に持ち合わせている生々しい恐怖の感情を想起させられる。
だからこそ、あれだけインターネット上で、熱い議論が行われているだと言っても過言ではないだろう。
一方で、 「君の名は。」は、「シン・ゴジラ」の対極に位置する作品だと言える。そもそも「君の名は。」では、「シン・ゴジラ」において、排除された恋愛というモチーフが、物語の主題となっているし、劇中で物語の軸となる隕石の衝突から人々を守ろうとするのは、政治家や官僚といった大人ではなく、あくまで幼さが残る思春期の高校生たちである。「君の名は。」はどこまでも非治者的、非統治者的な作品だと言える。
上記の点などで「君の名は。」と「シン・ゴジラ」は、その物語の構造やモチーフにおいて対極に位置している。しかし、自然災害を執拗と言っても過言ではないほど丁寧に描写しているという点で、両者は共通している。
東京の都会の少年、瀧と、同い年である岐阜の田舎の少女、三葉が、夢の中で、身体が 入れ替わり、入れ替わりを繰り返すうちに、両者に恋愛感情が生まれてくる、というのが、「君の名は。」における序盤までのストーリーである。
上記の、まるでラブコメの王道をいくかのようなストーリーは、彗星が地球に最接近するという事態を前に、変化していく。
それは、なぜかと言えば、瀧が追い求め、探していた少女、三葉が、彗星の破片である隕石の衝突によって三年前に亡くなっていたからだ。
夢の中で入れ替わっていた、そして、繰り返される入れ替わりの中で愛しく思うようになっていた三葉が、隕石の衝突によって既に死亡していたという事態に、瀧は動揺を隠せず、もがくように三葉を追い求める。それより先の詳しいストーリー展開については、是非、劇場で確かめてもらいたいが、最終的に瀧は、三葉を救うことに成功する。
この「君の名は。」の後半において示されているこの三葉の救済という展開は、ある意味で「慰霊」だと言える。
一度死んだ人間は当然、生き返ることはないし、人間は時間を遡ることは不可能である。だからこそ、死という事態、状態はその重みを増し、我々の精神、あるいは社会に大きな影響を与えている。多くの人々が死ねば、いくら赤の他人だとしても、良い気分はしないし、まして、愛しい人間の死は、時として生きている人間の精神を破壊させる。死は突然であれば、あるほど、重大で残酷なものになる。
そして、その死の重大性、残酷性が一気に生きてる我々に襲いかかってくるのは、現代日本においては、その多くが自然災害である。
五年前の東日本大震災の際は、一万人を超える人々が一瞬にして、命を奪われた。未だに遺体すら見つかっていない死者は少なくない。仮に遺体が見つかっても、原型を留めていることは稀だと云う。
そんな自然災害の後、遺された生者は、死者の霊、あるいは魂、精神といったものを慰霊し、慰める。なぜ慰霊をするのか-慰霊という営為の意味については、個々人に思うところがあるだろうし、一概にこうである、といった具合に断定するのは乱暴だが、多くの場合、非業の死を迎えた死者を、少しでも救済したいという気持ちがあるということは、否定し難いのではないか。事実、種々の慰霊式や追悼式で述べられ、あるいは慰霊塔などの碑文には、「安らかにお眠り下さい」といった趣旨の文言が挿入されていることが多い。私は民俗学や宗教学に詳しくないが、これらの文言に、死者の魂がせめてあの世では幸福であってもらいたい、という魂の彼岸での救済を希望する意味合いが含まれていることは、明らかだろう。
そして、その魂の救済という、「慰霊」をフィクションの中で行っているのが、「君の名は。」だと言えるのではないだろうか。
非業の死を遂げた三葉をどうにかして、救済したい。瀧の純粋な想いに、観客は次第に自身の感情を同化させていく。そして、途中で、入れ替わりが戻った後は、三葉に感情を同化させる。
これほどまでに、「君の名は。」が感動的であるのは、RADWIMPSの美しい音楽や、美しい背景がその一因だと、もちろん言えるだろうが、我々が果たすことができない、死者を復活させるという究極の「慰霊」、魂の救済の理想形を、「君の名は。」に見いだしているのではないか。
「もし、私があの時、ああしていたらあの人は救うことができたかもしれない」「もしあの時ああしていたら彼女は幸せな最期を迎えたのかもしれない」。我々が何処かの地点で経験する、肉感的な死、愛しい人の死を前にして、我々がとっさに考える、夢想、妄想。それを叶えた物語、それが「君の名は。」という作品ではないだろうか。
夢想、妄想を叶えた物語と言えば、悪いイメージを抱く方も居るかもしれない。確かに、観客の願望を叶えるというあり方は、観客に甘えていると言えるかもしれない。しかし、「君の名は。」において、絶対に不可能な死者の救済の理想形を提示することで、監督の新海誠氏は、観客を救済しようとしたのではないか。いや、それは生き方と言っていいかもしれない。死者に相対した後の生者の生き方。そういった我々生者の生き方に、希望を与えようとしたのかもしれない。実際、最期の、二十代になった瀧と三葉が出会うシーンは、それまでの新海誠氏の「秒速5センチメートル」といった作品とは明確に異なった、いわゆる「運命的な出会い」と呼ぶに相応しい明るい最期を迎えている。
この最期は、我々に希望を与える。そして、その希望は死者の過去ではなく、生者の未来に向いている。
死者を救済し、尚且つ生者を救済する-新海誠氏の才能に驚くばかりだ。