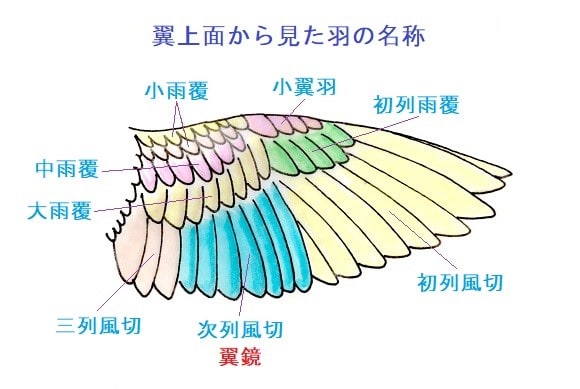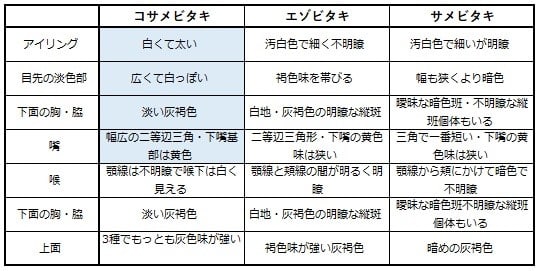今回はアカゲラ。代表的なキツツキの仲間である。キツツキには子供のころから何故か特別な思いがあった気がするが、キツツキという名前の鳥はいなくて、アカゲラ・アオゲラ・コゲラなどのことだと知ったのはだいぶ後になってからであった。
その特別な思いというのは、やはり木の幹をつつき穴を開けて、中の昆虫を探して食べるというその習性がおもしろく感じられたためだろうと思う。
このキツツキの仲間が自宅周辺の木に来ているのを見かけることはあったが、餌台に来ることは予想していなかった。
もうだいぶ前にこのアカゲラがシジュウカラなどのカラの仲間に混じってやってきたのであるが、後にも先にも、餌台に来たのはこの時だけのことである。シジュウカラにと思って用意してあった牛脂を食べに来たのであった。
アカゲラによく似た種に、オオアカゲラとコアカゲラがいると図鑑に記されているが、今回紹介する種は羽色や大きさからアカゲラと判断している。
いつもの原色日本鳥類図鑑(小林桂助著、1973年保育社発行)には、アカゲラは次のように記されている。
「形態 黒、白、赤の配色顕著なキツツキ。嘴峰26~29mm、翼長124~136mm、尾長77~90mm、跗蹠21~23mm。額白く以下の背面は黒。肩羽の先端白く背に大きな白紋を形成する。♂は後頸鮮紅色であるが♀はこれを欠く。尾は中央のものは黒、その他は白く黒色黄はんがある。翼は黒く白色黄はんあり。顔と下面とは汚白色で顎線は太く黒い。頸側にも黒帯がある。下腹部と下尾筒とは美しい鮮紅色。幼鳥は♂♀共頭上全体が紅色である。
生態 山地の森林中に生息する。飛行は波状。キョッ、キョッとなき時々嘴で樹幹を打ちカラ、カラ、カラ・・・・と音を立てることは他のキツツキ類と同様である。
分布 本州(中部以北には普通であるが西日本には少ない)・対馬に生息繁殖し、八丈島でも採集されたことがある。」
次の写真は牛脂を食べに餌台に来たアカゲラで、長い間餌台にとどまり牛脂をつついていた。この間シジュウカラ、ヒガラ、コガラそしてヤマガラはじっと近くで待機していたのであろう、アカゲラがいなくなると次々と交代しながらやってきては牛脂をついばんでいた。
このアカゲラ、一部後頭部の赤が写っていることから♂と判定することができる。
くちばしから胸と後頭部に伸びる黒い帯を顎線と呼ぶが、最後の写真などこれが役者の隈取りの文様のように見えておかしい。








自宅庭の餌台に来て牛脂をつつくアカゲラ♂(2016.3.13 撮影)
このアカゲラがいなくなると、早速いつものカラ達が次々と来ては大好きな牛脂をつつき始めた。面白いことにカラ達も同時には来ないで、交代しながら牛脂を食べに来るのである。

餌台の牛脂をつつくシジュウカラ(2016.3.13 撮影)

餌台の牛脂をつつくヒガラ(201x.3.13 撮影)

餌台の牛脂をつつくコガラ(2016.3.13 撮影)

餌台の牛脂をつつくヤマガラ(2016.3.13 撮影)
自宅庭のモミジに来た時の写真は次のようである。

庭のモミジの枝に止まるアカゲラ♂ 1/2 (2019.12.26 撮影)

庭のモミジの枝に止まるアカゲラ♂ 2/2 (2019.12.26 撮影)
キツツキの仲間はくちばしと長い舌を使って樹皮の内部やすき間にいる昆虫を食べたり、幹につつき掘った巣穴を作るとされる。
この巣作りに関して、「軽井沢のホントの自然」(2012年 ほおずき書籍発行)には次のような記述がある。
「・・・キツツキのアカゲラは、やわらかい枯木を選んで穴を掘り、巣をつくります。気に入らなければ、1本の木にいくつもの穴を掘り直すことがあります。そして子育てが終わると、来年はまた別の場所に新しく穴を掘ります。・・・近年の研究では、アカゲラは枯木に好んで巣穴を掘り、翌年はコムクドリなどがそこを利用し、さらに3年目以降になると、木もいよいよ朽ちて倒れる率が高まるそうです。・・・
森の新陳代謝のためには、若い木、壮年の木、老齢の木が適度に混じっていることが必要です。そして、そこに枯れた木が立っているのも、健康な森の姿なのです。・・・」
別荘地では、こうした枯木を放置することは危険なので、取り除くことが行われるが、そのためかどうか、別荘の壁面に穴を開けるキツツキも結構いる。
しばらく使われることがなく、放置されている別荘などでは、壁面に十カ所以上もの穴があけられているのを見ることがある。
時々聞かれるあのカラ、カラ、カラ・・・という木の幹を打つ音はエサを探している時の音なのか、巣穴を開けようとしている時の音なのかと思って調べてみると、そのどちらでもなく、繁殖期に縄張りを主張したり、♂の場合♀へのアピールをするためのものだという。ドラミングと呼ばれている。この速さは毎秒20回、頭部への衝撃の強さは20Gに及ぶとされる。
今年の1月から雲場池に散歩に出かけるようになったが、そこでもアカゲラをよく見かけ、ドラミングが聞こえてくることもあった。
静かな朝、カラ、カラ、カラ・・・と減衰して響くこの音を聞くのはなかなかいいものである。次の写真はこの雲場池周辺でのもの。

雲場池で見たアカゲラ♀ 1/6 (2020.3.16 撮影)

雲場池で見たアカゲラ 2/6 (2020.4.2 撮影)

雲場池で見たアカゲラ♂ 3/6 (2020.3.15 撮影)

雲場池で見たアカゲラ♂ 4/6 (2020.3.15 撮影)

雲場池で見たアカゲラ 5/6 (2020.1.29 撮影)
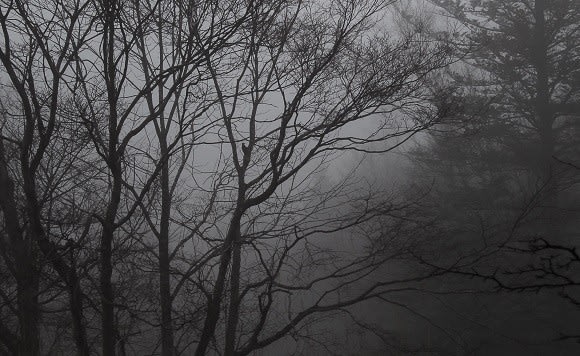
雲場池で見たアカゲラ 6/6 (2020.4.17 撮影)