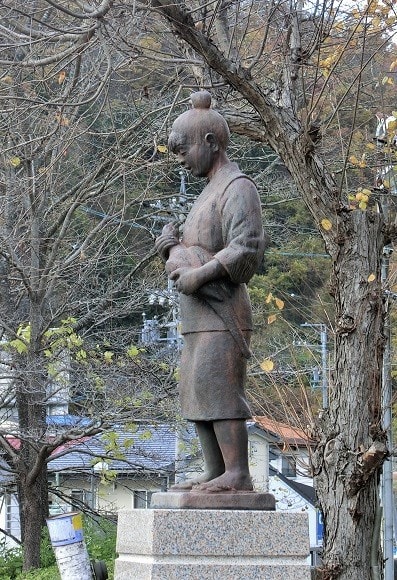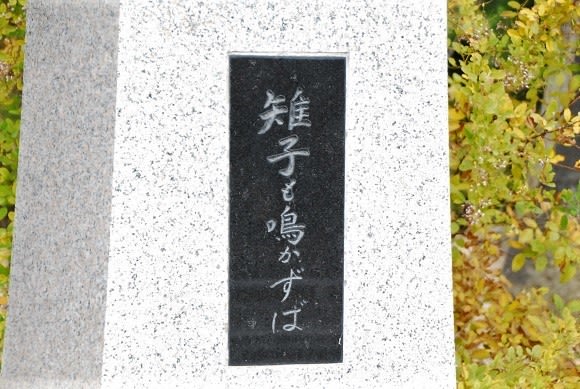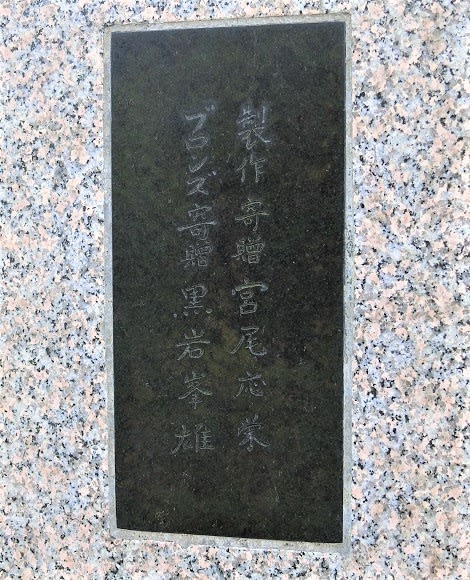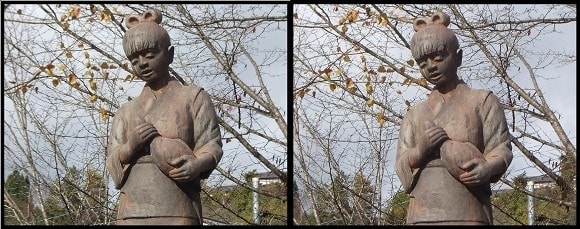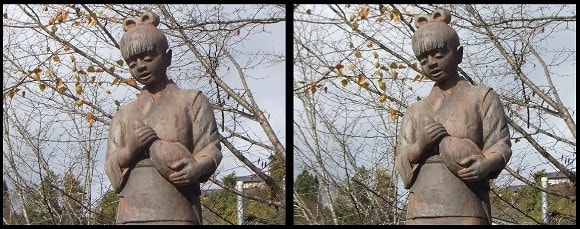今回はダイサギ。シラサギと総称される3種のうち最大のもので、よく似た種にチュウサギ、コサギがいる。
雲場池でこの1年ほどの間に見かけたのは、このうちのダイサギだけである。チュウサギととてもよく似ていて、同定の特徴とされる嘴の色、足の色、眼先の色なども季節により変化するので判りづらい。写真から、口角が眼の後方まで伸びていると思えるので、ここではダイサギと判定した。
このダイサギには2種の亜種がいるとされるが、ダイサギ(オオダイサギ)とチュウダイサギの2種を紹介している図鑑「日本の鳥550・水辺の鳥」(2000年 文一総合出版発行)もあれば、ダイサギだけの紹介で、チュウダイサギにはまったく触れていない図鑑「野鳥観察図鑑」(2005年 成美堂出版発行)もある。
いつも参考にしているやや古い「原色日本鳥類図鑑」(小林桂助著 1973年保育者発行)ではチュウダイサギの方を主に取り上げ、ダイサギを亜種として分類しているので、ますます混乱するのである。
「原色日本鳥類図鑑」のチュウダイサギの項を紹介すると、次のようである。
「【形態】我国の白サギ中最大。嘴峰100~117mm.翼長337~394mm.尾長127~163mm.跗蹠136~165mm。
【生態】夏鳥として我国に渡来し近畿地方の御陵の森にはチュウサギ、コサギ、ゴイサギ、アマサギ、アオサギなどに混じって集団営巣するものが多い。営巣地から4km以上もはなれた海岸の干潟や広い田などにてえさをとる。飛行の翼動は緩慢である。本種は広く中国南部・馬来諸島・印度支那半島・印度・濠州などに分布し我国で繁殖した大部分のものは冬季これらの地方に渡去する。
【分布】本州・九州で繁殖し北海道・伊豆七島・四国・奄美大島などにも渡来する。
【亜種】ダイサギは一層大形(嘴峰109~138mm.翼長400~465mm.尾長140~185mm.跗蹠148~1215mm.)であり、我国には冬鳥として少数渡来するにすぎない。」
一方、「日本の鳥550・水辺の鳥」のダイサギの項を見ると次の解説がある。
「日本では2亜種の記録があり、亜種ダイサギ(オオダイサギ)は西南シベリア以西のユーラシア大陸で繁殖し、日本には冬鳥として飛来。亜種チュウダイサギは夏鳥として本州・四国・九州で繁殖し、一部は越冬する。」
こうした記述と、前記のような口角付近の特徴から、私が撮影したのは冬鳥のダイサギであろうと判断したのであった。
ところで、シラサギというと姫路城の別名白鷺城をすぐに思い浮かべるが、私はそのほかに2つの出来事のことを懐かしく思いだす。
ひとつは、小学生の頃の話であるが、当時住んでいた地域には白鷺公園と呼ばれている公園があった。夏によく「とりもち」を塗った竹竿を持ってセミ取りに出かけた場所で、シラサギが住みついていたという記憶はないが、体育の授業で時々この公園までマラソンをしていた。
今、改めて地図を見ると小学校からの距離は600mほどで、記憶とはだいぶ違っている。当時は結構長い距離に感じたものであった。
この小学校の同級生にA君がいた。家が一番近い友達であったので、よく一緒に野球をしたりして遊んだ。運動神経のとても優れた人で、野球もうまかったが、クラスでも一番足が速く、運動会では花形であった。
恐らく5年生か6年生の頃のことと記憶しているが、そのA君は授業中に担任のY先生に注意されると、プイと教室を飛び出して、一目散に白鷺公園の方に向かって走り出すのであった。
先生に言われて、数名の同級生と共に私も後を追いかけて同じように白鷺公園に向かって走り出す。A君を説得し、連れ帰るためである。ただA君は足が速いのでなかなか追いつかないのであった。こうしたことが何度か繰り返されていたので、今でも同窓会での語り草になっている。
そのA君は中学校に進学してすぐに転校していったので、その後の消息は詳しくは知らないが、彼と親しかった同級生から聞いたところでは20歳を過ぎて間もなく病没したという。私の手元には法被・鉢巻き姿で地元の夏祭りの神輿を一緒に担いだ時の写真が残されているので、いつまでもそのままの姿で記憶に残っている。
もう一つのシラサギ談はずっと後年になってからの1995年頃のもので、広島県三次市に単身赴任していた時のものである。
三次市内の市街地から少し離れたところの道路沿いに、宗祐(むねすけ)池というため池があり、大きさは500mx200mほどの細長いものであった。この池の道路の対岸の林地に多くのシラサギなどが営巣していた。
そのシラサギ(多分コサギ)の写真を撮りたくて、日曜日の早朝、池に接する道路脇でしばらく撮影をしていたところ、私同様単身赴任で三次に来ていた職場の同僚3人(F氏、T氏、O氏)が車で通りかかり、声をかけられた。彼らはどこかにドライブに出かけるところであったらしい。
その時撮影した写真は、朝方で光量が十分でない時間帯だったこともあり、スローシャッターと手振れにより、まともなものではないが数百羽のシラサギが何かの拍子に一斉に飛び立つ様子が写っていて懐かしく、当時が思い出される。

広島県三次市にある宗祐池のシラサギの群れ(1995年頃撮影)
その翌日だったか、職場でO氏と話をしていて、前日のことになったときに彼から、「朝早くからあんなところで池をじっと見つめていたので、自殺でもしようとしているのかと思ったよ!」と言われて、そんなふうに見えていたのかと、こちらが驚いてしまった。このO氏は私と同年であったが、すでに10年ほど前に亡くなっている。
さて、シラサギにまつわるほろ苦い話題になったが、雲場池のシラサギは至って健康そのもの、元気である。
昨年3月に2度、雲場池の脇を流れる精進場川に単独でいるところを見かけた。そして昨年秋から直近まで、冬鳥として渡ってきたのであろう、何度も雲場池で見かけるようになった。今年は8羽ほどの群れで来ることもあり、撮影のチャンスも数回あったので、飛翔している姿など、たくさんの写真を撮ることができた。これらを以下に紹介する。

雲場池脇の精進場川のダイサギ(2020.3.14 撮影)

雲場池のダイサギ(2020.11.9 撮影)

雲場池脇の精進場川のダイサギ(2020.12.14 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.1 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.10 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.10 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.10 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.10 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.10 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.2.11 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.1.6 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.2.11 撮影)

雲場池のダイサギ(2021.2.11 撮影)
完