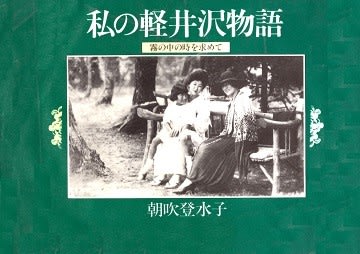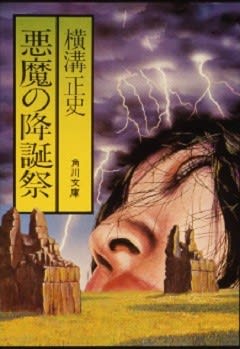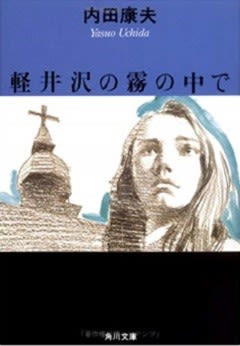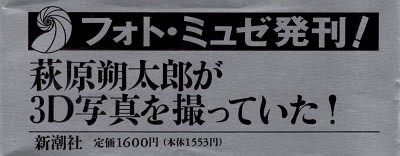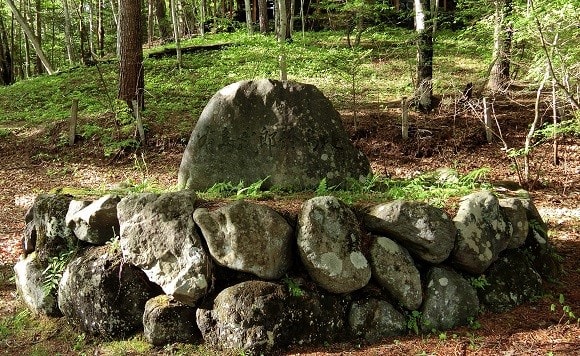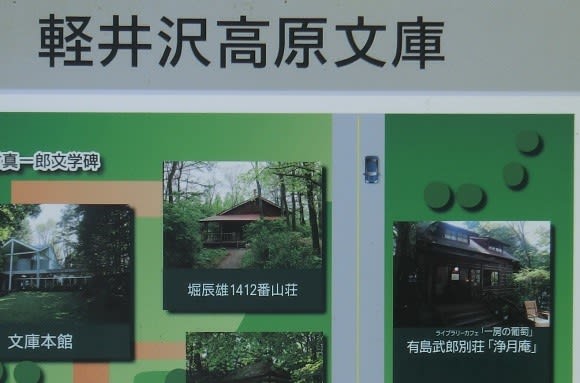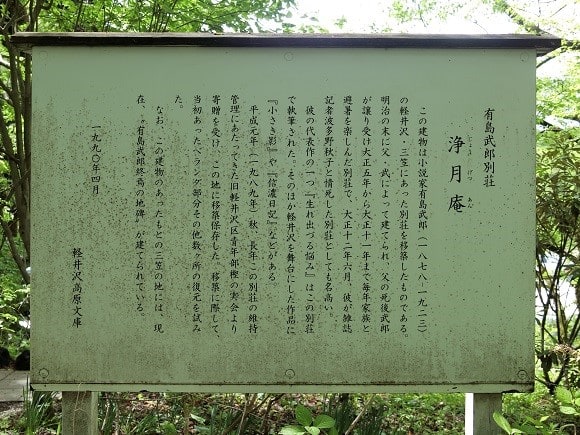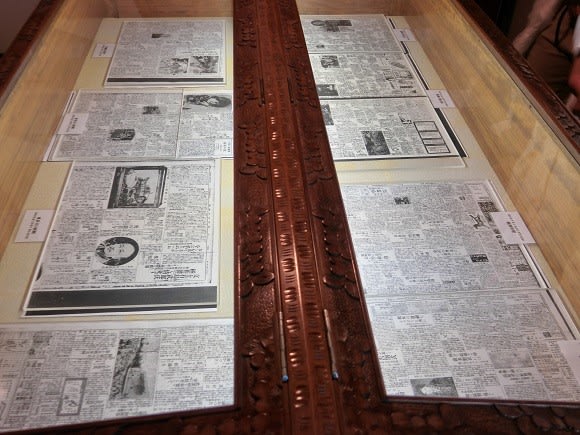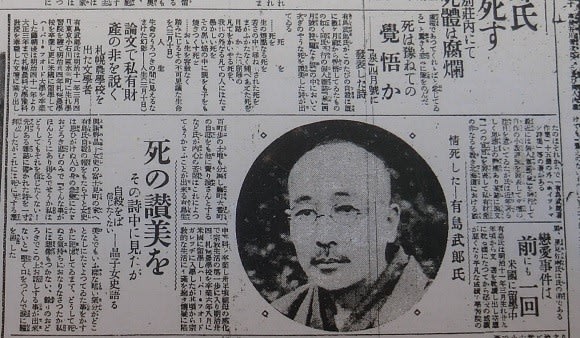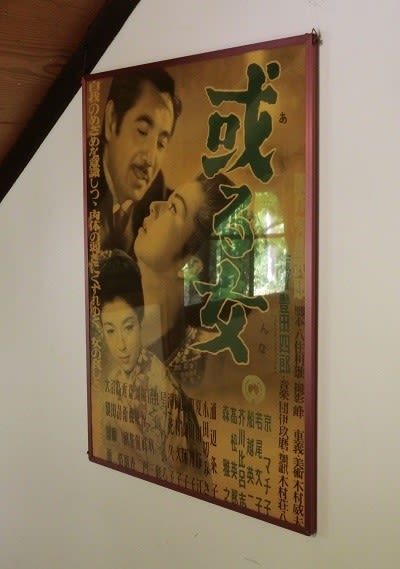市街地を車で走っていて、何か周囲の様子が違っていると感じることがあるが、それは電柱が取り払われて、電線や通信線が地中化されている時が多い。景観に与える電柱・電線の影響は大きいようである。軽井沢の町内でもこの無電柱化が順次進められている。
現在、無電柱化が完成しているのは、軽井沢駅入口から東雲交差点までの区間と、かつて旅籠が軒を連ねていた旧中山道の追分エリアで、共に2013年度までに工事が行われた。
軽井沢駅周辺では観光地としての景観向上のため、また、旧追分宿では石畳風の道路にするなど大規模な改良工事を行い、江戸時代の面影を演出するために行われている。
県佐久建設事務所は、続いて軽井沢本通りの東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーション前まで、580m区間の電線を地中に埋める工事計画を発表している。これによると、工事は2016年(平成28年)度に着手し、2019年(平成31年/令和元年)度の完成を目指している。事業費総額は4億円である。


軽井沢駅前から旧軽井沢銀座方面の無電柱化状況
2016年11月の住民説明会では、工事は原則、10~4月を中心とした閑散期のみ実施され、5区画にわけ東雲交差点から旧軽井沢方面へ向かって、中部電力サービスステーションまでの区間で実施し、都市下水路移設工事、上下水の移設、電線地中化工事、電柱撤去、舗装工事を行い完了する予定とされた。
最近、2019年9月にも住民への説明会が行われているが、それによると、今後、雨水を流す都市下水路を歩道から車道の地中に移設したのち、地中に送電線などを埋設する。車道幅を1m狭め、西側の歩道幅を現状の3.5mから4.5mに広げ、両側の歩道に自転車通行帯を設置する計画という。
さらに、旧軽井沢銀座通りも含め、サービスステーションより北側の無電柱化も、将来の構想に入っている。この工事が完成すれば、軽井沢の入り口である駅前から、旧軽井沢銀座通りまでの無電柱化が完成することになり、町の景観は大きく変化するものと期待される。

既に無電柱化工事が完了した軽井沢駅前から東雲交差点区間(2019.10.8 軽井沢駅側から撮影)

既に無電柱化工事が完了した軽井沢駅前から東雲交差点区間(2019.10.8 東雲交差点側から撮影)

現在無電柱化工事が進められている東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーションまでの区間(2019.10.8 東雲交差点側から撮影)

現在無電柱化工事が進められている東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーションまでの区間(2019.10.8 中部電力軽井沢サービスステーション側から撮影)

将来無電柱化の計画のある中部電力軽井沢サービスステーションから旧軽井沢銀座通り入り口までの区間(2019.10.8 中部電力軽井沢サービスステーション側から撮影)

将来無電柱化の計画のある中部電力軽井沢サービスステーションから旧軽井沢銀座通り入り口までの区間(2019.10.8 旧軽井沢銀座通り入り口側から撮影)

将来無電柱化の計画のある旧軽井沢銀座通り(2019.10.8 旧軽井沢銀座通り入り口側から撮影)

将来無電柱化の計画のある旧軽井沢銀座通り(2019.10.8 二手橋方面のつるや旅館側から撮影)
参考までに、上の最後の写真で、電柱や電線を写真上で消してみると次の様になる。なかなかすっきりとした景観になる。

前の写真の電柱や電線を写真上で消してみた
日本はかねてから、欧米はおろか、アジアの主要都市と比較しても無電柱化の割合は著しく低いことが指摘されている。こうした事態を打開し、「積極的に政府や民間等との連携・協力を図り、無電柱化のより一層の推進により、安全で快適な魅力のある地域社会と豊かな生活の形成に資することを目的」として、2015年に「無電柱化を推進する市区町村長の会」が設立された。軽井沢町もこれに参加している。
観光地としては、もっぱら景観の改善が目的となるが、果たして景観改善が地域経済にどの程度の効果をもたらすのか、また無電柱化のそれ以外のメリットにはどのようなものがあるのか見ておきたいと思う。
これまでに電柱の地中化を行った観光地としては、東京の銀座6丁目付近、 奈良県奈良市の三条通りなどがあり、景観改善と共に通行空間の確保が図られている。また、埼玉県川越市の川越一番街では、電柱・電線によって隠れていた蔵造りの町並がよみがえり、それまで年間150万人であった観光客数が400万人に増加しているという事例や、三重県伊勢市のおはらい町では、電柱・電線によって破壊されていた伊勢の伝統的な木造建築の町並みをよみがえらせた結果、1992年に約35万人まで落ち込んでいた通りの往来者は、1994年に200万人に急増し、2008年には400万人を超えるようになったという具体的な数字も見られる。
軽井沢駅の南側に広がるアウトレット・モール(プリンス・ショッピング・プラザ)は新しい施設であるが、ここも全域が無電柱化されている。
また、別荘地としての軽井沢にとっては、別荘地内の景観をよくし、ブランド価値を高めることは重要であり、このために限られたエリア内ではあるが、無電柱化が行われている例もある。同様のことは、全国にも見られ、兵庫県芦屋市の六麓荘町では、開発の当初からガス、水道のみならず電気、電話を地下に埋設するという構想の下に住宅地の造成が進められた結果、芦屋市でも最も高級な住宅地として知られているというし、奈良県奈良市の近鉄あやめ池住宅地では、「あやめ池」の地域価値を向上するために、一部エリアで共同溝を設けて電線等を地下に配置している。

無電柱化されているプリンス・ショッピング・プラザ (2019.10.8 撮影)
景観改善以外の電柱地下化のメリットとしては、むしろこちらの方が急務ではないかと思える位であるが、台風や地震といった災害時に電柱が倒れたり、垂れ下がった電線類が、消防車などの緊急用車両の通行の邪魔をする危険がなくなり、防災性が向上するという点が挙げられる。
このことは、今年千葉県を襲った台風15号による直接の被害と、それに伴う大規模な停電、そしてその後の電力供給の回復状況を見れば明らかである。阪神・淡路大震災では震度7の地域で、電柱の停電率は10.3%であったが、地中線は4.7%であり、電柱に対する地中線の被害率は45.6%と低かったと報じられている。
10月7日の読売新聞には、「電柱大国ニッポン」として日本の電柱数の多さが示されたが、それによると2017年度末の電柱数は3,585万本であり、今も毎年7万本づつ増加を続けているという。この多くの電柱が災害で倒れた数もまた示されているが、次のようである。
・1995年1月、阪神淡路大震災・・・電力 約4500本、通信 約3600本
・2003年9月、沖縄県宮古島市・・・電柱 800本
・2011年3月、東日本大震災・・・・・電力 約2万8000本、通信 約2万8000本
・2013年9月、竜巻・・・・・・・・・・・・・埼玉県越谷市 46本、千葉県野田市 5本
・2018年9月、台風21号・・・・・・・・・電柱 約1700本、停電最大 約260万戸
・2019年9月、台風15号・・・・・・・・・電柱 1000本超、停電最大 約93万4900戸
被害額の推定は示されていないが、いったいどれくらいになるのであろうか。
この記事には、日本と世界各都市の無電柱化率も比較して記されているが、それによると、
・ロンドン・・・・・・・・100%
・パリ・・・・・・・・・・・100%
・シンガポール・・・100%
・香港・・・・・・・・・・100%
・ハンブルグ・・・・ 95%
・ニューヨーク・・・ 83%
・ワシントン・・・・・ 65%
・ソウル・・・・・・・・ 49%
・ホーチミン・・・・・ 17%
であり、わが日本の主要都市の無電柱化率は、
・東京23区・・・ 7.8%
・大阪市・・・・・ 5.6%
・名古屋市・・・ 5.0%
・日本全体・・・ 1.2%
という数字である。彼我の差は一目瞭然である。次のような図も掲載されていた。

日本の都道府県別無電柱化率(2019.10.7 読売新聞から)
この図によると、無電柱化率が3%を超えているのは、東京都だけであり、2~3%は神奈川、岐阜、福井、大阪、兵庫の5府県、1~2%が23県、残る18府県では1%未満である。
このように無電柱化が日本で遅れている要因としては、「故障時の対応に時間がかかる」、「工事中の通行のへの妨げ」、「電線を地下化しても地上部の変圧器の場所は必要」といったことがあげられているが、やはり最大の要因は1kmあたり5.3億円とされるコストの問題であろう。現在、軽井沢で計画されている、前記の580m の区間の総費用は、約4億円とされているから、寒冷地での工事費用は更に割高になっていると思われる。
これに対しては、電線を埋める深さを浅くして、掘削量を減らしたり、土に代わって発泡スチロールを使って埋め戻し時間を減らすなどにより、工期短縮を図る工夫が取り入れられている。また、従来は通信への影響を避けるために、離れて埋めなければならないとされていた電力と通信のケーブルを同じ側溝状のボックスに埋めるなどのコスト対策も進められているという。
しかし、高速道路網や新幹線網、リニア鉄道建設などのことを考え合わせると、もう少しバランスのとれた国土のインフラ整備はできないものかと思う。
日本で最初に電線地中化が行われたのは、前出の兵庫県芦屋市に高級住宅街として造成された六麓荘町とされているが、これは90年も前の1928年のことであった。その後、1986年度から1998年度までに、全国で約3,400kmの地中化が達成されているというが、このままのペースでいけば、日本全体の電線地中化が完了するまでに2700年かかるという計算もある。
東京都知事になった小池百合子氏が発足人となって作られた無電柱化推進議員連盟、無電柱化小委員会により作成された「無電柱化推進法案」が2016年12月9日に無電柱化の推進に関する法律として成立している。また、東京都と大阪府もそれぞれ2018年2月と2018年3月に「(仮称)東京都無電柱化計画」(素案)、「(仮称)大阪府無電柱化推進計画」(素案)を発表している。
国土交通省は、上記法律を受けてであろうか、災害時に緊急車両が走る幹線道路では、2016年以降電柱を新設することを禁じているし、災害時の輸送で重要となる道路を対象として、電力会社や通信会社に電柱を撤去させる制度を新設すると発表している。
地球温暖化が進む中、台風15号のあとにはまだまだ大型で強力な台風が日本に押し寄せてくる気配である。千葉県のような住宅被害や大規模停電が、再び起きなければよいがと願わずにはいられない。
現在、無電柱化が完成しているのは、軽井沢駅入口から東雲交差点までの区間と、かつて旅籠が軒を連ねていた旧中山道の追分エリアで、共に2013年度までに工事が行われた。
軽井沢駅周辺では観光地としての景観向上のため、また、旧追分宿では石畳風の道路にするなど大規模な改良工事を行い、江戸時代の面影を演出するために行われている。
県佐久建設事務所は、続いて軽井沢本通りの東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーション前まで、580m区間の電線を地中に埋める工事計画を発表している。これによると、工事は2016年(平成28年)度に着手し、2019年(平成31年/令和元年)度の完成を目指している。事業費総額は4億円である。


軽井沢駅前から旧軽井沢銀座方面の無電柱化状況
2016年11月の住民説明会では、工事は原則、10~4月を中心とした閑散期のみ実施され、5区画にわけ東雲交差点から旧軽井沢方面へ向かって、中部電力サービスステーションまでの区間で実施し、都市下水路移設工事、上下水の移設、電線地中化工事、電柱撤去、舗装工事を行い完了する予定とされた。
最近、2019年9月にも住民への説明会が行われているが、それによると、今後、雨水を流す都市下水路を歩道から車道の地中に移設したのち、地中に送電線などを埋設する。車道幅を1m狭め、西側の歩道幅を現状の3.5mから4.5mに広げ、両側の歩道に自転車通行帯を設置する計画という。
さらに、旧軽井沢銀座通りも含め、サービスステーションより北側の無電柱化も、将来の構想に入っている。この工事が完成すれば、軽井沢の入り口である駅前から、旧軽井沢銀座通りまでの無電柱化が完成することになり、町の景観は大きく変化するものと期待される。

既に無電柱化工事が完了した軽井沢駅前から東雲交差点区間(2019.10.8 軽井沢駅側から撮影)

既に無電柱化工事が完了した軽井沢駅前から東雲交差点区間(2019.10.8 東雲交差点側から撮影)

現在無電柱化工事が進められている東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーションまでの区間(2019.10.8 東雲交差点側から撮影)

現在無電柱化工事が進められている東雲交差点から中部電力軽井沢サービスステーションまでの区間(2019.10.8 中部電力軽井沢サービスステーション側から撮影)

将来無電柱化の計画のある中部電力軽井沢サービスステーションから旧軽井沢銀座通り入り口までの区間(2019.10.8 中部電力軽井沢サービスステーション側から撮影)

将来無電柱化の計画のある中部電力軽井沢サービスステーションから旧軽井沢銀座通り入り口までの区間(2019.10.8 旧軽井沢銀座通り入り口側から撮影)

将来無電柱化の計画のある旧軽井沢銀座通り(2019.10.8 旧軽井沢銀座通り入り口側から撮影)

将来無電柱化の計画のある旧軽井沢銀座通り(2019.10.8 二手橋方面のつるや旅館側から撮影)
参考までに、上の最後の写真で、電柱や電線を写真上で消してみると次の様になる。なかなかすっきりとした景観になる。

前の写真の電柱や電線を写真上で消してみた
日本はかねてから、欧米はおろか、アジアの主要都市と比較しても無電柱化の割合は著しく低いことが指摘されている。こうした事態を打開し、「積極的に政府や民間等との連携・協力を図り、無電柱化のより一層の推進により、安全で快適な魅力のある地域社会と豊かな生活の形成に資することを目的」として、2015年に「無電柱化を推進する市区町村長の会」が設立された。軽井沢町もこれに参加している。
観光地としては、もっぱら景観の改善が目的となるが、果たして景観改善が地域経済にどの程度の効果をもたらすのか、また無電柱化のそれ以外のメリットにはどのようなものがあるのか見ておきたいと思う。
これまでに電柱の地中化を行った観光地としては、東京の銀座6丁目付近、 奈良県奈良市の三条通りなどがあり、景観改善と共に通行空間の確保が図られている。また、埼玉県川越市の川越一番街では、電柱・電線によって隠れていた蔵造りの町並がよみがえり、それまで年間150万人であった観光客数が400万人に増加しているという事例や、三重県伊勢市のおはらい町では、電柱・電線によって破壊されていた伊勢の伝統的な木造建築の町並みをよみがえらせた結果、1992年に約35万人まで落ち込んでいた通りの往来者は、1994年に200万人に急増し、2008年には400万人を超えるようになったという具体的な数字も見られる。
軽井沢駅の南側に広がるアウトレット・モール(プリンス・ショッピング・プラザ)は新しい施設であるが、ここも全域が無電柱化されている。
また、別荘地としての軽井沢にとっては、別荘地内の景観をよくし、ブランド価値を高めることは重要であり、このために限られたエリア内ではあるが、無電柱化が行われている例もある。同様のことは、全国にも見られ、兵庫県芦屋市の六麓荘町では、開発の当初からガス、水道のみならず電気、電話を地下に埋設するという構想の下に住宅地の造成が進められた結果、芦屋市でも最も高級な住宅地として知られているというし、奈良県奈良市の近鉄あやめ池住宅地では、「あやめ池」の地域価値を向上するために、一部エリアで共同溝を設けて電線等を地下に配置している。

無電柱化されているプリンス・ショッピング・プラザ (2019.10.8 撮影)
景観改善以外の電柱地下化のメリットとしては、むしろこちらの方が急務ではないかと思える位であるが、台風や地震といった災害時に電柱が倒れたり、垂れ下がった電線類が、消防車などの緊急用車両の通行の邪魔をする危険がなくなり、防災性が向上するという点が挙げられる。
このことは、今年千葉県を襲った台風15号による直接の被害と、それに伴う大規模な停電、そしてその後の電力供給の回復状況を見れば明らかである。阪神・淡路大震災では震度7の地域で、電柱の停電率は10.3%であったが、地中線は4.7%であり、電柱に対する地中線の被害率は45.6%と低かったと報じられている。
10月7日の読売新聞には、「電柱大国ニッポン」として日本の電柱数の多さが示されたが、それによると2017年度末の電柱数は3,585万本であり、今も毎年7万本づつ増加を続けているという。この多くの電柱が災害で倒れた数もまた示されているが、次のようである。
・1995年1月、阪神淡路大震災・・・電力 約4500本、通信 約3600本
・2003年9月、沖縄県宮古島市・・・電柱 800本
・2011年3月、東日本大震災・・・・・電力 約2万8000本、通信 約2万8000本
・2013年9月、竜巻・・・・・・・・・・・・・埼玉県越谷市 46本、千葉県野田市 5本
・2018年9月、台風21号・・・・・・・・・電柱 約1700本、停電最大 約260万戸
・2019年9月、台風15号・・・・・・・・・電柱 1000本超、停電最大 約93万4900戸
被害額の推定は示されていないが、いったいどれくらいになるのであろうか。
この記事には、日本と世界各都市の無電柱化率も比較して記されているが、それによると、
・ロンドン・・・・・・・・100%
・パリ・・・・・・・・・・・100%
・シンガポール・・・100%
・香港・・・・・・・・・・100%
・ハンブルグ・・・・ 95%
・ニューヨーク・・・ 83%
・ワシントン・・・・・ 65%
・ソウル・・・・・・・・ 49%
・ホーチミン・・・・・ 17%
であり、わが日本の主要都市の無電柱化率は、
・東京23区・・・ 7.8%
・大阪市・・・・・ 5.6%
・名古屋市・・・ 5.0%
・日本全体・・・ 1.2%
という数字である。彼我の差は一目瞭然である。次のような図も掲載されていた。

日本の都道府県別無電柱化率(2019.10.7 読売新聞から)
この図によると、無電柱化率が3%を超えているのは、東京都だけであり、2~3%は神奈川、岐阜、福井、大阪、兵庫の5府県、1~2%が23県、残る18府県では1%未満である。
このように無電柱化が日本で遅れている要因としては、「故障時の対応に時間がかかる」、「工事中の通行のへの妨げ」、「電線を地下化しても地上部の変圧器の場所は必要」といったことがあげられているが、やはり最大の要因は1kmあたり5.3億円とされるコストの問題であろう。現在、軽井沢で計画されている、前記の580m の区間の総費用は、約4億円とされているから、寒冷地での工事費用は更に割高になっていると思われる。
これに対しては、電線を埋める深さを浅くして、掘削量を減らしたり、土に代わって発泡スチロールを使って埋め戻し時間を減らすなどにより、工期短縮を図る工夫が取り入れられている。また、従来は通信への影響を避けるために、離れて埋めなければならないとされていた電力と通信のケーブルを同じ側溝状のボックスに埋めるなどのコスト対策も進められているという。
しかし、高速道路網や新幹線網、リニア鉄道建設などのことを考え合わせると、もう少しバランスのとれた国土のインフラ整備はできないものかと思う。
日本で最初に電線地中化が行われたのは、前出の兵庫県芦屋市に高級住宅街として造成された六麓荘町とされているが、これは90年も前の1928年のことであった。その後、1986年度から1998年度までに、全国で約3,400kmの地中化が達成されているというが、このままのペースでいけば、日本全体の電線地中化が完了するまでに2700年かかるという計算もある。
東京都知事になった小池百合子氏が発足人となって作られた無電柱化推進議員連盟、無電柱化小委員会により作成された「無電柱化推進法案」が2016年12月9日に無電柱化の推進に関する法律として成立している。また、東京都と大阪府もそれぞれ2018年2月と2018年3月に「(仮称)東京都無電柱化計画」(素案)、「(仮称)大阪府無電柱化推進計画」(素案)を発表している。
国土交通省は、上記法律を受けてであろうか、災害時に緊急車両が走る幹線道路では、2016年以降電柱を新設することを禁じているし、災害時の輸送で重要となる道路を対象として、電力会社や通信会社に電柱を撤去させる制度を新設すると発表している。
地球温暖化が進む中、台風15号のあとにはまだまだ大型で強力な台風が日本に押し寄せてくる気配である。千葉県のような住宅被害や大規模停電が、再び起きなければよいがと願わずにはいられない。