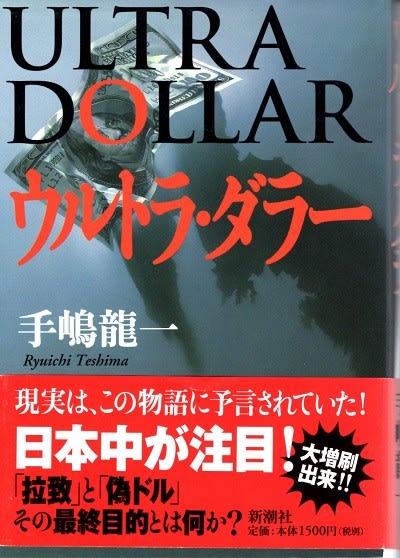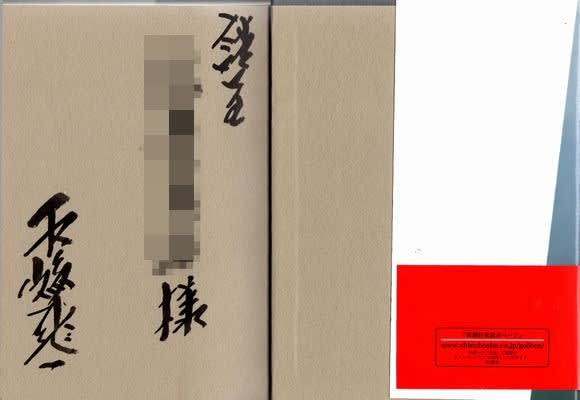やなぎ書房での「軽井沢の夜話」に参加し、松井孝典さんのお話を聞いたことがきっかけとなり、ふだんは考えることのほとんどない、地球生命の誕生について改めて調べてみようという気になった。
前回紹介したが、松井さんが言われた「クリック博士の仮説」とは何かを知りたいと思ったこともあるし、今回話をうかがった、「宇宙と生命」に関する松井さんの考えをさらに整理した形で知りたいと思ったからでもあった。
目の前にある、デスク上の「回転する地球儀」(2021.2.12 公開当ブログ)を見ながらそんなことを考えている。
回転する地球儀
松井さんの軽井沢の夜話とNHKのラジオ放送の講話、およびウィキペディアの記述内容などを通じて、私たちの世代が若い頃に学んだ地球上の生命誕生に関する説が、その後大きな困難に遭っていること、そしてそれに代わる地球生命の宇宙起源説が注目を集め始めていることがわかってきた。
ここで、現在地球上の生命誕生についてどのような説があるのか、今一度整理しておこうと思う。
ウィキペディアで「生命の起源」をみると、「概要」では次のように記されている。
「・・・現在、地球上の生命の起源に関しては大別すると三つの考え方が存在する。第一は、超自然的現象として説明するものであり、例として挙げると神の行為によるものとする説やインテリジェント・デザイン説がある。第二は、地球上での化学進化の結果と考える説である。第三は、宇宙空間には生命の種のようなものが広がっており、それが地球に到来した結果生命が誕生したという説(パンスペルミア説)である。現代でも、第一や第三の説を発表する科学者は多い。自然科学者の間では一般的には、アレクサンドル・オパーリン(1894.2.18-1980.4.21)などによる物質進化を想定した仮説(化学進化説)が広く受け入れられている・・・ 」
今日、地球上の生命は、無機物から地球上で誕生・進化したとする化学進化説を受け入れる科学者が多いようであるが、地球外の宇宙にその起源を求めるパンスペルミア説もまた一定の支持を集めていることが窺える内容である。
ところで、このウィキペディアの脚注には、「 ちなみに、2009年に全米科学振興協会に所属する科学者たちに対して調査を行ったところ、科学者のちょうど半数ほど(51%)が、神あるいは何らかの超越的な力を信じている、と回答した。」という記述もあることから、この生命誕生のテーマは宗教の影響が大きいものであることが実感される。
さて、夜話で松井さんが話された「クリックの仮説」とはどのようなものか。これは上記の第三の説、パンスペルミア説の一つとして解説されている。
まずは「パンスペルミア説」についてもう少し詳しく見ていくと、ウィキペディアに次の記述がある。
「『宇宙空間には生命の種が広がっている』、『最初の生命は宇宙からやってきた(=地球で生命が生まれたのではない)』とする仮説である。この説の原型となる考え自体は1787年にスパランツァーニによって唱えられていた。
1906年にスヴァンテ・アレニウスによって提唱され、この名が与えられた。彼は『生命の起源は地球本来のものではなく、他の天体で発生した微生物の芽胞が宇宙空間を飛来して地球に到達したものである』と述べた。
この説の20世紀後半での有名な支持者としては、DNA二重螺旋で有名なフランシス・クリックほか、物理学者・SF作家のフレッド・ホイルがおり、その後もこの仮説に関連して、真剣に調査を試みる科学者は増えてきており・・・」
ちなみに、このスヴァンテ・アレニウスはアレニウスの式で有名なアレニウス(1859.2.19-1927.10.2)のことであり、スウェーデンの科学者である。1903年に電解質の解離の理論に関する業績により、ノーベル化学賞を受賞している。アレニウスの式のほか、月のクレーター Arrhenius、ストックホルム大学の研究所名などにも名を残している。
このパンスペルミア説の一つに「意図的パンスペルミア説」があり、1981年にフランシス・クリック(1916.6.8-2004.7.28)とレスリー・オーゲル(1927.1.12ー2007.10.27)が提唱した。これは、高度に進化した宇宙生物が生命の種子を地球に送り込んだとするものである(ウィキペディアから引用。後に示すように、最初の提唱は1973年とする報告もある)。
「地球が誕生する以前の知的生命体が、意図的に『種まき』をした」とするもので、まるでサイエンス・フィクションのようにも聞こえる説ではあるが、クリックはこの説の根拠として次の二つを示したとされる。
ひとつは、現在の地球上の生物ではモリブデンが必須微量元素として重要な役割を果たしているが、クロムとニッケルは重要な役割を果たしていない。しかし、地球の組成はクロムとニッケルが多く、モリブデンはわずかしか存在しない。このことから、モリブデンが豊富な星で生命が誕生した名残りだと考えることができるとしたのである。
もうひとつの根拠は、「地球上の生物の遺伝暗号がおどろくほどに共通したしくみになっていることであり、これは『たったひとつの種』がまかれて、その種から地球上の全ての生物に変化していったと考えられる」というものである。
DNAの発見者、ノーベル賞受賞科学者(1962年 生理学・医学賞)の意見だけに、遺伝暗号に関係するこの内容は重みのある説明である。
「軽井沢の夜話」での、松井さんが国会議員に勧めたというロケットに細菌を搭載して宇宙に向けて発射する話は、確かにこのクリックの仮説を、今度は地球人類の手で成し遂げようとする壮大なものである。
ただしかし、こうした説はいまのところ仮説であって、科学者はこうした仮説を検証するために努力を重ねている。困難な時間のかかる作業である。
1906年に提唱したアレニウスは別としても、クリックというノーベル賞受賞科学者がこうした説に向かう理由は何か。それは生命誕生の化学進化説を実験的に検証しようとするこれまでの試みが、ハロルド・ユーリー(1893.4.29-1981.1.5)とスタンリー・ミラー(1930.3.7-2007.5.20)の実験以降はことごとく成功していないという事実があるからだという。
この部分を、ふたたびウィキペディアから引用すると次のようである。
「化学進化説に関する考察や実験は、・・・個々の仮説のようなことが実際に起こりえるのか、科学者が推定した太古の地球上の環境を・・・実験室的に、太古の地球環境だったであろう状況を再現して・・・具体的に実験を行うことであり、1980年代まではそのような流れが支配的であった。・・・
だが、多くの科学者が、太古の地球にあったであろう環境を作って、たとえば雷などを再現するために高圧電流を流すなどの検証実験を・・・いくら行っても、実験室の試験管やほかの容器のなかで生命が誕生するということはまったく起きなかった・・・」
実験室的に無機物から有機物を作り出すことができても、そこから生命を誕生させるまでには途方もない時間がかかるのではと推定されたことから、そのすべてのプロセスを地球上で起きたものと考えるには無理があるとの考えが広まってきた。別の番組で、松井さんの考えは次のように紹介されている。
「・・・アストロバイオロジーの第一人者で、世界的な権威でもある松井孝典氏(東大名誉教授・千葉工業大学惑星探査研究センター所長⦅当時⦆)は、そんなパンスペルミア説を提唱する科学者の一人だ。そもそも地球上でランダムにタンパク質の合成が進んだ結果、今日のような生命体が偶然組成される可能性は、数学的には10の4万乗分の1程度の確率しかない。地球の誕生から46億年しか経っていないことを考えると、その限られた時間内に10の4万乗分の1の確率でしか起こりえない組み合わせが偶然実現すると考えるには無理がある。しかし、もし宇宙に地球と同じような惑星が無数にあるとすれば、そのどこかの惑星でそれが実現する可能性は十分にあり得ることとなる(松井孝典、神保哲生、宮台真司氏の討論 2015.4.11から)。」
地球誕生後の経過時間46億年という数字もまた、途方もなく大きな数字であるが、これが46x10の8乗年であることを考えると、10の4万乗という数字の大きさがわかる。また46億年を秒に直したとしても、1.5x10の17乗秒でしかないとなると、上で示されている、偶然性がいかに困難なものか実感される。
この10の4万乗分の1の確率という数値は、ビック・バンの名付け親であり、イギリス人天文学者だった故フレッド・ホイル博士(1915.6.24ー2001.8.20)が提示したものであり、1981年4月に出版された「 Evolution from Space」『チャンドラ・ウィックラマシンゲ(1939.1.20-)との共著』という本の中で、最も単純な単細胞生物に必要な酵素が全て作られる確率は 10の40,000乗 分の1であると計算したことによる。

「 Evolution from Space」(Fred Hoyle, Chandra wickramasinghe 著 1981年 J.M.Dent & Sons 発行)の表紙
「我々の宇宙に存在する原子の個数はこれに比べると極々小さい(約 10の80乗個)ため、生命が誕生したとされる原始スープが宇宙全体を満たしていたとしてもそのような物質が作られる機会はないとホイルは論じた(ウィキペディア)」のである。
この計算の詳細について、松井さんは「スリランカの赤い雨」(松井孝典著 株式会社KADOKAWA 2013年発行)の中で次のように説明している。

「スリランカの赤い雨」(松井孝典著 株式会社KADOKAWA 2013年発行)の表紙
「・・・生命の誕生する確率がいかに低いかは、例えば以下のようなことを考えてみるとよい。タンパク質はアミノ酸の連なる高分子である。酵素の場合、その立体的な形の背骨を構成するのは10から20個のアミノ酸である。酵素の活性にかかわる部位のアミノ酸は少なくとも4個である。背骨を12個、活性部位のアミノ酸を4個としよう。地球産の生命は20種類のアミノ酸を使用している。ということは一つの位置にある特定のアミノ酸が来る確率は20分の一である。それぞれのたんぱく質にはそれぞれの位置にある特定のアミノ酸が並ぶ必要があるから、背骨にあたる部分のアミノ酸の数を16とすれば、それがうまい具合に並ぶ確率は20分の一の16乗になる。これは10の20乗分の一程度である。さらにそれが2000種類必要であるから、酵素というたんぱく質だけで、10の20乗分の一のさらに2000乗、すなわち10の4万乗分の一という低い確率でしか作られないことになる。・・・」
10の40,000乗という数字を聞くと、確かに絶望的に小さな確率ということになる。確率だけを例えれば、1から10までの数字が書かれた正10面体(無いが、あったとして)のサイコロを4万個同時に振って、すべての数字が1になっている確率ということになる。もちろん確率なので、起こり得ないとは言えない。最初の1回目で、すべてが1になることも、絶対にないとはいえないのであるが。

たくさんのサイコロを同時に振ってすべてが1になる確率は?
さてそれでは、生命誕生が地球上では確率の計算から無理があるとして、宇宙にその可能性を求める場合その確率はどのように変化するか。宇宙に存在する生命誕生の可能性のある惑星の数は無数ではない、有限の数字で考えなければならない。宇宙の星の数は、現在のところ10の22乗個程度とされているので、各星(恒星)に1個地球に似た惑星があると仮定すれば、同じだけの数の惑星を想定することができる。
その場合、宇宙全体で見ると生命誕生の確率は、10の4万乗分の1の10の22乗倍ということになるので、10の39,978乗分の1になる。
地球上では10の40,000乗分の1、宇宙全体で見ると10の39,978乗分の1ということになるが、果たして最初の生命誕生の場を地球上から宇宙全体に拡大したとして、これは意味のあることだろうか。
この点については、松井さんはフレッド・ホイルの提唱する定常宇宙論を用いて説明している。定常宇宙論というのは、宇宙には始まりも終わりもなく、いつでも、今あるような姿で存続し続けていることを主張する理論体系である。
「宇宙が無限に続くとしたら、生命の誕生は、その確率がどんなに小さい現象でも、有限の事象なので必ず1にできる(前出『スリランカの赤い雨』P100)」というのであるが。
クリックの仮説は、こう考えて来ると宇宙論と密接につながるものである。宇宙における生命の誕生の確率が、ホイルの指摘するように極めて小さなものだとすれば、その起源は地球以外に求めざるを得なくなるが、それでも現在知られている宇宙に存在する星と惑星の数ではまだ足りない。生命の誕生する確率を説明するためには、宇宙は永遠に続く始まりも終わりも無いものとして考えざるを得なくなる。。。
宇宙で誕生した生命が地球に来る可能性はどうであろうか。どこかの惑星で誕生した生命(胞子)が宇宙空間を旅して地球にくるという、単純なアレニウスのパンスペルミア説については、クリック博士は「長時間放射線を浴びれば胞子は死滅してしまう」として否定し、それに耐えられるような宇宙船に載せて、バクテリアを運べばいいと提案したのであった。
この論文は、1973年に「イカルス」誌にクリックとオルゲルにより「Directed panspermia」と題する論文で紹介された(「スリランカの赤い雨」より。次の写真は「イカルス」創刊号の表紙)。

「ICARUS」(Vol.1, No.1 May 1950)の表紙
1973年と言えば、系外惑星が発見されるよりもずいぶん前のことである。系外惑星とは太陽系以外の恒星の周りにある惑星のことであるが、意外なことに、宇宙に太陽系以外に惑星が存在することが確認されたのは、1995年のことだという。それまでは、存在しているであろうという推測でしかなく、それを確認する手段がなかった。
最新の望遠鏡が利用できるようになり、太陽系以外の惑星(系外惑星)探査が進められたが、成果はなかなか得られず、アメリカの専門家からは1995年8月に、「太陽系以外に惑星は存在しない、従って地球のように生命の存在する惑星は存在しない」とまで言われるようになったという。
しかし、思いがけない形で系外惑星の存在が確認された。惑星探査における「フーコーの振り子」である。
発見の発表は、上記アメリカの専門家からの発表の直後、1995年10月、スイス・ジュネーブ大の科学者、ミシェル・マイヨール(1942.1.12-) とディディエ・ケロー(1966.2.23-) によってであった。この二人は 米プリンストン大のジェームズ・ピーブルス(1935.4.25-)と共に2019年のノーベル物理学賞を受賞している。
一旦惑星の存在とその探索の手法が確認されると、その後はどんどん惑星の発見が続く。2020年4月現在、4000個から10000個の惑星が見つかっているという。太陽系のように恒星の周りを惑星が回るという姿は、宇宙に広く存在していることが判ってきた。その中には、地球に似た条件を備えたものもあることが判ってきた。
カール・セーガン博士(1934.11.9-1996.12.20)が、パイオニア10号、11号に宇宙人へのメッセージを搭載して宇宙に送り出したのは、1972年と1973年のことであるから、この頃はまだ宇宙に惑星が存在するということは確認されていなかったことになるので、クリック博士の説と同様、惑星の存在を当然存在するものとしての試みであったことになる。
宇宙の姿については、現在は138億年まえのビッグバンに始まり、その後は膨張を続けているという説が、一般に受け入れられているが、ビッグバン前はどうであったのか、このまま宇宙は永遠に膨張を続けるのかといったことはまだ判っていないとされる。
これに対して、定常宇宙論は宇宙は永遠に膨張と収縮とを繰り返すという説であり、生命の誕生が10の4万乗分の1という極めてまれにしか起きない偶然の産物だとすれば、これを説明するために必要な仮説ということになる。
松井さん自身は、この意図的パンスペルミア説についてはどのように捉えているか。少し古い著書であるが、「宇宙誌」(1993年 徳間書店発行、P298)の中で次のように記している。1993年というと、先に記した通り系外惑星が発見される2年前のことである。

「宇宙誌」(松井孝典著 1993年 徳間書店発行)の表紙
「・・・今日、アレニウスのこの考え方(パンスペルミア説のこと)は、少なくともまっとうな科学者からは、一顧の価値もないものとみなされている。有害な宇宙線にに満ちあふれた宇宙空間を、生きた胞子が何の障害も受けずに長い旅を続け、地球にたどり着いて新たな生命を育むなどとは、とても考えられないからだ。
ところが、フランシス・クリックと彼の長年の同僚であるレスリー・オーゲルは、アレニウスの考えの不備な点を修正し、確かに微生物は他の天体から地球に届けられた、それも宇宙船に乗ってやって来た、という論文を、1973年、カール・セーガンが編集長をつとめていたアメリカ天文学会惑星部会の学会誌に発表した。それが”意図的”あるいは”ねらい撃ち”パンスペルミア説である。
『ある遠くの惑星に40億年ほど前に、私たちのような高等生物が存在し、科学や技術を今の地球をはるかに超えるほどに発達させていたとしよう。・・・』
しかし彼らは、自分たちの惑星上での文明がいつまでも続かないことを知っていた。・・・彼らは当然、自分たちの太陽系や近くの惑星系を探査し、移住に適当な惑星を探したが、ついに発見できなかった。そこで彼らは宇宙船を作り、新しい世界まで定住者を運ぶことを計画した。・・・高等生物は・・宇宙の旅をとても切り抜けられない。・・生命そのものが存続可能であればよしとする内容に計画を変更した。・・・彼らはいろいろ考えた末、それには微生物が最もふさわしいと結論する。
そして今から40億年ほども前、それらの宇宙船の一つが原始地球に到達し、微生物はわれわれの惑星の表面一面にばらまかれる。・・・一部は海などに落ちて、環境にいちばん適した種が増殖した。・・・これから先の物語は、もはや語る必要もあるまい。いうまでもなく、地球における生命の起源とは、そのようにして運ばれてきた微生物であり、つまるところその直系の子孫が、我々なのだーーー。
さて、ここまでの話を読んできて、いささかの当惑を感じない人は少ないだろう。これがあまり出来のよくないSF小説ならともかく、その語り手が現代で最も有名な科学者の一人で、ノーベル賞受賞者でもあるフランシス・クリックだけに、戸惑いも深い。物語の是非よりも何よりも、クリックは本当にこんなことを信じているのだろうか。信じているのだとしたら、彼は一体どうやってその真実を証明しようというのだろう。信じていないのだとしたら、このホラ話には何か特別の意図が隠されているのだろうか。・・・
もとよりクリックは、自説にそれほどこだわっているわけではなく『それは根拠のある科学的理論だが、まだ未熟なのだと認め』ている。・・・
生命の起源は、つきつめれば、おそらく純粋に生化学の問題だろう。だが問題の解決に迫るには、何よりもまず40億年前の地球環境がいかなる状況にあったかを理解しなければならない。加えてクリックは、初源の生命がこの地球上で発生したと固執するのは、必ずしも賢明な態度ではなく、他の天体から運ばれてきた可能性も検討に価することを示したのである。・・・」
1993年発行のこの本からは、松井さんが当時パンスペルミア説に対して、やや慎重ながらも中立の立場をとっていたことが窺えるのであるが、それから20年後、2013年発行の「スリランカの赤い雨」のあとがきには次のように記している。
「生命の起源について、一般的には、地球上での化学進化を考えるのが普通である。しかしそれは・・・現実的にはかなり難しい。なぜか? まだ、タンパク質の材料であるアミノ酸の合成程度にとどまり、その20種類のアミノ酸のうちから一つを選び、それぞれがある決まった順に100個以上も連なった高分子を無機的に合成するまでには至っていないからだ。・・・酵素だけを取りあげても、それがランダムな試行錯誤からすべてが作られる可能性は、10の4万乗分の1くらいと推定される。・・・しかもそのようなことが地球誕生後の数億年以内に起こらねばならないのである。
そこで生命の起源は、もっとずっと広い時空、すなわち宇宙で考えようというのが、パンスペルミア説という考えの基にあることを紹介した。・・・
20世紀以降で本格的に論を展開しているのは、スウェーデンの物理化学者、スヴァンテ・アウグスト・アーレニウスと、英国の天文学者、フレッド・ホイルとチャンドラ・ウィックラマシンゲくらいである。・・・
ホイル亡き後も、チャンドラは孤軍奮闘でパンスペルミア説を展開している。ひょんなことから、筆者もチャンドラとの共同研究を始めたが、パンスペルミア説は現代の科学で、その是非が検証できるテーマであることを確信している。
そのためには、赤い雨のような歴史上の未知の現象を一つずつ、地道に解明していく以外に方法はない。」
ここには、パンスペルミア説を検証しようとする強い気持ちが窺える。
以下次回。