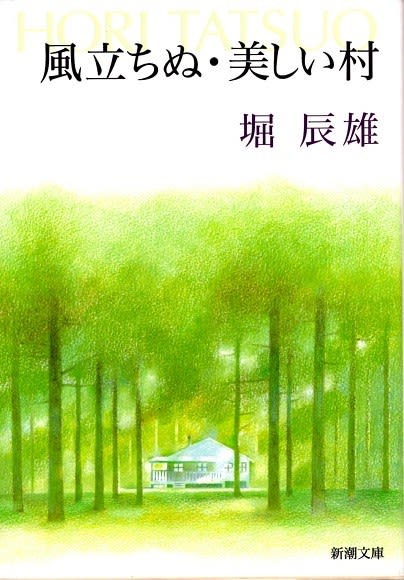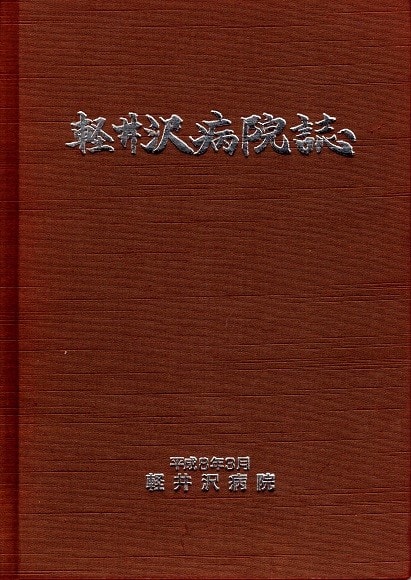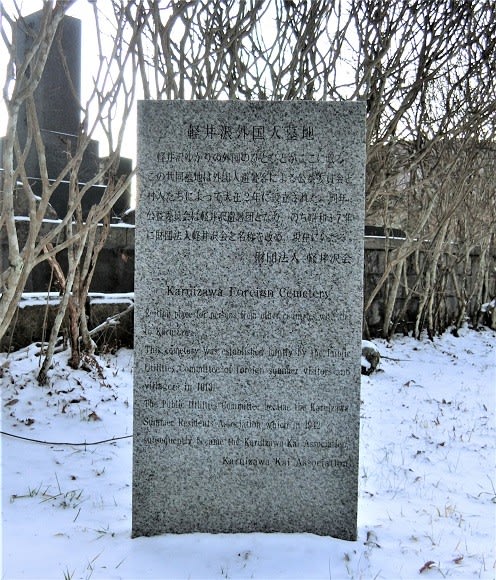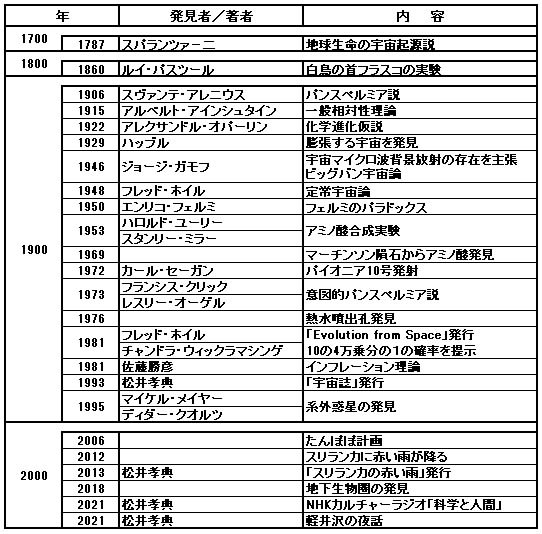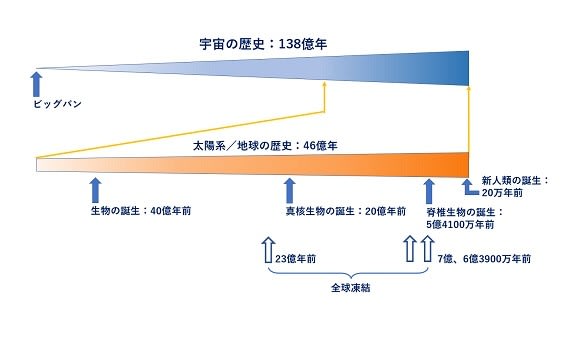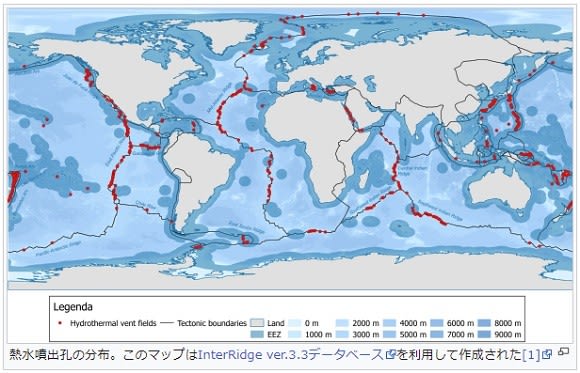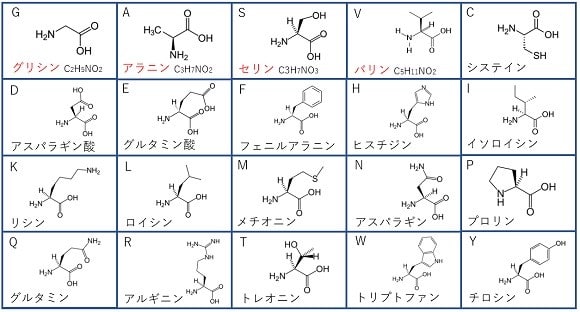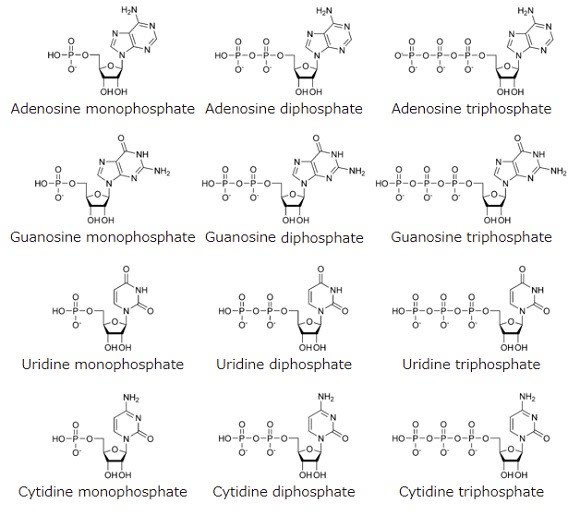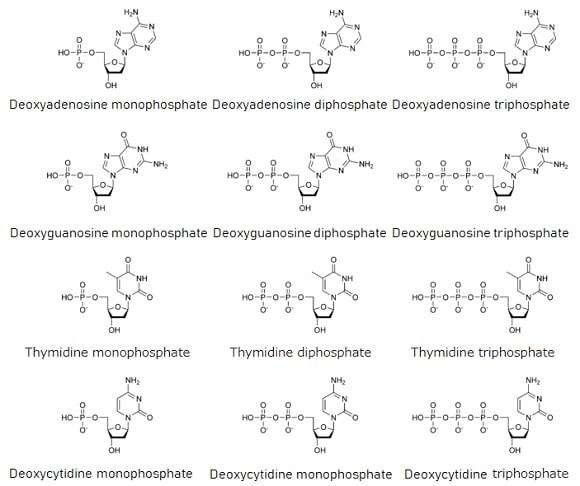50年前、武装した連合赤軍のメンバーが、南軽井沢・レークニュータウン内にあった河合楽器の保養所に立てこもった「あさま山荘事件」が起きている。1972年2月19日の事であった。
この事件については、軽井沢に移り住んだことがきっかけになり、調べてみたいと思い、現地保養所や関連した場所に行くとともに、書籍を読むなどして得た情報を当ブログで紹介(2017.8.18 公開)したことがあった。
その際の関心は専らこの保養所での立てこもりに至るまでの犯人達の行動、その後の警察・機動隊との攻防・人質の救出と全員逮捕、そしてその後の犯人達のことであった。
今月になり、2月6日の信濃毎日新聞が1面と31面に、この「あさま山荘事件」を採りあげた。
1面の見出しは、「半世紀 複雑な思いなお」であり、「あさま山荘事件 人質女性」、「救出で2人死亡『申し訳ない』」と小見出しが続く。
記事中には昭和47年(1972年)2月29日付け同新聞1面の、事件を伝える記事がそのまま掲載され、「泰子さん救出、五人逮捕」、「『連合赤軍』九日ぶり解決」、「警官死亡二人に」といった見出しが見える。
31面には「遺族とお会いしない方が」、「『あさま山荘』50年 今も慰霊祭控える人質の女性」という見出しがある。

「あさま山荘事件」を伝える2022年2月6日発行の信濃毎日新聞1面

「あさま山荘事件」を伝える2022年2月6日発行の信濃毎日新聞31面
これらの見出しからも想像できることではあるが、記事を読み進んでいくと、今回の記事はこのあさま山荘事件そのものについて報じているのではなく、事件の人質となった女性に焦点をあてて書かれていることが判る。
31面には、「ただ一人の人質として巻き込まれた牟田泰子さん(81)は信濃毎日新聞のインタビューに、事件から半世紀を経ても心のつかえは消えていないことを吐露した。・・・」という記事内容と共に、取材に当たった記者の思いが次のように記されている。
「記者は今年1月、泰子さんと夫の郁男さん(85)宛てに手紙を送り、事件から半世紀の節目に、当時の関係者の思いや、事件が残したものは何だったのかを知り、読者に伝えたい-との思いをつづった。今月、町内の自宅を訪ねると、泰子さんが静かな口調で語り始めた。・・・」
そして、インタビューの内容を紹介する記事の最後を次のように締めくくっている。
「半世紀たち、当時を直接知る人は少なくなった。長年の『沈黙』を破った泰子さん。被害者として、後世にどんな思いを伝えたいのか-との問いに、『私はもう過去の人だから』と多くを語らなかったものの、その表情には真実を伝えたい-との決意のようなものがにじんだ。」
「あさま山荘事件」という、それまでにも、その後にも例のない事件に人質として巻き込まれた女性とその夫の2人が今なお「複雑な思い」を、そして事件解決に向かった警察官2人が銃撃され死亡したことに「今も申し訳ない気持ち」を持ち続け、毎年、事件で殉職した2警官の命日に合わせ軽井沢町発地の顕彰碑「治安の礎」前で行われる慰霊祭への参加を、出席する遺族らと顔を合わせることが「つらいから」として、ためらう背景に一体何があるのだろうかと考えさせられる。
この記事の最後の部分で、記者は「当時のメディア報道についてどう思っていたのか」という質問をするが、これに対する泰子さんの答えは「(事実と)『ちょっと違う』と悩んだこともあった。書かれる側の気持ちを考えてほしいのは、今でもそうじゃないでしょうか」と答えている。
この質問と回答に、今回の記事を掲載しようとした記者の意図が込められていると思える。というのは、私には一つ思い当たることがあるからである。
先日、あるきっかけで、軽井沢病院の建物の歴史を調べたが、その時、「軽井沢病院誌」(平成8年 軽井沢病院発行)という本があることを知り、読み進むうちに、病院関係者の言葉として、「あさま山荘事件」についての記述が複数個所あることを知った。病院で、救護に当たった当時の医師や看護師が、この時の様子を自らの体験として記録に残していたのである。
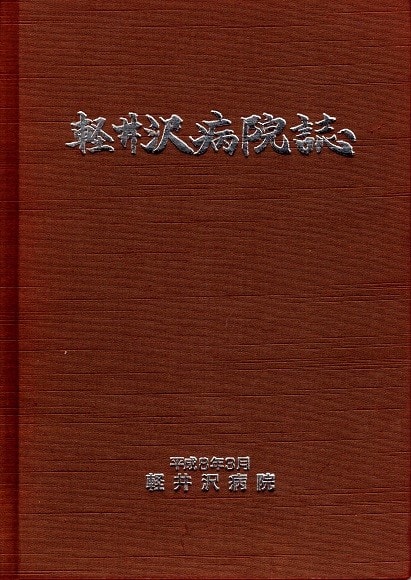
「軽井沢病院誌」(平成8年3月 軽井沢病院発行、町立軽井沢図書館所蔵)の表紙
一般に販売された書籍ではないが、軽井沢図書館の蔵書であり、閲覧は自由にできる。ここには、軽井沢病院の歴史と、関係者のさまざまな思い出が綴られているのであるが、複数の方々が「あさま山荘事件」のことを心に残る忘れられない思い出として書き残していた。中でも、散弾銃で銃撃され負傷した機動隊員の手術をした医師や、事件の人質であった牟田泰子さんを直接診察したお二人の医師の話が詳しく記されているので、ここに引用させていただく。
前田 弘氏(元 産婦人科医)は、
「昭和47年2月19日、土曜日の午後、当番医として病院に残っていた。この年は軽井沢にしては、珍しく雪の多い寒い年であった。当時は、冬期に時間外に来院する患者さんは殆どないのが常であったが、その寒い日、けたたましいパトカーのサイレンと共に、機動隊の制服を着た一人の屈強な男が飛び込んできた。
妙義山のアジトを追われた連合赤軍が軽井沢方面に向かったらしいとの情報のもとに、冬期の空き別荘の点検を行っていたところ、いきなり別荘の窓から猟銃で撃たれたとの事であった。
X線検査をしたところ、顔面と左前腕にに7発の散弾が撃ち込まれていた。深さは約5mm程度であった。直ちに局部麻酔をしながら摘出を始めたが、射入口は小さく、弾は丸いため、一個取り出すのにかなり手間が掛かる。特に顔面は傷を大きくしたくなかったので、尚更であった。隊員はイライラしはじめ、『麻酔はいらない。傷口も大きくてよいから、早くして呉れ。すぐに犯人達の追跡に加わりたいのだ』という。
彼の我慢強さと警官としての使命感の強さにビックリしたものである。実際にすべての弾を抜き終わると、『行ってきます』と言って病院を飛び出していった。翌日の新聞には彼の言葉通りに追跡隊に復帰していた事が報じられていた。
しかし、この時点では、あれほどの大事件の発端になろうとは思ってもいなかったのである。その後の2月28日に警察隊が突入して解決したのであるが、当日早朝、警察からの要請で浅間山荘から70メートル程離れた、死角になる場所に停めた大型救急車に待機し、怪我人の処置と護送病院の手配の役を引受けたりもした。現場にいて、報道されなかった貴重な多くの経験もした。・・・」
木戸千元氏(五代目院長)は、人質の牟田泰子さんと直接接触したが、その時のことを更に詳しく次のように記している。
「縁あって、軽井沢病院に赴任したのは昭和44年秋の頃であった。・・・
病院就任以来、町には浅間山の大爆発、新道の大火などの事件があったが、昭和47年2月、静かな冬の軽井沢に降って沸いた様に突然銃声が響いて、この事件が勃発した。・・・
警察は、総力を挙げて、10日間の攻防戦の末、2名の殉職警官の犠牲を払いながらも人質を無事解放し、犯人を全員逮捕したものである。
事件が始まるや、当院は最前線の医療機関に指定されたため、大学病院から応援の医師を依頼して待機態勢を採っていたが、厳重な包囲網をくぐって山荘に近ずこうとした一民間人が頭部を銃撃され、救急車で搬送されるという事もあった。・・・
10日間のにらみ合いの末、・・・夕闇迫るころ、遂に落城した。人質は無事に救出されて直ちに病院に運ばれた。異常な体験を強いられた人質であったが、水を被り寒さに凍える以外は擦り傷程度の外傷があったくらいで、他覚的な異常所見はなく、思いの外元気であり、気丈でもあった。
精神的にも大分痛め付けられて居るのではと予想されたので、拘禁症状の有無等について、予めお願いしてあった国立小諸療養所の精神科医にも立ち会ってもらったが、特に異常所見はなくホッとしたものであった。
この際の一問一答が、翌日の某大新聞の一面にそっくり載っていて、驚いたのであったが、後に病室で盗聴器が発見され、報道合戦の凄まじさに目をむいたものであった。
当日のテレビカメラは朝から一日中山荘に焦点をあてて放映しており、どこのチャンネルを回しても浅間山荘一色となり、全国の視聴者もテレビ画面に釘づけとなったため、国道18号の如きは交通量が激減したとの事であった。当院でもリアルタイムのテレビで逐一経過を追いながら入院準備などに万全を期していたのであった。
この頃からは人質に関するマスコミの取材攻勢が激化し、初めはテレビ・新聞、次いで週刊誌・月刊誌と、夜打ち・朝駆けまである熾烈な競争に巻き込まれて、マスコミの実態についてつぶさに体験させられた。・・・
数日後、院内で人質との共同記者会見が設けられ、全国にトップニュースとなって流されて、ようやく報道陣が潮が引く様に去って行き、元の静けさに帰ったのであった。
この事件で、警察は犠牲を払いながらも、全国民の声援と激励を受けて解決し、非の打ち所のない対応と評価された・・・」
次は原 久弥氏(元 外科医師)の印象に残った出来事として書かれた、あさま山荘事件である。
「・・・当時の日記に、比較的詳しく、その時のことが記載してありますので、ここに軽井沢病院の勤務医から見た、この事件について、記します。
・・・警察が駆け付けたとき、彼らは南軽井沢、レイクニュータウン近くの急な山の斜面に建つ河合楽器の寮、あさま山荘へ逃げ込み、管理人の奥さん、牟田泰子さんを人質にとり、たてこもりました。このニュースは、たちまち病院にも伝わりました。・・・どのような事態に発展するか判らず、一応、病院として待機状態をとることになり、足止めせざるを得なくなりました。・・・
2日目(月)の午後、新潟市でスナックを経営している田中安彦さんという人が、単身、牟田泰子さんの身代わりになろうとして、山荘に近づいたところ、散弾銃で撃たれ、病院にかつぎこまれました。そして、このときより軽井沢病院は、この事件の最前線基地として、世の注目を浴びるようになりました。
この人は、結局、銃弾による脳挫傷があり、上田市の小林脳外科へ転送されましたが、死亡しております。
あさま山荘を、取り巻き、ぞくぞくと武装した警察の機動隊員が集合し、軽井沢町は、機動隊員とマスコミの人々で、真夏のようにごった返し、人間であふれかえりました。
いつ、どんな激しい銃撃戦が始まるか、判らず、外科として、それに対応出来る体制を整えねばならず、大学の医局へ連絡、直ちに2名の外科医が交代で派遣されました。
現場は、タテを持った機動隊員が取り巻き、まず、人質の牟田泰子さんの、親族による『人質』を返してくれという呼びかけが行われました。続いて、連合赤軍の坂口、吉野氏の母親による涙ながらの説得が行われましたが、何らの動きもなく、機動隊員が少しでも、山荘に近づくと、容赦なく散弾銃を撃ちまくりました。彼らの射撃能力は抜群で、タテの眼の部分に開けられた、僅かのスキマに、遠方から的確に命中させる能力を持っておりました。
病院は、時々起きる怪我人が救急車で運ばれるほか、人口が急に増えたための、一般のカゼとか、ちょっとしたケガなどで、夏なみに忙しい毎日でした。
現場近くの、見晴らしのきくところは、見物する人たちが、押し掛け、どのように発展するか、かたずを飲んで、成り行きを見守っておりました。
毎日、緊張して待機しておりましたが、10日目、2月28日、ついに警察は朝より、強行突入に入りました。ビルの解体に使う、大きな鉄球で玄関を破壊し、屋根を真上からぶち抜き、高圧放水車で外壁を吹き飛ばし、厳冬の中、大量の冷水を浴びせかけました。そして多数のガス弾を、密閉に近い部屋の中でさく裂させ、催涙ガスを充満させました。
すでに暗くなった18時15分、ついに、連合赤軍の若者たちが逮捕され、人質も救出されました。次々とサイレンを鳴らして救急車が、怪我人を運び込み、その処置に戦場のような騒ぎになりましたが、病院のスタッフは、秩序正しく、落ち着いて治療に専念いたしました。・・・
人質の牟田泰子さんは、冷たいホースの水を浴び、催涙ガスで眼や鼻を侵された上、氷のように冷え、応援に来ていた同級の藤井医師は、夢中になって、彼女の全身マッサージに集中いたしました。
このときから、外科医としての役割は、終わりましたが、続いてマスコミの、猛烈な取材合戦が始まり、病院は、ただ、もみくちゃにされたといっても良いような状態になりました。
取材合戦が熾烈になったのは、人質の牟田泰子さんからの取材が、警察により、差し止められたからです。救出直後、泰子さんは、肉体的に衰弱しておりましたが、精神的には、極めて元気でした。あさま山荘では、赤軍の若者、坂口弘、坂東国男、吉野雅邦の三人に大切にされ、楽しかったと口走り、〇〇ちゃんは、大丈夫かしら、などと発言し、それが警察当局を激怒させることになりました。
警察は犠牲者まで出し、7日間、寝ずに、ただ人質の救出に全力をあげていたわけですから無理もありません。その最初の一言が、マスコミに報道されてしまったため、全国からも怒りの声が殺到し、泰子さん宛ての手紙が、沢山届き・・・。
それ以来、郵便物は、一切、警察が管理し、マスコミの取材をシャットアウトしてしまいました。泰子さんは、連日、警察の厳しい事情聴取が続けられ、最初の元気さは、影をひそめ、次第に精神的に落ち込み、ノイローゼ気味になって行きました。
私達ドクターは、毎日、診察のため、接しておりましたが、日ごとに衰弱していくのが良く判りました。マスコミは、取材を止められたため、ますます他社に先んじて、人質中の新しい事実を知るべく、殺気立ってまいりました。我々ドクターが、何か知っているのではないか、と言うことで、官舎に昼夜を問わず押し寄せ、電話は使い放題、その傍若無人さには、ただ唖然とした次第です。
なんとか泰子さんのいる病室に盗聴器をしかけようと、白衣を着て忍び込もうとしたり、出前持ちのふりをして、入ろうとしたり、それは物凄い取材合戦でした。・・・
そして、人質解放の13日目、ついに、牟田泰子さんの、記者会見が軽井沢病院の内科診療室で行われることになりました。・・・
その状況は、全国に放映されました。担当者による質問に答える内容は、救出直後のものと、全く異なり、人質中は、ひどい仕打ちを受け、あのような若者は、絶対に許されるものではない、という内容でした。・・・」
こうした医師の証言ともいえる記述を目にすると、当時人質であった牟田泰子さんをめぐって何が起きたのかを想像することができる。このことについては、ウィキペディア(最終更新 2022年2月16日)にも「事件後の人質」の項に、前記の入院中の出来事や、記者会見の様子について、医師の記述と同様の内容ががまとめられている。
こうしたことから、今回、信濃毎日新聞の記者が、表現に苦心をしながらも、読者に伝えたかったことが見えてくるのである。
あさま山荘事件の被害者は、人質となった牟田泰子さんであり、その人質解放と犯人逮捕に向かって命を落とした二人の警察官と、善意の民間人である。
人質の無事救出と犯人逮捕に使命感をもって臨んだ警察官と機動隊員の中から犠牲者を出したことはまことに痛ましい。と同時に、人質となった牟田泰子さんの命もまた同じように当時は危険にさらされていた。
幸い、犯人グループは人質となった泰子さんに手荒いことをすることはなく、中でも当時未成年であった犯人の1人は、泰子さんに思いやりを示す場面もあったようである。こうした体験を解放後、軽井沢病院の担当医師に率直に語った言葉が、マスコミが仕掛けた盗聴器により外部に漏れ、その事がきっかけになり、泰子さんは世間から、さらにはマスコミからもバッシングを受けることとなった。
信濃毎日新聞の記事にはインタビューに答える泰子さんの話が次のように書かれている。
「『手荒なことはしなかった』・・・縛られたのは当初だけ、ベッドルームにいさせられた。動き回ることはできなかったけれど、部屋にいれば良かった。手荒なことはしなかった。食事は作ってくれた。・・・
⦅当時のメディア報道については⦆(事実と)『ちょっと違う』と悩んだこともあった。・・・」
このように、解放後に受けた心の傷は、50年後の今なお完全には癒やされることなく、牟田さん夫婦を苦しめている。
牟田泰子さんは事件後、口をつぐんできた。また、自身の救出にあたり亡くなった警察官や民間人の遺族との接触も遠慮してきた。
この「あさま山荘事件」はまだ解決していないと考える関係者は多いという。犯人の1人がその後、超法規措置で釈放され、海外に逃亡を続けているからでもあるが、その他にもここで示されているように、人質となった泰子さんにとっても、未だ事件は解決していないといえるのではないか。
先日配布された軽井沢町の広報誌「広報 かるいざわ」(No.715)には、2月28日に「あさま山荘事件殉職警察官慰霊祭」が顕彰碑「治安の礎」現地で行われるとの「お知らせ」が掲載されていた。牟田ご夫妻は今年もまた参列を見送ることになるのだろうか。関係者の尽力で、何とかそうした事態を回避し、「あさま山荘事件」の一端が解決されることを願いたいと思う。

「広報 かるいざわ 2022年2月号」(軽井沢町発行)の表紙

同誌「お知らせ」欄の記事