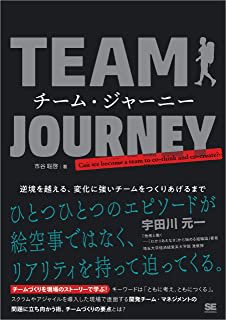チームジャーニー
【学びたいこと】
チームを鼓舞するリーダーである
【概要】
一人では成し遂げられない成果を生み出すために、私たちは他者を必要とする存在なのだ。2
① この本
チームづくり、共に考え、共に乗り越えるチーム
◉ともにつくる一体感
ともに考え、ともにつくる292
0-0-0
★★★僕たちはお互いに気付き合えるし、お互いから学び合える。そうして、自分一人では到達でき得ない視界を得ることができる。325
「あなたは何をする人なのか?」
自分ともにあるチームという存在が支えになるのです。この問いに一人で答え切れないなら、あなたのそばにいるチームメイトや同僚、仲間とともに向き合えば良いのです。327
★★★誰が状況を変える行動を始めるのか?それは「気づいた」人だ。
「気づいた」人が行動を取らなければ、変化の兆しをつくることもできない。32
君はまだチームとは何かを知らない。11
②-a
◆チームになるための4条件
→目指すべき:一人の人間のようなチーム146
1チームの目的を揃える Why
★★★われわれはなぜここにいるのか?15
個人としてのWhy:自分はなぜここにいるのか?
チームとしてのWhy:私たちは何をする者なのか?
チームとしてのHow:そのために何を大事に知るのか?
2共通の目標を認識する
チームの行動の質を高めていくために、わかっていないことのうち何がわかれば良いのかを問い続ける必要がある。29
▲
◉ビジョン:中長期的に顧客にどういう状況になってもらいたいか?118
▲
★★★ユーザーを自分たちに憑依させるんやで。
“一人のユーザー”の体験を最適にしようと考えたら、もっとチーム間での絡みがあるもんよ。236
自分らのプロダクトが解決することで特に値打ちを感じたもらえるような「切実な問題」は何なのか仮説を立てておこう。切実な問題、それにこそユーザーが対価を払ってくれる。241
3お互いの持ち味を把握する
4協働で仕事をするためのやり方を整える
「見える化」「場づくり」「一緒にやる」123
▲
②-b
プロダクトづくりは人と人が適切に情報を得て、十分に同期しあい、判断を揃え進めていくということ。121
◆成功循環モデル
仕事や活動の“結果の質”を高めるためには、まずメンバー間の“”関係の質を高めるべきだという考え。
関係性が良くなれば、“思考の質”も向上する。思考の質が高まれば、“行動の質”も良くなり、結果の質が向上していく。53
【学びたいこと】
チームを鼓舞するリーダーである
【概要】
一人では成し遂げられない成果を生み出すために、私たちは他者を必要とする存在なのだ。2
① この本
チームづくり、共に考え、共に乗り越えるチーム
◉ともにつくる一体感
ともに考え、ともにつくる292
0-0-0
★★★僕たちはお互いに気付き合えるし、お互いから学び合える。そうして、自分一人では到達でき得ない視界を得ることができる。325
「あなたは何をする人なのか?」
自分ともにあるチームという存在が支えになるのです。この問いに一人で答え切れないなら、あなたのそばにいるチームメイトや同僚、仲間とともに向き合えば良いのです。327
★★★誰が状況を変える行動を始めるのか?それは「気づいた」人だ。
「気づいた」人が行動を取らなければ、変化の兆しをつくることもできない。32
君はまだチームとは何かを知らない。11
②-a
◆チームになるための4条件
→目指すべき:一人の人間のようなチーム146
1チームの目的を揃える Why
★★★われわれはなぜここにいるのか?15
個人としてのWhy:自分はなぜここにいるのか?
チームとしてのWhy:私たちは何をする者なのか?
チームとしてのHow:そのために何を大事に知るのか?
2共通の目標を認識する
チームの行動の質を高めていくために、わかっていないことのうち何がわかれば良いのかを問い続ける必要がある。29
▲
◉ビジョン:中長期的に顧客にどういう状況になってもらいたいか?118
▲
★★★ユーザーを自分たちに憑依させるんやで。
“一人のユーザー”の体験を最適にしようと考えたら、もっとチーム間での絡みがあるもんよ。236
自分らのプロダクトが解決することで特に値打ちを感じたもらえるような「切実な問題」は何なのか仮説を立てておこう。切実な問題、それにこそユーザーが対価を払ってくれる。241
3お互いの持ち味を把握する
4協働で仕事をするためのやり方を整える
「見える化」「場づくり」「一緒にやる」123
▲
②-b
プロダクトづくりは人と人が適切に情報を得て、十分に同期しあい、判断を揃え進めていくということ。121
◆成功循環モデル
仕事や活動の“結果の質”を高めるためには、まずメンバー間の“”関係の質を高めるべきだという考え。
関係性が良くなれば、“思考の質”も向上する。思考の質が高まれば、“行動の質”も良くなり、結果の質が向上していく。53