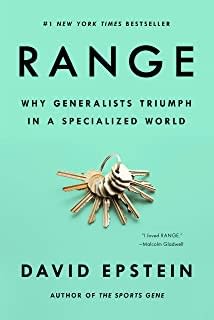レンジ
【学びたいこと】
理解度の振り返り
世界への行き方の提示
①この本
【概要】
AIに人間は余裕で勝てる
1万時間の法則の嘘ほんと
不確実性の高い時代に必要なのは、専門特化、ヘッドスタートではない
チェス・ゴルフ:
0-0-0
あなたにとって大切な活動が、すベてチェスやゴルフのようなものではない28
→
◉同じパターンが繰り返され、非常に正確なフィードバックが、通常はすぐに提供される分野
◉こういうカテゴリーなら意識的な練習、1万時間の法則は適応される
親しんだパターンを直感で思い出して活用すること
◉繰り返されるパターンを膨大に学ぶ
▲
内容を成文化できて、コンピューターに渡せるならば、コンピューターのほうがうまくできる。33
結論:
訓練の幅の広さは、応用の幅の広さにつながる。109
◉考える方法を学ぶ前に専門特化しすぎるな
◉人生とは? 実験、経験の旅である
◉より道をすること
後れを取ったと思わないこと
自分を誰かと比べるなら、自分より若い人ではなく、自分自身と比べよう。成長のスピードは人それぞれであり、他の人を見て後れを取ったとは思わないことだ。399
▲
生み出す作品が多ければ多いほど失敗作が増えていき、同時に画期的な作品を生み出す可能性も高まる。396
▲
②-a
◉核心
★★★自分のスキルを同じようなことが行われていない場所に持っていく。自分のスキルを新しい問題に使ってみる。372
自分がどんな人間であるかは、実際に生きることによってのみ知り得る。前もって知ることはできない。223
★★★「遠くまで見通せる鳥のほうが優れいているとか、深くまでみることができるからカエルのほうが優れいていると考えるのは、愚かなことだ。
私たちには、焦点の定まったカエルと視野の広い鳥が両方とも必要だ。
世界を開拓するためには鳥とカエルが一緒に働く必要がある。」〜ダイソン277
★★★学習では、経験をすべて脇に置かなければならない場合もある。318
★★★任天堂は「違うやり方でイノベーションを起こした。ゲームをやらない人がいるのは画質のためではなく、ゲームが複雑だからだということを任天堂は理解していた」〜クレイトン・クリステンセン 275
◉未知の状況における予測の立て方:学習的スタンス+アナロジー 類推思考
スタート:ありとあらゆることに関しての純粋な好奇心310
科学にとても興味のある人たちは、その内容が自分の現在の信念に合っていなくても、常に新たなエビデンスを見ることを選んだ。314
◉予測者は、問われている出来事の中身にだけフォーカスするのではなく、根底にある構造が似ている出来事のリストをつく理、それによって予想の精度を高める。317
②-b ここの思考法
▲A
・正しく問いを立てる思考 286
◉まず核となる問いを考え、専門知識をもっている人にそれを質問する。286
◆水平思考:情報を別の文脈に置き換えてイメージし直しこと。277
★★★よく位置付けられた問題は、半分解決されている〜ジョン・デューイ161
B
★★★アナロジー思考は、新しいものをなじみ深いものにする。145
予期せぬ問題を前に、どれだけお幅(レンジ)のアナロジーを使えるかによって、どれだけ新しいことを学べるかが決まった。166
あまり見られない課題だと、もっと遠いアナロジーが活用される。表面的な類似性から離れて、深いところにある構造的な類似性を探究する。165
◉ゴッホとマッチクオリティ
★★★「1つ確かなことは、お前は芸術家じゃないってことだ」
「始めるのが遅すぎたな」ゴッホが若かりしに日に浴びせられた言葉。
ゴッホの方向転換は徹底していて、夜の空を描くときにも黒を使わなくなったほどだ。
青年は新しい芸術を生み出した。激しく、絵具を大量に使い、色彩にあふれ、永遠のものを捉えることを除いて何のルールもない芸術だ。177
「勝者」は合っていないと感じたら早くやめ、やめることについて悪い感情を抱かない。190
ファン・ゴッホは、選択肢をあらん限りの力で試し、それが自分の合っているかを。できるだけ早く知ろうとした。201
「ゴッホがいたから、アーティストの行動が変わった」178
※ゴッホは、画家になるまでに、書店員、聖職者などかなりの職を転々とした。
重要なことは最初は誰もゴッホが画家に向いていないと思っていたこと。
<人生の方向性を定めるには?>
昨日のことを話しても仕方ないわ。だって、昨日の私は今日の私と違うもの。〜アリス『フシの国のアリス』222
▲
C
マッチクオリティ:
経済学の用語で、ある仕事をする人とその仕事がどれくらい合っているか、つまり、その人の能力や性質と仕事の相性を表す言葉だ。180
★★★何らかの目的を達成するために大きな力が必要だが、その大きな力を直接かけることができない場合、さまざまな方向から同時に力をかけても、同じ効果をもたらす可能性がある。149
事実:
◉誰もがさまざまな領域を行き来する、思考習慣が必要だということだ。70
◉経験なしで学ぶ:
言い換えると、新しいアイデア同士を結びつけ、領域を超えて考えることができる概念的な論理能力が、急速に変化する「意地悪な」世界で求められている。75
▲
C
計算的論理思考では、複雑で大きな問題に取り組むとき、その問題を抽象化し、分解し、問題を適切に象徴することがらを選び出す71
◉新しい発想を生むためにできること
D
アウトサイドインの思考:
★自分の専門分野から遠いほど解決できる可能性が高い245
★★★大きなイノベーションというのはほとんどの場合、その問題から遠く離れた分野の人が、問題を別の角度から捉え直して、解決策を生み出している。245
対象となる問題から遠く離れた分野の経験をもとに、解決方法を見つけることだ。239
<サンプリング期間の過ごし方>
◉ゆっくり専門を決めることが成功のカギ14
エリート選手=スポーツは体験期間sampling periodを経て、専門特化している
サンプリング期間には、さまざまなスポーツを自由に体験している。
▲
上達した生徒たちの練習量が他の生徒たちよりも大きく増え始めるのは、自分がフォーカスしたい楽器がわかってあkらだ。その楽器が他の楽器よりもうまく演奏できたり、好きだったりしたために、その楽器を選んでいる。93
★★★「片足を別の世界に置いておくこと」
ノーベル賞を受賞した人たちでは、アマチュアの俳優やダンサー、マジシャンなどのパフォーマーである確率が少なくとも22倍高い。
一つの領域で取り組む課題を大幅に多様なものにすること。49
★★★問題が曖昧で、明確なルールがない「意地悪な」世界では、「幅(レンジ)」が人生を生産的、かつ効率的にするための戦術となる。52
事実〜
★★★今の子供たちは、昔に比べて、明示されていないルールやパターンを、よりうまく探し出せるということだ。57
前提〜パターン認識=科学のメガネ
私たちは「科学のメガネ」で世界を見ている。つまり直接の経験に頼るのではなく、分類の仕組みを通じて現実を理解し、何層もの抽象的な概念を使って、情報同士の関係を理解する。私たちは分類の仕組みの世界で成長していきた。63
▲
<これからの時代に必要な学び>=フェルミ推定しかり、関係性を意識する
◉関係を意識することで学びは深くなる。
★★★最も優れた問題解決者は、まず、どんなタイプの問題かを解明するために頭を絞り、つぎにその問題い適した戦略を適用する。135
◉学習効果を高めること E
・望ましい困難
学習における障壁=すぐにヒントがなく自ら答えを出さざるを得ない状況
・生成効果
自分一人で答えを出そう(生成しよう)と奮闘することは、たとえ出した答えが間違っていても、その後の学びは強化される。121
・過剰修正効果
学習者の答えが間違っていて、その人がその答えに自信を持っていればいるほど、正しい答えが強く記憶に残るということだ。122
★★★最良の学びの道はゆっくりしたもので、あとで高い成果をあげるためには、今出来が良くないことが不可欠だ。127
◆知識移転:
ある分野、エリアで起きたことを別の分野、地域で応用すること
★★★長く使える知識は柔軟なもので、メンタル・スキーマ(考え方や枠組みや法則)によって、構成され、それが新しい問題に適用される。
知識の構造がとても柔軟で、新しい血強いや全く新しい状況にその知識を効果的に適用できるとき、そうした適用を「遠い移転」と呼ぶ。138
◆未知に挑む〜アナロジー
◉深いアナロジー思考とは、表面上はほとんど共通性がないように見える領域やシナリオの間で、概念的な類似点を発見することだ。144
直感→アナロジー 視点を外に移す。
外的視点:現在の問題とは異なるものの中に、構造的な類似性を求めて精査する。
〜背景
★★★50歳の人は30歳の人に比べて、企業を立ち上げ大成功する確率が2倍高い。30歳の人たちは20歳の人たちよりも、その確率が高い。19
★★★誰もが自分の溝を深く掘り下げ続けることに専念しており、もしかしたら、隣の溝に自分が抱えている問題の答えがあるかもしれないのに、立ち上がって隣を見ようとしない。21
★★★経験は全く助けにならなかった。それどころか、経験は自信を高めはするものの、スキルを高めることはなかった。29
#子育て #子育てママ #子育てぐらむ #子育ての悩み #学び #コーチング #生き方 #自己成長 #スキルアップ #経験 #フリーランス #ビジネス #独立 #チャンス
【学びたいこと】
理解度の振り返り
世界への行き方の提示
①この本
【概要】
AIに人間は余裕で勝てる
1万時間の法則の嘘ほんと
不確実性の高い時代に必要なのは、専門特化、ヘッドスタートではない
チェス・ゴルフ:
0-0-0
あなたにとって大切な活動が、すベてチェスやゴルフのようなものではない28
→
◉同じパターンが繰り返され、非常に正確なフィードバックが、通常はすぐに提供される分野
◉こういうカテゴリーなら意識的な練習、1万時間の法則は適応される
親しんだパターンを直感で思い出して活用すること
◉繰り返されるパターンを膨大に学ぶ
▲
内容を成文化できて、コンピューターに渡せるならば、コンピューターのほうがうまくできる。33
結論:
訓練の幅の広さは、応用の幅の広さにつながる。109
◉考える方法を学ぶ前に専門特化しすぎるな
◉人生とは? 実験、経験の旅である
◉より道をすること
後れを取ったと思わないこと
自分を誰かと比べるなら、自分より若い人ではなく、自分自身と比べよう。成長のスピードは人それぞれであり、他の人を見て後れを取ったとは思わないことだ。399
▲
生み出す作品が多ければ多いほど失敗作が増えていき、同時に画期的な作品を生み出す可能性も高まる。396
▲
②-a
◉核心
★★★自分のスキルを同じようなことが行われていない場所に持っていく。自分のスキルを新しい問題に使ってみる。372
自分がどんな人間であるかは、実際に生きることによってのみ知り得る。前もって知ることはできない。223
★★★「遠くまで見通せる鳥のほうが優れいているとか、深くまでみることができるからカエルのほうが優れいていると考えるのは、愚かなことだ。
私たちには、焦点の定まったカエルと視野の広い鳥が両方とも必要だ。
世界を開拓するためには鳥とカエルが一緒に働く必要がある。」〜ダイソン277
★★★学習では、経験をすべて脇に置かなければならない場合もある。318
★★★任天堂は「違うやり方でイノベーションを起こした。ゲームをやらない人がいるのは画質のためではなく、ゲームが複雑だからだということを任天堂は理解していた」〜クレイトン・クリステンセン 275
◉未知の状況における予測の立て方:学習的スタンス+アナロジー 類推思考
スタート:ありとあらゆることに関しての純粋な好奇心310
科学にとても興味のある人たちは、その内容が自分の現在の信念に合っていなくても、常に新たなエビデンスを見ることを選んだ。314
◉予測者は、問われている出来事の中身にだけフォーカスするのではなく、根底にある構造が似ている出来事のリストをつく理、それによって予想の精度を高める。317
②-b ここの思考法
▲A
・正しく問いを立てる思考 286
◉まず核となる問いを考え、専門知識をもっている人にそれを質問する。286
◆水平思考:情報を別の文脈に置き換えてイメージし直しこと。277
★★★よく位置付けられた問題は、半分解決されている〜ジョン・デューイ161
B
★★★アナロジー思考は、新しいものをなじみ深いものにする。145
予期せぬ問題を前に、どれだけお幅(レンジ)のアナロジーを使えるかによって、どれだけ新しいことを学べるかが決まった。166
あまり見られない課題だと、もっと遠いアナロジーが活用される。表面的な類似性から離れて、深いところにある構造的な類似性を探究する。165
◉ゴッホとマッチクオリティ
★★★「1つ確かなことは、お前は芸術家じゃないってことだ」
「始めるのが遅すぎたな」ゴッホが若かりしに日に浴びせられた言葉。
ゴッホの方向転換は徹底していて、夜の空を描くときにも黒を使わなくなったほどだ。
青年は新しい芸術を生み出した。激しく、絵具を大量に使い、色彩にあふれ、永遠のものを捉えることを除いて何のルールもない芸術だ。177
「勝者」は合っていないと感じたら早くやめ、やめることについて悪い感情を抱かない。190
ファン・ゴッホは、選択肢をあらん限りの力で試し、それが自分の合っているかを。できるだけ早く知ろうとした。201
「ゴッホがいたから、アーティストの行動が変わった」178
※ゴッホは、画家になるまでに、書店員、聖職者などかなりの職を転々とした。
重要なことは最初は誰もゴッホが画家に向いていないと思っていたこと。
<人生の方向性を定めるには?>
昨日のことを話しても仕方ないわ。だって、昨日の私は今日の私と違うもの。〜アリス『フシの国のアリス』222
▲
C
マッチクオリティ:
経済学の用語で、ある仕事をする人とその仕事がどれくらい合っているか、つまり、その人の能力や性質と仕事の相性を表す言葉だ。180
★★★何らかの目的を達成するために大きな力が必要だが、その大きな力を直接かけることができない場合、さまざまな方向から同時に力をかけても、同じ効果をもたらす可能性がある。149
事実:
◉誰もがさまざまな領域を行き来する、思考習慣が必要だということだ。70
◉経験なしで学ぶ:
言い換えると、新しいアイデア同士を結びつけ、領域を超えて考えることができる概念的な論理能力が、急速に変化する「意地悪な」世界で求められている。75
▲
C
計算的論理思考では、複雑で大きな問題に取り組むとき、その問題を抽象化し、分解し、問題を適切に象徴することがらを選び出す71
◉新しい発想を生むためにできること
D
アウトサイドインの思考:
★自分の専門分野から遠いほど解決できる可能性が高い245
★★★大きなイノベーションというのはほとんどの場合、その問題から遠く離れた分野の人が、問題を別の角度から捉え直して、解決策を生み出している。245
対象となる問題から遠く離れた分野の経験をもとに、解決方法を見つけることだ。239
<サンプリング期間の過ごし方>
◉ゆっくり専門を決めることが成功のカギ14
エリート選手=スポーツは体験期間sampling periodを経て、専門特化している
サンプリング期間には、さまざまなスポーツを自由に体験している。
▲
上達した生徒たちの練習量が他の生徒たちよりも大きく増え始めるのは、自分がフォーカスしたい楽器がわかってあkらだ。その楽器が他の楽器よりもうまく演奏できたり、好きだったりしたために、その楽器を選んでいる。93
★★★「片足を別の世界に置いておくこと」
ノーベル賞を受賞した人たちでは、アマチュアの俳優やダンサー、マジシャンなどのパフォーマーである確率が少なくとも22倍高い。
一つの領域で取り組む課題を大幅に多様なものにすること。49
★★★問題が曖昧で、明確なルールがない「意地悪な」世界では、「幅(レンジ)」が人生を生産的、かつ効率的にするための戦術となる。52
事実〜
★★★今の子供たちは、昔に比べて、明示されていないルールやパターンを、よりうまく探し出せるということだ。57
前提〜パターン認識=科学のメガネ
私たちは「科学のメガネ」で世界を見ている。つまり直接の経験に頼るのではなく、分類の仕組みを通じて現実を理解し、何層もの抽象的な概念を使って、情報同士の関係を理解する。私たちは分類の仕組みの世界で成長していきた。63
▲
<これからの時代に必要な学び>=フェルミ推定しかり、関係性を意識する
◉関係を意識することで学びは深くなる。
★★★最も優れた問題解決者は、まず、どんなタイプの問題かを解明するために頭を絞り、つぎにその問題い適した戦略を適用する。135
◉学習効果を高めること E
・望ましい困難
学習における障壁=すぐにヒントがなく自ら答えを出さざるを得ない状況
・生成効果
自分一人で答えを出そう(生成しよう)と奮闘することは、たとえ出した答えが間違っていても、その後の学びは強化される。121
・過剰修正効果
学習者の答えが間違っていて、その人がその答えに自信を持っていればいるほど、正しい答えが強く記憶に残るということだ。122
★★★最良の学びの道はゆっくりしたもので、あとで高い成果をあげるためには、今出来が良くないことが不可欠だ。127
◆知識移転:
ある分野、エリアで起きたことを別の分野、地域で応用すること
★★★長く使える知識は柔軟なもので、メンタル・スキーマ(考え方や枠組みや法則)によって、構成され、それが新しい問題に適用される。
知識の構造がとても柔軟で、新しい血強いや全く新しい状況にその知識を効果的に適用できるとき、そうした適用を「遠い移転」と呼ぶ。138
◆未知に挑む〜アナロジー
◉深いアナロジー思考とは、表面上はほとんど共通性がないように見える領域やシナリオの間で、概念的な類似点を発見することだ。144
直感→アナロジー 視点を外に移す。
外的視点:現在の問題とは異なるものの中に、構造的な類似性を求めて精査する。
〜背景
★★★50歳の人は30歳の人に比べて、企業を立ち上げ大成功する確率が2倍高い。30歳の人たちは20歳の人たちよりも、その確率が高い。19
★★★誰もが自分の溝を深く掘り下げ続けることに専念しており、もしかしたら、隣の溝に自分が抱えている問題の答えがあるかもしれないのに、立ち上がって隣を見ようとしない。21
★★★経験は全く助けにならなかった。それどころか、経験は自信を高めはするものの、スキルを高めることはなかった。29
#子育て #子育てママ #子育てぐらむ #子育ての悩み #学び #コーチング #生き方 #自己成長 #スキルアップ #経験 #フリーランス #ビジネス #独立 #チャンス