本ブログの姉妹ブログ「本の宇宙」の書評記事「経済学の考え方」に色々とコメントをいただいていた。私の運営する3ブログの中で、一番閑散としているブログにアクセスが増えるのはありがたいが、本来あちらのブログは、本のレビューを中心とする運営をしており、また、コメント欄でやりとりするには長くなっているので、こちらのブログにて私の見解を述べたい。
○庶務さんへの回答
私が「雇用の流動化」に異議を述べている理由が理解できないとのことですが、その理由は、既に述べていると思います。もっと端的に言えば、雇用を流動化して市場原理に任せたとしても、はたして労働市場が効率的に働くかという疑問を持っているということです。市場は失敗をすることもああります。よく引き合いに出されるアダムスミスの「見えざる手」は、仮定を積み重ねたような実際にはありえない市場でしか働いてくれないでしょう。
仮に雇用規制を撤廃するとすると、経営者は一種のモラルハザードにより、経営努力をするより、安易なリストラで短期的な利益の確保に走る可能性があります。そしてその際に放出された労働力が、同等以上の条件でどこかに吸収されるという保証は全く無く、結局は社会不安を招き、かえって企業の業績にも悪影響を与えかねないと考えます。
また労働といっても反復的な単純労働から高度の知的労働まで様々なレベルがあります。これを層別せずに、十把一絡げで「労働市場」として扱うのは乱暴な議論でしょう。
庶務さんは、「ある個人の他の企業からの評価(すなわち賃金)は低くなるので、ある個人は転職をしないという決断を下すだけで、雇用の流動化への反論とはなりません。」と書かれていましたが、ここで問題としているのは「辞める自由」ではなく、「辞めさせる自由」の方であり、そこには「転職をしない」という結論はあり得ないということを指摘しておきます。
なお、私の意見は、あくまでも市場のユーザーとしてのものですので、疑義があるので異論を述べるという形になっています。これ以上の細かい学問上の理論的な前提や条件などが必要なら、それは、結論を同じくするという、経済学の専門家(の卵?)である庶務さんのほうでぜひ補強していただきたいと思っています。
○ bobbyさんへの回答
確かに、新卒採用への偏重は、もっと緩和しても良いと思います。それは、企業の中に多様性を与え、いわゆる「企業の論理」に走るリスクを低減する効果も期待できるでしょう。しかし、経営や開発などで、いわゆるヘッドハンティングのあるような業種は転職もしやすいでしょうが、例えば縁の下の力持ち的な部門でのキャリアを積んできた人には転職の敷居は高いでしょうね。
中国の場合、「あるプリンタの部品工場では、1000人の工員の約半分が1年で入れ替わります。」とのことですが、現在発展中の中国とどちらかというと枯れた国である日本を単純に比較することはできないと思います。発展中の中国の場合は、単に、別の職がいくらでもあるということでしょう。しかし、経済全体が不況となった場合は、別の職がすぐに見つかるという保証は無いと思います。
また、香港やシンガポールのように「3年から5年で社員が転職する社会では、社内のスキルは平準化して似たものとなります」とのことですが、日本の製造業では、現場レベルまで巻き込んでTQCやTPM活動の行えることが強みの一つだろうと考えます。「3年から5年」で転職しては、このような強みは構築できないのではないでしょうか。
(ぽちっとお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら
「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら
○庶務さんへの回答
私が「雇用の流動化」に異議を述べている理由が理解できないとのことですが、その理由は、既に述べていると思います。もっと端的に言えば、雇用を流動化して市場原理に任せたとしても、はたして労働市場が効率的に働くかという疑問を持っているということです。市場は失敗をすることもああります。よく引き合いに出されるアダムスミスの「見えざる手」は、仮定を積み重ねたような実際にはありえない市場でしか働いてくれないでしょう。
仮に雇用規制を撤廃するとすると、経営者は一種のモラルハザードにより、経営努力をするより、安易なリストラで短期的な利益の確保に走る可能性があります。そしてその際に放出された労働力が、同等以上の条件でどこかに吸収されるという保証は全く無く、結局は社会不安を招き、かえって企業の業績にも悪影響を与えかねないと考えます。
また労働といっても反復的な単純労働から高度の知的労働まで様々なレベルがあります。これを層別せずに、十把一絡げで「労働市場」として扱うのは乱暴な議論でしょう。
庶務さんは、「ある個人の他の企業からの評価(すなわち賃金)は低くなるので、ある個人は転職をしないという決断を下すだけで、雇用の流動化への反論とはなりません。」と書かれていましたが、ここで問題としているのは「辞める自由」ではなく、「辞めさせる自由」の方であり、そこには「転職をしない」という結論はあり得ないということを指摘しておきます。
なお、私の意見は、あくまでも市場のユーザーとしてのものですので、疑義があるので異論を述べるという形になっています。これ以上の細かい学問上の理論的な前提や条件などが必要なら、それは、結論を同じくするという、経済学の専門家(の卵?)である庶務さんのほうでぜひ補強していただきたいと思っています。
○ bobbyさんへの回答
確かに、新卒採用への偏重は、もっと緩和しても良いと思います。それは、企業の中に多様性を与え、いわゆる「企業の論理」に走るリスクを低減する効果も期待できるでしょう。しかし、経営や開発などで、いわゆるヘッドハンティングのあるような業種は転職もしやすいでしょうが、例えば縁の下の力持ち的な部門でのキャリアを積んできた人には転職の敷居は高いでしょうね。
中国の場合、「あるプリンタの部品工場では、1000人の工員の約半分が1年で入れ替わります。」とのことですが、現在発展中の中国とどちらかというと枯れた国である日本を単純に比較することはできないと思います。発展中の中国の場合は、単に、別の職がいくらでもあるということでしょう。しかし、経済全体が不況となった場合は、別の職がすぐに見つかるという保証は無いと思います。
また、香港やシンガポールのように「3年から5年で社員が転職する社会では、社内のスキルは平準化して似たものとなります」とのことですが、日本の製造業では、現場レベルまで巻き込んでTQCやTPM活動の行えることが強みの一つだろうと考えます。「3年から5年」で転職しては、このような強みは構築できないのではないでしょうか。
(ぽちっとお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら

「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら













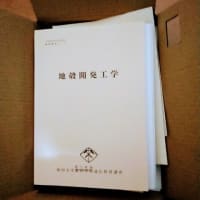












これを経営者のモラルハザードと言うのは、資本主義の理念からいってどうかと思います。株主が企業の短期的な利益向上を求め、経営者が株主の期待に沿って、即効性の高い利益改善策として不採算部門でのレイオフを行う事は、経営者として合理的行動だと理解します。
逆に労働者が自分の生存する責任を企業に取らせよううとする現在の慣習も、香港で生活する私から見ると大変無責任に見えます。
沈没中のタイタニック号の船室で、レストランのウェイトレスのマナーを叱っても、1時間後にみんな死んでいるのなら意味がありません。
おそらく21世紀中ずっとグローバリゼーションが進行するであろう世界的環境の中で、TQCやTPM活動といっても意味があるとは思えません。企業は生き残る為に、可能で合法で合理的な事は何でもするでしょう。20年後の国内工場の作業が、ほとんどはロボットが行われていたとしても私は驚きません。
私のブログに「官僚達の夏」の教訓として書きましたが、駄目だとわかっている事は、抵抗するよりも早めに手を打つ事です。行政に何かできるとすれば、いま工場労働者を守る事よりも、工場労働者をどのように将来性のある業種へ転換させるかを、問題が深刻化する前に手を打つべきです。
http://bobby.hkisl.net/mutteraway/?p=1628