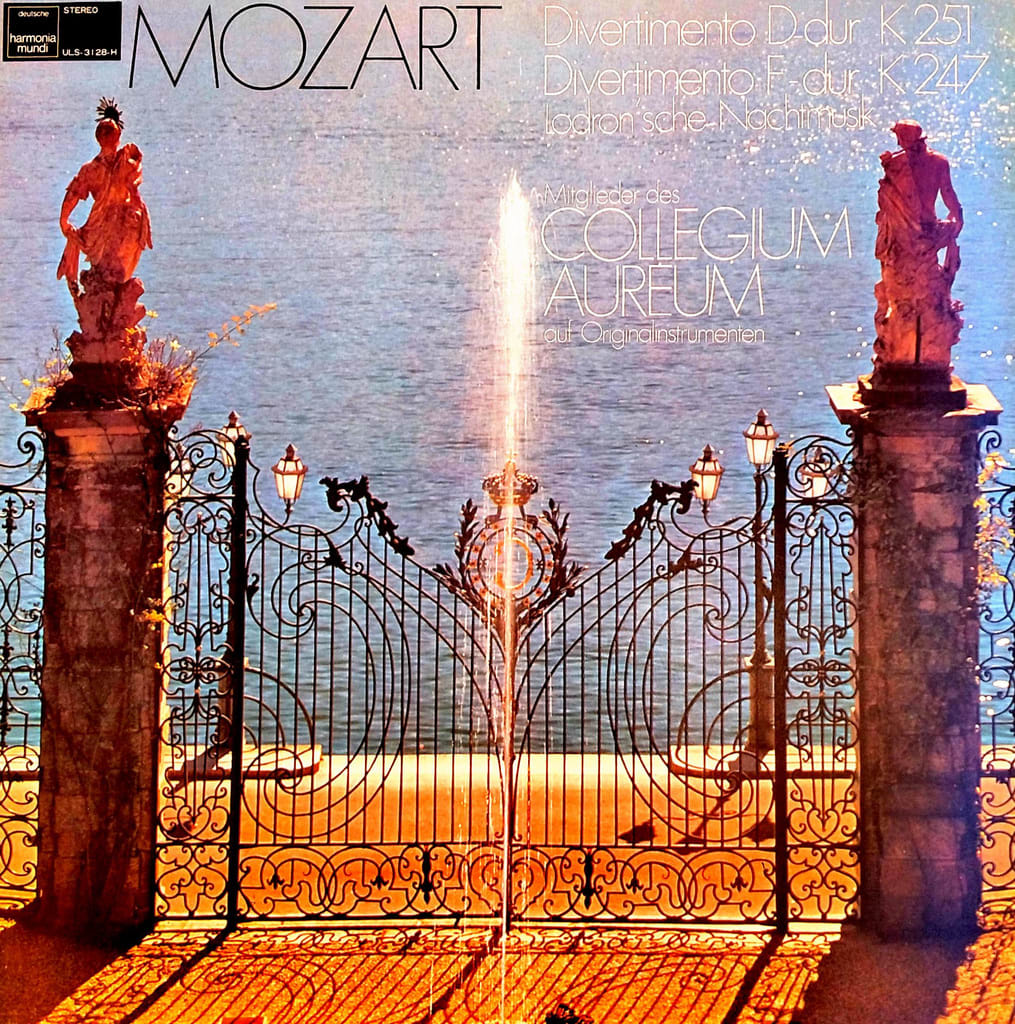シェーンベルク:浄夜
ワーグナー:ジークフリート牧歌
ヒンデミット:ヴィオラと弦楽合奏のための葬送音楽
指揮:ダニエル・バレンボイム
管弦楽:イギリス室内管弦楽団
ヴィオラ:セシル・アロノヴィッツ(ヒンデミット)
LP:東芝EMI EAC‐30336
このLPレコードの1曲目はシェーンベルク:浄夜。この曲は、1899年、シェーンベルクが25歳の時にウィーンで作曲した弦楽六重奏曲が元の曲。リヒャルト・デーメルの、月下の男女の語らいが題材となっている同名の詩「浄夜」に基づいて作曲されている。シェーンベルクというと無調音楽や12音階音楽の創始者というイメージが強いが、この作品は後期ロマン派、とりわけワーグナーやブラームスから影響を受けた作品で、半音階や無調の要素を取り入れはいるものの、いわゆる現代音楽とは程遠い作品だ。全体はデーメルの詩に対応した5つの部分からなる、30分ほどの単一楽章からなっている。つまり、この曲は、完全に表題音楽であり、しかも室内楽曲という非常に珍しい形態の曲だ。この曲を聴くには、デーメルの詩「浄夜」をあらかじめ読んでおく必要がある。このLPレコードには、その一節が54行にわたって紹介してある(入野義朗訳)ので、鑑賞には打って付けである。シェーンベルクは、この曲を、1917年に自ら弦楽合奏用に編曲した。2曲目は、ワーグナー:ジークフリート牧歌。この曲は、室内オーケストラのための作品で、妻コジマへの誕生日の贈り物として作曲されたもの。1870年12月25日に、スイスのルツェルン湖畔の自宅のコジマの寝室の傍らの階段に陣取った15人の楽士と作曲者自身の指揮で演奏された。それを聴いた妻のコジマは大変感激したと言われている。3曲目は、ヒンデミット:ヴィオラと弦楽合奏のための葬送音楽。この曲は、8分ほどの短い曲。ちょうどヒンデミットがロンドンに滞在していた時に、国王のジョージ5世が崩御され、哀悼の曲として作曲されたもので、ヒンデミットは、徹夜をして一晩で仕上げたという。全体は、4つの部分からなるが、全楽器が弱音器をつけて演奏する終曲は、コラール「我汝の玉座の前に立つ」の旋律に基づいている。このLPレコードは、まずこれら3曲の選曲のセンスの良さが光る。それと、名ピアニストであるダニエル・バレンボイムが、指揮者としても超一流の腕を持っていることを証明した初期の頃の録音内容だ。イギリス室内管弦楽団とバレンボイムとが一体化し、芳醇な音質に加え、微妙なニュアンスの表現が一際優れている。とりわけ、シェーンベルク:浄夜では、緊迫した男女のやり取りを巧みに表現し尽して、同曲の録音の中でも最高のレベルに位置づけられよう。ワーグナー:ジークフリート牧歌では穏やかな表現力が光るし、ヒンデミット:ヴィオラと弦楽合奏のための葬送音楽では、鎮魂の思いがよく表現されている。(LPC)