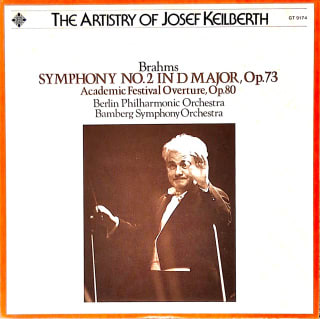モーツァルト:ヴァイオリンソナタ 変ロ長調 K.378
ホ短調 K.304
ヘ長調 K.376
ト長調 K.301
変ロ長調 K.454
イ長調 K.526
ヴァイオリン:アルテュール・グリュミオー
ピアノ:クララ・ハスキル
LP:日本フォノグラム(フィリップス・レコード) SFL‐9662~63
このLPレコードは、ヴァイオリンのアルテュール・グリュミオー(1921年―1986年)とピアノのクララ・ハスキル(1895年―1960年)の名コンビによるモーツァルト:ヴァイオリンソナタ選集である。ジャケットを見ると晩年のクララ・ハスキルの姿が大きく配置され、アルテュール・グリュミオーの姿は見えない。これはこのLPレコードが、“クララ・ハスキルの遺産”というシリーズの第4集に当たるため。それに、モーツァルトのヴァイオリンソナタは、当時の一般的な傾向として、ヴァイオリンソナタという名前は付いているが、実際にはヴァイオリンとピアノが対等か、あるいは、ピアノが主役でヴァイオリンが伴奏役に回ることも珍しくない。このLPレコードのライナーノートで、小石忠男氏は「ハスキルとグリュミオーの個性はかなり違いがあり、普通ならこれほど美しい二重奏は成立しなかったのではないかと思われる」と書いている。これを見て私は一瞬目を疑った。しかし、よく考えてみると、小石氏の言わんとすることを理解できた。アルテュール・グリュミオーは、フランコ・ベルギー楽派の正統的な後継者である。フランコ・ベルギー楽派は、ヴァイオリンを輝かしく響かせ、美しい旋律を優雅に演奏するスタイルをとる。つまり、演奏効果が常に外向きであり、きらびやかさが身上である。これに対し、クララ・ハスキルのピアノ演奏は、精神性の高いもので、どちらかというと演奏効果は、内向きになる傾向がある。普通、そんな二人がコンビを組んでも良い効果は出にくいと思われる。しかし、ハスキルとグリュミオーのコンビは、それが逆に作用し、互いの特徴を一層際立たせる効果をもたらす。そのことは、二人が一番知っていることを、このLPレコードを聴くとよく分かる。このLPレコードは、全部でモーツァルト:ヴァイオリンソナタ6曲が2枚に収録されているが、いずれの曲も甲乙を付け難いほど完成度の高い演奏内容となっている。ある意味で、モーツァルト:ヴァイオリンソナタ演奏の決定版的な録音であり、このコンビを上回ることは至難の技と言えよう。しなやかに歌うように奏されるグリュミオーのヴァイオリンを、ハスキルのピアノがやさしく見守るように、限りなく美しも流麗に弾かれ、二人の演奏は、聴いていて時が経つのも忘れそうになる。グリュミオーは、来日時のインタビューで「あなたの一番好きなレコードは」と問われ、即座に「ハスキルと共演したモーツァルトのヴァイオリンソナタ」と答えたそうである。(LPC)