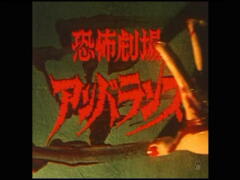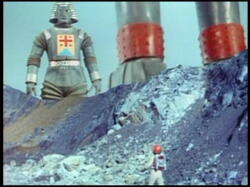『いとしのファブリオ』(1990年放映)コンプリート。…いや、スカパー見ながら作業していたら、む?何やらとんでもない人形劇がやっているぞ?という事で録り始めたのがこの番組です。『カノッサの屈辱』(1990年放映)とか、『NIGHT HEAD』(1992年放映)とか、『征服王』(1992年放映)とかやっていた、フジテレビの深夜番組シリーズの一つですね。(…あ、この時間帯で『シチリアの龍舌蘭』もやっていたのか…)いや、僕、ファブリオーってよく知らないんですけど…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BC
ファブリオー(ファブリオ、fabliau, 複数形:fabliaux または fablieaux)は、13世紀頃にフランス北東部でジョングルールによって作られた喜劇的な、一般に匿名の説話のこと。韻文世話話と訳される。ファブリオーは概してこのうえなく下品である。
(Wikipediaより)
…という事みたいで。多分、男同士、あるいは女同士で集まった時にする猥談の起承転結あるやつを集めた説話集な感じじゃないかと思うんですが…どうなんでしょう。このファブリオーを、きたろうと、池上季実子(!)の語りで、人形劇で上演するというかなり異色な作品です。
…というか人形劇でここまでやっていいのか?否、人形劇だから、ここまで放送できるのか?という、相当エロスな番組になっています。まあ、何と言うか男も女も強かに、とにかく“やってる”話になっています。えっと……ぱらっと抜き出した1話を引用してみると…

娘は従順に従い、白い指を灼熱の高まりに結びつけると、ゆっくりと動かしはじめる…
司祭「ううう……まだだ」
娘「しつこい悪魔ですね…」
司祭「どうしても、(悪魔が)飛び出さない………では、お前の口で吸いだしてはくれんか」
娘「吸いだす?」
司祭「砂漠で、毒蛇に噛まれたらどうする…?」
娘「…!傷口から、毒を吸い出します…」
娘は納得して、高まりきった司祭に、唇を近づける……
(第18話「悪魔祓いの儀式(2)」より)
…うむ。なんというエロゲ(`・ω・´) というか、エロマンガネタやね。というか、この展開の元ネタ、ファブリオーだったのか!……いやw人類が寄り集まれば、どこでも出てくる猥談でしょうねw…というワケで、ちょっと変わった人形劇番組でした。ふう……また、いいモノを録ってしまったぜぇ(`・ω・´)