今日は街道歩き2日目です。
天候は好天、昨日に続き快適な街道歩きが期待できそうですが、一つ問題は蟹田宿で津軽線とお別れしなければいけない事です。
今回の街道歩きは、ほぼ国道280号に辿って歩きます。この280号線と並行する形でJR東日本・津軽線が走っているので、何かアクシデントが発生した場合でも、津軽線の駅に辿り着ければ電車を利用する事ができます。
しかし、津軽線は蟹田宿(蟹田駅)から内陸に向かうので、蟹田駅以降は電車の利用ができず、今日の目的地とした平館宿までは何としても自力で歩くしかありません。
今日の街道歩きは、スタートが蓬田宿、打止めが平館宿です。
歩行距離は、蓬田宿から蟹田宿間が8.2km、蟹田宿から平館宿間が13.5km、合わせて21.5kmを予定しています。これまでの経験から、見学しながら、写真を撮りながらでは、1時間で歩く距離は3km程なので、計算では7時間ほど歩かなければいけない事になります。
打止め(宿到着)時間を15時と想定すると、昼食時間など加味すれば蓬田宿を7時にはスタートしたいところです。蓬田宿に停車する電車は蟹田駅始発が5:32で、以降は7:06、9:20発なので、前日投宿の際に朝食時間を6時15分でお願いし、7:06発の電車に乗車し、蓬田宿を7時16分スタートと計画しました。 
宿泊した「中村旅館」さんは街道筋にあるので、なるべく蓬田宿・蟹田宿間は身軽で歩こうと不要な荷物は旅館に預かってもらいました。
蓬田駅から歩き、今日のスタートとなる街道筋に立つと左手に立派なお寺「正法院」さんが見えます。寛文7年(1667年)に木喰僧・円空が、この街道を北上し蝦夷地(北海道)に渡ったそうですが、こちらのお寺にも円空仏「木彫観世音菩薩坐像」が伝わっているようです。

その先に、二級河川の阿弥陀川が流れていますが、その畔に赤い鳥居が見えてきます。
こちらは稲荷神社です。
今日の朝のルーチンは、稲荷神社での旅の安全祈願となります。こちらの稲荷神社には二組の狛犬が奉納されています。その内の狛犬一対(大正十二年建之)をご覧ください。


狛犬の阿像、不二家のペコちゃんのように下をペロッと上向きに出しています。街道歩きではたくさんの狛犬たちを見てきましたが、このような姿は初めて出会いました。
川を渡ると左手が蓬田村役場です。明治22年(1889年)4月1日の町村制施行で蓬田村、長科村、中沢村、阿弥陀川村、郷沢村、瀬辺地村、広瀬村が合併し蓬田村が誕生しました。総面積は80.84平方キロメートル、その約80%が山林のようです。人口は、10月末時点で2,819人、世帯数は1,153世帯です。 時刻は7時50分過ぎ、小学校のスクールバスが子供たちを乗せて出発するところでした。

蓬田漁港を過ぎ、郷沢駅を過ぎ、村役場から40分弱歩くと玉松海水浴場に隣接した「よもぎた物産館マルシェよもぎた」に到着です。幸い営業時間が8時からなので立ち寄ってみました。


新鮮な野菜や村の特産品が並べられ、特に看板にもあるように「トマト」が有名のようです。私達もミニトマトを購入し、海を見ながら、トマトを食べながら、暫し休憩しました。
9時過ぎ、街道筋に戻り出発です。

しばらく進むと左手に小さな社があります。これまでも、街道筋にはこのような地蔵尊を祀る小さな社が百万遍石塔と共に何カ所も祀られていますが、集落の境に設けられているような気がします。
瀬辺地駅を過ぎ、津軽線は街道から離れますが蟹田駅に近づくにつれ、海岸線と280号線、津軽線が接近してきます。そんな所に蟹田駅9時20分発の津軽線の上り電車が通過して行きました。
私達は、この間暫く280号線下にある防波堤の上が道路の様になっているので、海を眺めながら歩きました。
10時少し前に蓬田村から旧蟹田町(現外ヶ浜町蟹田)に入りました。
ここから10分程進むと左手に「八幡宮」が見えてきます。
お参りに境内に入ると、こちらにも二対の狛犬が奉納されています。初めに出会う狛犬もユニークで、おかっぱ頭をしているような感じがします。昭和6年奉納とありました。


こちらは本殿に近い狛犬です。風化した感じが、可哀そうな、不気味なような、偶然出会った神社関係の方の話では、大正時代に奉納されたもので、冬期に松の枝に積もった雪が解け落ちて狛犬を侵食したとの事でした。


参拝を終わり、しばらく進むと蟹田駅入口です。地方の街道歩きで困るはトイレと食事、時になかなか見付ける事ができず困ってしまいます。これまでトイレは、駅か食事を採るお店、運が良ければ寺社でと言った感じです。今回も蟹田駅近くの公衆トイレを利用するため街道筋を少し離れます。
街道に戻る前に、旅館から蟹田駅に向かう途中で見つけた真宗大谷派のお寺「長楽寺」を参拝する事にしました。

その後、「中村旅館」さんに寄り、預かって頂いた荷物を受け取り、リュックの重さに耐えながらの街道歩きが始まります。 蟹田川を渡り、しばらく進むと右手に高い建物が見えてきたので、何だろうと思い建物に向かいました。この建物、「風のまち交流プラザ・トップマスト」と言い、観瀾山公園海水浴場に隣接し地上30mの展望台となっているようです。1階には、蟹田の特産品を販売する売店と津軽と下北を結ぶ陸奥湾フェリーの乗船手続き所があります。一日2往復、蟹田港から脇野沢港間を就航しています。
売店のお姉さんが、展望室まで階段を上ると素晴らしい景色が見えますよと教えてくれたので、覚悟を決め登る事にしました。 実は、階段のステップが格子状で下が見えてしまうので、高所恐怖症に打勝ち上らなければいけないのです。
でも、展望台からの景色は最高です。 こちらは、眼下が観瀾山公園海水浴場、遠景は今日の打止めとする平館宿方面です。
こちらは、眼下が蟹田港、遠景は下北半島です。
11時過ぎ、トイレも済ませ街道に戻ります。蟹田塩越地区まで40分程、この辺りは京都・伊根の舟屋のような感じの建物が続きます。


国道沿いには、トイレ休憩できる場所が殆んどありませんが、唯一「ゆとりの駐車場」が4~5kmの間隔で設けられているので助かります。そして、待望の「松前街道」と書かれた石柱を見つけ、街道を歩いている実感が湧いて来ました。


一段と下北半島が近づいて来たようです。

しばらく進むと平館地区に入ったようです。テトラポットにはカモメ?ウミネコ?が陽を浴び、アザミには遠距離を移動するアサギマダラ?(この時期にこの地域にいるのかなー?)が留まっているので、気付かれないようにパチリ。


13時過ぎ、平舘舟岡地区に入ったようです。久須志神社の鳥居がありますが社が全く見えないので、参拝に向かうのをためらってしまいます。

13時30分、平舘今津尻高地区で国道280号線を右に曲がり、今津と書かれている旧道に入って行きます。これまで食堂が見付からず、昼食がわりに蟹田駅近くの物産店で購入したリンゴしか食べていません。ホタテの看板を見て近くに食堂がありホタテを食べる事ができると思ったのですが、残念ながら、この看板は春の街道歩きで通った平内町の「ほたて広場」のものでした。
 国道280号線は松並木が続いているようです。
国道280号線は松並木が続いているようです。
分岐から10分ほど歩くと平館今津間沢地区となります。左手に稲荷神社が見えますが、階段を見ると写真だけ撮って参拝はパスします。

さらに10分ほど歩くと平館野田山下地区に入ります。これまでも、たくさん見てきましたが、左手に地蔵堂と百万遍碑があります。やはり、集落の境に造られているようです。

ここから少し進んだ所に「吉田松陰 乗船の場」と書かれた、新しそうな案内板を見つけました。さて、この地からどこに向かったのか?

時刻は14時30分過ぎ、食堂や食品を購入できるお店が全くありません。あ~腹へった~。仕方なく、先を急ぎ歩いていると湯の沢温泉「ちゃぽらっと」の案内板を発見、スマホで調べてみると日帰り温泉施設で食事もできそうです。そこで、街道から離れ施設に向かいました。 ところが、到着してみると何と残酷な事か「本日休館日」とあります。
よく考えて見れば、今日は月曜日、公共施設であれば休みは納得できます。ここでの食事を諦め、今日の宿泊場所「ペンションだいば」近くにある、道の駅「たいらだて」目指し街道に戻ります。 30分ほど歩くと左手に「平舘神社」の鳥居が見えてきました。
ここから10分ほど歩くと、旧道の両側は松並木が続き、「津軽国定公園」の標識があります。津軽国定公園は、東津軽郡外ヶ浜町(旧平舘村)から西津軽郡深浦町(旧岩崎村)に至る、延長約180キロメートルの海岸部と山岳部、湖沼群等から成り、昭和50年3月31日に指定されました。 高野崎や竜飛岬、十三湖や屏風山、世界自然遺産に登録されている白神山地や青池で有名な十二湖などが含まれる広範なエリアのようです。

この辺りから、砂防林となっているのか松林が続きます。また、松林の中にはハマギクの群生が見られます。


海岸線は平舘海水浴場となっているようです。遠景で見えるのは下北半島です。
しばらく進むと、幕命に寄り津軽藩が外国船の警戒のために造った西洋式台場の土濠跡が扇状に残っています。吉田松陰が、嘉永五年(1852年)3月に、台場と附近の情景を「東北遊日記」に残しているそうです。 

そして、台場跡の隣には国道280号沿いに立つ真っ白な平舘灯台あります。一般的に灯台は岬の突端近くにあるので、国道沿いにあるのは珍しいようです。平舘灯台は、鉄筋コンクリート造の高さ23m、灯火標高23mで、明治32年(1899年)に設置され、昭和35年(1960年)に改修され、外壁は白色ペンキ塗り仕上げられています。
 今日の宿泊は、この灯台の近くにある「ペンションだいば」です。時刻は16時過ぎ、チェックインには丁度良い時間です。チェックインを済ませましたが、夕暮れにはまだ少し時間が有るので付近を散策しました。付近には、コテージやオートキャンプ場などの施設がある「おだいばオートビレッジ」と目標としていた道の駅「たいらだて」があります。道の駅に寄ってみましたが、残念ながら16時で閉館していました。 結局、今日の昼食はリンゴだけとなりました。
今日の宿泊は、この灯台の近くにある「ペンションだいば」です。時刻は16時過ぎ、チェックインには丁度良い時間です。チェックインを済ませましたが、夕暮れにはまだ少し時間が有るので付近を散策しました。付近には、コテージやオートキャンプ場などの施設がある「おだいばオートビレッジ」と目標としていた道の駅「たいらだて」があります。道の駅に寄ってみましたが、残念ながら16時で閉館していました。 結局、今日の昼食はリンゴだけとなりました。


宿に戻る前に、もう一度海を眺めに海岸線向かいました。宿に戻って、夕食時間は早めの18時でお願いし、疲れをとろうとお風呂に向かいました。


本日の予定歩行距離21.5km程、歩数計は前日宿泊した中村旅館を出てから39,911歩を示していました。

















 (
(
 (
( (
( (
(
 (
( (
(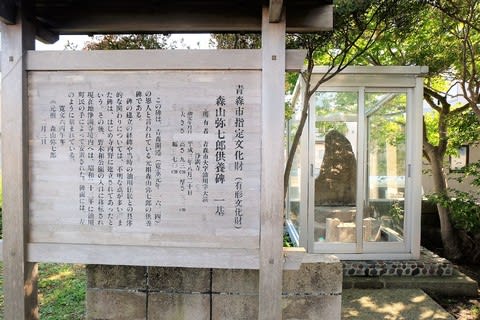


 (
( (下北半島方向)
(下北半島方向)






 (
(


 (T-4)
(T-4)

















 (飛来時です)
(飛来時です) 






























