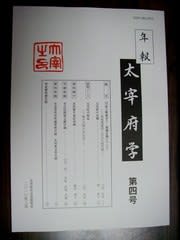先日、太宰府市の北東にそびえる名峯・宝満山の北谷に行ってきました。
ここには博多三代古刹のひとつに数えられる承天寺の別院があります。
別院が所有されている山林には、将来の寺院の建て替えを見越したヒノキが
育ち、管理されています。
この山林には実に多くのコシアブラが育っています。
コシアブラは1~2メートルくらいの高さで直径1~2㎝未満の若木です。

そこで承天寺別院にお住まいの遠藤住職さまに、年に1~2度の下草刈り
をしつつ、コシアブラを育成させてほしいとお願いしにお伺いしました。

コシアブラの若木を確認していただき…。
快く了解していただきました。
具体的な活動などのお話はこれからですが、太宰府でコシアブラを育てる取り組み
を始めることができそうです。
承天寺別院の住職さま、本当にありがとうございます。