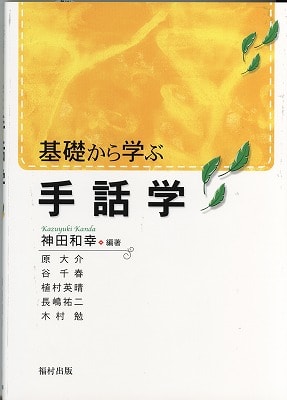1996年に出た「基礎からの手話学」の改訂版が出ました! タイトルがちょっと変わって「基礎から学ぶ手話学」に。
残念ながらというのか「手話学」を一般向けに解説した本は、この神田先生の本以外、1996年以来10年以上も経つのにない。何だかなぁ~。
しかし、中身はこの10年のいろいろを踏まえてとっても面白いものになっています。ただ、その経過を知らない人にとってはちょっと第1章は難しいかも。
まえがきに書いてある以下の指摘はなかなか的を射ていると思う。
「手話の『先進国』である北欧やアメリカの過去を見ると、手話の発展にはいくつかの局面がある。潜伏期(ろう社会だけの隠れた存在)、黎明期(手話が世間の目に触れるようになる)、変化期(音声言語と接触し新たな手話ができる)、発展期(社会に認知され普及する)、拡大期(手話のいろいろな変種ができる)、収縮期(純粋化を目指す)、安定期(変種の棲み分けができる)が想定される。日本手話は現在、拡大期から収縮期に向かっていると考えられる。アメリカとの差は30年と考えられ、この『言語進化の歴史的必然』という視点に立てば現在の手話バラエティの多様化は正鵠を射ている。一方で、ろう運動家からは日本手話の純粋化、古手話の復刻などの主張がさらに強くなると予想される。しかし一方で手話の純粋化運動は一般学習者の減少にもつながる。」
まだ第1章を読んでる途中ですが、示唆に富んだ指摘が多く、今後、手話研修センターから「反論書としての手話学入門」が出ることを大いに期待したいと思います。
■日本手話研究がろう運動の一環になってしまったことは科学的言語研究としての手話学にとっては不幸なことである。(24ページ)
■諸外国において手話が公用語化され使用者が増えているという潮流が日本に届かない原因の1つはろう者を狭く定義していることに関係があると思われる。(25ページ)
■日本手話の歴史は百年足らずであるという俗説がある。この説は権威ある筋から流布されたせいもあり、信じている人が多いが、実は推測に過ぎない。(31ページ)
■手話奉仕員養成制度は多くの聴者に手話学習の機会を与えたが、その学習対象になった手話はろう者の手話ではなく、ピジン手話であったと想像される。その理由は当時発行されたテキスト類を見ると、すべて単語の説明であり、日本語がどのような手話単語に置き換えられるかを学習するようになっている。文法に関する記述はまったくない。(35ページ)
これはいまもあんまり変わってないように思うけど・・・。
■読話とピジン手話の併用は、聴者からするとピジン手話の単語だけでは何か言い足りない所を口話で補えるという利点がある。実際に伝わったかどうか別にして発話者としての満足感がある。
これかなり言えてますよねぇ~。
聴覚障害者からすれば、口話だけではわからない所を手話単語で補って理解できるので、情報獲得できる利点がある。双方に利点のあるこの方法が普及したのは当然である。しかし、これは手話というより、手話単語付きの口話であるから、ピジン手話よりさらに日本語に近いものになる。アメリカでは、こうした手話利用法をSSS(手話支援発話)と呼んでいる。これは後述する同時法的手話とは異なるが、内容は似ている。本書では手話付き口話と訳しておこう。(37ページ)
奉仕員養成講座で、「声を出さずに手話を表現してみましょう」と指導しても、どうしても例文を声を出して読みながら手話をする方がいる。それはまさに「手話付き口話」状態だ。でも、それと大差ない手話通訳者がいることも事実だと思う。
■こうした実情に対し、完全なコミュニケーションを求める聴覚障害者はろう者的手話の社会的是認を求めるようになる、ろう者手話という表現は前提として『聴者手話』を認めることになるが、それは手話ではないと彼らは主張したい。実際はどうあれ、ピジン手話は日本語の変種に過ぎないという意味を込めて、自らの手話を「日本手話」と呼ぶ。しかし、手話通訳養成などでピジン手話が普及し、その恩恵にあずかる人々にとってはピジン手話も手話と信じているので、ピジン手話は手話でないという主張は、これまで『ろうあ運動=手話運動』であった歴史を考えると、自己否定につながってしまうため、到底容認できるものではない。聴覚障害者の間でも議論があるゆえんである。
アメリカろう運動の影響を受けた若いろう者による日本手話への評価は、日本手話の歴史的視点に立てばルネサンスを迎えているといってよいだろう。(39ページ)
多くの手話通訳者にとって、「日本手話」の存在は、まさに「自己否定」状態ですよねぇ~。
■シムコムとは定義的には、口話と一緒に手話を提示することで、併用法と同じだが、ろう者の側からすると、口話に付随してくる不完全な手話(手話付き口話)のことである。言語干渉の結果、どうしても手話が省略的になる。とくにピジン手話しか知らない聴者の場合、その手指表現はろう者には理解しがたいものになる。
厳しいご指摘ですよねぇ~。
■中途失聴者やろう教育関係者には日本語対応手話という表現を好む人が多い。これは「聴覚障害者の言語である手話」という運動スローガンにも適合し、日本語をコミュニケーションの基本とするろう教育の理念にも合致するから、多くの人に受け入れられやすい。
しかし、言語学という立場から見ると曖昧で、日本人の好きな曖昧な決着の付け方である。日本手話が1つの言語であるなら、日本語に対応する日本手話というのはありえない。英語対応日本語とか、日本語対応英語とはいわない。これは単語レベルでの直訳のことであり、現実の場で使用されれば、いわゆるブロークン英語である。言語学的に見ればピジン英語で、1つの言語現象である。(中略)しかし、日本語対応手話とはろう教育でいう「手指メディア」による日本語表示のことで、あえて言語分類すれば日本語に属するだろう。文法は日本語だからである。ではなぜ手話と呼ぶかというと、手話単語を利用するために、手話に思えるからである。指文字や手話単語が手話そのものだと思っている人は多い。そこからくる誤解と、ろう運動スローガンや教育的配慮から、手話の概念を曖昧にしているのである。
確かに「日本語対応英語」なんて聞いたことないですよねぇ~。
ずいぶん引用が長くなってしまいました、神田先生スミマセン。でも、この本は近年出た手話関係の書籍としては一番のお勧めです。最後にさらに目次を掲載させていただきます。この本を日聴紙がどんな書評で紹介してくれるのかとっても楽しみです。
まえがき
第1章 手話学の基礎
1 手話とはどういうことばか
2 聴覚障害とは何か
3 手話の成立と歴史
4 手話の種類
5 世界の手話
第2章 手話のしくみ
1 音韻論
2 手話音韻規則
3 手話の語形成と文法
4 統語論
第3章 手話学習
1 手話教育
2 手話検定
第4章 手話通訳
1 手話通訳士
2 手話通訳の実際
第5章 手話と聴覚障害者支援
1 手話工学
2 支援機器
第6章 ろう文化
1 聴覚障害者人口、ろう人口と手話人口
2 聴覚障害者の社会環境
3 ろう文化とは何か