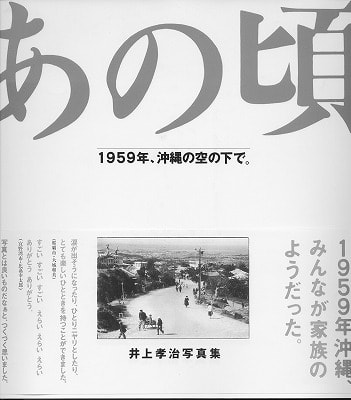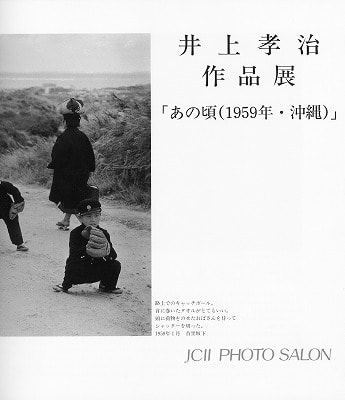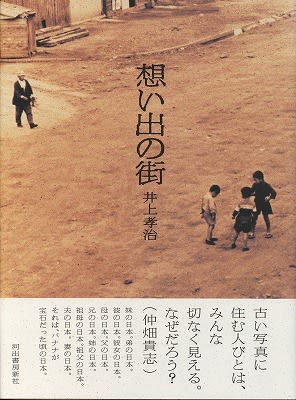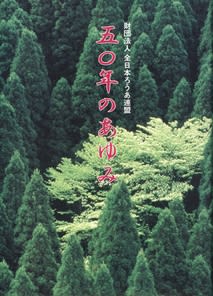以前、「下流志向」って本がとても面白そうだと思って
紹介したことがあるんですが、最近「R25」っていう無料雑誌を読んでいて、またまた「面白い記事だなぁ~」と感じるのに出会いました(2月5日(木)版R25「ブレークスルーとは何か」)。それが内田樹さんへのインタビュー記事だったのです。
■横にいる他人なんか見てもしょうがないんですよ。本当に見るべきなのは、自分自身でしょう。
■向上心に他人は関係ないんです。
■自分の身に起こる悪いことは絶対に考えちゃいけない。強く念じたことは、それがプラスでもマイナスでも必ず実現する。『取り越し苦労はするな』ということを、僕は多田先生(合気道の多田宏九段)から教わりました。
■”こんなことが起きたらイヤだ”っていう不幸な未来をありありとイメージして、そのリストを長くしている。でも、そうすると必ず”起こって欲しくないこと”が起こる。”こんなことが起きたらいいな”というリストを長くする方が、はるかに効果的な生き方でしょう。
どれも納得です。その記事に著書として「街場の教育論」という新刊が載っていたのですが、まだ高そうだったのでこれはいずれブックオフで探すとして、他にどんな本を書かれているんだろうと探したら、なんと「下流志向」の著者だったんですねぇ~。
しかもそのさらに以前に読んだ「寝ながら学べる構造主義」の著者でもあったのです。驚きました。「下流志向」と「寝ながら学べる構造主義」の著者が同じだったなんて!
そんでもってこの「寝ながら学べる構造主義」がメチャメチャ面白いのです。最初に読んだときも端を折って線が引いてある箇所がたくさんあったんですが、今回改めて読み直してみてもとっても面白い。ちょーお奨めです。確か前回も「紹介したい箇所が多すぎてブログに書くのをやめた」気がするのですが、今回も同じ気持ちです。
【10頁】無知というのはたんなる知識の欠如ではありません。「知らずにいたい」というひたむきな努力の成果です。無知は怠惰の結果ではなく、勤勉の結果なのです。
【11頁】知性がみずからに科すいちばん大切な仕事は、実は「答えを出すこと」ではなく、「重要な問いの下にアンダーラインを引くこと」なのです。
【12頁】入門書が提供しうる最良の知的サービスとは、「答えることのできない問い」、「一般解のない問い」を示し、それを読者一人一人が、自分自身の問題として、みずからの身に引き受け、ゆっくりと嚙みしめることができるように差し出すことだと私は思っています。
【25頁】 構造主義というのは、ひとことで言ってしまえば、次のような考え方のことです。
私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属しており、その条件が私たちのものの見方、感じ方、考え方を基本的なところで決定している。だから、私たちは自分が思っているほど、自由に、あるいは主体的にものを見ているわけではない。むしろ私たちは、ほとんどの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に「見せられ」「感じさせられ」「考えさせられている」。そして自分の属する社会集団が無意識的に排除してしまったものは、そもそも私たちの視界に入ることがなく、それゆえ、私たちの感受性に触れることも、私たちの思索の主題となることもない。
私たちは自分では判断や行動の「自律的な主体」であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。
【33頁】フロイトは心理学の目的を「自我はわが家の主人であるどころか、自分の心情生活の中で無意識に生起していることについては、わずかばかりの報告をたよりにしているに過ぎないのだ、ということを実証」することである、と書いています。
【34頁】「無意識の部屋」は広い部屋でさまざまな心的な動きがひしめいています。もう一つの「意識の部屋」はそれよりずっと狭く、ずっと秩序立っていて、汚いものや危ないものは周到に排除されており、客を迎えることができるサロンのようになっています。そして、「二つの部屋の敷居のところには、番人が一人職務を司っていて、個々の心的興奮を検査し検閲して、気に入らないことをしでかすとサロンに入れないようにします。」(『精神分析入門』フロイト)
【35頁】この機制は二種類の無知によって構成されています。一つは、「番人」がいったい「どんな基準で」入室して良いものといけないものを選別しているのか、私たちは知らないということ。いま一つは、そもそも「番人」がそこにいて、チェックしているということ自体、私たちは知らないということです。この構造的な「無知」によって、私の意識は決定的な仕方で思考の自由を損なわれています。
【39頁】私たちは生きている限り、必ず「抑圧」のメカニズムのうちに巻き込まれています。そして、ある心的過程から組織的に目を逸らしていることを「知らないこと」が、私たちの「個性」や「人格」の形成に決定的な影響を及ぼしています。(中略)私たちは自分を個性豊かな人間であって、独特の仕方でものを考えたり感じたりしているつもりでいますが、その意識活動の全プロセスには、「ある心的過程から構造的に目を逸らし続けている」という抑圧のバイアスがつねにかかっているのです。
【44頁】 技芸の伝承に際しては、「師を見るな、師が見ているものを見よ」ということが言われます。弟子が「師を見ている」限り、弟子の視座は「いまの自分」の位置を動きません。「いまの自分」を基準点にして、師の技芸を解釈し、摸倣することに甘んじるならば、技芸は代が下るにつれて劣化し、変形する他ないでしょう。(現に多くの伝統技芸はそうやって堕落してゆきました。)
それを防ぐためには、師その人や師の技芸ではなく、「師の視線」、「師の欲望」、「師の感動」に照準しなければなりません。師がその制作や技芸を通じて「実現しようとしていた当のもの」をただしく射程にとらえていれば、そして、自分の弟子にもその心像を受け渡せたなら、「いまの自分」から見てどれほど異他的なものであろうと、「原初の経験」は汚されることなく時代を生き抜くはずです。
【45頁】これはヘーゲルが「自己意識」ということばで言おうとしていた事態とそれほど違うものではありません。というのは、「自己意識」とは、要するに、「いまの自分」から逃れ出て、想像的に措定された異他的な視座から自分を振り返る、ということに他ならないからです。
【50頁】ニーチェによれば、「大衆社会」とは成員たちが「群」をなしていて、もっぱら「隣の人と同じようにふるまう」ことを最優先的に配慮するようにして成り立つ社会のことです。
【66頁】ソシュールは言語活動とはちょうど星座を見るように、もともとは切れ目の入っていない世界に人為的に切れ目を入れて、まとまりをつけることだというふうに考えました。
【67頁】言語活動とは「すでに分節されたもの」に名を与えるのではなく、満天の星を星座に分かつように、非定型的で星雲状の世界に切り分ける作業そのものなのです。ある観念があらかじめ存在し、それに名前がつくのではなく、名前がつくことで、ある観念が私たちの思考の中に存在するようになるのです。
【68頁】外国語を母国語の語彙に取り込むということは、「その観念を生んだ種族の思想」を(部分的にではあれ)採り入れるということです。そのことばを使うことで、それ以前には知られていなかった、「新しい意味」が私たちの中に新たに登録されることになります。私の語彙はそれによって少しだけ豊かになり、私たちの世界は少しだけ立体感を増すことになります。
ですから、母国語にある単語が存在するかしないか、ということは、その国語を語る人たちの世界のとらえ方、経験や思考に深く関与してきます。
【72頁】私たちはごく自然に自分は「自分の心の中にある思い」をことばに託して「表現する」というような言い方をします。しかしそれはソシュールによれば、たいへん不正確な言い方なのです。
「自分たちの心の中にある思い」というようなものは、実は、ことばによって「表現される」と同時に生じだのです。と言うよりむしろ、ことばを発したあとになって、私たちは自分が何を考えていたのかを知るのです。それは口をつぐんだまま、心の中で独白する場合でも変わりません。独白においてさえ、私たちは日本語の語彙を用い、日本語の文法規則に従い、日本語で使われる言語音だけを用いて、「作文」しているからです。
私たちが「心」とか「内面」とか「意識」とか名づげているものは、極論すれば、言語を運用した結果、事後的に得られた、言語記号の効果だとさえ言えるかも知れません。
【73頁】私か確信をもって他人に意見を陳述している場合、それは「私自身が誰かから聞かされたこと」を繰り返していると思っていただいて、まず聞違いありません。
【80頁】第三章 ミシェル・フーコー(社会史)
ある制度が「生成した瞬間の現場」、つまり歴史的な価値判断がまじり込んできて、それを汚す前の「なまの状態」のことを、のちにロラン・バルトは「零度」と術語化しました。構造主義とは、ひとことで言えば、さまざまな人間的諸制度(言語、文学、神話、親族、無意識など)における「零度の探求」であると言うこともできるでしょう。
【84頁】「エスニック・アイデンティティ」というものを私たちはあたかも「宿命的刻印」のようなものとして重々しく語ります。しかし、多くの場合、それは選択(というより、組織的な「排除」)の結果に過ぎません。ある祖先ただ一人が選ばれ、それ以外のすべての祖先を忘れ去り、消滅させたときにのみ、父祖から私へ「一直線」に継承された「エスニック・アイデンティティ」の幻想が成り立つのです。
【102頁】国家主導による体操の普及のねらいはもちろん単なる国民の健康の増進や体力の向上ではありません。そうではなくて、それはなによりも「操作可能な身体」、「従順な身体」を造型することでした。
「軍隊では体操は、素人兵に集団戦法を訓練するときに使われました。体操は、一人一人ではたいした力を期待できない戦いの素人たちを、号令とともに一斉に秩序正しく行動できるように訓練します。近代的軍隊においては、兵士たちは個人的な判断で臨機応変に戦うというよりも、集団の中においてあらかじめ決められたわずかな役割を任命され、合図に応じてこれを繰り返し反復するだけです。(略)体操が集団秩序を高めることを目的とするのは、この戦街上の必要を満たすためであり、いいかえれば、それは平凡な能力しか持たない個人を有効に活用するための方法であったのです。」(『「健康」の日本史』)
近代国家は、例外なしに、国民の身体を統御し、標準化し、操作可能な「管理しやすい様態」におくこと-「従順な身体」を造型することを最優先の政治的課題に掲げます。「身体に対する権力の技術論」こそは近代国家を基礎づける政治技術なのです。
【103頁】身体を標的とする政治技術がめざしているのは、単に身体だけを支配下に置くことではありません。身体の支配を通じて、精神を支配することこそこの政治技術の最終目的です。この技術の要諦は、強制による支配ではありません。そうではなくて、統御されているものが、「統御されている」ということを感知しないで、みずから進んで、みずからの意志に基づいて、みずからの内発的な欲望に駆り立てられて、従順なる「臣民」として権力の網目の中に自己登録するように仕向けることにあります。
【104頁】権力が身体に「刻印を押し、訓育し、責めさいなんだ」実例を一つ挙げておきましょう。1960年代から全国の小中学校に普及した「体育坐り」あるいは「三角坐り」と呼ばれるものです。
ご存知の方も多いでしょうが、これは体育館や運動場で生徒たちをじべたに坐らせるときに両膝を両手で抱え込ませることです。竹内敏晴によると、これは日本の学校が子どもたちの身体に加えたもっとも残忍な暴力の一つです。両手を組ませるのは「手遊び」をさせないためです。首も左右にうまく動きませんので、注意散漫になることを防止できます。胸部を強く圧迫し、深い呼吸ができないので、大きな声も出せません。竹内はこう書いています。
「古くからの日本語の用法で言えば、これは子どもを『手も足も出せない』有様に縛りつけている、ということになる。子ども自身の手で自分を文字通り縛らせているわけだ。さらに、自分でこの姿勢を取ってみればすぐに気づく。息をたっぷり吸うことができない。つまりこれは『息を殺している』姿勢である。手も足も出せず息を殺している状態に子どもを追い込んでおいて、やっと教員は安心する、ということなのだろうか。これは教員による無自覚な、子どものからだへのいじめなのだ。」(竹内敏晴『思想する「からだ」』)
生徒たちをもっとも効率的に管理できる身体統御姿勢を考えた末に、教師たちはこの坐り方にたどりついたのです。しかし、もっと残酷なのは、自分の身体を自分の牢獄とし、自分の四肢を使って自分の体幹を緊縛し、呼吸を困難にするようなこの不自然な身体の使い方に、子どもたちがすぐに慣れてしまったということです。浅い呼吸、こわばった背中、痺れて何も感じなくなった手足、それを彼らは「ふつう」の状態であり、しばしば「楽な状態」だと思うようになるのです。
私が尊敬する竹内敏晴さんまで登場した!実に面白いですねぇ~。これでやっと半分です。(ここまで2009-02-27 20:34:56記)
【122頁】第4章 ロラン・バルト(記号学「零度の記号」)
「例えば、私が「おじさんのエクリチュール」で語り始めるや、私の口は私の意志とかかわりなしに突然「現状肯定的でありながら愚痴っぽい」ことばを吐き出し始めます。「教師のエクリチュール」に切り替えると、とたんに私は「説教臭く、高飛車な」人間になります。同じようにヤクザは「ヤクザのエクリチュール」で語り、営業マンは「営業マンのエクリチュール」で語ります。そして、そのことばづかいは、その人の生き方全体をひそかに統御しているのです。
これって結構ショックですよねぇ~。確かに「手話通訳者養成講師のエクリチュール」になってる自分っているかもしれません。
【123頁】言語を語るとき、私たちは必ず、記号を「使い過ぎる」か「使い足りない」か、そのどちらかになります。「過不足なく言語記号を使う」ということは、私たちの身には起こりません。「言おうとしたこと」が声にならず、「言うつもりのなかったこと」が漏れ出てしまう。それが人間が言語を用いるときの宿命です。
【148頁】第五章 レヴィ・ストロース(文化人類学者)
「私は曇りない目でものを見ているという手前勝手な前提から出発するものは、もはやそこから踏み出すことができない。」
【184頁】第六章 ジャック・ラカン(精神分析)
「私が自分の過去の出来事を「思い出す」のは、いま私の回想に耳を傾けている聞き手に、「私はこのような人間である」と思って欲しいからです。私は「これから起きて欲しいこと」、つまり他者による承認をめざして、過去を思い出すのです。私たちは未来に向けて過去を思い出すのです。」
「『自我』とは主体がどれほど語っても、決してことばがそこに届かないものです。主体をして語ることへ差し向ける根源的な「満たされなさ」のことです。」
「ラカンの『自我』は、その「言葉にならないけれど、それが言葉を呼び寄せる」ある種の磁場のようなものだと思ってください。」
「『私』とは、主体が「前未来形」で語っているお話の『主人公』です。」
「こどもが育つプロセスは、ですから言語を習得するというだけでなく、「私の知らないところですでに世界は分節されているが、私はそれを受け入れる他ない」という絶対的に受動的な位置に自分は「はじめから」置かれているという事実の承認をも意味しているのです。」
「平たく言ってしまえば『怖いもの』に屈服する能力を身につけること、それがエディプスというプロセスの教育的効果なのです。」
どんどん難解な話になっていくのですが、結局最初に書かれている構造主義ってのは
「私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属しており、その条件が私たちのものの見方、感じ方、考え方を基本的なところで決定している。だから、私たちは自分が思っているほど、自由に、あるいは主体的にものを見ているわけではない。むしろ私たちは、ほとんどの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に「見せられ」「感じさせられ」「考えさせられている」。そして自分の属する社会集団が無意識的に排除してしまったものは、そもそも私たちの視界に入ることがなく、それゆえ、私たちの感受性に触れることも、私たちの思索の主題となることもない。
私たちは自分では判断や行動の「自律的な主体」であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。」
という文に還るって感じですね。僕も2回読み直して(つまり最初に読んだ時を含めて3回読んで)、やっと理解の入り口に立てたかなって感じです。