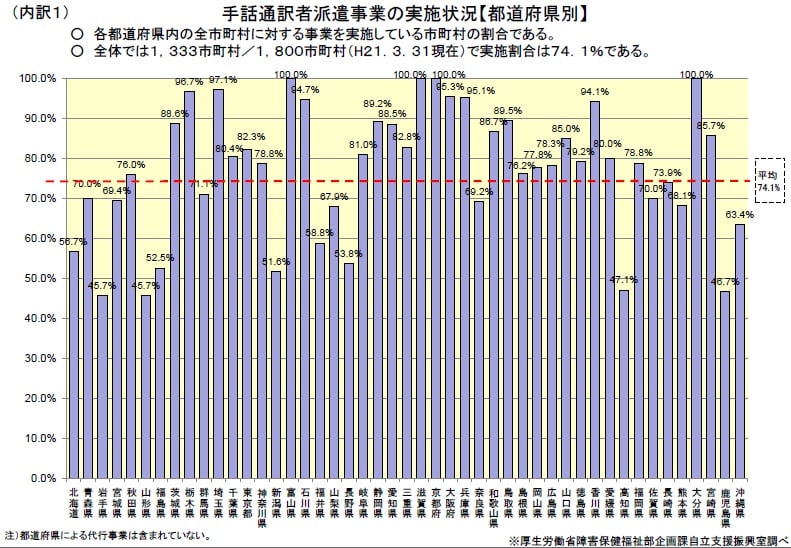2010年9月22日付けの茨城新聞にこんな記事が・・。
わぁ~あの分厚くて重くて持ち運びにくいの改訂するんだ。
全面的にウェブに移行させたりはしないんだろうか?
あるいはiphoneソフトにするとか・・。
記事は辞書の改訂と「新しい手話」作りの議論がごっちゃに書かれている気がするし・・。
「懐が痛む」で数時間の議論ですか・・。まぁ「研究所」ですから、そういうもんなんでしょうねぇ。
でも、さすがにもうあのバカ高い辞書買う人、よっぽど「懐に余裕のある人」しかいないように思うのだけれど・・時代が大きくデフレに触れていること、またIT化が進行していることを認識されているのだろうか? それとも日立製作所の手話アニメーション・システムでやるのかな? でもあれもなんだかインストール面倒くさそうで、「裁判員手話」のデータ落とした切りになっています。日立製作所ももう少し小回りが利くとなぁ~。IT庶民には敷居が高い。
それと、医療用語の「インフルエンザ」はいいとして、「インターネット」は今さら「IT用語」とも言えないでは?せめて「ツイッター」とか「フェイスタイム」とかネェ。
私は「新しい手話」は「新語(新しく時代に登場した用語)」に限定しちゃってもいいんじゃないかと思う。かつ、「スピード」を重視して毎月日本手話研究所ホームページに掲載するような形が良いと思う。
「日本語-手話辞典」の紙ベースの改訂版は、全日ろう連の出版事業赤字につながるのでは?・・・なんて余計なお世話でした。
でもウィ・ラブ・パンフの利益は何に使うんだ?って声が上がってる中で、こういう記事はいかがなもんでしょうか?などと要らぬ心配をしてしまいました。
手話辞典、十数年ぶりに大改訂
「懐が痛む」どう表現?/手話辞典、新語も登場
全国で約120万人が使用していると言われる手話。年々新しい単語が生まれる一方で、日本語特有の微妙なニュアンスの表現に迷うケースも多い。誰もが理解し、使える手話を目指し、十数年ぶりに大掛かりな辞典の改訂作業が進んでいる。
▽例文入り
「胸を指さした後、手のひらを揺らし『痛い』とやったらどうか」
「それだと『胸が痛い』になっちゃう」
京都市右京区の研修施設。大学教授や特別支援学校の元教師らが会議室で、手の動きを交えながら意見を交わす。
テーマは「懐が痛む」。「いっそのこと、お金を捨てるしぐさにしようか」。議論が数時間に及んでも、結論はなかなか出ない。
集まったのは教材づくりなどを手掛ける「日本手話研究所」(京都市)の検討メンバー。「実際の会話で役立つように」と世界で初めて単語と例文を並べて掲載し、1997年に編さんした「日本語―手話辞典」の改訂作業を進めている。
「懐が痛む」は「手持ちのお金が少なくなる」という意味だが、「出費がかさんで苦しい」とのニュアンスも含む。辞典を監修する米川明彦(よねかわ・あきひこ)梅花女子大教授(55)は「単語をつなげただけでは、全然違う意味に取られることがある」と一筋縄ではいかない難しさを打ち明ける。
▽IT、医療用語も
手話の起源は定かではないが、聴覚障害者が身ぶり手ぶりで“会話”していたものがそのまま定着したり、学校教育用に人工的につくられたり、いくつかのパターンがあるとされる。国によって言語が異なるように、手話の形も国や地域によってさまざまだ。
日本では1878年に手話を使って授業を行う「京都盲唖院」を設立。その後聴覚障害者の団体や手話サークルが各地にできた。
1969年に全日本ろうあ連盟(東京)が国内で初めて全国共通の手話表現をまとめた単語辞典「わたしたちの手話」を発刊。しかし「飲む・のむ」のように「酒を飲む」「薬を飲む」「息をのむ」など用例が多岐にわたる単語では、使い方に戸惑うことがあった。
日本手話研究所が手掛ける改訂版は来春に発刊される。掲載数は97年版より約2割増え、約6千の単語と1万以上の例文になる予定。「インターネット」(左手で握りこぶしをつくり、小指を立てた右手で周りを1周させる)、「インフルエンザ」(小指を立てた右手を口に当て、せきをする)など、ITや医療の専門用語も加える。
欧米では多くの企業や行政機関が専門の手話通訳者を置いているが、日本は限られたボランティアなどに頼っているのが実情。同研究所長で、自身も聴覚障害のある高田英一(たかだ・えいいち)さん(77)は「辞典を通じて手話を身近に感じ、勉強する人が増えてほしい」と期待を込める。
(共同通信社)
わぁ~あの分厚くて重くて持ち運びにくいの改訂するんだ。
全面的にウェブに移行させたりはしないんだろうか?
あるいはiphoneソフトにするとか・・。
記事は辞書の改訂と「新しい手話」作りの議論がごっちゃに書かれている気がするし・・。
「懐が痛む」で数時間の議論ですか・・。まぁ「研究所」ですから、そういうもんなんでしょうねぇ。
でも、さすがにもうあのバカ高い辞書買う人、よっぽど「懐に余裕のある人」しかいないように思うのだけれど・・時代が大きくデフレに触れていること、またIT化が進行していることを認識されているのだろうか? それとも日立製作所の手話アニメーション・システムでやるのかな? でもあれもなんだかインストール面倒くさそうで、「裁判員手話」のデータ落とした切りになっています。日立製作所ももう少し小回りが利くとなぁ~。IT庶民には敷居が高い。
それと、医療用語の「インフルエンザ」はいいとして、「インターネット」は今さら「IT用語」とも言えないでは?せめて「ツイッター」とか「フェイスタイム」とかネェ。
私は「新しい手話」は「新語(新しく時代に登場した用語)」に限定しちゃってもいいんじゃないかと思う。かつ、「スピード」を重視して毎月日本手話研究所ホームページに掲載するような形が良いと思う。
「日本語-手話辞典」の紙ベースの改訂版は、全日ろう連の出版事業赤字につながるのでは?・・・なんて余計なお世話でした。
でもウィ・ラブ・パンフの利益は何に使うんだ?って声が上がってる中で、こういう記事はいかがなもんでしょうか?などと要らぬ心配をしてしまいました。
手話辞典、十数年ぶりに大改訂
「懐が痛む」どう表現?/手話辞典、新語も登場
全国で約120万人が使用していると言われる手話。年々新しい単語が生まれる一方で、日本語特有の微妙なニュアンスの表現に迷うケースも多い。誰もが理解し、使える手話を目指し、十数年ぶりに大掛かりな辞典の改訂作業が進んでいる。
▽例文入り
「胸を指さした後、手のひらを揺らし『痛い』とやったらどうか」
「それだと『胸が痛い』になっちゃう」
京都市右京区の研修施設。大学教授や特別支援学校の元教師らが会議室で、手の動きを交えながら意見を交わす。
テーマは「懐が痛む」。「いっそのこと、お金を捨てるしぐさにしようか」。議論が数時間に及んでも、結論はなかなか出ない。
集まったのは教材づくりなどを手掛ける「日本手話研究所」(京都市)の検討メンバー。「実際の会話で役立つように」と世界で初めて単語と例文を並べて掲載し、1997年に編さんした「日本語―手話辞典」の改訂作業を進めている。
「懐が痛む」は「手持ちのお金が少なくなる」という意味だが、「出費がかさんで苦しい」とのニュアンスも含む。辞典を監修する米川明彦(よねかわ・あきひこ)梅花女子大教授(55)は「単語をつなげただけでは、全然違う意味に取られることがある」と一筋縄ではいかない難しさを打ち明ける。
▽IT、医療用語も
手話の起源は定かではないが、聴覚障害者が身ぶり手ぶりで“会話”していたものがそのまま定着したり、学校教育用に人工的につくられたり、いくつかのパターンがあるとされる。国によって言語が異なるように、手話の形も国や地域によってさまざまだ。
日本では1878年に手話を使って授業を行う「京都盲唖院」を設立。その後聴覚障害者の団体や手話サークルが各地にできた。
1969年に全日本ろうあ連盟(東京)が国内で初めて全国共通の手話表現をまとめた単語辞典「わたしたちの手話」を発刊。しかし「飲む・のむ」のように「酒を飲む」「薬を飲む」「息をのむ」など用例が多岐にわたる単語では、使い方に戸惑うことがあった。
日本手話研究所が手掛ける改訂版は来春に発刊される。掲載数は97年版より約2割増え、約6千の単語と1万以上の例文になる予定。「インターネット」(左手で握りこぶしをつくり、小指を立てた右手で周りを1周させる)、「インフルエンザ」(小指を立てた右手を口に当て、せきをする)など、ITや医療の専門用語も加える。
欧米では多くの企業や行政機関が専門の手話通訳者を置いているが、日本は限られたボランティアなどに頼っているのが実情。同研究所長で、自身も聴覚障害のある高田英一(たかだ・えいいち)さん(77)は「辞典を通じて手話を身近に感じ、勉強する人が増えてほしい」と期待を込める。
(共同通信社)