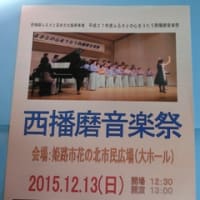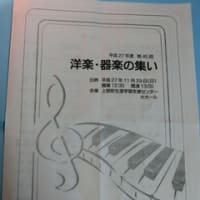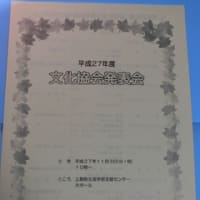日本において、年末の行事に欠かせないもののひとつが第九交響曲の演奏会。
結婚前に一度だけ市民合唱で参加したことがありますがそれっきりです。そのころはあまりこの曲の意味とか深さに目を向けずに、ただうまく歌うことだけに集中していました。
最近、この曲のもつ意味に触れる機会があり、あらためてベートーベンって、偉大なだけでなく、なんて人間味のある人だったのだろうと思ったのでした。
ベートーベンの父親は宮廷音楽家とはいえ、あまりぱっとしない、のんだくれのどうしようもない人で、家計は火の車。音楽家という職業がが当時の役人階級の中で一番身分が低く、幼いころからいわれのない差別を受けて育ってきたベートーベンにとって世の中で何が大切なことかが、ずっと考え続けてきたことでした。
時代はフランス革命から端を発し、専制政治から市民社会への転換期で、血で血を洗うような事件や混乱の中にあり、そのような中で、平等と博愛の精神を謳ったドイツの詩人、シラーの「歓喜に寄す」と言う詩に出会います。
ベートーベンはその詩を何度も声に出して読み、そうして第九がこの世に生み出されました。
以来、200年たった今でも多くの人を魅了し、演奏され続ける第九。
この楽譜と、ベートーベンのたどった人生の道筋と、時代背景と、それらをもっと深く知ることで、名曲の名曲たるゆえんを理解し、ますます人々の心を捉えて離さない、もっと言えば生きる意味までも示してくれる、そんな力を持つ音楽のひとつです。
そのメロディーの一節を聞くだけでもいい曲だなあ、と思ったら、やはりもっと深入りしなくっちゃ。音楽はいくらでもその扉を開いて私たちを招き入れてくれます。
結婚前に一度だけ市民合唱で参加したことがありますがそれっきりです。そのころはあまりこの曲の意味とか深さに目を向けずに、ただうまく歌うことだけに集中していました。
最近、この曲のもつ意味に触れる機会があり、あらためてベートーベンって、偉大なだけでなく、なんて人間味のある人だったのだろうと思ったのでした。
ベートーベンの父親は宮廷音楽家とはいえ、あまりぱっとしない、のんだくれのどうしようもない人で、家計は火の車。音楽家という職業がが当時の役人階級の中で一番身分が低く、幼いころからいわれのない差別を受けて育ってきたベートーベンにとって世の中で何が大切なことかが、ずっと考え続けてきたことでした。
時代はフランス革命から端を発し、専制政治から市民社会への転換期で、血で血を洗うような事件や混乱の中にあり、そのような中で、平等と博愛の精神を謳ったドイツの詩人、シラーの「歓喜に寄す」と言う詩に出会います。
ベートーベンはその詩を何度も声に出して読み、そうして第九がこの世に生み出されました。
以来、200年たった今でも多くの人を魅了し、演奏され続ける第九。
この楽譜と、ベートーベンのたどった人生の道筋と、時代背景と、それらをもっと深く知ることで、名曲の名曲たるゆえんを理解し、ますます人々の心を捉えて離さない、もっと言えば生きる意味までも示してくれる、そんな力を持つ音楽のひとつです。
そのメロディーの一節を聞くだけでもいい曲だなあ、と思ったら、やはりもっと深入りしなくっちゃ。音楽はいくらでもその扉を開いて私たちを招き入れてくれます。