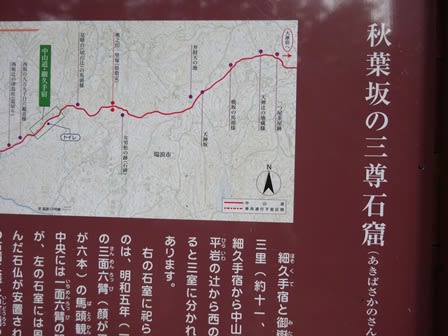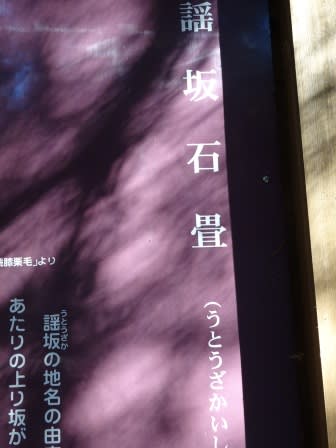今回は関ヶ原を越えていよいよ近江路に入りました。
5月28日(土)くもり。湿度は高めだが歩くにはちょうど良い気候。
最終ラインの大垣から美濃赤坂間は本数が少ないので逆算するとこの「のぞみ」が乗り継ぎに最も便利。
「のぞみ」の特急割引は効かないけれど、今回からジパングを使用。

名古屋から岐阜、岐阜から大垣と乗り継ぎ、大垣で歩き仲間のいっちゃんと合流。
懐かしい美濃赤坂に着いたのは11時頃。

谷汲街道との分岐点.
車が複雑な動きを見せて交差する独特の四つ辻あたり、は昔ながらの古いお屋敷が立ち並ぶ。


中仙道はなぜ大きな大垣を通らずに美濃赤坂~美江寺を経て加納につながったか、またこの街を囲む山々がむき出しの岩肌になっているのはなぜか、
など、地元のいっちゃんに興味深いお話を聞きながら歩く。
中仙道と、東海道に至る美濃路との分岐を過ぎやがて垂井の宿。
なかなかに風情のある宿場で垂井の湧水は有名。
つい最近まで営業していた旅籠、亀丸屋さんは女将さんが御年で店仕舞いしたとか・・。

通りに忽然と姿を現す南宮大社の鳥居。

匠工業の盛んであった町並み。
そろそろ12時近くになるのでお昼を食べる場所を探していたら、小さな小さな入口に青い暖簾のかかった料理屋さんを発見。
ここで77才になる板前のおじいさんのこだわりの料理に堪能!
突出しにトリ貝のぬた、気仙沼の生マグロ、新鮮なイカ、宍道湖のふっくらとしたシジミ、ていねいにおろした信州大王園のわさび・・
そして、何と云っても極めつけが自作のたまり醤油!
〆にこのたまり醤油をたらしたご飯を出してくれましたが、その美味しいことと云ったら!
いやはや水のありがたさをしみじみ感じました。

充分に満足して次の関が原へ。左に不破の関病院や新幹線を見ながら国道21線に沿って歩く。
いつのまにかそれらしき絵が描かれているマンホールが並び始める。
実は山側の関ヶ原の古戦場跡などは見ないで通過し次の宿へ行こうかと思ったが、やはり天下分け目の戦い、
幾万の兵の雄叫びの聞こえた地を実際に見たくなり、
歩く歴史家、いっちゃんのご案内でそれぞれの大名の陣地や首塚、開戦の地を見て回る。
すべてみて歩いたら10㎞以上あるのでほんのさわりだけでも、と。
資料館の自転車置き場の壁面。

旗印を憶えるのも大変。
歴史に「もしも」はないけれど、ここで石田三成側(西軍)が勝っていたら、小早川が裏切らなかったら・・と想像せずにはいられない。

しばし休憩。
関東関西と云う土地の呼び方もこの関ヶ原から東、あるいは西、という分け方だからまさに戦国時代の終焉を告げるその土地のど真ん中にいるわけである。
さて、この合戦場跡は今はハイキングコースになっているので間違えるはずもなかったのだが、なぜか道を間違えて線路際の墓地に出てしまい、
やむなく道なき道の林の中をショートカット。
けっこうサバイバル感あり(^^);;。

ようやく抜けて藤古川ダムを横切り、線路を渡る。
ここからは今須宿にいたる今須峠を抜け、里山の中をゆく。ノリウツギが盛んに咲いていた。

峠を降りて今須の一里塚を越え、踏切を渡ると今須の宿場。
じゃん!民家の前のおばさんがぽつんと座っていて、わたしたちが通り過ぎようとすると「ここが境だよ」と声をかけてくれる。

ここ、今須のこの小さい水路を挟んでついに近江路に入った。
このおばさんがいなかったら知らずに通り過ぎる所であった。まさに国境の守り役である。すぐそばにはこんな石碑がある。

田畑の続く穏やかな今須を過ぎると本日のゴール、柏原の宿場となる。
美濃赤坂の出発が11時だったのと関ヶ原を散策したので少し時間がかかって柏原の駅を18時発の東海道線に乗る。

この時季は陽が長いので助かる。
本日の泊りは大垣のホテル。荷物を置いて長良川の鵜飼いに繰り出すために再び宿を出て岐阜へ。
先回りして待っていてくれたいっちゃんと奥様と合流。
夕闇迫る岐阜の駅。

ここからが本日の旅のもうひとつのお楽しみイベント!!
奥様の運転する車で岐阜城が高く美しく輝く金華山の麓の河原に降りる。
ところがところが5月の11日から連日繰り出しているはずの鵜飼いの船が一艘も見当たりません。
真っ暗な河川敷で待つわたしたち。
奥様が検索してみたらなんと、鵜匠の方が何日か前に川に落ちて亡くなりそのご遺体が一日目前に見つかったそうで
28,29日の鵜飼いは中止になったとのこと!
そういえば新聞のニュースでそんな記事があったような・・。
ということで今回は残念ながら鵜飼い見学はあきらめ、飲み屋さんに二軒はしご。
一軒目は最近新しく開いたらしいモダンな日本酒処。
前回宿泊した各務原産の「青波」ともう一本、(名前を失念)で乾杯(^^)!

そして2軒目が、いっちゃんの一押し!「Field」という元は本屋さんで現在は家庭料理とお酒やコーヒを出してくれるすてきなお店。
入った瞬間に懐かしさが充満、美味しいお料理をさっと出してくれるご主人と奥様のふたりでやっておられます。

こういうお店はホントに貴重。岐阜に来たら是非また立ち寄りたい。

お酒も食事もお喋りも大いに弾みました。楽しかった(^0^)
ご馳走様でした☆
本日の歩行距離、約22㎞(関ヶ原散策を含む)、
京都まであと約78㎞。