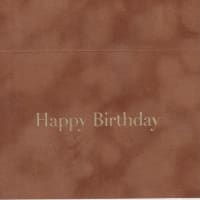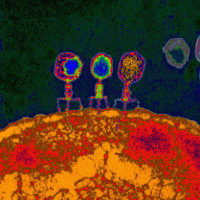10月になると、各地でインフルエンザワクチンの接種がはじまります。
冬に流行する、かぜのような症状の原因になるウイルスは100種類以上あるといわれていますが、インフルエンザウイルスは別格の位置づけになっています。
ヒトの健康に大きな影響を与える、公衆衛生上もインパクトが大きいという。。。ことからであります。
そのインパクトの評価も実は国によって一様ではなく、「しかたないんじゃない?自然現象でしょ」というところから、「拡大阻止!なるべくワクチン!」という広いレンジがあって国ごとにワクチンの位置づけが大きく違っています。
もっとも、ブツとしてのワクチンや、ワクチンの選択肢じたいが同じではありませんし、もともとの健康リスクが対象によって異なります。喘息や心臓疾患があるという人と、全く何も問題ない!という人ではちがいますし、職業や家族構成などももちがいます。
ですので、不要論など雑な意見は論外として、ていねいに考え発信していくことの大切さを痛感します。
国や専門団体が出す方針が現場や一般の人の理解や動向に影響するのは確実。
インフルエンザの予防としてワクチンに一番熱心なのは、米国ではないかとおもいます。
多様な人種、経済力によって大きく異なる医療アクセス、重症化した時に発生する高額な医療費、できることをやっておかない(説明しない)と責任が問われる緊張感。
米国は「誤接種が怖い」と思うほどに選択肢があります。
説明や同意確認など、たいへんそうです。
CDC 2013-2014シーズン用に承認されたインフルエンザワクチンの一覧
病院全体、社会全体での在庫管理とかもどうするんでしょうね。
米国の会議で関係者と雑談していたら、「日本人みたいに几帳面に手洗わないし、マスクしないし、肥満多いし、まあ1回やっておけばすむワクチンのほうが選択肢として妥当なんだよ」といわれました。
医療者は義務ですね。spirit of safeguarding patientsから、医学的に接種できない(過去にアナフィラキシーになったとか)と産業医の人が判断した、というような場合をのぞいて接種してくださいということになっています。
「ゼロトレランス=ゼロにはできないにしてもなるべくゼロに近づける努力をする」という考え方が医療安全の流れになっているからです。
なるべく多くの人に接種してもらうとなったら、在庫流通管理もたいへんですし、そもそも医療機関にそんなにたくさんの人がきたらたいへんです。
ですから、医師看護師だけでなく、訓練を受けた薬剤師さんも接種OKになっています。お買い物ついでに、ドライブスルーで、ショッピングモールで、などアウトリーチの機会提供もあるわけです。
(日本でも新型・・で住民に一斉に接種というような記載が書類にあるんですが、誰がどうやって、在庫流通管理はできるんですか?という疑問が)
でも、本当にいるんですか?という議論も当然あります。
Why Vaccines Should Be Mandatory For Most Americans
あまり熱心ではない(といったら怒られるかも・・)オランダでは、医療者でも接種率は高くありません。
改善すべき!というような熱いアプローチも主流ではありません。
関係者と雑談していたら、基礎疾患のある人にはワクチンや治療薬も検討されるが、それ以外のもともと健康な人は休めばいいだけ。
ナースや医師が発症したら感染性のあるときは休んでもらう。それだけ。
ナースの数が足りなくなったらベッドを臨時に閉じるだけ。
インフルエンザはそういうものということで、国民やメディアもキーキーいわない。
高齢者施設の入所者がインフルエンザで死亡→なぜだ!適切な予防をしていたのかワクチンしたのか、薬飲ませたのか、なぜ個室にいれないんだ、などなどムキー!!
インフルエンザで毎年どれくらい死亡があるのか、避けようがない背景などは勉強しないで記者会見、もよくわかりません。
杓子定規な対応は疲弊や負担しか残しません。
(ルールには妥当性という「倫理」も残しておいていただきたいですね)
さて日本ですが、日本は予防効果が期待できる新しい技術のインフルエンザワクチンを承認していない国ではありますが、開業医の先生方はすでに輸入して使っていますので、アクセスがないというわけでもありません。
日本では接種勧奨の対象が誰なのかグレーでありますが、公費補助があるのは高齢者。ハイリスク層だから。罹患率は子供の方が高いですが、死亡リスクは圧倒的に高齢者だから。
といってもインフルエンザウイルスにやられてしまうのではなくて、体調不良になったときに他の臓器への負荷もかかってもともと合併症もあってというなかで戦うに不利だからですよね。
しかし、日本の現在のワクチンでは、もともと免疫反応が低下している高齢者では期待するほどに効果が得られるかわからないというのが悩ましいところです。(タイプの当たり外れ論さておき)
その場合、無駄ならしなくていいんじゃね?という論の立て方もあるでしょうし、100%期待の効果が得られなくてもやれることはやりましょう。効果の部分や救える人たちがいることを忘れてはいけません、、というところに立つのかの違い。
また、国の予算の優先順位的にあきらめざるをえないレベルなのか、やれそうだ、なのかの違いもあります。
新しいワクチンの採用にあたって、ワクチン施策を変更したのは英国です。
Public Health UKの名のもとに、大きな改革が行われています。
英国におけるインフルエンザワクチン接種率のグラフはこちら。医療関係者で50%前後。
英国における対策の詳細はこちら
簡単にいいますと、それまではハイリスクな人たちに注射のワクチン接種、でしたが、今回のシーズンからは2-17歳へ鼻スプレー式のワクチン接種勧奨がルチンにおこなわれることになりました。
毎年、免疫のない子供達で流行し、それが家庭にもちこまれて親や地域の高齢者に広がるというのがよくあるパターンですので、若年集団での流行を止めることで社会全体の流行を止めようというものです。
注射式のワクチンから、より有効な粘膜へのスプレー式ワクチンに変更をしたとしても、米国のように「より広い対象に」と言わないところが英国式。
スプレー式は針を使いませんので、針を刺すことによって生じる健康被害もなくなりますし、医療廃棄物処理上も楽です。
学校などでの集団接種でも使いやすそうです。
新しい手法なので、教育資材も公開されています。
NHS 医療者向け教育ビデオ(約6分)
子どもへのスプレー式ワクチンの説明と実施
モデルのナースが、現場そのまま感たっぷりですが(^^;)。
子どもにもインフォームドコンセント、と丁寧な説明があります。熟練者集団がつくる教育やプロモーションのてあつさを見ますね。
その評価は来年春には出るでしょう。
[参考]
Health Law Perspectives (May 2013)
Health Law & Policy Institute University of Houston Law Center
The variable efficacy of current influenza vaccines result in mandatory flu vaccination policies forhealth care workers being difficult to justify
他の国ももっと調べてみたい:
ドイツの大学病院。医師の方が看護師より接種率が高い。というか、どちらも日本と比べてすごく低い(2007-8年ですが)
カナダの看護協会 ポジションペーパー
INFLUENZA IMMUNIZATION OF REGISTERED NURSES
これまでのサマリー:インフルエンザワクチンの歴史
冬に流行する、かぜのような症状の原因になるウイルスは100種類以上あるといわれていますが、インフルエンザウイルスは別格の位置づけになっています。
ヒトの健康に大きな影響を与える、公衆衛生上もインパクトが大きいという。。。ことからであります。
そのインパクトの評価も実は国によって一様ではなく、「しかたないんじゃない?自然現象でしょ」というところから、「拡大阻止!なるべくワクチン!」という広いレンジがあって国ごとにワクチンの位置づけが大きく違っています。
もっとも、ブツとしてのワクチンや、ワクチンの選択肢じたいが同じではありませんし、もともとの健康リスクが対象によって異なります。喘息や心臓疾患があるという人と、全く何も問題ない!という人ではちがいますし、職業や家族構成などももちがいます。
ですので、不要論など雑な意見は論外として、ていねいに考え発信していくことの大切さを痛感します。
国や専門団体が出す方針が現場や一般の人の理解や動向に影響するのは確実。
インフルエンザの予防としてワクチンに一番熱心なのは、米国ではないかとおもいます。
多様な人種、経済力によって大きく異なる医療アクセス、重症化した時に発生する高額な医療費、できることをやっておかない(説明しない)と責任が問われる緊張感。
米国は「誤接種が怖い」と思うほどに選択肢があります。
説明や同意確認など、たいへんそうです。
CDC 2013-2014シーズン用に承認されたインフルエンザワクチンの一覧
病院全体、社会全体での在庫管理とかもどうするんでしょうね。
米国の会議で関係者と雑談していたら、「日本人みたいに几帳面に手洗わないし、マスクしないし、肥満多いし、まあ1回やっておけばすむワクチンのほうが選択肢として妥当なんだよ」といわれました。
医療者は義務ですね。spirit of safeguarding patientsから、医学的に接種できない(過去にアナフィラキシーになったとか)と産業医の人が判断した、というような場合をのぞいて接種してくださいということになっています。
「ゼロトレランス=ゼロにはできないにしてもなるべくゼロに近づける努力をする」という考え方が医療安全の流れになっているからです。
なるべく多くの人に接種してもらうとなったら、在庫流通管理もたいへんですし、そもそも医療機関にそんなにたくさんの人がきたらたいへんです。
ですから、医師看護師だけでなく、訓練を受けた薬剤師さんも接種OKになっています。お買い物ついでに、ドライブスルーで、ショッピングモールで、などアウトリーチの機会提供もあるわけです。
(日本でも新型・・で住民に一斉に接種というような記載が書類にあるんですが、誰がどうやって、在庫流通管理はできるんですか?という疑問が)
でも、本当にいるんですか?という議論も当然あります。
Why Vaccines Should Be Mandatory For Most Americans
あまり熱心ではない(といったら怒られるかも・・)オランダでは、医療者でも接種率は高くありません。
改善すべき!というような熱いアプローチも主流ではありません。
関係者と雑談していたら、基礎疾患のある人にはワクチンや治療薬も検討されるが、それ以外のもともと健康な人は休めばいいだけ。
ナースや医師が発症したら感染性のあるときは休んでもらう。それだけ。
ナースの数が足りなくなったらベッドを臨時に閉じるだけ。
インフルエンザはそういうものということで、国民やメディアもキーキーいわない。
高齢者施設の入所者がインフルエンザで死亡→なぜだ!適切な予防をしていたのかワクチンしたのか、薬飲ませたのか、なぜ個室にいれないんだ、などなどムキー!!
インフルエンザで毎年どれくらい死亡があるのか、避けようがない背景などは勉強しないで記者会見、もよくわかりません。
杓子定規な対応は疲弊や負担しか残しません。
(ルールには妥当性という「倫理」も残しておいていただきたいですね)
さて日本ですが、日本は予防効果が期待できる新しい技術のインフルエンザワクチンを承認していない国ではありますが、開業医の先生方はすでに輸入して使っていますので、アクセスがないというわけでもありません。
日本では接種勧奨の対象が誰なのかグレーでありますが、公費補助があるのは高齢者。ハイリスク層だから。罹患率は子供の方が高いですが、死亡リスクは圧倒的に高齢者だから。
といってもインフルエンザウイルスにやられてしまうのではなくて、体調不良になったときに他の臓器への負荷もかかってもともと合併症もあってというなかで戦うに不利だからですよね。
しかし、日本の現在のワクチンでは、もともと免疫反応が低下している高齢者では期待するほどに効果が得られるかわからないというのが悩ましいところです。(タイプの当たり外れ論さておき)
その場合、無駄ならしなくていいんじゃね?という論の立て方もあるでしょうし、100%期待の効果が得られなくてもやれることはやりましょう。効果の部分や救える人たちがいることを忘れてはいけません、、というところに立つのかの違い。
また、国の予算の優先順位的にあきらめざるをえないレベルなのか、やれそうだ、なのかの違いもあります。
新しいワクチンの採用にあたって、ワクチン施策を変更したのは英国です。
Public Health UKの名のもとに、大きな改革が行われています。
英国におけるインフルエンザワクチン接種率のグラフはこちら。医療関係者で50%前後。
英国における対策の詳細はこちら
簡単にいいますと、それまではハイリスクな人たちに注射のワクチン接種、でしたが、今回のシーズンからは2-17歳へ鼻スプレー式のワクチン接種勧奨がルチンにおこなわれることになりました。
毎年、免疫のない子供達で流行し、それが家庭にもちこまれて親や地域の高齢者に広がるというのがよくあるパターンですので、若年集団での流行を止めることで社会全体の流行を止めようというものです。
注射式のワクチンから、より有効な粘膜へのスプレー式ワクチンに変更をしたとしても、米国のように「より広い対象に」と言わないところが英国式。
スプレー式は針を使いませんので、針を刺すことによって生じる健康被害もなくなりますし、医療廃棄物処理上も楽です。
学校などでの集団接種でも使いやすそうです。
新しい手法なので、教育資材も公開されています。
NHS 医療者向け教育ビデオ(約6分)
子どもへのスプレー式ワクチンの説明と実施
モデルのナースが、現場そのまま感たっぷりですが(^^;)。
子どもにもインフォームドコンセント、と丁寧な説明があります。熟練者集団がつくる教育やプロモーションのてあつさを見ますね。
その評価は来年春には出るでしょう。
[参考]
Health Law Perspectives (May 2013)
Health Law & Policy Institute University of Houston Law Center
The variable efficacy of current influenza vaccines result in mandatory flu vaccination policies forhealth care workers being difficult to justify
他の国ももっと調べてみたい:
ドイツの大学病院。医師の方が看護師より接種率が高い。というか、どちらも日本と比べてすごく低い(2007-8年ですが)
カナダの看護協会 ポジションペーパー
INFLUENZA IMMUNIZATION OF REGISTERED NURSES
これまでのサマリー:インフルエンザワクチンの歴史