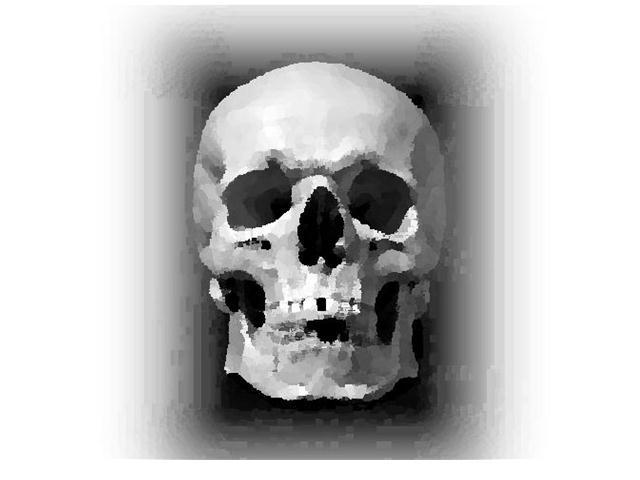・青森県岩木山北東麓の標高143~145メートルの舌状丘陵上に立地します。
・「環状列石」は、台地上を整地した後、土手状に盛土し、 . . . 本文を読む
(世界遺産・07)『亀ヶ岡遺跡』
はじめに青森県津軽半島のつがる市に所在し、岩木川沿岸の標高7~18メートルの丘陵上に立地します。海進期に形成された内湾である古十三湖(こ・じゅうさんこ)に面しています。
墓域は長期間にわたって構築されており、祖先崇拝が継続して行なわれたことを示しています。
土器から見えること
・器形から 底が丸底になっているのは、底の浅い湖沼を表しています。
. . . 本文を読む
世界遺産・縄文05)「御所野遺跡」(サケマスの供養)岩手県北部の一戸町に所在し、馬淵川沿岸の標高190~210メートルの河岸段丘に立地します。食料となるサケ・マスが遡上し、捕獲できるとともに、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていました。
集落の中央に配石遺構や墓などの墓域が造られ、その周囲には竪穴建物、掘立柱建物、祭祀に伴う盛土などが分布し、さらにその外側の東、西にも竪 . . . 本文を読む
はじめに「縄文土器」ということばを使いながら縄文土器本来の形や模様の解読ができていないのです。
模様や形を神話的思考だとか霊のなせる業だとか「非人間的な思考」で扱っているように思えるのです。これが現代ヒトの思考です。 . . . 本文を読む