都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「没後150年 歌川国芳展」 森アーツセンターギャラリー
森アーツセンターギャラリー
「没後150年 歌川国芳展」
2011/12/17~2012/2/12 *前期:2011/12/17~2012/1/17、後期:2012/1/19~2/12
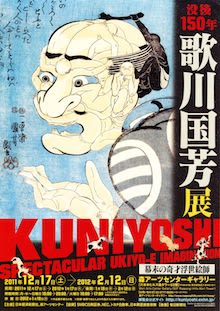
これぞ国芳展の決定版です。森アーツセンターギャラリーで開催中の「没後150年 歌川国芳展」のプレスプレビューに参加してきました。
さすがに人気の浮世絵師ということもあり、古くは東京ステーションギャラリーでの暁斎との二人展、また最近では府中市美術館での展示など、折に触れて見る機会もあった国芳ですが、今回ほどのスケールで開催されたことは今まで殆どありませんでした。

出品数は怒涛の全400点です。(前後期で総入れ替え。)会場には新発見、初公開を含む、主に国内の個人蔵の肉筆、版本、そして錦絵がずらりと勢揃いしていました。
章立ては以下の通りです。
簡潔で分かりやすいテーマ別の構成です。国芳を人気浮世絵師へと引き上げた「水滸伝」シリーズなどの役者絵を筆頭に、美人画や風景画、そして動物画や戯画などへと続いていました。
冒頭の武者絵から奇想の国芳全開モードです。1827年に出版された「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」は、当時の水滸伝ブームにものり、それまであまり注目されなかった国芳を一大スターへとのしあげました。
また前半で注目したいのは、ど迫力ワイド画面の大判3枚綴りのシリーズです。

左、「宮本武蔵の鯨退治」 右、「相馬の古内裏」
おなじみの「相馬の古内裏」と「宮本武蔵の鯨退治」の揃い踏みに思わずぞくぞくしてしまったのは私だけでしょうか。
なお写真ではわかりにくいかもしれませんが、今回の出品作の状態はかなり良好です。国芳といえば、とかく大胆極まりない構図と、それこそ目に突き刺さんばかりの鮮やかな色に魅力があるだけに、美しい摺が揃っているというのもまた嬉しいところでした。

それに細かいところかもしれませんが、役者絵や説話など、とりわけ極彩色を多用した作品のコーナーの壁は黒です。その色味が効果的に引き立ちます。画面にぐいぐいと引き込まれました。
さて国芳といえば金魚、そして猫を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、そこでも特に注目すべき作品がいくつかあります。
それがともに新発見、初公開となる「金魚づくし」(注:後期展示)と、猫に由来するたとえを戯画に仕立てた「たとゑ尽の内」の三枚組です。
「金魚づくし」ではこれまで確認されていた8例の他に新たにイタリアで見つかったもう1例が、またバラバラに3枚別れていた「たとゑ尽の内」が初めて一枚物として展示されました。

これまでにも国芳展は何度かあったため、ともすると既視感を覚えてしまうかもしれませんが、今回はこうした新出を含む、あまり見たことのない珍しい作品があるのもポイントではないでしょうか。
ともかく大変なスケールの展示であるので、内容を細かに追っていくとキリがありませんが、私として興味深かったのは風景画における国芳の先取性です。
幕末という時代もありますが、国芳はオランダの銅版画挿絵をもとに、いくつかの洋風風景画を描きました。

左、「近江の国の勇婦於兼」
会場ではその例として、元になった銅版画のパネルと国芳の実際の版画が比較展示されています。この「近江の国の勇婦於兼」の背景の山々はニューホフの銅版画に由来するそうですが、パネルと見比べても元絵の描写にかなり迫っているのではないでしょうか。

また錦絵ではなく摺物、ようは私的な注文制作の非売品の版画の他、肉筆も数点出ている点も見逃せません。

左、「しんば連 魚かし連 市川三升へ送之」 右、「花車 五節句賛」
摺物ならではの繊細な描線、そして瑞々しい色をじっくりと味わうことが出来ました。

左、「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」 右、「としよりのよふな若い人だ」
諧謔味こそ国芳画の真骨頂なのかもしれません。ちらし表紙の「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」などのはめ絵から影絵に文字絵、そして彼の愛した動物、とりわけ猫らの登場する一連の戯画は、やはり展覧会のハイライトと言えるのではないでしょうか。
この膨大な出品作を前にするとあれこれ迷ってしまいますが、もし国芳この一点とするならやはり「宮本武蔵の鯨退治」をあげたいと思います。
画面か飛び出してくるといわんばかりの躍動感溢れる鯨の迫力は比類がありません。そういえば私が国芳を初めて意識したのは、いつぞやの展示でこの作品を見てからのことでした。 ちなみに前期中はこの鯨をモチーフとした力作がもう一点、出品されています。そちらも是非探してみて下さい。

なお初めにも触れましたが、展示はごく一部を除き、会期途中で作品がほぼ全て入れ替わります。 (出品リスト)
前後期の二期制です。十分にご注意下さい。
細かく区切ったパーティションも浮世絵の展示によく合っているのかもしれません。作品の量からしても、森アーツとしては異例とも言えるほど濃密な空間が出来上がっています。六本木と国芳の組み合わせは悪くありません。若い客層が多いだけに、他の博物館なりでの浮世絵展とはまた違った話題を集めるのではないでしょうか。 なお先行した大阪展では約12万名もの入場者が押し掛けたそうです。

画面の小さな浮世絵、とりわけ細部にウイットに富んだ工夫をこらす国芳画のことです。遠くから眺めてもあまり面白くありません。空いている環境がベストです。まずは会期のはじめか、比較的混雑しない夜間で観覧されることをおすすめします。なお今回の展観で森アーツセンターは火曜日を除き、連日20時まで開館しています。
 「もっと知りたい歌川国芳/東京美術」
「もっと知りたい歌川国芳/東京美術」
なおキャプションはあまり付いていません。一点一点の解説は図録に当たった方が良さそうです。
2012年2月12日までの開催です。ずばりおすすめします。
「没後150年 歌川国芳展 幕末の奇才浮世絵師」 森アーツセンターギャラリー
会期:前期、2011年12月17日(土)~2012年1月17日(火)。後期、2012年1月19日(木)~2月12日(日)。
休館:2012年1月18日(水)*展示替え日
時間:11:00~20:00 *但し火曜日は17時まで。
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。
「没後150年 歌川国芳展」
2011/12/17~2012/2/12 *前期:2011/12/17~2012/1/17、後期:2012/1/19~2/12
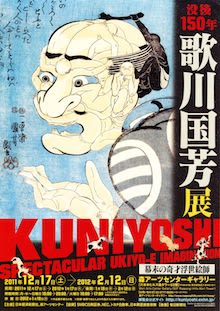
これぞ国芳展の決定版です。森アーツセンターギャラリーで開催中の「没後150年 歌川国芳展」のプレスプレビューに参加してきました。
さすがに人気の浮世絵師ということもあり、古くは東京ステーションギャラリーでの暁斎との二人展、また最近では府中市美術館での展示など、折に触れて見る機会もあった国芳ですが、今回ほどのスケールで開催されたことは今まで殆どありませんでした。

出品数は怒涛の全400点です。(前後期で総入れ替え。)会場には新発見、初公開を含む、主に国内の個人蔵の肉筆、版本、そして錦絵がずらりと勢揃いしていました。
章立ては以下の通りです。
第1章「武者絵」 みなぎる力と躍動感
第2章「説話」 物語とイメージ
第3章「役者絵」 人気役者のさまざまな姿
第4章「美人画」 江戸の粋と団扇絵の美
第5章「子ども絵」 遊びと学び
第6章「風景画」 近代的なアングル
第7章「摺物と動物画」 精緻な彫と摺
第8章「戯画」 溢れるウィットとユーモア
第9章「風俗・娯楽・情報」
第2章「説話」 物語とイメージ
第3章「役者絵」 人気役者のさまざまな姿
第4章「美人画」 江戸の粋と団扇絵の美
第5章「子ども絵」 遊びと学び
第6章「風景画」 近代的なアングル
第7章「摺物と動物画」 精緻な彫と摺
第8章「戯画」 溢れるウィットとユーモア
第9章「風俗・娯楽・情報」
簡潔で分かりやすいテーマ別の構成です。国芳を人気浮世絵師へと引き上げた「水滸伝」シリーズなどの役者絵を筆頭に、美人画や風景画、そして動物画や戯画などへと続いていました。
冒頭の武者絵から奇想の国芳全開モードです。1827年に出版された「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」は、当時の水滸伝ブームにものり、それまであまり注目されなかった国芳を一大スターへとのしあげました。
また前半で注目したいのは、ど迫力ワイド画面の大判3枚綴りのシリーズです。

左、「宮本武蔵の鯨退治」 右、「相馬の古内裏」
おなじみの「相馬の古内裏」と「宮本武蔵の鯨退治」の揃い踏みに思わずぞくぞくしてしまったのは私だけでしょうか。
なお写真ではわかりにくいかもしれませんが、今回の出品作の状態はかなり良好です。国芳といえば、とかく大胆極まりない構図と、それこそ目に突き刺さんばかりの鮮やかな色に魅力があるだけに、美しい摺が揃っているというのもまた嬉しいところでした。

それに細かいところかもしれませんが、役者絵や説話など、とりわけ極彩色を多用した作品のコーナーの壁は黒です。その色味が効果的に引き立ちます。画面にぐいぐいと引き込まれました。
さて国芳といえば金魚、そして猫を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、そこでも特に注目すべき作品がいくつかあります。
それがともに新発見、初公開となる「金魚づくし」(注:後期展示)と、猫に由来するたとえを戯画に仕立てた「たとゑ尽の内」の三枚組です。
「金魚づくし」ではこれまで確認されていた8例の他に新たにイタリアで見つかったもう1例が、またバラバラに3枚別れていた「たとゑ尽の内」が初めて一枚物として展示されました。

これまでにも国芳展は何度かあったため、ともすると既視感を覚えてしまうかもしれませんが、今回はこうした新出を含む、あまり見たことのない珍しい作品があるのもポイントではないでしょうか。
ともかく大変なスケールの展示であるので、内容を細かに追っていくとキリがありませんが、私として興味深かったのは風景画における国芳の先取性です。
幕末という時代もありますが、国芳はオランダの銅版画挿絵をもとに、いくつかの洋風風景画を描きました。

左、「近江の国の勇婦於兼」
会場ではその例として、元になった銅版画のパネルと国芳の実際の版画が比較展示されています。この「近江の国の勇婦於兼」の背景の山々はニューホフの銅版画に由来するそうですが、パネルと見比べても元絵の描写にかなり迫っているのではないでしょうか。

また錦絵ではなく摺物、ようは私的な注文制作の非売品の版画の他、肉筆も数点出ている点も見逃せません。

左、「しんば連 魚かし連 市川三升へ送之」 右、「花車 五節句賛」
摺物ならではの繊細な描線、そして瑞々しい色をじっくりと味わうことが出来ました。

左、「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」 右、「としよりのよふな若い人だ」
諧謔味こそ国芳画の真骨頂なのかもしれません。ちらし表紙の「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」などのはめ絵から影絵に文字絵、そして彼の愛した動物、とりわけ猫らの登場する一連の戯画は、やはり展覧会のハイライトと言えるのではないでしょうか。
この膨大な出品作を前にするとあれこれ迷ってしまいますが、もし国芳この一点とするならやはり「宮本武蔵の鯨退治」をあげたいと思います。
画面か飛び出してくるといわんばかりの躍動感溢れる鯨の迫力は比類がありません。そういえば私が国芳を初めて意識したのは、いつぞやの展示でこの作品を見てからのことでした。 ちなみに前期中はこの鯨をモチーフとした力作がもう一点、出品されています。そちらも是非探してみて下さい。

なお初めにも触れましたが、展示はごく一部を除き、会期途中で作品がほぼ全て入れ替わります。 (出品リスト)
前期:2011年12月17日(土)~2012年1月17日(火)
後期:2012年1月19日(木)~2月12日(日)
後期:2012年1月19日(木)~2月12日(日)
前後期の二期制です。十分にご注意下さい。
細かく区切ったパーティションも浮世絵の展示によく合っているのかもしれません。作品の量からしても、森アーツとしては異例とも言えるほど濃密な空間が出来上がっています。六本木と国芳の組み合わせは悪くありません。若い客層が多いだけに、他の博物館なりでの浮世絵展とはまた違った話題を集めるのではないでしょうか。 なお先行した大阪展では約12万名もの入場者が押し掛けたそうです。

画面の小さな浮世絵、とりわけ細部にウイットに富んだ工夫をこらす国芳画のことです。遠くから眺めてもあまり面白くありません。空いている環境がベストです。まずは会期のはじめか、比較的混雑しない夜間で観覧されることをおすすめします。なお今回の展観で森アーツセンターは火曜日を除き、連日20時まで開館しています。
 「もっと知りたい歌川国芳/東京美術」
「もっと知りたい歌川国芳/東京美術」なおキャプションはあまり付いていません。一点一点の解説は図録に当たった方が良さそうです。
2012年2月12日までの開催です。ずばりおすすめします。
「没後150年 歌川国芳展 幕末の奇才浮世絵師」 森アーツセンターギャラリー
会期:前期、2011年12月17日(土)~2012年1月17日(火)。後期、2012年1月19日(木)~2月12日(日)。
休館:2012年1月18日(水)*展示替え日
時間:11:00~20:00 *但し火曜日は17時まで。
住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。
注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )









