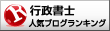念のためにペルー(秘露)国立公文書館に保存されている筈の日本人のおじいさまの外国人登録原票の写しを送って貰ったところ、氏名:XX XX(アルファベット)、生年月日1889年X月X日、出身:(東北の)F県、入国年:1909年、入港地:XXXと言ったデータが書かれてあります。生まれは、明治22年、入国年も明治42年ですから、誤記等を考慮に入れても、明治40年~43年前後に申請発行された旅券に関する申請者のデータが保存されていれば、本籍地が判るはずなのですが・・・。
飯倉の外務省外交資料館に問い合わせたところ、「移民取扱人による南米秘露国行の外国旅券下付表」なるマイクロフィルムが閲覧できるとのことでした。移民取扱人とは、旅行会社のようなものなのだそうです。そこには氏名、生年月日、本籍地等が書かれてある筈だとのことでした。しかし、県別になっているとはいえ、かなりの数があるので、調べるのは大変だとのこと。ん~・・・。
そこで、何年の移民船に乗船したかが判ればと思い、横浜にあるJICA海外移住資料館へ。親切な学芸員の方に、色々とお教え頂き、航海者名簿の中から、依頼人の祖父らしき人物を発見したのでした。アルファベットから想像していた漢字とは違った氏名でした。ちなみに、F県の地名を調べてみたら、K市にその地名がありました。こりゃ間違いなくF県の人だと断定し、再び外交資料館へ。
外交資料館の方も、さすがにご存じ!「一応、42年F県のものを探して見て下さい。場合によっては、出港地である神奈川県に紛れ込んでいる場合もありますから、そちらも確認して下さい。」と、さすが~資料館員!
この外務省外交資料館には、貴重な外交資料や公文書が保管されているようで、学者か大学院生のような人々が真剣に調べ物を探していました。私のようなアカデミックさに欠ける、図書館さえあまり利用しないようなオジさんにとってはちょっと窮屈な場所です。
さて、マイクロフィルムのスライドを見る器械の扱いを教えて貰って、ものの10分で、ありました!ありました!出生年は違っていましたが、月日は同じ!ビンゴー!という感じです。族籍:平民、身分:戸主XX弟、本籍地:XX郡XX村字・・・、一応これらをメモして、「あのう、この写しを貰うのはどうすれば良いので?」と聞くと、「複写申込書(戦前)」外務省外交資料館長殿と書かれた申請書に記入してその場で申込、後日、事務所にマイクロ写真工業なる会社から、この写しが配送されてきました。
一方、外交資料館でメモした本籍地、戸主名、依頼人の祖父名、それに使用目的、提出先等々記入して、F県K市へ「改製原戸籍」を職務請求しました。日系人の多い沖縄などの市町村では、取り出し易い場所に保管しているのだそうですが、そうでない市町村では、奥の方に仕舞い込んであり、探すのが大変で時間がかかることがあるそうですが・・・。
K市の場合、やや手間取りましたが、改製原戸籍が送られてきました。明治32年にXX某へ養子に行くも、41年協議離縁と記載されています。9歳で養子に行き、18歳でその家から離縁された若者は、その翌年、移民船に乗ってペルーへ渡った事が判りました。一体、彼にどんな事情があったのでしょうか?
なお、本籍地の移動や婚姻などの記載が一切ありませんので、そのままの本籍地で戸籍謄本の請求をしましたら、今度は横書きの「全部事項証明」が送られてきました。なお、このようなケースでは、年齢から生存している可能性がほとんど無いことから、推定死亡とされて除籍となっている場合もあります。
以上、なんとか依頼人の要望に応えられました。そして、昨年ですが、日本人と結婚しているご親族(孫)の方から、ご兄弟を呼び寄せたいのでとの事で、在留資格認定証明書(ビザのようなものです)の申請取次依頼を別途受け、今年、その認定証明書が交付されました。こうして、日系人の方々達は、再び日本に移民として来日して来るのでしょうか?