辺見庸『赤い橋の下のぬるい水』(文春文庫)
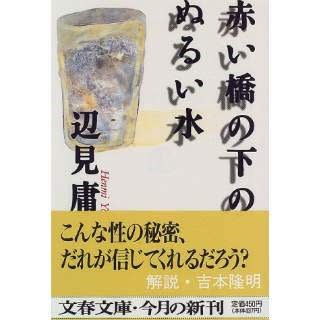
海水と川水が危うげに交じりあう河口の橋のたもとに、その女はいた。驚くべきからだの秘密をもてあましつつ、悲しげに…。性の奥深さ、不埓さを型破りに描き出す表題作他、女たちとの闇の道行きを綴った「ナイト・キャラバン」、日常に深く静かに忍び込む狂気をあぶり出す力作「ミュージック・ワイア」を併録。(「BOOK」データベースより)
◎代表的な2作も素晴らしいけれど
辺見庸は1991年、フィクション『自動起床装置』(文春文庫)で芥川賞を受賞して文壇デビューしました。そして1994年には、ノンフィクション『もの食う人びと』(角川文庫)で講談社ノンフィクション賞を受賞します。辺見庸は共同通信社の特派員として、北京やハノイで活躍していました。37歳のときに、中国共産党の機密文書でスクープ記事を書き、国外退去処分を受けています。
小説を書いたのは、それから10年後のことです。仕事の体験からヒントを得た『自動起床装置』(文春文庫)は、おおいに話題になりました。
いまではネットで、「JR.御用達自動起床装置」などというグッズが販売されています。本作が発表されたときは、まだ開発段階だったのだと思います。主人公「ぼく」は、眠りと樹木ばかりを研究している大学生(小野寺聡)といっしょにアルバイトをしています。仕事に忙しい当直の記者たちを、定刻に起こす役割です。
そんなある日に、自動起床装置なる機械の導入が決まりました。ぼくたちは機械の付け人みたいな役割になります。ところが当直者の一人が、心筋梗塞で死にかけます。ぼくと聡は懸命に蘇生させます。『自動起床装置』はこんなストーリーなのですが、眠りについて深く追求した奥深い作品になっていました。
その後も共同通信社のエース記者として勤務するかたわら、1994年に発表したのが『もの食う人びと』(角川文庫)でした。本書はノンフィクション・ジャンルとしては異例の売り上げとなりました。食にかんする楽しいエッセイは、数多くあります。東海林さだおや小泉武夫などが、その代表格です。
しかし私は2つの著作の間の1992年に発表された、『赤い橋の下のぬるい水』(文春文庫)を推薦させていただきます。本書のタイトルは、そのまま今村昌平監督が映画にしています。観てはいませんが、本書がベースになっていることは間違いありません。
◎辺見庸の代表小説
『赤い橋の下のぬるい水』(文春文庫)のテーマは、〈連鎖〉です。表題作は、オムニバス形式になっています。ときおり読者に語りかける話体は、新鮮な彩りをそえています。
文庫解説で吉本隆明は、本書を奇譚小説とくくっています。本書には表題作のほかに、2つの短編が収められています。私はそのなかでも、表題作が好きです。辺見庸らしい作品だと思います。著者がこだわる〈循環〉を、この作品はみごとに描ききっています。
主人公の「ぼく」は保険の営業をしています。「ぼく」はスーパーで、チーズを万引きする女を目撃します。フラミンゴを思わせる首の長い女は万引きをしたあと、恍惚の表情を浮かべてそこに立ち尽くしていました。
「ぼく」は女が立ち去るときに、耳たぶから金色のイヤリングが落下するのを見ます。拾いに行ってみると、女の立っていたところには、小さな水溜まりがありました。
――足もとのベージュ色の床に、小さな水たまりがあった。そのなかに、金色の魚の形のイヤリングが一匹光って泳いでいた。水たまりなんか世界中のどこにでもあるけれども、それは不思議な水たまりだった。(本文P12より)
「ぼく」は女を追いかけて、イヤリングを渡します。女はサエコといいます。彼女は万引きをした理由を正直に話すので、見逃してほしいといいます。彼女は身体に、水が溜まる病気をもっています。それはセックスか万引きをしないかぎり、身体から出すことはできません。その理由を問いただす場面があります。
――「どうしてチーズを盗んだの?」/サエコは口を噤んだ。/「どうしてさ。よかったら教えてほしいな」/「水が、水が、からだにたまったからなの……」/「水がたまると、その、ものを盗むの?」/「ああ、ひどいことをしている、してはいけないことをしている、と思うと、でるの。恥ずかしいわ、ほんとうに」(本文P38)
「ぼく」は、サエコに溜まった水を出す手伝いをするようになります。水はセックスのたびに、2リットルも出ます。
辺見庸は意図的に、セックス場面を淡白に描きます。その代わり、2人を取り巻く情景は、実にていねいに描き出します。「もの」にこだわる、著者らしい描写力です。「ぼく」の連鎖妄想は、際限がありません。最も印象深かった一節を引用して、〈連鎖〉をとめることにします。
――日傘は、ぼくと彼女のなりゆきを、青く包んで川をゆっくりと下っていった。盗まれたチーズがひと足先に女の家でぼくらを待っている。なりゆきが日傘をさして、チーズを食べにいく。チーズはぼくらに食べられる。めぐりめぐる。そう考えると、ぼくは不思議さに酔ったような気分になった。(本文P21)
これはサエコと水抜き契約を結んだ「ぼく」が、木越川の汽水に架かる赤い太鼓橋のたもとの家に向かう場面です。首の長い美しい女性を発見した「ぼく」。その女が万引きをしたところを見た「ぼく」。女の耳元から落下するイヤリング。その落下の先にあった水たまり。
辺見庸の文章は連続シャッター音をたてる、カメラマンの写真のようです。会話もすこぶる上質なものです。本書を読んで共感したら、サンドウイッチのように本書をはさんでいる『自動起床装置』と『もの食う人びと』をお読みください。
『もの食う人びと』は、いずれ「知・教養。古典ジャンル125+α」の1冊として紹介させていただきます。
(山本藤光1996. 09.22初稿、2018.03.08改稿)
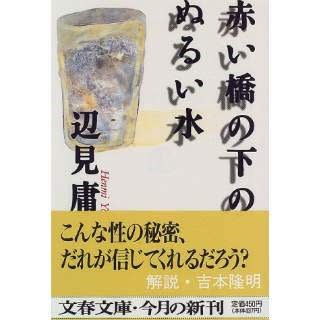
海水と川水が危うげに交じりあう河口の橋のたもとに、その女はいた。驚くべきからだの秘密をもてあましつつ、悲しげに…。性の奥深さ、不埓さを型破りに描き出す表題作他、女たちとの闇の道行きを綴った「ナイト・キャラバン」、日常に深く静かに忍び込む狂気をあぶり出す力作「ミュージック・ワイア」を併録。(「BOOK」データベースより)
◎代表的な2作も素晴らしいけれど
辺見庸は1991年、フィクション『自動起床装置』(文春文庫)で芥川賞を受賞して文壇デビューしました。そして1994年には、ノンフィクション『もの食う人びと』(角川文庫)で講談社ノンフィクション賞を受賞します。辺見庸は共同通信社の特派員として、北京やハノイで活躍していました。37歳のときに、中国共産党の機密文書でスクープ記事を書き、国外退去処分を受けています。
小説を書いたのは、それから10年後のことです。仕事の体験からヒントを得た『自動起床装置』(文春文庫)は、おおいに話題になりました。
いまではネットで、「JR.御用達自動起床装置」などというグッズが販売されています。本作が発表されたときは、まだ開発段階だったのだと思います。主人公「ぼく」は、眠りと樹木ばかりを研究している大学生(小野寺聡)といっしょにアルバイトをしています。仕事に忙しい当直の記者たちを、定刻に起こす役割です。
そんなある日に、自動起床装置なる機械の導入が決まりました。ぼくたちは機械の付け人みたいな役割になります。ところが当直者の一人が、心筋梗塞で死にかけます。ぼくと聡は懸命に蘇生させます。『自動起床装置』はこんなストーリーなのですが、眠りについて深く追求した奥深い作品になっていました。
その後も共同通信社のエース記者として勤務するかたわら、1994年に発表したのが『もの食う人びと』(角川文庫)でした。本書はノンフィクション・ジャンルとしては異例の売り上げとなりました。食にかんする楽しいエッセイは、数多くあります。東海林さだおや小泉武夫などが、その代表格です。
しかし私は2つの著作の間の1992年に発表された、『赤い橋の下のぬるい水』(文春文庫)を推薦させていただきます。本書のタイトルは、そのまま今村昌平監督が映画にしています。観てはいませんが、本書がベースになっていることは間違いありません。
◎辺見庸の代表小説
『赤い橋の下のぬるい水』(文春文庫)のテーマは、〈連鎖〉です。表題作は、オムニバス形式になっています。ときおり読者に語りかける話体は、新鮮な彩りをそえています。
文庫解説で吉本隆明は、本書を奇譚小説とくくっています。本書には表題作のほかに、2つの短編が収められています。私はそのなかでも、表題作が好きです。辺見庸らしい作品だと思います。著者がこだわる〈循環〉を、この作品はみごとに描ききっています。
主人公の「ぼく」は保険の営業をしています。「ぼく」はスーパーで、チーズを万引きする女を目撃します。フラミンゴを思わせる首の長い女は万引きをしたあと、恍惚の表情を浮かべてそこに立ち尽くしていました。
「ぼく」は女が立ち去るときに、耳たぶから金色のイヤリングが落下するのを見ます。拾いに行ってみると、女の立っていたところには、小さな水溜まりがありました。
――足もとのベージュ色の床に、小さな水たまりがあった。そのなかに、金色の魚の形のイヤリングが一匹光って泳いでいた。水たまりなんか世界中のどこにでもあるけれども、それは不思議な水たまりだった。(本文P12より)
「ぼく」は女を追いかけて、イヤリングを渡します。女はサエコといいます。彼女は万引きをした理由を正直に話すので、見逃してほしいといいます。彼女は身体に、水が溜まる病気をもっています。それはセックスか万引きをしないかぎり、身体から出すことはできません。その理由を問いただす場面があります。
――「どうしてチーズを盗んだの?」/サエコは口を噤んだ。/「どうしてさ。よかったら教えてほしいな」/「水が、水が、からだにたまったからなの……」/「水がたまると、その、ものを盗むの?」/「ああ、ひどいことをしている、してはいけないことをしている、と思うと、でるの。恥ずかしいわ、ほんとうに」(本文P38)
「ぼく」は、サエコに溜まった水を出す手伝いをするようになります。水はセックスのたびに、2リットルも出ます。
辺見庸は意図的に、セックス場面を淡白に描きます。その代わり、2人を取り巻く情景は、実にていねいに描き出します。「もの」にこだわる、著者らしい描写力です。「ぼく」の連鎖妄想は、際限がありません。最も印象深かった一節を引用して、〈連鎖〉をとめることにします。
――日傘は、ぼくと彼女のなりゆきを、青く包んで川をゆっくりと下っていった。盗まれたチーズがひと足先に女の家でぼくらを待っている。なりゆきが日傘をさして、チーズを食べにいく。チーズはぼくらに食べられる。めぐりめぐる。そう考えると、ぼくは不思議さに酔ったような気分になった。(本文P21)
これはサエコと水抜き契約を結んだ「ぼく」が、木越川の汽水に架かる赤い太鼓橋のたもとの家に向かう場面です。首の長い美しい女性を発見した「ぼく」。その女が万引きをしたところを見た「ぼく」。女の耳元から落下するイヤリング。その落下の先にあった水たまり。
辺見庸の文章は連続シャッター音をたてる、カメラマンの写真のようです。会話もすこぶる上質なものです。本書を読んで共感したら、サンドウイッチのように本書をはさんでいる『自動起床装置』と『もの食う人びと』をお読みください。
『もの食う人びと』は、いずれ「知・教養。古典ジャンル125+α」の1冊として紹介させていただきます。
(山本藤光1996. 09.22初稿、2018.03.08改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます