田山花袋『蒲団』(新潮文庫)
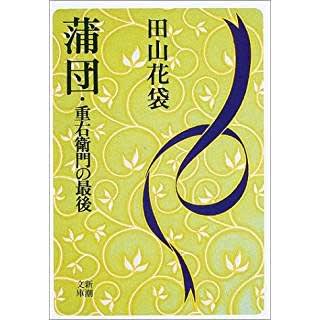
蒲団に残るあのひとの匂いが恋しい―赤裸々な内面生活を大胆に告白して、自然主義文学のさきがけとなった記念碑的作品『蒲団』と、歪曲した人間性をもった藤田重右衛門を公然と殺害し、不起訴のうちに葬り去ってしまった信州の閉鎖性の強い村落を描いた『重右衛門の最後』とを収録。その新しい作風と旺盛な好奇心とナイーヴな感受性で若い明治日本の真率な精神の香気を伝える。(「BOOK」データベースより)
◎自然主義文学の記念碑的な作品
花袋は島崎藤村(推薦作『夜明け前』全4巻、新潮文庫)とならび、自然主義文学の代表作家といわれています。田山花袋は泉鏡花(推薦作『高野聖』新潮文庫)とともに、尾崎紅葉(推薦作『金色夜叉』新潮文庫)の弟子でした。泉鏡花の方は早くに頭角をあらわすのですが、田山花袋の不遇な時代はつづきました。そのあたりのことは、坪内祐三(推薦作『考える人』新潮文庫)の著作を引いてみます。
――もともと尾崎紅葉の門下だった花袋はロマンティックな文学に憧れていた。けれどそのロマンティシズムは、やはり紅葉の門下だった同世代の作家泉鏡花と違って、板についていなかった。花袋は野暮で無骨だった。その「バタ臭い」、「泣蟲の」、「世間見ずの」小説は嘲笑の対象だった。(坪内祐三『近代日本文学の誕生』PHP新書P26より)
田山花袋は芥川龍之介(推薦作『羅生門』新潮文庫)から「感傷的風景画家」(花村太郎『知的トレーニングの技術』JICC出版局P195より。現ちくま学芸文庫)とあだ名をつけられていました。そんな田山花袋が花開いたのは、私小説に傾斜した作品『蒲団』(新潮文庫)だったのです。
そして『蒲団』は、島崎藤村『破戒』(新潮文庫)がなければ生まれていません。これは文庫あとがきで、福田恆存が断言しているとおりです。さらに田山花袋は「文章世界」の主筆になってから、自覚が生まれたという説もあります。いずれにせよ『蒲団』は、田山花袋本人にとっても、自然主義文学にとっても、記念碑的な作品であったのです。
その後の展開を語る、記述を紹介します。
――『蒲団』は『破戒』よりも、読者に人気があった。ことに『蒲団』は、作者の花袋本人の体験をもとにした自伝的要素の強い小説だったので、そのセンセーショナル性も手伝って人気が出たし、文学として妙に説得力があった。人気が出れば、作家たちだって「これで、いいのダ」と思い込んでしまう。(長尾剛『早わかり日本文学史』日本実業出版社より)
『蒲団』は日本の近代文学を知るために、絶対に避けて通れない作品です。夏目漱石(推薦作『吾輩は猫である』新潮文庫)が大嫌いだった自然主義文学を、『吾輩は猫である』と比較して読んでみてもらいたいと思います。
日本近代文学は、大きな節目によって流れが分断されています。節目とは、田山花袋・島崎藤村、森鴎外・夏目漱石、谷崎潤一郎・永井荷風となります。さらに流れを下れば、芥川龍之介・志賀直哉とつながるのです。
私小説の先駆けとして、森鴎外『舞姫』(岩波文庫。推薦作)が存在していました。しかし『舞姫』にはドロドロ感がありません。先に引用した「これで、いいのダ」は、そのまま後続の作家たちの胸のうちにも通じます。島崎藤村が姪との近親姦を描いた『新生』(上下巻、新潮文庫)も、そんな影響下の産物かもしれません。
◎退廃的な日常に一条の光
『蒲団』の主人公・竹中時雄は36歳。彼には妻と3人のこどもがいます。小説家ですが、あまり売れていません。生活を維持するために、地理書の編集の仕事をしています。ある日ファンだという読者から、1通の手紙が届きます。弟子にしてほしいという依頼でした。
依頼者は、岡山の名家の子女・横山芳子19歳でした。現在神戸の女学院に在籍しており、小説に一生を捧げたいといいます。両親の承諾も得ているという芳子にたいして、時雄は断りの返事を送ります。しかし芳子からはひんぱんに、懇願の手紙が送られてきます。結局時雄は、弟子入りを許可することになります。父親に連れられて、芳子が上京してきます。
――時雄は芳子と父とを並べて、縷々として文学者の境遇と目的を語り、女の結婚問題に就いて予め父親の説を叩いた。(本文P17より)
時雄の退廃的な日常に、一条の光が差しこみました。彼を「先生」と慕う芳子は、美しく華やいでいました。古いタイプの妻を疎んじていた時雄は、いつしか芳子に心を奪われてしまいます。最初は内弟子だったのですが、2人の親密さを周囲が心配しはじめます。結局1人暮らしの妻の姉のところに、芳子を預けることになりました。
芳子の帰宅が遅くなってきます。芳子には恋人ができました。それからの展開については、読んでのお楽しみとしておきます。「蒲団」という言葉は、とんと耳にしなくなってきました。
私ごとになるりますが、東京に下宿がきまったとき、蒲団と柳行李(やなぎごうり)をチッキで送ってもらいました。こんな記憶を語っても、若い人には意味が通じないと思います。私の記憶は、1970年代のものです。『蒲団』はそれよりも、半世紀前に書かれています。『蒲団』が書かれた時代を眺めておきます。
――『蒲団』の主題は、日露戦争後の国民的目標喪失とともに捨てられた旧道徳、そしていまだ生まれ得ぬ新しい規範、その谷間に落ちた「中間世代」の悲哀であった。(関川夏央『本よみの虫干し』岩波新書P61より)
時雄は偽善者であり、嫉妬深く、猜疑心がきわめて強い。読んでいて吐き捨てたくなるほど、ちっぽけな男です。それでいて倫理観や道徳心を兼ね備えています。それらがかろうじて、自己抑制のレバーを握り締めさせているのです。
一方芳子は、当時としてはハイカラな女性です。しかし恋人との交際では終始「純潔性」を主張してみせます。時雄は猜疑心のかたまりになっており、涙ながらの芳子の主張を信じられません。
いまどきの重量計では、測り切れない道徳という重み。これが日露戦争後の世の中だったのでしょう。うんと過去にネジを巻いて、文壇を刷新した『蒲団』を堪能してもらいたいと思います。
(山本藤光:2010.06.10初稿、2018.02.16改稿)
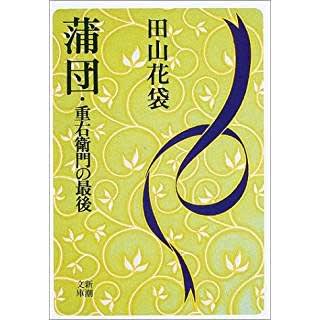
蒲団に残るあのひとの匂いが恋しい―赤裸々な内面生活を大胆に告白して、自然主義文学のさきがけとなった記念碑的作品『蒲団』と、歪曲した人間性をもった藤田重右衛門を公然と殺害し、不起訴のうちに葬り去ってしまった信州の閉鎖性の強い村落を描いた『重右衛門の最後』とを収録。その新しい作風と旺盛な好奇心とナイーヴな感受性で若い明治日本の真率な精神の香気を伝える。(「BOOK」データベースより)
◎自然主義文学の記念碑的な作品
花袋は島崎藤村(推薦作『夜明け前』全4巻、新潮文庫)とならび、自然主義文学の代表作家といわれています。田山花袋は泉鏡花(推薦作『高野聖』新潮文庫)とともに、尾崎紅葉(推薦作『金色夜叉』新潮文庫)の弟子でした。泉鏡花の方は早くに頭角をあらわすのですが、田山花袋の不遇な時代はつづきました。そのあたりのことは、坪内祐三(推薦作『考える人』新潮文庫)の著作を引いてみます。
――もともと尾崎紅葉の門下だった花袋はロマンティックな文学に憧れていた。けれどそのロマンティシズムは、やはり紅葉の門下だった同世代の作家泉鏡花と違って、板についていなかった。花袋は野暮で無骨だった。その「バタ臭い」、「泣蟲の」、「世間見ずの」小説は嘲笑の対象だった。(坪内祐三『近代日本文学の誕生』PHP新書P26より)
田山花袋は芥川龍之介(推薦作『羅生門』新潮文庫)から「感傷的風景画家」(花村太郎『知的トレーニングの技術』JICC出版局P195より。現ちくま学芸文庫)とあだ名をつけられていました。そんな田山花袋が花開いたのは、私小説に傾斜した作品『蒲団』(新潮文庫)だったのです。
そして『蒲団』は、島崎藤村『破戒』(新潮文庫)がなければ生まれていません。これは文庫あとがきで、福田恆存が断言しているとおりです。さらに田山花袋は「文章世界」の主筆になってから、自覚が生まれたという説もあります。いずれにせよ『蒲団』は、田山花袋本人にとっても、自然主義文学にとっても、記念碑的な作品であったのです。
その後の展開を語る、記述を紹介します。
――『蒲団』は『破戒』よりも、読者に人気があった。ことに『蒲団』は、作者の花袋本人の体験をもとにした自伝的要素の強い小説だったので、そのセンセーショナル性も手伝って人気が出たし、文学として妙に説得力があった。人気が出れば、作家たちだって「これで、いいのダ」と思い込んでしまう。(長尾剛『早わかり日本文学史』日本実業出版社より)
『蒲団』は日本の近代文学を知るために、絶対に避けて通れない作品です。夏目漱石(推薦作『吾輩は猫である』新潮文庫)が大嫌いだった自然主義文学を、『吾輩は猫である』と比較して読んでみてもらいたいと思います。
日本近代文学は、大きな節目によって流れが分断されています。節目とは、田山花袋・島崎藤村、森鴎外・夏目漱石、谷崎潤一郎・永井荷風となります。さらに流れを下れば、芥川龍之介・志賀直哉とつながるのです。
私小説の先駆けとして、森鴎外『舞姫』(岩波文庫。推薦作)が存在していました。しかし『舞姫』にはドロドロ感がありません。先に引用した「これで、いいのダ」は、そのまま後続の作家たちの胸のうちにも通じます。島崎藤村が姪との近親姦を描いた『新生』(上下巻、新潮文庫)も、そんな影響下の産物かもしれません。
◎退廃的な日常に一条の光
『蒲団』の主人公・竹中時雄は36歳。彼には妻と3人のこどもがいます。小説家ですが、あまり売れていません。生活を維持するために、地理書の編集の仕事をしています。ある日ファンだという読者から、1通の手紙が届きます。弟子にしてほしいという依頼でした。
依頼者は、岡山の名家の子女・横山芳子19歳でした。現在神戸の女学院に在籍しており、小説に一生を捧げたいといいます。両親の承諾も得ているという芳子にたいして、時雄は断りの返事を送ります。しかし芳子からはひんぱんに、懇願の手紙が送られてきます。結局時雄は、弟子入りを許可することになります。父親に連れられて、芳子が上京してきます。
――時雄は芳子と父とを並べて、縷々として文学者の境遇と目的を語り、女の結婚問題に就いて予め父親の説を叩いた。(本文P17より)
時雄の退廃的な日常に、一条の光が差しこみました。彼を「先生」と慕う芳子は、美しく華やいでいました。古いタイプの妻を疎んじていた時雄は、いつしか芳子に心を奪われてしまいます。最初は内弟子だったのですが、2人の親密さを周囲が心配しはじめます。結局1人暮らしの妻の姉のところに、芳子を預けることになりました。
芳子の帰宅が遅くなってきます。芳子には恋人ができました。それからの展開については、読んでのお楽しみとしておきます。「蒲団」という言葉は、とんと耳にしなくなってきました。
私ごとになるりますが、東京に下宿がきまったとき、蒲団と柳行李(やなぎごうり)をチッキで送ってもらいました。こんな記憶を語っても、若い人には意味が通じないと思います。私の記憶は、1970年代のものです。『蒲団』はそれよりも、半世紀前に書かれています。『蒲団』が書かれた時代を眺めておきます。
――『蒲団』の主題は、日露戦争後の国民的目標喪失とともに捨てられた旧道徳、そしていまだ生まれ得ぬ新しい規範、その谷間に落ちた「中間世代」の悲哀であった。(関川夏央『本よみの虫干し』岩波新書P61より)
時雄は偽善者であり、嫉妬深く、猜疑心がきわめて強い。読んでいて吐き捨てたくなるほど、ちっぽけな男です。それでいて倫理観や道徳心を兼ね備えています。それらがかろうじて、自己抑制のレバーを握り締めさせているのです。
一方芳子は、当時としてはハイカラな女性です。しかし恋人との交際では終始「純潔性」を主張してみせます。時雄は猜疑心のかたまりになっており、涙ながらの芳子の主張を信じられません。
いまどきの重量計では、測り切れない道徳という重み。これが日露戦争後の世の中だったのでしょう。うんと過去にネジを巻いて、文壇を刷新した『蒲団』を堪能してもらいたいと思います。
(山本藤光:2010.06.10初稿、2018.02.16改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます