メルヴィル『白鯨』(新潮文庫・上下巻、田中西二郎訳)
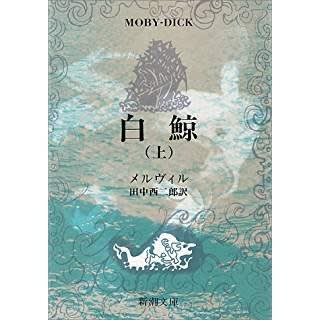
獰猛で狡知に長けた白鯨を追って、風雨、激浪の荒れ狂う海をピークォド号は進んだ。ホーン岬、インド洋、日本沖を経た長い航海の後、ついにエイハブは、太平洋の赤道付近で目ざす仇敵をみつけた。熱火の呪詛とともに、渾身の憎悪をこめた銛は飛んだ……。作者の実体験と文献の知識を総動員して、鯨の生態と捕鯨の実態をないまぜながら、エイハブの運命的悲劇を描いた一大叙事詩。(新潮文庫下巻の内容案内)
◎著者の気まぐれを受け入れる
『白鯨』は著者メルヴィル自身の、捕鯨船体験をもとに書かれました。メルヴィルは1841年に捕鯨船アクシュネット号に乗りこみます。それからの波乱万丈のできごとについて、書かれた本があります。紹介させてもらいます。なにやらこちらのほうが、おもしろい小説になりそうだと感じるのは、私だけでしょうか。
――当時、捕鯨船の労働条件は劣悪であった。そのことに嫌気が差したメルヴィルは、十八カ月後、船がマルキーズ諸島(南太平洋に浮かぶフランス領ポリネシア)に寄港したときに仲間とともに脱走する。ところが、その島には食人の習慣を持つ先住民がいて、彼らは「いつ自分たちが食われるか」と怯えながら過ごした。/一カ月後、偶然に寄港したオーストラリアの捕鯨船に乗って島を脱出したメルヴィルは、その捕鯨船内の暴動に巻きこまれ、タヒチ島で投獄されてしまう。その後脱走に成功したメルヴィルは近くの島に隠れ住み、やがてアメリカの捕鯨船に救われて一八四二年四月にハワイへ到着、ホノルルで店員などをした。(金森誠也・監修『世界の名作50選』PHP文庫)
『白鯨』は『モービー・ディック』というタイトルで、1951年に刊行されましたが、当時はまったく受け入れられませんでした。『白鯨』は長く、しかも鯨に関する論文のような文章が挿入されています。そのあたりについて、サマセット・モームの助言を紹介しておきます。
――わたくしがよんで退屈におぼえた章も、いくらかある。たとえば、図書館でくそ勉強をしておぼえこんだような、古物に関する知識だけからなる章とか、鯨の博物学をとりあつかった章とかがそれである。だが、メルヴィルがその深遠で玄妙な知識をひじょうに重んじていたことは明らかである。あなたは偉大なる才能をもつ作家の気まぐれな考えをそのままうけいれねばなるまい。(W.S.モーム『世界文学読書案内』岩波文庫、P135より)
『白鯨』は、10人を超える人が翻訳をしています。私が手にしたのはたまたま新潮文庫(田中西二郎訳)でしたが、意図したものではありません。山村修はその著書『書評家<狐>の読書遺産』(文春新書)のなかで、岩波文庫の八木敏雄訳を高く評価しています。山村修(推薦作『遅読のすすめ』ちくま文庫)は「狐」の名義で、ニュートラルな書評を数多く発信し、2006年に肺がんのために亡くなっています。
『白鯨』には、難解な記述が数多くあります。それゆえ翻訳の波長が、自分のリズムと合うか否かを確認することをお薦めします。
最近では2013年に、丸山健二『白鯨物語』(眞人堂)が出版されています。私の大好きな作家で、個人的には評価しています。ただしあまり流通されていません。丸山健二については別途、『夏の流れ』(講談社文芸文庫)を紹介させてもらいます。
翻訳のちがいを冒頭部分で検証しておきます。まずは新潮文庫(田中西二郎訳)から引用します。
――まかりいでたのはイシュメールと申す風来坊だ。もう何年前になるか――正確な年数などどうでもよかろう――懐中は文なし同然、陸地ではこれというおもしろいこともないので、しばらく船に乗って、水の世界を見て来ようと思った。わたしにとっては、それが憂鬱を追い払って、血行を良くする方法だったのだ。(本文P39)
河島弘美は『動物で読むアメリカ文学案内』(岩波ジュニア新書)で、原文の英語の下にみずからの翻訳文を書いています。
――わたしをイシュメイルと呼んでくれ。何年か前のこと――正確に何年かはどうでもよいのだが――財布の中身が底をつき、陸には興味をひかれるものもなかったので、船に乗って水の世界を見てこようと思った。それが凶暴性をなだめ、血行をよくするわたしのやり方だった。(河島弘美『動物で読むアメリカ文学案内』岩波ジュニア新書)
もうひとつならべてみます。
――人の名前なんぞというものにおよそどれほどの価値があるのかは知らないが、/若くしてとんでもない運命に遭遇し、/その渦に完全に巻きこまれてしまった、/極めて特異な体験の語り部として登場するおれのことは、/とりあえずイシュメールとでも名乗っておくことにしよう。(丸山健二『白鯨物語』眞人堂)
私は「水の世界」とか「血行をよくする」などの表現に、違和感をもっていました。翻訳が流れておらず、直訳っぽい場違いな単語が気になっていました。それを丸山健二はすべて削いで、みごとな滑り出しを描いてみせてくれました。
ほかに『白鯨』の訳書として、講談社文芸文庫(千石英世訳)と岩波文庫(八木敏雄訳)などがあります。読んでいませんが。
◎迫力満点の最終章
『白鯨』の語り手は、イシュメイルという無宿者です。鯨にかんする古今東西の文献の紹介や捕鯨にまつわる歴史なども、彼自身の言葉によって語られています。彼は捕鯨の街で、銛(もり)打ちのクィークェグと同宿します。2人は意気投合し、やがて片脚の船長・エイハブが陣頭指揮をする、捕鯨船・ピークォツド号に乗りこみます。この2人については最後に、笑ってしまった珍説(?)を紹介します。
船長・エイハブは、自身の片脚を奪った白鯨・モービー・ディックへの復讐を胸に、長い航海へと出発します。エイハブはマストにスペイン金貨をはりつけ、第一発見者にはそれを進呈すると宣言します。エイハブはあらゆる航海の常識を放棄し、ひたすら白鯨を追い求めつづけます。
エイハブには、人情のかけらもありません。荒れ狂う航海の安全にかんする、考慮すら欠けています。乗組員への配慮もありませんし、行き違うほかの捕鯨船への仲間意識も欠落しています。
エイハブ船長の怨念と、乗組員の諦念を乗せて、ピークォツド号は荒海を進みます。行けども行けども、白鯨・モービー・ディックは出現しません。乗組員たちの、寄港すべきだという主張は、とうに切り捨てられてしまっています。
『白鯨』は135章にもおよぶ長編です。しかし活劇が展開されるのは、最後の3章のみです。それまで読者は、たいくつな鯨学につきあわなければなりません。1度乗船したら降りることのできない海原ですので、しかたがありません。最終章(第135章)の迫力ある場面まで、読者は耐えて待たねばならないのです。
――突如、あたりの波が、ゆっくりと、広い円形にふくらんできた。それから、まるで水面下の氷山が急に浮き揚がるときのように、ふくらみは横すべりながら急激に高まった。低い地鳴りのような音が聞こえる。地底の鼻唄。次の瞬間、みな息を呑んだ。垂れる鯨索、銛と槍、それらを引きずりながら、巨大なるものが縦に――だが海面には斜めに跳り出たのだ。(下巻本文P513より)
私がこの文章を読むために、大学時代の階段教室での講義のような時間に耐えました。このあたりのことを、池澤夏樹はつぎのように語っています。
――真ん中の部分に何が書いてあるのか。ずうっと鯨の話です。鯨の種類、鯨という言葉の語源、鯨の生態、解剖学、捕る時の技術、その他種々、ありとあらゆる鯨学。それから捕鯨船の航海の詳細。いかなる人間が乗っていて、それぞれいかなるポジションについていて、どういう役割か。実際にいかにして鯨を見つけるのか。見つけたらどうやって追いかけて、捕まえて、母船まで運んで、最終的な処理をするか。そこから始まって、人類にとって鯨とは何かを哲学的に問う。具体的な応用例から、形而上学的な意味、旧約聖書に出てくる「ヨナの話」も出てきます。(池澤夏樹『世界文学を読みほどく』新潮選書より)
私には読みにくい作品でしたが、この作品を抜きにして「山本藤光の文庫で読む500+α」は完結しません。そんな思いで、学生時代に挫折した本書を、みごとに読破しました。退屈な部分はどんどん飛ばして読むと、分厚い上下巻はあっという間に読み終えることができます。念のため。
◎『白鯨』に寄せられたあれこれ
宮川雅は「『白鯨』はさまざまなレベルで読めるテキストである」として、つぎのように整理してくれています。
1. 十九世紀捕鯨業のルポルタージュ
2. 海洋冒険小説
3. シェクスピア的ないし神話的悲劇
4. 聖書のパロディ
5. 神や悪魔や認識の問題を巡る思想小説
6. フリーメーソンの象徴が解読され、エイハブと神の関係にグノーシス主義の思想
7. フランス批評家による図像学的・数秘学的解読
8. 男根冗句
(『世界文学101物語』高橋康也・編、新書館)
岩波文庫の『白鯨』(上中下巻、八木敏雄訳)は、11番目の邦訳だそうです。「狐」こと山村修は、訳注の豊かさに着目しています。特に「聖書」との関連については新鮮さを感じています。
――八木訳の特色をなすのは、その訳注のゆたかさだ。この小説は、語り手のイシュメールや船長のエイハブなど人名の借用をはじめ、いたるところい聖書本文の引用・暗示・パロディなどが織りこまれている。それが訳注で巨細にわたってしめされるばかりではない。訳文にも聖書読解にもとづく独特の工夫がこらされ、ときにはハッとさせられる。(山村修『書評家<狐>の読書遺産』文春新書)
もうひとつ、メルヴィルが他の作家から受けた影響について紹介させていただく。
――メルヴィルはホーソンを規範として、シェイクスピア悲劇の影響のもとに捕鯨の物語を書きなおした。そして、エイハブ船長は運命と悪に挑戦し、ついにはみずからを滅ぼすにいたるが、決して敗北はしないアメリカ的な英雄となる。(明快案内シリーズ:『アメリカ文学』自由国民社)
ホーソンは『緋文字』(新潮文庫)、シェイクスピアは『マクベス』(新潮文庫)を別途紹介させていただきます。最後は斎藤美奈子が笑わせてくれたので、引用しておきます。鯨=ゲイ、とすこしこじつけっぽいけれど、物語の冒頭で引用させてもらった2人は、確かに同じベッドで寝ているのです。
――親友(恋人?)のクィークェグを失い、「孤児」となった悲しみがイシュメールを鯨学に向かわせたのではなかったか。なぜかって鯨は親友(恋人?)の思い出に直結するからだ。そう思うと、いっけん退屈な鯨学の部分まで切なく感じる。ゲイ文学の傑作に認定したい。(斎藤美奈子『名作うしろ読み』中央公論新社)
(山本藤光:2011.02.18初稿、2014.10.11改稿)
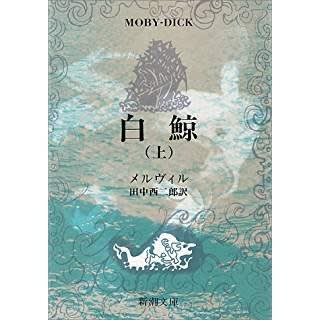
獰猛で狡知に長けた白鯨を追って、風雨、激浪の荒れ狂う海をピークォド号は進んだ。ホーン岬、インド洋、日本沖を経た長い航海の後、ついにエイハブは、太平洋の赤道付近で目ざす仇敵をみつけた。熱火の呪詛とともに、渾身の憎悪をこめた銛は飛んだ……。作者の実体験と文献の知識を総動員して、鯨の生態と捕鯨の実態をないまぜながら、エイハブの運命的悲劇を描いた一大叙事詩。(新潮文庫下巻の内容案内)
◎著者の気まぐれを受け入れる
『白鯨』は著者メルヴィル自身の、捕鯨船体験をもとに書かれました。メルヴィルは1841年に捕鯨船アクシュネット号に乗りこみます。それからの波乱万丈のできごとについて、書かれた本があります。紹介させてもらいます。なにやらこちらのほうが、おもしろい小説になりそうだと感じるのは、私だけでしょうか。
――当時、捕鯨船の労働条件は劣悪であった。そのことに嫌気が差したメルヴィルは、十八カ月後、船がマルキーズ諸島(南太平洋に浮かぶフランス領ポリネシア)に寄港したときに仲間とともに脱走する。ところが、その島には食人の習慣を持つ先住民がいて、彼らは「いつ自分たちが食われるか」と怯えながら過ごした。/一カ月後、偶然に寄港したオーストラリアの捕鯨船に乗って島を脱出したメルヴィルは、その捕鯨船内の暴動に巻きこまれ、タヒチ島で投獄されてしまう。その後脱走に成功したメルヴィルは近くの島に隠れ住み、やがてアメリカの捕鯨船に救われて一八四二年四月にハワイへ到着、ホノルルで店員などをした。(金森誠也・監修『世界の名作50選』PHP文庫)
『白鯨』は『モービー・ディック』というタイトルで、1951年に刊行されましたが、当時はまったく受け入れられませんでした。『白鯨』は長く、しかも鯨に関する論文のような文章が挿入されています。そのあたりについて、サマセット・モームの助言を紹介しておきます。
――わたくしがよんで退屈におぼえた章も、いくらかある。たとえば、図書館でくそ勉強をしておぼえこんだような、古物に関する知識だけからなる章とか、鯨の博物学をとりあつかった章とかがそれである。だが、メルヴィルがその深遠で玄妙な知識をひじょうに重んじていたことは明らかである。あなたは偉大なる才能をもつ作家の気まぐれな考えをそのままうけいれねばなるまい。(W.S.モーム『世界文学読書案内』岩波文庫、P135より)
『白鯨』は、10人を超える人が翻訳をしています。私が手にしたのはたまたま新潮文庫(田中西二郎訳)でしたが、意図したものではありません。山村修はその著書『書評家<狐>の読書遺産』(文春新書)のなかで、岩波文庫の八木敏雄訳を高く評価しています。山村修(推薦作『遅読のすすめ』ちくま文庫)は「狐」の名義で、ニュートラルな書評を数多く発信し、2006年に肺がんのために亡くなっています。
『白鯨』には、難解な記述が数多くあります。それゆえ翻訳の波長が、自分のリズムと合うか否かを確認することをお薦めします。
最近では2013年に、丸山健二『白鯨物語』(眞人堂)が出版されています。私の大好きな作家で、個人的には評価しています。ただしあまり流通されていません。丸山健二については別途、『夏の流れ』(講談社文芸文庫)を紹介させてもらいます。
翻訳のちがいを冒頭部分で検証しておきます。まずは新潮文庫(田中西二郎訳)から引用します。
――まかりいでたのはイシュメールと申す風来坊だ。もう何年前になるか――正確な年数などどうでもよかろう――懐中は文なし同然、陸地ではこれというおもしろいこともないので、しばらく船に乗って、水の世界を見て来ようと思った。わたしにとっては、それが憂鬱を追い払って、血行を良くする方法だったのだ。(本文P39)
河島弘美は『動物で読むアメリカ文学案内』(岩波ジュニア新書)で、原文の英語の下にみずからの翻訳文を書いています。
――わたしをイシュメイルと呼んでくれ。何年か前のこと――正確に何年かはどうでもよいのだが――財布の中身が底をつき、陸には興味をひかれるものもなかったので、船に乗って水の世界を見てこようと思った。それが凶暴性をなだめ、血行をよくするわたしのやり方だった。(河島弘美『動物で読むアメリカ文学案内』岩波ジュニア新書)
もうひとつならべてみます。
――人の名前なんぞというものにおよそどれほどの価値があるのかは知らないが、/若くしてとんでもない運命に遭遇し、/その渦に完全に巻きこまれてしまった、/極めて特異な体験の語り部として登場するおれのことは、/とりあえずイシュメールとでも名乗っておくことにしよう。(丸山健二『白鯨物語』眞人堂)
私は「水の世界」とか「血行をよくする」などの表現に、違和感をもっていました。翻訳が流れておらず、直訳っぽい場違いな単語が気になっていました。それを丸山健二はすべて削いで、みごとな滑り出しを描いてみせてくれました。
ほかに『白鯨』の訳書として、講談社文芸文庫(千石英世訳)と岩波文庫(八木敏雄訳)などがあります。読んでいませんが。
◎迫力満点の最終章
『白鯨』の語り手は、イシュメイルという無宿者です。鯨にかんする古今東西の文献の紹介や捕鯨にまつわる歴史なども、彼自身の言葉によって語られています。彼は捕鯨の街で、銛(もり)打ちのクィークェグと同宿します。2人は意気投合し、やがて片脚の船長・エイハブが陣頭指揮をする、捕鯨船・ピークォツド号に乗りこみます。この2人については最後に、笑ってしまった珍説(?)を紹介します。
船長・エイハブは、自身の片脚を奪った白鯨・モービー・ディックへの復讐を胸に、長い航海へと出発します。エイハブはマストにスペイン金貨をはりつけ、第一発見者にはそれを進呈すると宣言します。エイハブはあらゆる航海の常識を放棄し、ひたすら白鯨を追い求めつづけます。
エイハブには、人情のかけらもありません。荒れ狂う航海の安全にかんする、考慮すら欠けています。乗組員への配慮もありませんし、行き違うほかの捕鯨船への仲間意識も欠落しています。
エイハブ船長の怨念と、乗組員の諦念を乗せて、ピークォツド号は荒海を進みます。行けども行けども、白鯨・モービー・ディックは出現しません。乗組員たちの、寄港すべきだという主張は、とうに切り捨てられてしまっています。
『白鯨』は135章にもおよぶ長編です。しかし活劇が展開されるのは、最後の3章のみです。それまで読者は、たいくつな鯨学につきあわなければなりません。1度乗船したら降りることのできない海原ですので、しかたがありません。最終章(第135章)の迫力ある場面まで、読者は耐えて待たねばならないのです。
――突如、あたりの波が、ゆっくりと、広い円形にふくらんできた。それから、まるで水面下の氷山が急に浮き揚がるときのように、ふくらみは横すべりながら急激に高まった。低い地鳴りのような音が聞こえる。地底の鼻唄。次の瞬間、みな息を呑んだ。垂れる鯨索、銛と槍、それらを引きずりながら、巨大なるものが縦に――だが海面には斜めに跳り出たのだ。(下巻本文P513より)
私がこの文章を読むために、大学時代の階段教室での講義のような時間に耐えました。このあたりのことを、池澤夏樹はつぎのように語っています。
――真ん中の部分に何が書いてあるのか。ずうっと鯨の話です。鯨の種類、鯨という言葉の語源、鯨の生態、解剖学、捕る時の技術、その他種々、ありとあらゆる鯨学。それから捕鯨船の航海の詳細。いかなる人間が乗っていて、それぞれいかなるポジションについていて、どういう役割か。実際にいかにして鯨を見つけるのか。見つけたらどうやって追いかけて、捕まえて、母船まで運んで、最終的な処理をするか。そこから始まって、人類にとって鯨とは何かを哲学的に問う。具体的な応用例から、形而上学的な意味、旧約聖書に出てくる「ヨナの話」も出てきます。(池澤夏樹『世界文学を読みほどく』新潮選書より)
私には読みにくい作品でしたが、この作品を抜きにして「山本藤光の文庫で読む500+α」は完結しません。そんな思いで、学生時代に挫折した本書を、みごとに読破しました。退屈な部分はどんどん飛ばして読むと、分厚い上下巻はあっという間に読み終えることができます。念のため。
◎『白鯨』に寄せられたあれこれ
宮川雅は「『白鯨』はさまざまなレベルで読めるテキストである」として、つぎのように整理してくれています。
1. 十九世紀捕鯨業のルポルタージュ
2. 海洋冒険小説
3. シェクスピア的ないし神話的悲劇
4. 聖書のパロディ
5. 神や悪魔や認識の問題を巡る思想小説
6. フリーメーソンの象徴が解読され、エイハブと神の関係にグノーシス主義の思想
7. フランス批評家による図像学的・数秘学的解読
8. 男根冗句
(『世界文学101物語』高橋康也・編、新書館)
岩波文庫の『白鯨』(上中下巻、八木敏雄訳)は、11番目の邦訳だそうです。「狐」こと山村修は、訳注の豊かさに着目しています。特に「聖書」との関連については新鮮さを感じています。
――八木訳の特色をなすのは、その訳注のゆたかさだ。この小説は、語り手のイシュメールや船長のエイハブなど人名の借用をはじめ、いたるところい聖書本文の引用・暗示・パロディなどが織りこまれている。それが訳注で巨細にわたってしめされるばかりではない。訳文にも聖書読解にもとづく独特の工夫がこらされ、ときにはハッとさせられる。(山村修『書評家<狐>の読書遺産』文春新書)
もうひとつ、メルヴィルが他の作家から受けた影響について紹介させていただく。
――メルヴィルはホーソンを規範として、シェイクスピア悲劇の影響のもとに捕鯨の物語を書きなおした。そして、エイハブ船長は運命と悪に挑戦し、ついにはみずからを滅ぼすにいたるが、決して敗北はしないアメリカ的な英雄となる。(明快案内シリーズ:『アメリカ文学』自由国民社)
ホーソンは『緋文字』(新潮文庫)、シェイクスピアは『マクベス』(新潮文庫)を別途紹介させていただきます。最後は斎藤美奈子が笑わせてくれたので、引用しておきます。鯨=ゲイ、とすこしこじつけっぽいけれど、物語の冒頭で引用させてもらった2人は、確かに同じベッドで寝ているのです。
――親友(恋人?)のクィークェグを失い、「孤児」となった悲しみがイシュメールを鯨学に向かわせたのではなかったか。なぜかって鯨は親友(恋人?)の思い出に直結するからだ。そう思うと、いっけん退屈な鯨学の部分まで切なく感じる。ゲイ文学の傑作に認定したい。(斎藤美奈子『名作うしろ読み』中央公論新社)
(山本藤光:2011.02.18初稿、2014.10.11改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます