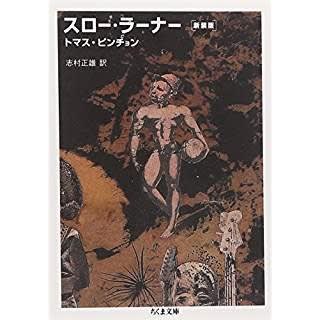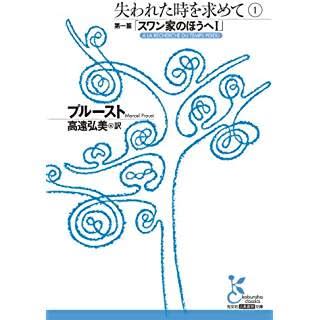バーネット『小公女』(新潮文庫、畔柳和代訳)
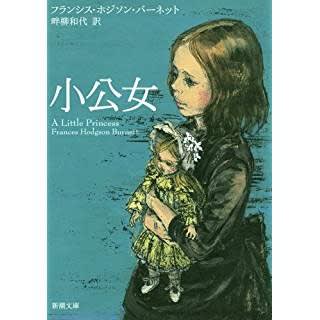
暗い冬の日、ひとりの少女が父親と霧の立ちこめるロンドンの寄宿制女学校にたどり着いた。少女セーラは最愛の父親と離れることを悲しむが、校長のミス・ミンチンは裕福な子女の入学を手放しで喜ぶ。ある日、父親が全財産を失い亡くなったという知らせが入る。孤児となったセーラは、召使いとしてこき使われるようになるが…。苦境に負けない少女を描く永遠の名作、待望の新訳! (「BOOK」データベースより)
◎V字回復のものがたり
バーネット『小公女』は、若いころに新潮文庫(伊藤整訳)で読んでいます。その後、青空文庫(菊池寛訳)でも読みました。今回新潮文庫から新訳(畔柳和代訳)が出たので、また読んでみました。
私はV字タイプのストーリーが好きなようです。頂点にいた主人公がどん底まで落ちて、ふたたび頂点をきわめる。ちょうど「V字回復」の構造になっている小説の、代表格が『小公女』だと思います。ちなみにバーネット『小公子』(新潮文庫、中村能三訳)は「ルート(√)型」の小説で、どん底から高みにのぼりつめる出世型の小説です。文藝春秋編『少年少女小説ベスト100』(文春文庫ビジュアル版1995年)では、『小公女』が45位、『小公子』が5位です。やはり「√型」のほうが人気があるようです。
『小公子』について少しだけ紹介させていただきます。
――祖父のイギリス貴族にひきとられたアメリカ生まれの少年が、その純真さで祖父の愛を得る善意の物語。(「新潮世界文学小辞典」より)
『小公女』の主人公セーラ・クルウは、インドに住む7歳の少女です。母親はセーラを産んですぐに亡くなり、彼女は父親の手で育てられました。セーラの父・クルウ大尉は、実業家で大金もちです。セーラはロンドンの、女子学院寄宿舎にあずけられることになりました。学院はミンチン女史が経営しています。セーラは特別室をあてがわれ、優遇されます。セーラはプリンセスと呼ばれます。
ところが父親のクルウ大尉は、事業に失敗して死んでしまいます。一文なしになったセーラに、ミンチン女史は冷酷なさたをくだします。部屋は屋根裏へ移され、下働きを命じたのです。行き場のないセーラは、黙々と働きました。食事も満足にあたえられず、こきつかわれつづけます。セーラと同様の境遇で小間使いをしている、同年代のベッキイに心をよせます。
ある日セーラは、道で銀貨を拾います。空腹だったので、それで甘パンを4個買うことにします。パン屋の女主人はセーラのみすぼらしい身なりをみて、2個おまけをしてくれます。しかしセーラは1個だけを残して、甘パンを乞食の女の子にわけあたえます。ひもじい思いを、特別のまじない(……のつもり)でいやします。セーラは身なりこそ貧そうですが、慈愛の心や気品は失いません。
お姫さまから一転、下働きとなったセーラのその後についてはあえてふれません。V字回復がどんな状況でおきるのか。苛め抜いたミンチン女史は、そのときどう豹変するのか。屋根裏部屋の隣人、小間使いのベッキイと乞食の女の子はどうなるのか。ぜひご確認ください。
青空文庫の『小公女』には、訳者の菊池寛の「はしがき(父兄へ)」があります。『小公子』との関係についてふれていますので、引用させてもらいます。
――『小公子』は、貧乏な少年が、一躍イギリスの貴族の子になるのにひきかえて、この『小公女』は、金持の少女が、ふいに無一文の孤児になることを書いています。しかし、強い正しい心を持っている少年少女は、どんな境遇にいても、敢然としてその正しさをまげない、ということを、バーネット女史は両面から書いて見せたに過ぎないのです。(青空文庫、菊池寛「はしがき(父兄へ)」より)
◎大人向けに訳された『小公女』
フランシス・ホジソン・バーネット作品は、『小公子』『小公女』(ともに新潮文庫)『秘密の花園』(光文社古典新訳文庫)という順序で読みました。白髪の爺(私のこと)とバーネット作品は、あまりにも不似合なのは重々承知していました。しかしバーネット作品を「山本藤光の文庫で読む500+α」の推薦作から除外することはできません。迷ったあげく『小公女』を選ぶことにしました。
孫は小学校低学年3人(男児2、女児1)と幼稚園児1人(女児1)です。彼らに読んで聞かせるとしたら、3作品のうちどれがいいだろうか。選択基準は完全に爺の立場ででした。お姫さまがどん底まで落ちる場面を、孫たちはどんなふうに受けとめるのでしょうか。そしてふたたびお姫さまにもどる場面に、どんな反応をしめすのでしょうか。
すでに『リトルプリンセス-小公女 新装版』(講談社青い鳥文庫、 藤田香・イラスト、曾野綾子訳)を買い求めてあります。おそらく来年になれば、書棚から選んでくれるだろうと期待しています。
新潮文庫(新訳版)の訳者である畔柳和代(くろやなぎ・かずよ)は「あとがき」で、大人も楽しめる翻訳を心がけたと書いています。そのとおりで、新訳はこども向けの表現を一掃しています。まず主人公の名前が、サアラ(伊藤整訳)からセーラにかわっています。このほうがずっと現代的だと思います。カバー挿画もSUITAから酒井駒子にかわり、華やいだものが消えています。
またせりふまわしが、大きくちがっています。ミンチン女史が孤児になったセーラに、新たな立場を伝える場面を比較してみます。
――「もったいぶったようすはやめてちょうだい。そんなようすをさせるわけは、なくなったのだから。もう公女さまなんかじゃないのだよ。馬車や小馬はよそへやってしまうし、女中にはひまをやる。いちばん古いいちばん汚い着物を着るのだよ――もうあんなぜいたくな着物なんかは、にあわないからね。ベッキイと同じだよ――自分の食べるだけの働きをしないといけないのだよ。」(新潮文庫、伊藤整訳、P132より)
――偉そうにするんじゃありません。もうそんな態度はとれないんだから。もうプリンセスじゃない。馬車もポニーもよそへやられる――女中はクビになる。一番古くて地味な服を着るんです――あの上等な服を着られる立場じゃないから、ベッキーのようなもんです。――働いて食い扶持を稼ぐんです」(新潮文庫、畔柳和代P119より)
ついでに菊池寛訳(青空文庫)もご紹介させていただきます。
――勿体ぶった様子なんかおしでないよ、もう、お前は宮様じゃアないのだからね。お前は、もう、ベッキイと同じことさ。自分で働いて、自分の口すぎをしなければならないのだよ。」(青空文庫、菊池寛訳より)
私は新訳にふれて、岩波少年文庫を読んでいるようなイメージを払しょくしました。訳者がいうように新訳『小公女』は、りっぱな大人向けの作品に変身していました。実は角川文庫から川端康成訳『小公女』が出ています。アマゾンでは3千円以上もしています。古書店で探しているのですが、いまだにゲットしていません。菊池寛、川端康成、伊藤整と大物が翻訳を手がけるほど、『小公女』は魅力的な作品なのです。
最後に重兼芳子からのメッセージを、引用させていただきます。
――父親の援助もなく、たった一人でこの世にほうり出されたセーラに対し、卑しい大人たちの手を変え品を変えてのいじめがはじまる。少女の運命を手中に収めたミンチン先生はじめ、同級生たちのいじめのいやらしさ。現代の学校で流行している陰湿ないじめ、いじめる方にもいじめられる方にも、『小公女』をじっくりと読んでもらいたい。(重兼芳子、朝日新聞学芸部編『読みなおす一冊』朝日選書より)
(山本藤光:2013.12.23初稿、2018.03.02改稿)
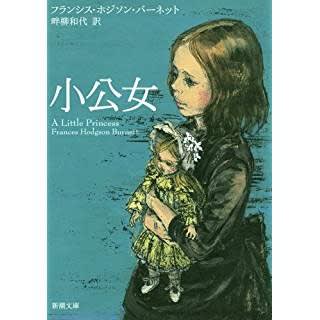
暗い冬の日、ひとりの少女が父親と霧の立ちこめるロンドンの寄宿制女学校にたどり着いた。少女セーラは最愛の父親と離れることを悲しむが、校長のミス・ミンチンは裕福な子女の入学を手放しで喜ぶ。ある日、父親が全財産を失い亡くなったという知らせが入る。孤児となったセーラは、召使いとしてこき使われるようになるが…。苦境に負けない少女を描く永遠の名作、待望の新訳! (「BOOK」データベースより)
◎V字回復のものがたり
バーネット『小公女』は、若いころに新潮文庫(伊藤整訳)で読んでいます。その後、青空文庫(菊池寛訳)でも読みました。今回新潮文庫から新訳(畔柳和代訳)が出たので、また読んでみました。
私はV字タイプのストーリーが好きなようです。頂点にいた主人公がどん底まで落ちて、ふたたび頂点をきわめる。ちょうど「V字回復」の構造になっている小説の、代表格が『小公女』だと思います。ちなみにバーネット『小公子』(新潮文庫、中村能三訳)は「ルート(√)型」の小説で、どん底から高みにのぼりつめる出世型の小説です。文藝春秋編『少年少女小説ベスト100』(文春文庫ビジュアル版1995年)では、『小公女』が45位、『小公子』が5位です。やはり「√型」のほうが人気があるようです。
『小公子』について少しだけ紹介させていただきます。
――祖父のイギリス貴族にひきとられたアメリカ生まれの少年が、その純真さで祖父の愛を得る善意の物語。(「新潮世界文学小辞典」より)
『小公女』の主人公セーラ・クルウは、インドに住む7歳の少女です。母親はセーラを産んですぐに亡くなり、彼女は父親の手で育てられました。セーラの父・クルウ大尉は、実業家で大金もちです。セーラはロンドンの、女子学院寄宿舎にあずけられることになりました。学院はミンチン女史が経営しています。セーラは特別室をあてがわれ、優遇されます。セーラはプリンセスと呼ばれます。
ところが父親のクルウ大尉は、事業に失敗して死んでしまいます。一文なしになったセーラに、ミンチン女史は冷酷なさたをくだします。部屋は屋根裏へ移され、下働きを命じたのです。行き場のないセーラは、黙々と働きました。食事も満足にあたえられず、こきつかわれつづけます。セーラと同様の境遇で小間使いをしている、同年代のベッキイに心をよせます。
ある日セーラは、道で銀貨を拾います。空腹だったので、それで甘パンを4個買うことにします。パン屋の女主人はセーラのみすぼらしい身なりをみて、2個おまけをしてくれます。しかしセーラは1個だけを残して、甘パンを乞食の女の子にわけあたえます。ひもじい思いを、特別のまじない(……のつもり)でいやします。セーラは身なりこそ貧そうですが、慈愛の心や気品は失いません。
お姫さまから一転、下働きとなったセーラのその後についてはあえてふれません。V字回復がどんな状況でおきるのか。苛め抜いたミンチン女史は、そのときどう豹変するのか。屋根裏部屋の隣人、小間使いのベッキイと乞食の女の子はどうなるのか。ぜひご確認ください。
青空文庫の『小公女』には、訳者の菊池寛の「はしがき(父兄へ)」があります。『小公子』との関係についてふれていますので、引用させてもらいます。
――『小公子』は、貧乏な少年が、一躍イギリスの貴族の子になるのにひきかえて、この『小公女』は、金持の少女が、ふいに無一文の孤児になることを書いています。しかし、強い正しい心を持っている少年少女は、どんな境遇にいても、敢然としてその正しさをまげない、ということを、バーネット女史は両面から書いて見せたに過ぎないのです。(青空文庫、菊池寛「はしがき(父兄へ)」より)
◎大人向けに訳された『小公女』
フランシス・ホジソン・バーネット作品は、『小公子』『小公女』(ともに新潮文庫)『秘密の花園』(光文社古典新訳文庫)という順序で読みました。白髪の爺(私のこと)とバーネット作品は、あまりにも不似合なのは重々承知していました。しかしバーネット作品を「山本藤光の文庫で読む500+α」の推薦作から除外することはできません。迷ったあげく『小公女』を選ぶことにしました。
孫は小学校低学年3人(男児2、女児1)と幼稚園児1人(女児1)です。彼らに読んで聞かせるとしたら、3作品のうちどれがいいだろうか。選択基準は完全に爺の立場ででした。お姫さまがどん底まで落ちる場面を、孫たちはどんなふうに受けとめるのでしょうか。そしてふたたびお姫さまにもどる場面に、どんな反応をしめすのでしょうか。
すでに『リトルプリンセス-小公女 新装版』(講談社青い鳥文庫、 藤田香・イラスト、曾野綾子訳)を買い求めてあります。おそらく来年になれば、書棚から選んでくれるだろうと期待しています。
新潮文庫(新訳版)の訳者である畔柳和代(くろやなぎ・かずよ)は「あとがき」で、大人も楽しめる翻訳を心がけたと書いています。そのとおりで、新訳はこども向けの表現を一掃しています。まず主人公の名前が、サアラ(伊藤整訳)からセーラにかわっています。このほうがずっと現代的だと思います。カバー挿画もSUITAから酒井駒子にかわり、華やいだものが消えています。
またせりふまわしが、大きくちがっています。ミンチン女史が孤児になったセーラに、新たな立場を伝える場面を比較してみます。
――「もったいぶったようすはやめてちょうだい。そんなようすをさせるわけは、なくなったのだから。もう公女さまなんかじゃないのだよ。馬車や小馬はよそへやってしまうし、女中にはひまをやる。いちばん古いいちばん汚い着物を着るのだよ――もうあんなぜいたくな着物なんかは、にあわないからね。ベッキイと同じだよ――自分の食べるだけの働きをしないといけないのだよ。」(新潮文庫、伊藤整訳、P132より)
――偉そうにするんじゃありません。もうそんな態度はとれないんだから。もうプリンセスじゃない。馬車もポニーもよそへやられる――女中はクビになる。一番古くて地味な服を着るんです――あの上等な服を着られる立場じゃないから、ベッキーのようなもんです。――働いて食い扶持を稼ぐんです」(新潮文庫、畔柳和代P119より)
ついでに菊池寛訳(青空文庫)もご紹介させていただきます。
――勿体ぶった様子なんかおしでないよ、もう、お前は宮様じゃアないのだからね。お前は、もう、ベッキイと同じことさ。自分で働いて、自分の口すぎをしなければならないのだよ。」(青空文庫、菊池寛訳より)
私は新訳にふれて、岩波少年文庫を読んでいるようなイメージを払しょくしました。訳者がいうように新訳『小公女』は、りっぱな大人向けの作品に変身していました。実は角川文庫から川端康成訳『小公女』が出ています。アマゾンでは3千円以上もしています。古書店で探しているのですが、いまだにゲットしていません。菊池寛、川端康成、伊藤整と大物が翻訳を手がけるほど、『小公女』は魅力的な作品なのです。
最後に重兼芳子からのメッセージを、引用させていただきます。
――父親の援助もなく、たった一人でこの世にほうり出されたセーラに対し、卑しい大人たちの手を変え品を変えてのいじめがはじまる。少女の運命を手中に収めたミンチン先生はじめ、同級生たちのいじめのいやらしさ。現代の学校で流行している陰湿ないじめ、いじめる方にもいじめられる方にも、『小公女』をじっくりと読んでもらいたい。(重兼芳子、朝日新聞学芸部編『読みなおす一冊』朝日選書より)
(山本藤光:2013.12.23初稿、2018.03.02改稿)