
楽しい音楽の時間デス・・・
東京新聞の日曜版に、ドラマ『のだめカンタービレ』で主人公の千秋真一を熱演している玉木宏さんのインタビューが掲載されていました。「クラシックに夢中」と題字された記事を読んでみると・・・
玉木さんは、このドラマに出演するまではクラシックとは縁遠い生活でしたが、撮影に入ってからはすっかり夢中になってしまい、今ではポップスを全く聴かなくなるほどクラシックに愛情を感じるようになったそうです。玉木さんの中にいた千秋が目を覚ましたのか、千秋を演じている間に音楽心が触発されたのか・・・
楽器の経験が全くなかったので、プロの演奏家の下で猛練習を重ねました。「たとえ演奏できなくても、手の位置、弾き方などは、しっかりやっておきたかった」という言葉から、福士さんと同じ役者魂を感じました。ピアノへの憧れが強いので、今回の役が終わったら、どこかで基本から「穴埋め」したい、ときっぱり言う玉木さん、どうやら半分ぐらい千秋の血が入ってしまったようですね。ちなみに、①幸せを感じるときは→「焼肉を食べているとき」 ②俳優になっていなかったら→「今となっては考えられない」 ③無人島にひとつだけ持っていくなら→「女性。子孫は残していかなければ」
ベートヴェンの『交響曲第7番イ長調作品92』は、千秋がシュトレーゼマンの代役で始めてタクトを振った思い出深い曲です。原作だと、その後Sオケの指揮者として演奏したナンバーは同じベートーヴェンでも『交響曲第3番〈英雄〉』に変更されましたが、留学前のR☆Sオケの公演で『7番』を演奏しているので、やはりこの曲が彼の「運命」の曲だと思います。トシ子は、オケの生演奏で(社会科実習&音楽学習)確か3、5、6番の第一楽章を聴いたことがありますが、『第九』以外のベートーヴェンの交響曲を持っておらず、『第七番』は、第二楽章しか知りませんでした。でも、改めて聴いてみると、第一楽章から非常に素晴らしく、この先、お気に入りの一曲になること間違いなしです!
お師匠さんに『第七番』のお勧めCDを教えてもらったのですが、銀座山野楽器に(のだめの着ぐるみが写真撮影禁止!の貼り紙付けて、ガラスケースに展示されていました。せこ~い)なかったので、何を買おうか考えました。『のだめオーケストラ LIVE!』CDの隣に置かれていたライブCDが、SACD/CDのマルチディスクなのに1550円と激安だったので、これを買うことにしました。それから、もう一つオマケに、ベートヴェンと同じ古楽器を使い、彼の指示通りに演奏されたCD(これも1300円と安い)を買いました。指揮者はノリントンという人でした。

(左)は、斬新なノリントン指揮/ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ(古楽器)
(右)は、クライバーの幻のライブ盤。こちらも走る走る回る回る情熱の嵐!
今日の『N響アワー』では、N響ファゴット主席演奏者の岡崎耕治さんをスタジオに迎え、実際にファゴットを演奏してもらったり、モーツァルトの『ファゴット協奏曲』などを聴いて、弦楽器だとチェロ&コントラバスに相当する楽器を魅力的に紹介していました。その後の芸術劇場では、何と、指揮者の金聖響さんが出演して、(トシ子はさっぱりわからなかったのですが)最近の傾向である「ピリオド奏法」についてレクチャーしてくれました。そして、「ピリオド奏法」の第一人者であるアーノンクールの指揮によるモーツァルトの『交響曲第39番、40番、41番』が、0時30分まで演奏されました。
動いたり、喋っている金聖響さんを見たのは初めてでした。
(これこれ、動物じゃないんだから、何という言い草するの!)
ひと目惚れです。格好いい人って、やはりいるんですね。千秋が少し丸顔になったら、こんな感じになるんじゃないかと、妄想しました(初登場で王子様ランキング1位?)。顔だけでなく、バリトンの声も魅力的で、「これは絶対に生演奏を聴きにいこう」と、心に誓いました。
金聖響さんも言ってましたが、ノリントンは「ピリオド奏法」側の人のようです。ヴィブラートをしないのが「ピリオド奏法」の特徴らしいのです。付け焼刃にもならない知識なので、間違っているかもしれませんが、当時の楽器を使って作曲者のスコアどおりに演奏することは、音の原理主義といってもいいでしょう。でも「ピリオド奏法」は、「当時と同じ音楽を再現すること」を目的としているわけではありません。なぜなら聴かせる相手は18世紀の人々ではなくて、現代の観客なのだから。金聖響さんは、「20世紀には20世紀のスタイルが、21世紀には21世紀のスタイルがあると思う」と言っていました。私は彼の言葉を聞いて、千秋がここにもいると思いました。金聖響さんの『7番』、聴いてみたいです。

のだめオケの『第7番』。1&4楽章だけでなく、通しで聴きたい!!
(ドラマ最終回エキストラ応募しました・・・)














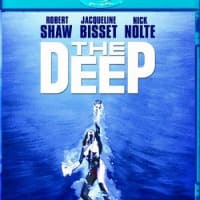





「金とく」ニュースを取り上げていただき有り難うございました。でも、情報源は下記の上海マダム、みか様のブログなんです。もうご存知かもしれませんが。
http://mikashanghai.blog76.fc2.com/
ここの情報の量と速さはすごいです。何しろ今現在洗足学園で進行中の「のだめカンタービレ」公開録画の実況中継まで入ってますから。私も今回のエキストラに応募したけど、迷っているうちに遅れを取ってしまい、何十回目にやっとFAXが送れたものの連絡無しでした。迷ったのは長丁場でキツそう、トイレもおやつも自由に出来ないらしいしーと弱気になったのと、舞台裏は見ない方が良いかなと思ったりして。でも、実況中継を読んだら、あーやっぱり行きたかった。
ところで、みか様のブログに「金とく」のオンエア外まで含めた詳細なレポートが載っていて、ぜひお勧めします。12月9日が待ちきれない方には特に。
私もベートーベン7番クライバー指揮ウィーンフィル1976年録音のを持ってます。これ聞くとぐわっと引き込まれてしまいますよね。
今日ののだめも楽しみです。
しかも今回はウイルス性胃腸炎という、ウイルス性の風邪で
3時間の点滴を2日も続けてするハメに・・(こんなの初めて)
いまだにまともにご飯も食べられず、ちょっとヘコみ気味
なんだけど、だいぶ良くなりつつあります。
私の住んでる地域で、今この風邪が大流行中なんだそうです。
ほんと・・ウイルスって恐い・・(私は母からもらいました)
そんな訳で、Toshiさんのところにもちょっと久しぶりに
やって来たんだけど、いろんな記事にとっても楽しませて
もらいました
コメントしたいところがいっぱいあったんだけど、
せっかくなので最新の記事に。(内容も私好みだしね・・笑)
芸術劇場、私も観てました♪
金聖響さん、男前でしたね。(いろんな意味で)
それに“聖なる響き”・・名前が素敵です。
私はまだあまり演奏を聴いたことがないので、これから
聴いてみようかなーと思ってます。
古楽器演奏(アーノンクールも)、私はここ1年くらいで
やっと聴き始めたところです。
やっぱりバロックや古典だと、“その当時響いていた音”
というのがどうしても聴いてみたくなるんですよね
のだめコミック、私は16巻までやっと読み終わりました。
記事を読んだ限りでは、Toshiさんも結構な勢いで買ってるみたい(笑)
福士くん、今日のオーボエ姿、様になってましたね。
個人的には「もじゃもじゃ組曲」が聴いてみたかったけど(笑)
24日のブログであった"紫のばらの人”で思い出しました!
”ガラスの仮面”・・・中学生の頃からリアルタイムで愛読していました。
新刊が出るのが待ち遠しいほどストーリーに引き込まれ、まやの天性とも言える演技にため息をつき、速水さんにドキドキしたり、まやとうまくいくといいのに・・・とハラハラしたり。
あれから何年経ったのでしょう?ドラマやアニメ、舞台・・・とあらゆる分野に進出したようですが、原作コミックはいまだに休載中で残念です
次の展開は・・・?月影先生は・・・?まやと速水さんは・・・?
トシ子さんのブログを見て思い出しただけでまた続きが読みくて仕方がないのは私だけかな~?
情報、ありがとうございました。みか様のブログにもいってまいりました。私のクライバーは82年の録音なので、76年度版も探してみようかなあ?
私が応募したのは『のだめ』CD付録の応募券です。まず当たりっこないと思いますが・・・
コミックはじっくり読んでいますが、1~16巻まで揃ってしまいました。あらあら・・・
金聖響さんには、本当に痺れました。良かった、kikiさんも見ていてくれて・・・
福士さんのオーボエ姿、良かったと思います。コミックを読んでしまうと、ここはこうしてほしいと勝手な願望が出てきてしまいます。『もじゃもじゃ組曲』も、その一つでした。聴きたかったなあ!
残念といえば残念ですが、終わってもらいたくない気もします。
北島マヤと速水真澄、「紫のバラの人」といえば、胸が切なくなります。『のだめ~』を16巻まで読み終わったら、『ガラスの仮面』を本棚の奥から引っ張り出そうかなあ?
ちょっと、仕事が一段落したので、お邪魔しに来ました。
以前書かせていただいたように、私は、幸運なことに聖響さんの指揮で『第九』を歌い、また、コンサートで『第九』を聴いたことがあります。
『N響アワー』は残念ながら見ていず、正直なところ『ピリオド奏法』についても、全然わからないのですが、とても、楽譜に忠実に演奏するように指示を出されていたことは、覚えています。
私が歌った中では、良い意味で一番「あっさりとした」演奏でした。
オーケストラの配置は、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを左右対称に置く配置(『対向配置』と呼ぶそうです)で、合唱のSp.の前に、コントラバスが配置されるので、低音が聞けて、とても歌いやすいのです。しっかりと支えてもらっているので、安心して上に飛べるという感じ。
その年は、指揮者はカッコイイし、結構調子も良かったので、私自身はとても満足したのですが…
その後、プロの合唱団との『第九』を聴いたとき、「流れるような心地よい演奏」に、金聖響さんにとっては、私達素人相手に「すごーく」大変だったろう…と実感して、落ち込んでしまいました。
今年も、落ち込むかも…
私も、聖響さんの『七番』聞きたいなあ…と思い出したのが、今年の2月5日、テレ朝系の音楽番組『題名のない音楽会21』の「指揮者のお仕事 裏側全部見せます リハーサル大公開」という企画で、下野竜也さん(往年の巨匠版)と金聖響さん(新進気鋭版)がリハーサル風景を公開するという番組が放送されたことです。ここで、使われた曲が、『ベートーヴェンの第7番の第1楽章』でした。
Toshiさんの記事を読むまで、すっかり忘れていて…
30分番組なので、ほんの少ししか聴くことはできなかったのですが、やはり、ヴィブラートを抑えているせいか、澄んだ響きでした。
いつか、コンサートホールで全曲聴きたいですね。
でもさすがに、しばらくはカゼ引かないっていう気がする。
この先1年分をまとめて引いたということにしておきます・・
ところで前にToshiさんが教えてくれた“さつまいも粥”
少し食べられるようになってきたので、今日作ってみました。
やさしい味で美味しかったです。どうもありがとう~
そうなんですよね。
原作を読んでしまうと、ここはこうして欲しかった、
なんていろいろと思ってしまう・・
玉木さんの千秋も素敵だとは思うんだけど、なんとなく
ちょっとキツすぎる気も・・
コミックだと千秋って、のだめに対するかんじが少しだけ
柔らかくなっていったり、ちょっと照れた感じも出てきたりして
そこが可愛いんだけどなー、なんて思ってしまったり・・
なんて言いつつ、結局は楽しんでるんだけど(笑)
そうそう、mamemo さんは聖響さんの指揮で!『第九』を歌ったことがあるんですよね。なるほど、楽譜に忠実に演奏するよう心がけていたのですね。ビブラートも抑えて・・・
聖響さんはピリオド奏法の第一人者ということですが、mamemo さんの文章を読んで、それがどういうものなのか、なんとなくわかってきたような気がします。バイオリンを左右に置くのはベートーヴェン時代の配置だそうですが、第1と第2の違いがよくわかり音の響きもいいので、聖響さんも採用しているのでしょうか? コントラバスの配置とか、役立つ情報と羨ましい経験を書いてくださり、ありがとうございました。
芋粥、実は私もウィルス性胃腸炎が少し良くなって、食事が取れるようになったときに食べたんですよ~
弱りきった胃腸に優しく、とてもおいしかったです。以来、体調に関わらず、ときどき食べるようになりました。
千秋の、のだめを見つめる眼差し、きついことはきついけど、若干優しくなったと思ったのですが、物語が進んでいくにつれて、変わっていくものだと期待しています!