
鹿島鉄道は、茨城県石岡市〈石岡〉駅と鉾田市〈鉾田〉駅間27.2kmの行程を計17の駅で結んだ非電化単線鉄道だ。一時間に一本運行されており、ローカル単線としては、かなり優秀だと思う。残念ながら今月31日をもって廃線となり、83年間続いた歴史に幕を下ろす。9両の気動車も、鉄道人生最後の日を迎える。
3月24日(土)
4時10分に目覚ましをかけたが、アラームを止めて横になってしまったのだろう。はっとして、目を開けると4時30分になっていた。5分で洗面&歯ブラシを済まし、国立駅へ向かった。さすがにまだ暗い。
ときたま利用することもある4時57分発の東京行きに乗り、次の西国分寺で武蔵野線に乗り換える。武蔵野線のホームは、5時6分の電車を待つ人々で結構賑わっていた。定刻どおり6分後に電車が到着した。
目が覚めたら、東川口駅に着くところだった。西国分寺から新小平、新秋津と地下を走っている間に、早くも眠りこんでしまったようだ。最初から眠るつもりだったので一向に構わないが・・・外はすっかり明るくなっていた。曇りとの予報だったが、まずまずの晴れである。
武蔵野線には10年以上前にそれも一度だけ、吉川まで乗ったことがあるが、このあたりの空の比率はその頃から殆ど変わっていないようだ。目障りな中高層建物が皆無で、実に気持ちが良い。宅地造成されたのか、見るからに人工的な感じに様変わりしている土地もあるが、この土色が住宅で埋まるとは到底信じられない。それほど広く、今のところは、平らな土地を一直線に走っている立派な農道以外何もない。赤信号を先頭に、十数台の車が数珠繋ぎに停まっていた。
6時2分に新松戸に着いた。6時8分の取手行き常磐線に乗り換える。なかなか連絡が良い。6時21分、我孫子に着く。ここで6時26分発高荻行き常磐線に乗り換える。10駅揺られて7時14分、石岡着。これが最も早く石岡に着くルートだが、インターネットの路線案内に従っただけだ。昔と違って、時刻表とにらめっこする必要がなくなったのは便利だが、ルートを考える楽しさと、そうして見つけたルートを計画したとおりに乗る楽しさも当然失われた。
石岡駅に着くや、「7時17分発の鹿島鉄道に乗られる方はお急ぎ下さい」という放送が流れた。自分と同じようにこの駅に降りた人々が、一斉に高架連絡橋を上り下りして、JR〈石岡〉駅の一番端にある鹿島鉄道〈石岡〉駅のホームに向かう。ホームは人でごった返していた。短時間では切符(殆どの人が1100円のフリー切符を購入)をさばき切れず、自分を含む半分近くが車内で切符を購入した。
後からわかったことだが、このとき乗った気動車は、主力車両として1889年と1992年に発注された16m級のKR-500形4両のうちの1両のKR-505だった。クリーム地に水色の帯が目印の505は、新撰組号と呼ばれていたらしい。

最初に乗ったKR-505。常陸小川駅で上りのキハ601を待つ。
実をいうと自分は、鉄道マニアの末席にも座ることすら出来ない身分である。何しろ、ディーゼルエンジンの気動車に乗ること自体が、今日を入れてわずか二回目という素人(電化される前の八高線に乗ったのが唯一の体験)だ。だから偉そうなことは何一つ喋れないのだけど、初めて電車に乗った子供のように、運転手の後ろに立って、前方を見つめた。

常陸小川駅で上り車両(キハ601)とすれ違い、離れていく駅を見送った。ここにはDD901形ディーゼル機関車が静態保存されている筈なのだが、見当たらない。後で調べたところ、何と、2月27日に解体されてしまったらしい・・・機関車がなければ、引込み線のレールと枕木も、見当たらない(写真の右側分岐)。廃線前なのに早々撤去するとは、なんで~

しばらく一直線の線路を行く。ここで最高スピードを出す。快感!

正面に霞ヶ浦が現れ、左に見える家を巻く感じで左へ曲がる。快感!
写真だと小さいが、実際は「ドーン」と、目の前に霞ヶ浦が現れる!

桃浦駅まで湖畔に沿って走る。綺麗~

一度湖と別れ、切りとおしを右に曲がって行く間に次駅の〈八木蒔〉がある。撮影ポイントが多いのだろう、鉄道写真家が大勢降りた。続く〈浜〉駅でも、鉄道が再び湖畔を走ることもあり、多くのカメラマンや乗客が下車する。


次の〈玉造町〉駅で、再び上り車両とすれ違う。鹿島鉄道の可愛らしいキャラクターシールを貼ったKR-501が来た。このあと、気動車は上り勾配にさしかかる。ディーゼルエンジンの音も高くなる。

右に左に熊笹をかきわけ、山道を登っていく。最後の直線を上り切ると、「よっこらしょ」と一息ついて、あとはリズミカルに平地へ下っていく。杉林を通り過ぎ、二駅後、巴川駅に着いた。鉄道模型でよく見かける曲線形のホームがいい感じ。この日の夕方、鉾田から石岡に向かったキハ714〈夕張〉が、ちょうどこの場所でエンコしてしまう・・・



8時14分。終点の鉾田駅に到着。まだ早い時間なので、駅構内の売店も、立ち食い蕎麦屋も鉾田名物の鯛焼き屋さんも、営業していない。8時31分発の同じ車両で石岡に折り返すことにした。


石岡~鉾田間を往復している間、ありとあらゆる場所に鉄道写真家が張りついていたが、この日の朝の往復では、沿道に住む地元の人々も、気動車が近づくと庭に出て、暖かい目線で車両を見送ってくれた。尻尾を振りながら気動車と平行して走り出した犬もいた。いつもこんな感じで散歩させているのかもしれない。4月1日以降、飼い主はどうするのか、少し気になった。
この日集まった人々を観察していたら、同じ鉄道マニアでも、どうやら二つのタイプがあることがわかった。まずは、鉄道写真家。半分近くの人は鉄道に乗らない。乗ってしまったら、走る姿を撮影することができないから。ここぞと思う位置に陣取り、一日中車両を待ち続けるタイプと、鉄道や車で次の撮影ポイントまでせわしなく移動するタイプに分かれる。いずれも、複数のカメラ&三脚&ビデオ機材を持ち歩く。
続いて、乗車派。彼らもカメラやビデオを持ち歩くが、記念撮影の延長線上ぐらいに考えているのか、第一のタイプのように1本何十万円もするレンズをぶら下げている者は少ない。コンパクトデジカメやケータイで済ます人もいる。彼らの場合、カメラよりビデオの方が重要なアイテムだろう。車窓風景を撮影したり、エンジン音や走行音を録音するため、ビデオカメラは必須のアイテムともいえる。
どちらのタイプも、オール男性。ごくたまに見かける女性は、皆地元の人かもしれない。鹿島鉄道は好きでも、根っからの鉄道好きではない。三往復もした私は、乗車派であることは間違いないが、やはり鉄道マニアとは違う、と自己分析した。

鹿島鉄道全17駅














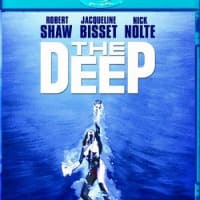





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます