
味のある奥多摩駅(旧駅名は「氷川」)の駅舎とアオガエル。
梅干しと梅大福をお土産に青梅梅郷を後にすると、(吉野街道から)青梅街道に戻って奥多摩駅へと向かいました。20分後に到着です。バイクの機動力には今更ながら感心したりして・・・。
写真の右端に、駅構内で停車中の車両が写っています。長年、オレンジ色の201系が和んでいたのですが、去年のダイヤ改正を境に、新型車両に置き換えられてしまいました。
ダイヤ改正といえば、3月14日の今日、東京発の最後のブルートレイン「富士&はやぶさ」が廃止になりました。思えば、2~3月に連休を取って「富士&はやぶさ」に乗って熊本へ行き、本物のアオガエル(熊本電鉄・東急5000系。唯一の現役アオガエル)にまた乗ってこようと目論んだのですが、うまくいかず(2月は仕事が忙しく、3月の連休は廃止後の月末)、その代わりに?バイクのアオガエルを買ってしまったのでした・・・。


(左)お昼にはやや早かったけれど(11時20分)、駅舎の二階にあるギャラリー&駅蕎麦屋さんで、鳥だしの暖かいめんつゆにつけて食べる「田舎せいろ」(500円。100円値上がりした?)をいただきました。ギャラリーはときどき変わるのでしょう。今回は、マンホール熱中人?による、東京都の各市町村の「マンホール写真」が展示されていました。ちなみに、国立は「三角駅舎と桜」。ニワトリさんも、ときどきマンホール写真を撮るけれど、自分の住んでいる国分寺市のマンホールの絵柄を問われると、実は知らなかったりして・・・。
(右)「奥多摩 山の恵みカレー」。第一弾が「鹿肉とわさび」、好評につき第二弾「あわび茸とわさび」が発売されました。肉の代わりにあわび茸を使った第二弾はカロリーも低く、女性の圧倒的支持を受けて第一弾以上のヒット商品になったそうです。一食400円。ニワトリさんも買ってみました(おいしかったら、後日レポートしますね)。


奥多摩駅から奥多摩湖(小河内ダム)に向かって走って行くと、架橋の下をくぐりました。トンネルも見えます(写真左)。ダム建設資材を運ぶために氷川駅(現・奥多摩駅)から水根まで敷かれた工事専用鉄道の跡です。このブログを始めた頃に「奥多摩むかし道」を歩きましたが、そのときも非常に気になりました。この高さだったら登れそうなので、ヘルメットをかぶったまま!よじ登ると・・・(右写真)。架橋に敷かれた木材は完全に腐っていて危険です。


どうやって橋を渡ったのかは問わないでください・・・(左写真)。工事専用線(東京都水道局小河内線)は、1952年に開通して1957年にその役目を終えました。観光線として利用する計画もあったけれど、放置されてしまいました。書類上は「廃止」ではなくて「休止」ですが、半世紀の間に木々に覆い尽くされてしまい・・・(右写真)。自然の力ってスゴイですね!

東京都民の水がめ=小河内ダム(奥多摩湖)。ニワトリさんも知らなかったのですが、ダム建設から完成に至るまで様々な出来事が起きています。
かつての東京市がダム建設候補地の調査を開始したのが1926(大正15)年。市西多摩郡小河内村が最終的に選ばれましたが、小河内村は絶対反対を表明します。「幾百万市民の生命を守り、帝都の御用水のための光栄ある犠牲である」と再三説得され泣く泣く応じると、利水をめぐって東京VS神奈川の紛争が勃発し、1936(昭和11)年にようやく工事着工にこぎつけたところ、1943(昭和18)年には太平洋戦争が激化したために工事中断、戦後1948(昭和23)年に工事再開、1957(昭和32)年に竣工しました。
ダム建設にあたり、小河内村と山梨県丹波山村及び小菅村の945世帯約6000人が移転を余儀なくされ、工事期間中に87名の人命が奪われました。これらの歴史は、奥多摩湖バス停&駐車場前の「奥多摩 水と緑のふれあい館」でも展示されています(「むかし道」を歩いたときも寄りました)。
土地を奪われたといえば、ツキノワグマもその一人かもしれません。湖畔の山々は昔からツキノワグマの生息地で、人がまれに襲われることもありますが、彼らの生活圏にニンゲンが入っていることを忘れずに・・・。

(左)この時期はいつもこんな感じなのでしょうか? 水量がかなり少ない気が・・・。
(右)湖畔に梅が咲いていました。ダムができる前からここにあったのでしょうか?

奥多摩湖には、峰谷橋(赤)、深山橋(クリーム)、三頭橋(青)と、魅力的な橋が架かっています(湖水に浮かぶ二本の浮橋=ドラム缶橋も魅力的!)。車が殆ど通らなかったので、深山橋の路肩に止めて記念撮影! いいアーチだなあ~♪


(左)奥多摩側と五日市(檜原村)を結ぶ全長19.7kmの奥多摩周遊道路の標高933mにある月夜見展望台(周遊道路は、最高地点1146m、標高差602mのワインディングロード)。夜間は通行禁止なので「月見」はできません。奥多摩有料道路(バイクブームの去った1990年に無料化された)時代の80年代は、峠を走るローリング族のメッカで、頻繁に事故が起きていました。「救急車が到着するまで約2時間かかります」という看板が、料金所や駐車場にかけられていましたが、殆ど効果がなかったみたいです(かく言うニワトリさんも、その昔、有料道路手前で転倒&骨折しました・・・)。「夜間、バイクのヘッドライトと排気音が聞こえてきたら振り向いてはいけない。オートバイには車輪がなく、乗っているのは首なしライダーだから」という噂も、まことしやかに喧伝されていました。
(右)先ほど立っていた湖畔(写真の左上端)を見下ろすと、やはり保水量がかなり減っている感じ・・・。 題名、前回の「ぐるっと」は打ち間違いで、今回の「ぶるっと」が正しかったのです。バイクの排気音「ぶるるっ」と、寒さに震える「ぶるるっ」をひっかけたつもりでした・・・
題名、前回の「ぐるっと」は打ち間違いで、今回の「ぶるっと」が正しかったのです。バイクの排気音「ぶるるっ」と、寒さに震える「ぶるるっ」をひっかけたつもりでした・・・














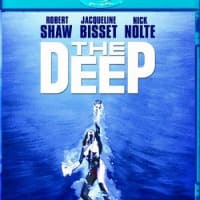





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます