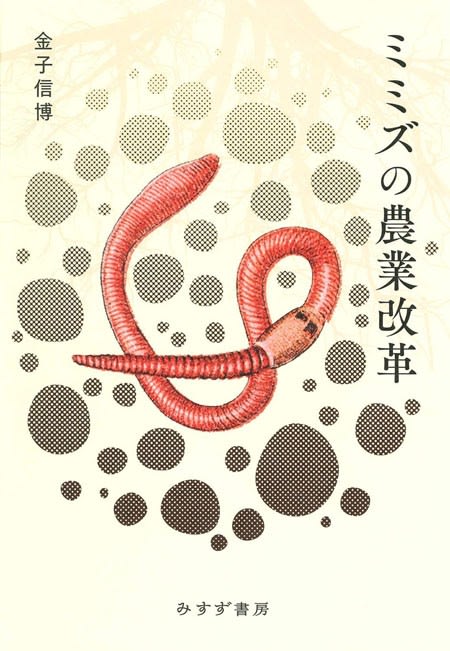
「文藝春秋」誌3月特別号「著者は語る」からの転載です。
「ミミズの農業改革」 金子信博(のぶひろ)
「ミミズのつもりになって土に潜ってみよう。土は、どんなところだろう」
表紙いっぱいに描かれたミミズが目を引く本書で、著者金子信博さんは戸惑う読者を土中へと誘う。
足元に広がるその世界は、生物の進化とともに数億年かけて地球上に形成された複雑な構造物。微生物から植物、動物まで多様な生物が相互作用し合うワンダーランドだ。
「子どもの頃から動物も植物も大好きでしたが、土壌生物の研究者になるとは思っていませんでした。クマやサルの研究に憧れて京大の研究室に入ったはずが、もの好きな性格からか、いつしか土中のダニや窒素濃度を分析していたのです。」
いざ、土に潜って驚いたのは、その多様性と多機能性だった。
例えば、土壌生物の代表格であるミミズは、毎日人知れず大量の落葉と土を食べて体内で粉砕し、排泄する。
糞の中では微生物の働きが活性化され、生成された窒素はやがて植物の根から養分として吸収される。団粒構造になっている糞は保水性と排水性を併せ持ち、風雨による土壌の流出を防いでいます。
人の手が加えられていない土壌の非の打ち所のないエコシステム。
一方、農薬や除草剤を使い特定の植物の生長のみを目的とする農地は、多様性が極端に低く安定性を欠く。環境に優しいはずの有機農業も例外ではない。
「問い直されるのは『土は耕すほど豊かになる』という常識です。
実はミミズにとっては"耕す"という行為自体が蛮行といえる。鍬やトラクターで体を切断されるか、地表に放り出され鳥や昆虫のエサとなる。驚いたことに、一度耕した土にはなかなかミミズが寄り付かず、生態系は壊れ、耕すほど貧しくなるのです。」
土壌生態学者として欧米の研究者らと推進するのが、土本来の機能を取り戻す「環境再生型(ジェネラティブ)有機農業」だ。環境破壊や食糧自給の観点からいまや世界的潮流となっている。
「二十年程前、弘前市で自然栽培を実践する木村秋則さんの『奇跡のりんご』が話題になった時、残念なことに農水省の調査では『例外』と結論づけられました。
だけど、実際に土を調査すると多様性が極めて高かった。現実に起きていることを奇跡や例外と片付けず、説明し、再現性を高めていく科学者の役割が、これからもっと重要になると感じています。」
今年六十五歳。定年退職後は実践を通じた土の再生に取り組む。
「生きものを育てるのは楽しいこと」と笑う金子さんの科学を支えるのは、生態系への揺ぎない愛着だった。















その他の著作。
木村秋則さんの実践。
わたくしも、自然からの恩恵と心得化学肥料や農薬は使いませんわ。
ミミズは、土を堆肥に換えてくれます。
我が家の枇杷の美味しさは、天からの贈り物。
貴姉は、実践的にご存知なのですね。
小生は、頭ではわかっているつもりですが、
ここまでしっかり理解していませんでした。
まずは、本書を購入するなり、借りるなりして熟読して
みたいと思います。