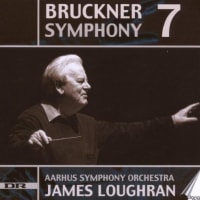大野和士芸術監督がプログラム編成の柱の一つに掲げるダブルビルの第一弾、ツェムリンスキーの「フィレンツェの悲劇」とプッチーニの「ジャンニ・スキッキ」が初日を迎えたが、残念ながら、公演は低調だった。
「フィレンツェの悲劇」ではシモーネ役が圧倒的な存在感を誇るが、同役を歌うベテランのセルゲイ・レイフェルクスは、新国立劇場のFacebookによると、本作のリハーサル中に73歳の誕生日を迎えたそうだ。73歳‥。一抹の不安がよぎった。
幕が開くと、案じた通り、声に凄みがない。かつてのドスの効いた声ではない。舞台姿に衰えはないが、アクの強さというか、押しの強さというか、そんなオーラが薄れたように感じる。ドラマの進展とともに、存在感が増していったので、最初はペースを抑え気味だったのだろうが、それにしても、粘りつくような嫌らしさはあまりなく、最後の決闘の場面でも不気味な威圧感はなかった。
レイフェルクスといえども、年齢からくる変化は避けがたいのだろう。それは(肉体的・精神的な)自然な変化なので、良いとか悪いとかという話ではないのだが、そろそろシモーネという役は卒業ではないだろうか。
他の2人の歌手(いうまでもないが、本作はシモーネを含めた3人の歌手からなる)と演出、美術、衣装、照明に関しては、とくにいうべきことはなかった――それも寂しいが。
一方、「ジャンニ・スキッキ」は、タイトルロールのカルロス・アルバレスが、現役バリバリの活きのよさで気を吐いた。オペラはやっぱり歌手だな、と思った。タイトルロール以外はすべて日本人の歌手で固めたが、その中ではリヌッチョを歌った村上敏明が、張りのある声と切れのよい歌いまわしで、舞台に活気をもたらした。ラウレッタを歌った砂川涼子もよかったが、本領発揮には至らなかった。
だが、「ジャンニ・スキッキ」も、わたしにはつまらなかった。1950年代に設定したという粟國淳の演出その他(美術、衣装、照明)が学芸会的に見えた。大人のオペラではなかった。日本人が制作すると、どうしてこうなるのだろうと、わたしは一般論で考えたくなった。子どもっぽい甘えのあるオペラ。それを楽しむ層もいるだろう。でも、現実社会との接点は、そこには見出せない。言い換えると、今なぜこのオペラをやるのか、という視点が弱い。
沼尻竜典指揮の東京フィルの演奏は、両作品とも場面ごとの意味を的確に捉え、綿密に表現していた。
(2019.4.7.新国立劇場)
「フィレンツェの悲劇」ではシモーネ役が圧倒的な存在感を誇るが、同役を歌うベテランのセルゲイ・レイフェルクスは、新国立劇場のFacebookによると、本作のリハーサル中に73歳の誕生日を迎えたそうだ。73歳‥。一抹の不安がよぎった。
幕が開くと、案じた通り、声に凄みがない。かつてのドスの効いた声ではない。舞台姿に衰えはないが、アクの強さというか、押しの強さというか、そんなオーラが薄れたように感じる。ドラマの進展とともに、存在感が増していったので、最初はペースを抑え気味だったのだろうが、それにしても、粘りつくような嫌らしさはあまりなく、最後の決闘の場面でも不気味な威圧感はなかった。
レイフェルクスといえども、年齢からくる変化は避けがたいのだろう。それは(肉体的・精神的な)自然な変化なので、良いとか悪いとかという話ではないのだが、そろそろシモーネという役は卒業ではないだろうか。
他の2人の歌手(いうまでもないが、本作はシモーネを含めた3人の歌手からなる)と演出、美術、衣装、照明に関しては、とくにいうべきことはなかった――それも寂しいが。
一方、「ジャンニ・スキッキ」は、タイトルロールのカルロス・アルバレスが、現役バリバリの活きのよさで気を吐いた。オペラはやっぱり歌手だな、と思った。タイトルロール以外はすべて日本人の歌手で固めたが、その中ではリヌッチョを歌った村上敏明が、張りのある声と切れのよい歌いまわしで、舞台に活気をもたらした。ラウレッタを歌った砂川涼子もよかったが、本領発揮には至らなかった。
だが、「ジャンニ・スキッキ」も、わたしにはつまらなかった。1950年代に設定したという粟國淳の演出その他(美術、衣装、照明)が学芸会的に見えた。大人のオペラではなかった。日本人が制作すると、どうしてこうなるのだろうと、わたしは一般論で考えたくなった。子どもっぽい甘えのあるオペラ。それを楽しむ層もいるだろう。でも、現実社会との接点は、そこには見出せない。言い換えると、今なぜこのオペラをやるのか、という視点が弱い。
沼尻竜典指揮の東京フィルの演奏は、両作品とも場面ごとの意味を的確に捉え、綿密に表現していた。
(2019.4.7.新国立劇場)