常連読者の皆さんは如何お過ごしだろうか?
学生の皆さんは充実した夏休みを送っているだろうか?
今回は非常に当たり前のお話を真面目にしたい
今回は当ブログの名物キャラである『変態おじさん』は登場しないのだ
品格を維持したい
ところで皆さんのギターのコンディションは如何だろうか?
良い演奏には『良いメンテ』が不可欠なのだ
実はこの辺りが曖昧な人も少なくない
ギター歴数十年というベテランですら間違って理解している事も多い
「弾き易いからいいんじゃない?」
という結果オーライ的な発想もあるが・・・
実は適切なメンテを行うなだけでさらに弾き易く、音色も向上するのだ
何事においても自己流には限界がある
基本を踏まえた上での自己流であるべきなのだ
私はそう考えている
行きつけの楽器店に出入りするようになりそんな事意識するようになった
加えてネットに発信するようになりその意識が高まったのだ
「間違った情報を発信するのはダメでしょ?」
私には責任感と使命感があるのだ
ギターは環境の影響を受けやすい
理由は木材で作られているからなのだ
金属パーツは経年劣化は起こすが季節に影響されることは少ない
特にネックはシビアなのだ
そもそも聴力が強いギター弦と常に戦っているのだ
その状況は過酷を極める
概ね、ネックは年に二回ほど大きく動く
夏と冬なのだ
理由は『湿度変化』なのだ
エアコンなども影響しているのだ
湿度とネックの関係を整理しておきたい
夏場は蒸す
湿度が上がれば木材が湿度を含み膨張する
ネックは『逆反り』になる
同時にエアコンなどの冷気を受け、ネック内部のトラスロッド(金属棒)が縮む
これも逆反りの一端になっている
冬場はこの逆だと考えれば良いのだ
今回はすべてのギターのネックが一律に逆反ったのだ
良い事だと思う
メンテ側としては分かり易い

ストラトも反った

子象も反った・・

ギターには調整しなくてはならない部分が沢山ある
”調整しなくては鳴らない部分・・”
と言い換えることも出来る
弦高調整の前にネック調整なのだ

最近の私は弦を張ったまま調整してしまう

超高級ギターや異常なほどギターを大事にしている人はその都度弦を緩めた方が良い
たしかにロッドにかかる負担はないとはいえない
しかしながら、ロッドを回す範囲は短い
僅かなのだ
しかも動きが良いロッドはスムースなのだ
レスポールなどカバーの片側のネジを外すだけなのだ
むしろ、弦を張ったり、緩めたりする方が各部に負担がかかる
まぁ、消耗したパーツは交換すれば良いだけの話だが・・
ネック調整、ブリッジ&サドル調整という流れになる
現行は12フレットで2㎜!
これは厳守した方が幸せになれる
誰が決めたのか?
この状態が最高なのだ
この状態を基準に考えると調整がし易い
余談だが・・
ストラトマスターのChar氏はさらに高く設定しているという
あの生き生きとした音はテクに加え、高い弦高が貢献しているのだ
カッティングやピッキング時のアタック感が増す
私は一つの基準としてアルペジオの弾き易さを目安にしているのだ
張りがない弦は楽しくない
フレーズも浮かばない
アルペジオが気持ちいい状態からのカッティングなのだ
キレキレの音が飛び出す
ギターや弦に弾かされている感がある
むしろ、それは好ましい状態なのだ
キャリアが増せばどんな状態のギターでもそこそこ格好良く鳴らせる
ビギナーのギブソンよりも匠のコピーモデルなのだ
しかしながら、実際に弾いている匠はあまり気分が乗っていないという・・
伝わっているだろうか?
以前にも紹介したが・・
不要ピックを使った『弦高センサー』はお勧めなのだ

コストがかからない
メジャーで測るよりも繊細で正確なのだ
1.87と2.00の二枚なのだ
実際には隙間のセメダインの厚みもあると思うが・・
概ね、二枚のピックの合計で問題ないと思う

ストラトも新品時はかなりネックが動いたのだ
フロリダから空輸された直後に私が購入したという流れも大きい
輸入されて数年が経過したギターも多い
あるプロが経験した本当の話・・
海外の暑い国でライブを終えた後にそのまま、北海道でライブを行ったという
「ボディに無数のクラックが入っちゃったんだよ」
そんな逸話もあるのだ
最近はネックも落ち着いたのだ

もっとも細いレンチなのだ

ちなみに子象はネックを取り外すタイプなのだ

ヴィンテージタイプのストラトもこのタイプなのだ
はっきり言って面倒臭い
しかもコツが必要なのだ

私は弦を張ったまま作業してしまう
以前はテープなどで弦が暴れないように処理したが・・
最近はそのままなのだ
慣れないうちは弦をネックに固定してからネックを外した方が良い
ネジを締める前にネックのセンターズレや仕込み角度もチェックしておくと良い
子象はある意味でかなり『玄人なギター』なのだ
このギターをちゃんと鳴らすには知識とコツが不可欠なのだ
実際に演奏するにはこのギターに合った音作りと弾き方も必要になってくる
脱初心者の試験として最適なのだ
意外にベテランに人気があるギターなのだ
値段はオモチャではない
その辺りが理由だろうか?
新品の子象は安くない
初心者の場合、そのお金があればフルスケールのギターを買ってしまう
希にネットなどで子象の動画などに影響されて中古を買う人がいる
中古はさらにハードルが高い
言葉は悪いが・・
ゴミのような状態から楽器に復刻する自信があるだろうか?
電装関係やナット、ブリッジの状態・・
ネックとロッドの状態など
特に実物に触れる事が出来ないネックは危険なのだ
希に良い状態のまま押し入れの中で眠っていたギターに出会う
ミント状態なのだ
私のギターなのだ
私の場合、実物を手に取り音を出した
ロッドに関しては行きつけの楽器店を信頼したのだ
「ロッドの残りってあるの? 回していい?」
店員さんの前でロッドをグリグリ回すのは失礼であり非常識なのだ
そもそも、この程度のギターでそこまで神経質になるような人にギターを弾く資格はない
業界も願っている
「他の趣味に行ってほしいなぁ・・」
面倒臭い事を言わないで買い物をしてくれるお客さんは大歓迎なのだ
昨今はネットの情報が行き交うということもあると思うが・・
面倒臭い人が増えてきた
ギターを購入した後に自宅で面倒臭いのは悪くない
誰にも迷惑をかけていない
徹底的に拘れば良い
むしろ、そんなギター的な変態が増えることを私は望む
買い物はサッパリと・・
購入後はじっくりと・・・
が良いと思う
今回の湿度の影響が湿度管理シートのセンサーに表れていた

ピンク色で湿度過多なのだ
画像ではわかり難いと思うが・・
青色が取れて薄いピンク色に変色している
何度も再利用できるようだ
センサーが青色になるまで天日に干すのだ
これはストラトのケース内のシートなのだ
割と天井に高い場所に保管していた
一方、こちらはギブソンのケース内のシートなのだ
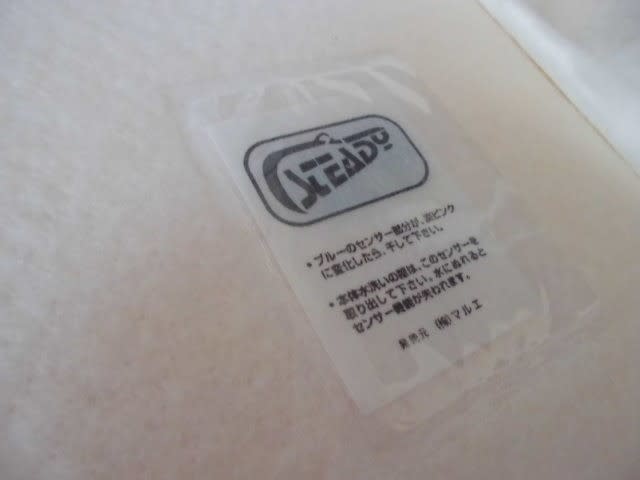
青色が残っている
このケースは湿度管理機能があるクローゼットに置いてあった
ちなみに二枚のシートは同時期に購入したのだ
購入当初はセンサーの色が変化しなかった
「本当に効果あるの?」
少し疑っていたのだ
まぁ、ケース内の乾燥剤のような感じなのだ
お守り的な扱いなのだ
ハードケースの最良のメンテは使うことなのだ
常に開け閉めするのが良い
ギターを入れても入れなくても良いのだ
最悪な使い方はギターを入れたまま、湿度の影響を受け易い場所に放置することなのだ
一部、ギターの知識がない人は押し入れの中で『熟成』すると思っている
ギターはハムではない
熟成はしない
劣化するのだ
数十年という時間を経た古いギターがゴミなのだ
はっきりいってゴミに近しいギターもある
大事なことは良い状態での管理なのだ
さらに大事なことは『入力』なのだ
”魂を込めるように弾き込む・・・”
これが入力なのだ
ギターは購入者によって差が出る
購入から1年くらい経過した頃に第一段階の差がでる
その後、毎年何かしらの変化が訪れる
最近は塗装の技術が上がったのだ
目に見えるほど外観に変化が起こることは少ない
褪色するイメージが強いレスポールだが・・
近年のレスポールはまっったく色が変わらない
むしろ、ポリ塗装のフェンダー系の方が変化する
変化を嫌う人もいる
「白を買ったのに・・何で黄色になるの?」
変化を好む人もいる
分かり易い例としてイングヴェイのストラトがよい
元の色は白色なのだ
検索してみていただきたい
ちなみに私のベースは白、ストラトはパールホワイトなのだ
共にかなり黄色へと変化している
ストラトのヘッドも新品時はかなり薄い色だった
現在はかなり色が付いているのだ
今回が画像を用意できなかったが・・・
アコギも新品時は白が強いスプルース板だった
現在は飴色に近いような感じになってきた
当然ながら、すべてのギターの音が変化しているのだ
その変化の過程を楽しみたい
そしてユーザーとして状態を把握しておくべきだと思う
話をネックに戻そう・・
最近はメンテに関するブログを見かけない
理由は簡単なのだ
メンテそのものが軽視されているからなのだ
メンテを理解していない人がギター系のブログを書いているというケースも多々ある
読み手側の読者もそんなことを求めないという・・・
『ライトな流れ』になりつつある
時代の変化と弾き手の意識の変化を感じてしまう
「オークションで安く買えたんだよ~」
演奏そのものよりも買い物に楽しみを感じるというタイプが増えている
”買い物燃え尽き症候群・・・”
私はそんな呼び名を付けている
そんな人にギターのその後を問うだけヤボなのだ
そもそも、ギターの状態を引き出せない人に弦選びなど不要なのだ
良い状態あってこその弦なのだ
伝わっているだろうか?
高級ギターVS安ギターという意味がない戦いはいまだ続いている
メンテが出来ない初心者が購入した高級ギターのその後はかなり悲惨なのだ
ギターを良く知る人が少し触ればその酷い状態に驚かされる
「ネックやブリッジを調整してあげようか?」
という親切な申し出も実は迷惑なのだ
「何か逆に弾き難くなっちゃった・・・」
「元の状態の方が良かったんだけど・・」
「って言っても元の状態が分らないよ~」
ありがた迷惑なのだ
良い事をしてあげて恨まれるという・・・
基本、面倒見が良い私も気をつけている
ネットは良い
私が読者の皆さんのギターに触れる事は出来ない
むしろ、それが良いのだ
興味ない人はスルーする
理解できない人もスルーする
興味ある方だけに発信しているのだ
「メチャ、ギターが弾き易くなった~」
「マジで感謝! このブログって神だと思う」
そこまで感動する人がいないと思うが・・・
現状、アクティブなブログで当ブログほど有用で役立つブログは少ない
買い物ネタは個人的にはお腹一杯なのだ
「だから・・何? それで~?」
という気持ちになってくる
奏法を解説している系のブログは好きなのだ
個人的には楽しませてもらっているのだ
しかしながら、思う事もあるのだ
「どれだけの人が理解できているのかな?」
まぁ、そこまで考えてしまったら何も発信できない
深く考えない事が良いこともある
私は常に読み手や聴き手の顔とレベルを想像しているのだ
今回は真面目一辺倒なのだ
学生の皆さんは充実した夏休みを送っているだろうか?
今回は非常に当たり前のお話を真面目にしたい

今回は当ブログの名物キャラである『変態おじさん』は登場しないのだ
品格を維持したい
ところで皆さんのギターのコンディションは如何だろうか?
良い演奏には『良いメンテ』が不可欠なのだ
実はこの辺りが曖昧な人も少なくない
ギター歴数十年というベテランですら間違って理解している事も多い
「弾き易いからいいんじゃない?」
という結果オーライ的な発想もあるが・・・
実は適切なメンテを行うなだけでさらに弾き易く、音色も向上するのだ
何事においても自己流には限界がある
基本を踏まえた上での自己流であるべきなのだ
私はそう考えている
行きつけの楽器店に出入りするようになりそんな事意識するようになった
加えてネットに発信するようになりその意識が高まったのだ
「間違った情報を発信するのはダメでしょ?」
私には責任感と使命感があるのだ
ギターは環境の影響を受けやすい
理由は木材で作られているからなのだ
金属パーツは経年劣化は起こすが季節に影響されることは少ない
特にネックはシビアなのだ
そもそも聴力が強いギター弦と常に戦っているのだ
その状況は過酷を極める
概ね、ネックは年に二回ほど大きく動く
夏と冬なのだ
理由は『湿度変化』なのだ
エアコンなども影響しているのだ
湿度とネックの関係を整理しておきたい
夏場は蒸す
湿度が上がれば木材が湿度を含み膨張する
ネックは『逆反り』になる
同時にエアコンなどの冷気を受け、ネック内部のトラスロッド(金属棒)が縮む
これも逆反りの一端になっている
冬場はこの逆だと考えれば良いのだ
今回はすべてのギターのネックが一律に逆反ったのだ
良い事だと思う
メンテ側としては分かり易い

ストラトも反った

子象も反った・・

ギターには調整しなくてはならない部分が沢山ある
”調整しなくては鳴らない部分・・”
と言い換えることも出来る
弦高調整の前にネック調整なのだ

最近の私は弦を張ったまま調整してしまう

超高級ギターや異常なほどギターを大事にしている人はその都度弦を緩めた方が良い
たしかにロッドにかかる負担はないとはいえない
しかしながら、ロッドを回す範囲は短い
僅かなのだ
しかも動きが良いロッドはスムースなのだ
レスポールなどカバーの片側のネジを外すだけなのだ
むしろ、弦を張ったり、緩めたりする方が各部に負担がかかる
まぁ、消耗したパーツは交換すれば良いだけの話だが・・
ネック調整、ブリッジ&サドル調整という流れになる
現行は12フレットで2㎜!
これは厳守した方が幸せになれる
誰が決めたのか?
この状態が最高なのだ
この状態を基準に考えると調整がし易い
余談だが・・
ストラトマスターのChar氏はさらに高く設定しているという
あの生き生きとした音はテクに加え、高い弦高が貢献しているのだ
カッティングやピッキング時のアタック感が増す
私は一つの基準としてアルペジオの弾き易さを目安にしているのだ
張りがない弦は楽しくない
フレーズも浮かばない
アルペジオが気持ちいい状態からのカッティングなのだ
キレキレの音が飛び出す
ギターや弦に弾かされている感がある
むしろ、それは好ましい状態なのだ
キャリアが増せばどんな状態のギターでもそこそこ格好良く鳴らせる
ビギナーのギブソンよりも匠のコピーモデルなのだ
しかしながら、実際に弾いている匠はあまり気分が乗っていないという・・
伝わっているだろうか?
以前にも紹介したが・・
不要ピックを使った『弦高センサー』はお勧めなのだ

コストがかからない
メジャーで測るよりも繊細で正確なのだ
1.87と2.00の二枚なのだ
実際には隙間のセメダインの厚みもあると思うが・・
概ね、二枚のピックの合計で問題ないと思う

ストラトも新品時はかなりネックが動いたのだ
フロリダから空輸された直後に私が購入したという流れも大きい
輸入されて数年が経過したギターも多い
あるプロが経験した本当の話・・
海外の暑い国でライブを終えた後にそのまま、北海道でライブを行ったという
「ボディに無数のクラックが入っちゃったんだよ」
そんな逸話もあるのだ
最近はネックも落ち着いたのだ

もっとも細いレンチなのだ

ちなみに子象はネックを取り外すタイプなのだ

ヴィンテージタイプのストラトもこのタイプなのだ
はっきり言って面倒臭い
しかもコツが必要なのだ

私は弦を張ったまま作業してしまう
以前はテープなどで弦が暴れないように処理したが・・
最近はそのままなのだ
慣れないうちは弦をネックに固定してからネックを外した方が良い
ネジを締める前にネックのセンターズレや仕込み角度もチェックしておくと良い
子象はある意味でかなり『玄人なギター』なのだ
このギターをちゃんと鳴らすには知識とコツが不可欠なのだ
実際に演奏するにはこのギターに合った音作りと弾き方も必要になってくる
脱初心者の試験として最適なのだ
意外にベテランに人気があるギターなのだ
値段はオモチャではない
その辺りが理由だろうか?
新品の子象は安くない
初心者の場合、そのお金があればフルスケールのギターを買ってしまう
希にネットなどで子象の動画などに影響されて中古を買う人がいる
中古はさらにハードルが高い
言葉は悪いが・・
ゴミのような状態から楽器に復刻する自信があるだろうか?
電装関係やナット、ブリッジの状態・・
ネックとロッドの状態など
特に実物に触れる事が出来ないネックは危険なのだ
希に良い状態のまま押し入れの中で眠っていたギターに出会う
ミント状態なのだ
私のギターなのだ
私の場合、実物を手に取り音を出した
ロッドに関しては行きつけの楽器店を信頼したのだ
「ロッドの残りってあるの? 回していい?」
店員さんの前でロッドをグリグリ回すのは失礼であり非常識なのだ
そもそも、この程度のギターでそこまで神経質になるような人にギターを弾く資格はない
業界も願っている
「他の趣味に行ってほしいなぁ・・」
面倒臭い事を言わないで買い物をしてくれるお客さんは大歓迎なのだ
昨今はネットの情報が行き交うということもあると思うが・・
面倒臭い人が増えてきた
ギターを購入した後に自宅で面倒臭いのは悪くない
誰にも迷惑をかけていない
徹底的に拘れば良い
むしろ、そんなギター的な変態が増えることを私は望む
買い物はサッパリと・・
購入後はじっくりと・・・
が良いと思う

今回の湿度の影響が湿度管理シートのセンサーに表れていた

ピンク色で湿度過多なのだ
画像ではわかり難いと思うが・・
青色が取れて薄いピンク色に変色している
何度も再利用できるようだ
センサーが青色になるまで天日に干すのだ
これはストラトのケース内のシートなのだ
割と天井に高い場所に保管していた
一方、こちらはギブソンのケース内のシートなのだ
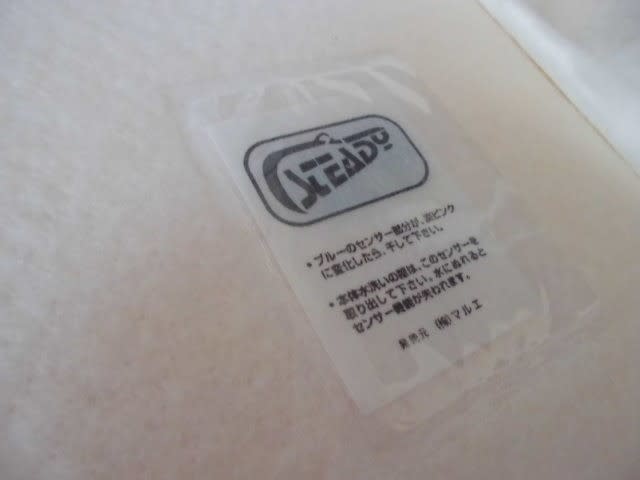
青色が残っている
このケースは湿度管理機能があるクローゼットに置いてあった
ちなみに二枚のシートは同時期に購入したのだ
購入当初はセンサーの色が変化しなかった
「本当に効果あるの?」
少し疑っていたのだ
まぁ、ケース内の乾燥剤のような感じなのだ
お守り的な扱いなのだ
ハードケースの最良のメンテは使うことなのだ
常に開け閉めするのが良い
ギターを入れても入れなくても良いのだ
最悪な使い方はギターを入れたまま、湿度の影響を受け易い場所に放置することなのだ
一部、ギターの知識がない人は押し入れの中で『熟成』すると思っている
ギターはハムではない
熟成はしない
劣化するのだ

数十年という時間を経た古いギターがゴミなのだ
はっきりいってゴミに近しいギターもある
大事なことは良い状態での管理なのだ
さらに大事なことは『入力』なのだ
”魂を込めるように弾き込む・・・”
これが入力なのだ
ギターは購入者によって差が出る
購入から1年くらい経過した頃に第一段階の差がでる
その後、毎年何かしらの変化が訪れる
最近は塗装の技術が上がったのだ
目に見えるほど外観に変化が起こることは少ない
褪色するイメージが強いレスポールだが・・
近年のレスポールはまっったく色が変わらない
むしろ、ポリ塗装のフェンダー系の方が変化する
変化を嫌う人もいる
「白を買ったのに・・何で黄色になるの?」
変化を好む人もいる
分かり易い例としてイングヴェイのストラトがよい
元の色は白色なのだ
検索してみていただきたい
ちなみに私のベースは白、ストラトはパールホワイトなのだ
共にかなり黄色へと変化している
ストラトのヘッドも新品時はかなり薄い色だった
現在はかなり色が付いているのだ
今回が画像を用意できなかったが・・・
アコギも新品時は白が強いスプルース板だった
現在は飴色に近いような感じになってきた
当然ながら、すべてのギターの音が変化しているのだ
その変化の過程を楽しみたい
そしてユーザーとして状態を把握しておくべきだと思う
話をネックに戻そう・・
最近はメンテに関するブログを見かけない
理由は簡単なのだ
メンテそのものが軽視されているからなのだ
メンテを理解していない人がギター系のブログを書いているというケースも多々ある
読み手側の読者もそんなことを求めないという・・・
『ライトな流れ』になりつつある
時代の変化と弾き手の意識の変化を感じてしまう
「オークションで安く買えたんだよ~」
演奏そのものよりも買い物に楽しみを感じるというタイプが増えている
”買い物燃え尽き症候群・・・”
私はそんな呼び名を付けている
そんな人にギターのその後を問うだけヤボなのだ
そもそも、ギターの状態を引き出せない人に弦選びなど不要なのだ
良い状態あってこその弦なのだ
伝わっているだろうか?
高級ギターVS安ギターという意味がない戦いはいまだ続いている
メンテが出来ない初心者が購入した高級ギターのその後はかなり悲惨なのだ
ギターを良く知る人が少し触ればその酷い状態に驚かされる
「ネックやブリッジを調整してあげようか?」
という親切な申し出も実は迷惑なのだ
「何か逆に弾き難くなっちゃった・・・」
「元の状態の方が良かったんだけど・・」
「って言っても元の状態が分らないよ~」
ありがた迷惑なのだ
良い事をしてあげて恨まれるという・・・

基本、面倒見が良い私も気をつけている
ネットは良い
私が読者の皆さんのギターに触れる事は出来ない
むしろ、それが良いのだ
興味ない人はスルーする
理解できない人もスルーする
興味ある方だけに発信しているのだ
「メチャ、ギターが弾き易くなった~」
「マジで感謝! このブログって神だと思う」
そこまで感動する人がいないと思うが・・・
現状、アクティブなブログで当ブログほど有用で役立つブログは少ない
買い物ネタは個人的にはお腹一杯なのだ
「だから・・何? それで~?」
という気持ちになってくる
奏法を解説している系のブログは好きなのだ
個人的には楽しませてもらっているのだ
しかしながら、思う事もあるのだ
「どれだけの人が理解できているのかな?」
まぁ、そこまで考えてしまったら何も発信できない
深く考えない事が良いこともある
私は常に読み手や聴き手の顔とレベルを想像しているのだ

今回は真面目一辺倒なのだ




















