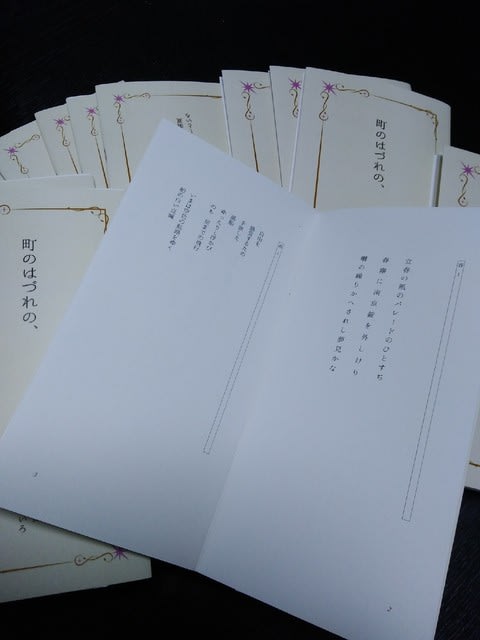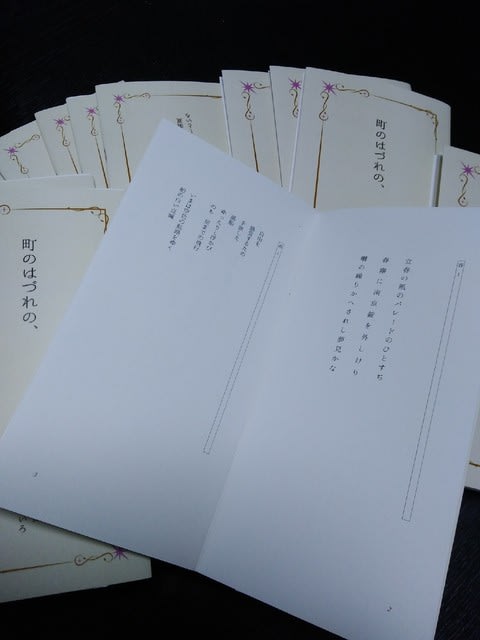7月13日(土)、
野川朗読会10が無事に終了いたしました。
梅雨の晴れ間にご来場いただいた皆さま、有難うございました。
当日の様子を、簡単にまとめてみたいと思います。
今年は野川朗読会の開催が10回目を迎える節目の年でした。
私自身、最初に野川朗読会を聴きに行ったのは学生時代の頃です。
そこから記憶にある限りでは毎年、野川朗読会に訪れて、気付けば自分が出演者になっていました。
年に一回の開催なので、10年の年月が流れたことになりますが、あっという間でした。
これからも長く続いて行く朗読会になることを祈っております。
今年の<ひとことテーマ>は「怖い話」でした。
どんな怖い話が飛び出したか、かいつまんで記しておきます。
生野毅さん「決して一人では見ないでください。」~映画『サスペリア』のキャッチコピーより~
渡辺めぐみさん「人の生死にかかわる予知夢を見てしまうことがある。」
浜江順子さん「雨の日の夜、仕事帰りの道で、ふと振り向くと首を締めようとする男がいた。」
北爪満喜さん「人間たちには聞こえないけれど木々たちは会話をしている。」
新井高子さん「知らぬ間に血がなくなっていく奇病発生」~『水木しげる展』より~
杉本真維子さん「自分が昔に書いた詩「穴」を思い出す。」
長野まゆみさん「昔の地元のバスの行き先「多摩墓場行き」に乗っていたご老人たちの気持ちを考えてしまう。」
田野倉康一さん「田野倉家のある血筋では、60歳まで生きられないこと。誰かが16歳の時に誰かが死ぬこと。霊感はないが虫の報せがあること。」
樋口良澄さん「乾麺のうどんがなぜか袋の中で短くなっていく……ゴキブリが袋のなかで乾麺を食べていた。」
相沢正一郎さん「雛人形がなんとなく怖い。」
野村喜和夫さん「『ラッパーに噛まれたらラッパーになる』というドラマを深夜に見た。同じように詩人のゾンビが人を襲って詩人ゾンビにしてしまったら、世の中が少し良くなるのではと思った。」
一色真理さん「ある日の夜中、部屋に宇宙人がいた。あくる朝父曰く「夜中に何か気配がして部屋を調べたけれど、真ちゃんの部屋だけがなかった。」」
岡島弘子さん「ムンクの「叫び」が怖い。私の居場所がないという怖さを感じる。」
私はと言うと、「蛾が怖い。山奥のコテージに泊まったときの夜、窓に標本のようにあらゆる蛾が止まっていた光景がどうしても忘れられない。」とお話ししました。
朗読では、「怖い話」に関連して怖い詩や散文を読む方もいらっしゃっいました。
新井高子さんは、地方の方言で語る石川啄木の短歌と、その本の後書きを読まれました。方言の温かみのある話し方が心地よく感じました。
岡島弘子さんは一工夫ある朗読で、朗読する詩にテスト風の設問を用意して、会場の皆さんに「この詩は次のうちどれを表現したものか。」というような問いを投げかけていらっしゃいました。
野川トークのテーマは「古代・古墳時代の謎をひも解く」と、テーマ付けられるでしょう。
私も事前に色々調べたのですが、長野さん、田野倉さんの知識量には到底およばず、聞き役に徹した感じでした。とほほ。
なので、当日にお二方がお話しされたことは、例えば神様や人名をカタカナでしかとらえられず、また地理的な位置関係を想像するのがやっとで、全体的にどのような話だったか、私は覚えられませんでした。
そのため、朗読会の資料として、長野さんが配られた資料を要約したものを、記しておこうと思います。
「一口坂の謎を解く」
<一口坂(ひとくちざか)の旧称は一口坂(いもあらいざか)>
なぜ、一口坂をいもあらいざかと読むか。
かつて京都に存在した巨椋池(おぐらいけ)と淀川をむすぶただひとつの出口だったところに「東一口」「西一口」という地名が残る。
そこにあった一口稲荷を江戸へ勧請。その場所が九段の一口坂だった。
一口稲荷は小野篁が疱瘡神(いもあらい)を祀ったところ。
疱瘡=ほうそうの別称はイボ、それがなまってイモ、いもあらいとなった。
疱瘡神としてもうひとり有名なのは菊理姫(ククリヒメ、またはキクリヒメ)。菊の花の形が疱瘡(あばた)の形に似ているため、そのような名前になったか。
「ククリ」という読み方は「潜り」に通じる。
黄泉の国から逃げ帰るイザナギノミコトに禊(みそぎ)を教えた。
「古事記」では桃の実を三つとって投げつけて、イザナギは追っ手を退けた。
モモと言えばヤマトトトヒモモソヒメ。
ヤマトトトヒモモソヒメはオオモノヌシノカミの妻になった。
この夫婦にはこんな伝説がある。
オオモノヌシノカミは昼は留守にして、夜にだけヤマトトトヒモモソヒメのもとを訪れる。
姫は「お顔をみたい」と謂う。
大神は「あなたの櫛箱に入っていよう。私の姿に驚かぬよう。」と云う。
姫は夜明けに櫛箱をあけた。するとそこにはうるわしい小蛇(こおろち)がいた。
姫は叫び、大神は恥じて人の姿になる。
姫は悔い、坐りこんだところそこにあった箸にほとを突かれ、亡くなってしまった。
そのヤマトトトヒモモソヒメが埋葬されている古墳を「箸墓古墳」という。
……以上のような流れでトークは始まり、古墳時代のこと、百舌古市古墳群のこと、蛇のことなどが語られました。
蛇に流れ着いた結果、長野さんが興味深いことをおっしゃいました。
「蛇に関連する諏訪大社の紋は梶の葉。私の(長野さんの)物語のなかでカジという名前が出て来たら、蛇のことを指している。」
このような発言だったと思います。
長野さんの物語を読み解くヒントが一つ得られました。
朗読もトークも、ひと際に濃い内容の、10回目の野川朗読会でした。
来年はどのような内容の<ひとことテーマ>、野川トークのテーマになるでしょうか。
また梅雨の晴れ間に皆さんにお会いできることを楽しみにしております。