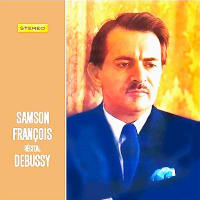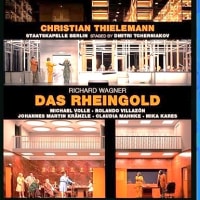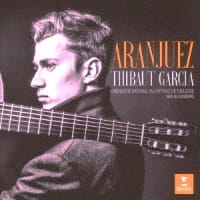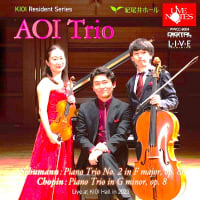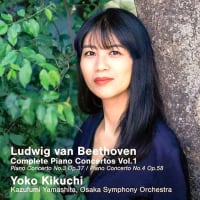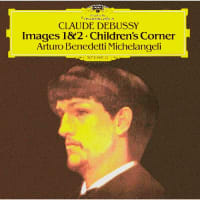<新刊情報>
書名:フォーレ:《レクイエム》 ~もっときわめる! 1曲1冊シリーズ ⑥~
著者:相場ひろ
発行:音楽之友社(ON BOOKS advance)
各曲をしっかり聴きたい人向けに1冊で1曲を扱うシリーズ第6弾。楽曲の成立過程、フォーレにおける「レクイエム」の独自性、作曲当初より演奏されていた大編成版(1900年版)と近年出版された小編成版(1893年版)の詳細、演奏・録音史と名盤30点余、日本人が愛してやまない同曲の魅力を多角的に紹介。【目次】 第1章 フォーレ《レクイエム》の魅力 第2章 楽曲紹介 01/フォーレ《レクイエム》の成立と作曲過程 02/楽譜について(大編成版の成立) 03/楽曲解説 第3章 フォーレ《レクイエム》の演奏・録音史 01/1900年版の録音史 02/1893年版の録音史 03/その他の版による演奏
著者:相場ひろ
発行:音楽之友社(ON BOOKS advance)
各曲をしっかり聴きたい人向けに1冊で1曲を扱うシリーズ第6弾。楽曲の成立過程、フォーレにおける「レクイエム」の独自性、作曲当初より演奏されていた大編成版(1900年版)と近年出版された小編成版(1893年版)の詳細、演奏・録音史と名盤30点余、日本人が愛してやまない同曲の魅力を多角的に紹介。【目次】 第1章 フォーレ《レクイエム》の魅力 第2章 楽曲紹介 01/フォーレ《レクイエム》の成立と作曲過程 02/楽譜について(大編成版の成立) 03/楽曲解説 第3章 フォーレ《レクイエム》の演奏・録音史 01/1900年版の録音史 02/1893年版の録音史 03/その他の版による演奏
◇
書名:二十世紀のクラシック音楽を取り戻す~三度の戦争は音楽に何をしたか~
著者:ジョン・マウチェリ
訳者:松村哲哉
発行:白水社
20世紀後半に作曲されたクラシック音楽の作品で、その後世界中のオーケストラや歌劇場のレパートリーに加わった作品はごく少ない。そして、現代の音楽であるはずの「現代音楽」は、一部の愛好家を除けば人気があるとは言いがたい。この状況を著者は、「現代のクラシック音楽というものが狭い範囲に限定されたからこそ、他のジャンルの音楽が大いに栄えているのに、オーケストラやオペラハウスがいわゆる『危機的状況』にある」と見る。現在もレパートリーの中心をなしているかつての大作曲家の系譜はどこへ行ってしまったのか?映画『風と共に去りぬ』の作曲者でウィーン楽友協会音楽院に学んだマックス・スタイナーは、かつて「仮にワーグナーが今世紀に生きていたら、映画音楽でナンバーワンの作曲家になっていたでしょう」と語った。同書は20世紀クラシック音楽の歴史を、この問題に大きな影響を与えた第一次・第二次世界大戦、冷戦とのかかわりから見ていくものである。「現代音楽」たる前衛音楽、政治的な事情で埋もれてしまった作曲家に、クラシック音楽家の系譜につらなる映画音楽やミュージカルの作曲家まで含めて語る。
著者:ジョン・マウチェリ
訳者:松村哲哉
発行:白水社
20世紀後半に作曲されたクラシック音楽の作品で、その後世界中のオーケストラや歌劇場のレパートリーに加わった作品はごく少ない。そして、現代の音楽であるはずの「現代音楽」は、一部の愛好家を除けば人気があるとは言いがたい。この状況を著者は、「現代のクラシック音楽というものが狭い範囲に限定されたからこそ、他のジャンルの音楽が大いに栄えているのに、オーケストラやオペラハウスがいわゆる『危機的状況』にある」と見る。現在もレパートリーの中心をなしているかつての大作曲家の系譜はどこへ行ってしまったのか?映画『風と共に去りぬ』の作曲者でウィーン楽友協会音楽院に学んだマックス・スタイナーは、かつて「仮にワーグナーが今世紀に生きていたら、映画音楽でナンバーワンの作曲家になっていたでしょう」と語った。同書は20世紀クラシック音楽の歴史を、この問題に大きな影響を与えた第一次・第二次世界大戦、冷戦とのかかわりから見ていくものである。「現代音楽」たる前衛音楽、政治的な事情で埋もれてしまった作曲家に、クラシック音楽家の系譜につらなる映画音楽やミュージカルの作曲家まで含めて語る。
◇
書名:世界の音~楽器の歴史と文化~
著者:郡司すみ
解説:森重 行敏
発行:講談社(講談社学術文庫)
「打楽器を持たない民族はいない」。古来、人は自身の体やモノを叩いて感情を伝え、動物の鳴き声や雨風などの自然音を真似、再現してきた。楽器発祥から2万年。信仰の祭礼、政治儀式、軍事の士気高揚・・・・・・あらゆる場面に浸透していった「音」と「音楽」。気候風土や時代背景に合わせ、世界各地の「音」は、どのように姿を変えてきたのか。西洋音楽と民族音楽、その対比が示す真意は? 「音」で考える、ユニークかつ雄大な文化人類学(同書は『世界楽器入門 好きな音 嫌いな音』<1989年1月 朝日選書>を改題)。【目次】 第一章 ミンゾク楽器 第二章 楽器の起源 第三章 楽器分類を通して見た諸民族の楽器観 第四章 楽器の音 第五章 楽器の分布と歴史 第六章 風土と音 第七章 音・数・楽器 第八章 メディアとしての楽器 第九章 手作りについて 第十章 好きな音嫌いな音 第十一章 東方の楽器・西方の楽器 解説「人類共通の財産ーー音楽とは何か?ーー」森重行敏(洗足学園音楽大学現代邦楽研究所所長)
著者:郡司すみ
解説:森重 行敏
発行:講談社(講談社学術文庫)
「打楽器を持たない民族はいない」。古来、人は自身の体やモノを叩いて感情を伝え、動物の鳴き声や雨風などの自然音を真似、再現してきた。楽器発祥から2万年。信仰の祭礼、政治儀式、軍事の士気高揚・・・・・・あらゆる場面に浸透していった「音」と「音楽」。気候風土や時代背景に合わせ、世界各地の「音」は、どのように姿を変えてきたのか。西洋音楽と民族音楽、その対比が示す真意は? 「音」で考える、ユニークかつ雄大な文化人類学(同書は『世界楽器入門 好きな音 嫌いな音』<1989年1月 朝日選書>を改題)。【目次】 第一章 ミンゾク楽器 第二章 楽器の起源 第三章 楽器分類を通して見た諸民族の楽器観 第四章 楽器の音 第五章 楽器の分布と歴史 第六章 風土と音 第七章 音・数・楽器 第八章 メディアとしての楽器 第九章 手作りについて 第十章 好きな音嫌いな音 第十一章 東方の楽器・西方の楽器 解説「人類共通の財産ーー音楽とは何か?ーー」森重行敏(洗足学園音楽大学現代邦楽研究所所長)
◇
書名:クリティカル・ワード ポピュラー音楽~〈聴く〉を広げる・更新する~
著者:永冨真梨、忠聡太、日高良祐=編著|有國明弘、ヴィニットポン ルジラット(石川ルジラット)、大嶌徹、大尾侑子、尾鼻崇、大和田俊之、葛西周、加藤賢、上岡磨奈、川本聡胤、金悠進、源河亨、篠田ミル、ジョンソン・エイドリエン・レネー、谷口文和、中條千晴、鳥居祐介、永井純一、平石貴士、福永健一、藤嶋陽子、増田聡、松浦知也、溝尻真也、村田麻里子、山崎晶、輪島裕介
発行:フィルムアート社
28のキーワードで学ぶポピュラー音楽研究の基礎から最前線まで。ジェンダー、人種、階級、ジャンル、法、アニメ、シティ、アマチュアリズム・・・幅広いキーワードと現代的な事例から、音楽文化を考え常識を問い直す。近年、学術的な研究領域としての地位を確立しつつある「ポピュラー音楽」研究に関する基礎的な知識を解説しつつ、最新の動向を初学者にも分かりやすく紹介した本邦初の入門書。同書は3部構成になっており、「第1部 基礎編」では、ポピュラー音楽研究の基底を支える概念として8つを取り上げ、それぞれのキーワードからポピュラー音楽を概観する。「第2部 事例編」では、ポピュラー音楽研究のなかでも比較的蓄積の多いトピックを照射する。各項目はそれぞれの学術的議論を概観した上で、ポピュラー音楽研究全体、そして、他分野と横断・接続し、新しい学術領域を開拓する、発展的な学術的問いも示唆する。「第3部 拡張編」では、近年の音楽文化を領域横断的に語る上で欠かせないキーワードを掲げて、ポピュラー音楽それ自体とそのコンテクストを扱ってきた従来の研究から一歩外に踏み出し、新鮮な空気を吸うための論考を集めた。これまで日本語で読むことのできなかった重要トピックや論点も多数収録し、研究者や学生だけでなく、音楽を「分析したい人」、「語りたい人」にとっての手引きとしても有用な一冊となっている。
著者:永冨真梨、忠聡太、日高良祐=編著|有國明弘、ヴィニットポン ルジラット(石川ルジラット)、大嶌徹、大尾侑子、尾鼻崇、大和田俊之、葛西周、加藤賢、上岡磨奈、川本聡胤、金悠進、源河亨、篠田ミル、ジョンソン・エイドリエン・レネー、谷口文和、中條千晴、鳥居祐介、永井純一、平石貴士、福永健一、藤嶋陽子、増田聡、松浦知也、溝尻真也、村田麻里子、山崎晶、輪島裕介
発行:フィルムアート社
28のキーワードで学ぶポピュラー音楽研究の基礎から最前線まで。ジェンダー、人種、階級、ジャンル、法、アニメ、シティ、アマチュアリズム・・・幅広いキーワードと現代的な事例から、音楽文化を考え常識を問い直す。近年、学術的な研究領域としての地位を確立しつつある「ポピュラー音楽」研究に関する基礎的な知識を解説しつつ、最新の動向を初学者にも分かりやすく紹介した本邦初の入門書。同書は3部構成になっており、「第1部 基礎編」では、ポピュラー音楽研究の基底を支える概念として8つを取り上げ、それぞれのキーワードからポピュラー音楽を概観する。「第2部 事例編」では、ポピュラー音楽研究のなかでも比較的蓄積の多いトピックを照射する。各項目はそれぞれの学術的議論を概観した上で、ポピュラー音楽研究全体、そして、他分野と横断・接続し、新しい学術領域を開拓する、発展的な学術的問いも示唆する。「第3部 拡張編」では、近年の音楽文化を領域横断的に語る上で欠かせないキーワードを掲げて、ポピュラー音楽それ自体とそのコンテクストを扱ってきた従来の研究から一歩外に踏み出し、新鮮な空気を吸うための論考を集めた。これまで日本語で読むことのできなかった重要トピックや論点も多数収録し、研究者や学生だけでなく、音楽を「分析したい人」、「語りたい人」にとっての手引きとしても有用な一冊となっている。