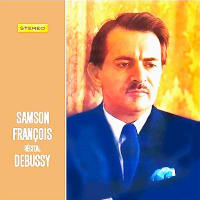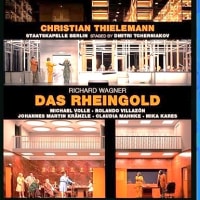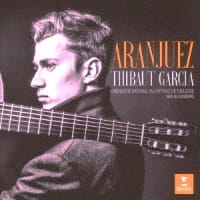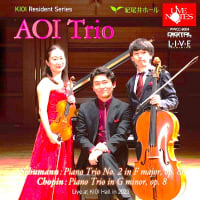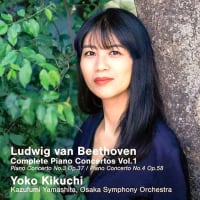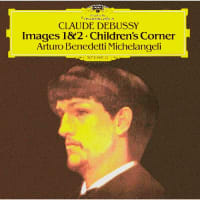<新刊情報>
書名:音楽力を伸ばす「譜読み」の基本~楽譜攻略13のステップ~
著者:山本美芽
発行:ヤマハミュージックエンタテインメント
「楽譜はなぜ読めたほうがいい?」「耳コピはダメ?」「効率的な身につけ方は?」「音楽的な活用法は?」「そもそも譜読みってなんだろう」――そんな疑問がすべて解決。楽譜との向き合い方を変え、「譜読み」を効率的に身につけ演奏を変えるための一冊。楽譜を自由に読めるようになるのは意外に大変。世の中には、楽譜が読めなくても楽器を自由に演奏している人もたくさんいる。では、苦労して楽譜を読めるようにすることに、どのような意味があるのか?同書は、楽譜を読んで演奏すること(譜読み)の意味を根本から問い直し、譜読みの意義や目的、そして演奏につなげるための効率的な学習法を考えていく。ピアノ教本研究家でもある著者が、数多くの音楽指導者への取材を通して見えてきた譜読みの効果とは? また、より実践的な目的につなげるための学習法や実践法とは?同書を読むことで譜面への理解が深まり、音楽との向き合い方がきっと変わるはず。
著者:山本美芽
発行:ヤマハミュージックエンタテインメント
「楽譜はなぜ読めたほうがいい?」「耳コピはダメ?」「効率的な身につけ方は?」「音楽的な活用法は?」「そもそも譜読みってなんだろう」――そんな疑問がすべて解決。楽譜との向き合い方を変え、「譜読み」を効率的に身につけ演奏を変えるための一冊。楽譜を自由に読めるようになるのは意外に大変。世の中には、楽譜が読めなくても楽器を自由に演奏している人もたくさんいる。では、苦労して楽譜を読めるようにすることに、どのような意味があるのか?同書は、楽譜を読んで演奏すること(譜読み)の意味を根本から問い直し、譜読みの意義や目的、そして演奏につなげるための効率的な学習法を考えていく。ピアノ教本研究家でもある著者が、数多くの音楽指導者への取材を通して見えてきた譜読みの効果とは? また、より実践的な目的につなげるための学習法や実践法とは?同書を読むことで譜面への理解が深まり、音楽との向き合い方がきっと変わるはず。
◇
書名:日本のクラシック音楽は歪んでいる~12の批判的考察~
著者:森本恭正
発行:光文社(光文社新書)
同書における批判の眼目は、日本における西洋音楽の導入において、いかに我々は間違ってそれらを受け入れ、その上その間違いに誰も気がつかず、あるいは気がついた者がいたとしても訂正せず、しかも現在まで間違い続けてきたか、という点である(「批評1 日本のクラシック音楽受容の躓き」より)。明治期に導入された西洋音楽。だが、その釦は最初から掛け違っていた。そして日本のクラシック音楽は、掛け違った釦のまま「権威」という衣を纏い、今日へと至る。作曲家・指揮者として活躍する著者が、20年を超える思考の上に辿り着いて示す、西洋音楽の本質。【目次】批判1 日本のクラシック音楽受容の躓き 批判2 西洋音楽と日本音楽の隔たり 批判3 邦楽のルーツ 批判4 なぜ行進は左足から始まるのか 批判5 西洋音楽と暴力 批判6 バロック音楽が変えたもの 批判7 誰もが吉田秀和を讃えている 批判8 楽譜から見落とされる音 批判9 歌の翼 批判10 音楽を運ぶ 批判11 現代日本の音楽状況 批判12 創(キズ)を造る行為
著者:森本恭正
発行:光文社(光文社新書)
同書における批判の眼目は、日本における西洋音楽の導入において、いかに我々は間違ってそれらを受け入れ、その上その間違いに誰も気がつかず、あるいは気がついた者がいたとしても訂正せず、しかも現在まで間違い続けてきたか、という点である(「批評1 日本のクラシック音楽受容の躓き」より)。明治期に導入された西洋音楽。だが、その釦は最初から掛け違っていた。そして日本のクラシック音楽は、掛け違った釦のまま「権威」という衣を纏い、今日へと至る。作曲家・指揮者として活躍する著者が、20年を超える思考の上に辿り着いて示す、西洋音楽の本質。【目次】批判1 日本のクラシック音楽受容の躓き 批判2 西洋音楽と日本音楽の隔たり 批判3 邦楽のルーツ 批判4 なぜ行進は左足から始まるのか 批判5 西洋音楽と暴力 批判6 バロック音楽が変えたもの 批判7 誰もが吉田秀和を讃えている 批判8 楽譜から見落とされる音 批判9 歌の翼 批判10 音楽を運ぶ 批判11 現代日本の音楽状況 批判12 創(キズ)を造る行為
◇
書名:ルービンシュタイン 全録音をCDで聴く
著者:藤田恵司
発行:アルファベータブックス
ルービンシュタインの生涯にわたってなされた全ての録音(1928年~1976年)を、彼の人生においての出来事とともに論じ、CDで聴けるようにガイドする。「己の演奏を後世に残す」という強い使命感を持って晩年まで録音に挑み続けたピアニストのアルトゥール・ルービンシュタイン(1887年―1982年)。彼の代名詞とも言えるショパンの演奏をはじめ、全ての録音データを網羅するとともに、彼の音楽人生も辿っていく。【全録音ディスコグラフィー付】
著者:藤田恵司
発行:アルファベータブックス
ルービンシュタインの生涯にわたってなされた全ての録音(1928年~1976年)を、彼の人生においての出来事とともに論じ、CDで聴けるようにガイドする。「己の演奏を後世に残す」という強い使命感を持って晩年まで録音に挑み続けたピアニストのアルトゥール・ルービンシュタイン(1887年―1982年)。彼の代名詞とも言えるショパンの演奏をはじめ、全ての録音データを網羅するとともに、彼の音楽人生も辿っていく。【全録音ディスコグラフィー付】
◇
書名:ロックの正体~歌と殺戮のサピエンス全史~
著者:樫原辰郎
著者:樫原辰郎
発行:晶文社
なぜ歌うのか? なぜ踊るのか? なぜ戦うのか?ロック文化から見えてくる、ヒト 700 万年の Like a Rolling Stone!ロックとはなんだったのか? 進化心理学、認知科学、神経科学、人類学、霊長類学、自然主義哲学、二重過程理論、処刑理論、生物学的市場仮説、お婆ちゃん仮説 etc. ──最新のサイエンスと歴史知識を駆使してロック文化を多角的に考察する。情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、縁側で渋茶をすするお爺さんのように語る、ポップカルチャーの哲学。好評連載「ロックの正体」(晶文社スクラップブック)を完全書籍化。
なぜ歌うのか? なぜ踊るのか? なぜ戦うのか?ロック文化から見えてくる、ヒト 700 万年の Like a Rolling Stone!ロックとはなんだったのか? 進化心理学、認知科学、神経科学、人類学、霊長類学、自然主義哲学、二重過程理論、処刑理論、生物学的市場仮説、お婆ちゃん仮説 etc. ──最新のサイエンスと歴史知識を駆使してロック文化を多角的に考察する。情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、縁側で渋茶をすするお爺さんのように語る、ポップカルチャーの哲学。好評連載「ロックの正体」(晶文社スクラップブック)を完全書籍化。