一昨日は伊勢に伝わる説話の蘇民将来子孫家門について書きました。この旅行中にもう一つの民話を知りました。それは種まき権兵衛さんの話です。
まずは、その舞台となる熊野古道、馬越峠(まごせとうげ)の写真です。
今回の旅行は全く土地勘がなく(旅行って大抵そんなものです)、伊勢神宮といっても125もの宮があり(有名なのは外宮と内宮ですが)、熊野古道といっても三重県和歌山県に広がっていて、2泊3日でどこをどう回るのがいいのか、なかなか難しかったのですが、1日めはまず伊勢神宮にお参りし、2日目伊勢市でレンタカーを借りて、南下していきました。世界遺産にもなっている馬越峠を少し歩きました。海山(みやま)の道の駅の近くに車を停めて、登っていきます。



きれいな石畳の道がずっと続いています。これは「夜泣き地蔵」。もともとは旅の安全を祈念していたが、いつしか子供の夜泣きを封じ込める信仰になったとか。大正時代までは石じゃなくてお地蔵さんがあったそうです。

石の一枚板。

もっとずっとこの道を行けば峠の頂上まで行けるのですが、何せこの日は西日本豪雨の日で、実際にはそんなに降られなかったのですが、天気予報ではいつ雨が降るかわからずこの辺りで引き返しました。
で、話は元に戻りますが、種まき権兵衛。
この海山地区の民話です。下記はウィキに出ている種まき権兵衛のお話です。
権兵衛は当地の武士の家に生まれたが、父の上村兵部の死後は武士の身分を捨て、父の望みであった農家となり荒地の開墾をはじめた。
しかしもともと武士であった権兵衛には何もかもが初めてのこと。慣れない手つきで見よう見まねの農作業は、種をまくそばからカラスに食べられてしまうほどで、近隣の農家の笑いものになっていた。
それでもあきらめず懸命に農業を続けた権兵衛は、やがて村一番の農家になっていたという。
権兵衛は狩猟の腕にも秀でており、その評判は紀州藩主・徳川宗直の耳に届くほど。宗直の前で見事3発の弾を標的に命中。宗直が褒美に田を与えようとしたところ、権兵衛はこれを辞退し、代わりに村人の年貢を免じてもらって村人から喜ばれた。
狩猟の腕に自信の権兵衛、馬越峠(まごせとうげ)に大蛇が出ると聞くと、大蛇を退治するべく猟銃を持って山に入った。
見事大蛇を仕留めたものの、彼自身も大蛇の毒液を浴びてしまい、村人の介抱もむなしく1736年(元文元年)12月26日に死去した。(ウィキペディアより)
お話に出てくる権兵衛が大蛇を退治したのが馬越峠というわけです。
この権兵衛さんは、ことわざにもなっています。
「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」 - (まいた種をカラスに食べられてしまうことから)努力が実らないこと、無駄なことの意。人が苦労してやったことを他の人がぶち壊してしまいせっかくの骨折りが無駄になること。
そして、民謡にもなっているのですが、民謡だけでなく黒人霊歌の替え歌にもなっている??
まずは民謡。お座敷ずんべら。
権兵衛が種まきゃ からすがほじくる
三度に一度は 追はずばなるまい
ずんべら すんべら ずんべら
こちらは藤原義江版。民謡ともまた違う趣です。美しいテノールのずんべらずんべら。
墨田男性合唱団のコーラスがこちら。これが黒人霊歌の替え歌だそうですが、民謡とは当然ながら全く違う曲です。が、内容的には同じ権兵衛さん?
ごんべが、たねまく、パラパラ、からすが、あとから、ほじくる
ずんべらってどんな意味なんでしょう?
まずは、その舞台となる熊野古道、馬越峠(まごせとうげ)の写真です。
今回の旅行は全く土地勘がなく(旅行って大抵そんなものです)、伊勢神宮といっても125もの宮があり(有名なのは外宮と内宮ですが)、熊野古道といっても三重県和歌山県に広がっていて、2泊3日でどこをどう回るのがいいのか、なかなか難しかったのですが、1日めはまず伊勢神宮にお参りし、2日目伊勢市でレンタカーを借りて、南下していきました。世界遺産にもなっている馬越峠を少し歩きました。海山(みやま)の道の駅の近くに車を停めて、登っていきます。



きれいな石畳の道がずっと続いています。これは「夜泣き地蔵」。もともとは旅の安全を祈念していたが、いつしか子供の夜泣きを封じ込める信仰になったとか。大正時代までは石じゃなくてお地蔵さんがあったそうです。

石の一枚板。

もっとずっとこの道を行けば峠の頂上まで行けるのですが、何せこの日は西日本豪雨の日で、実際にはそんなに降られなかったのですが、天気予報ではいつ雨が降るかわからずこの辺りで引き返しました。
で、話は元に戻りますが、種まき権兵衛。
この海山地区の民話です。下記はウィキに出ている種まき権兵衛のお話です。
権兵衛は当地の武士の家に生まれたが、父の上村兵部の死後は武士の身分を捨て、父の望みであった農家となり荒地の開墾をはじめた。
しかしもともと武士であった権兵衛には何もかもが初めてのこと。慣れない手つきで見よう見まねの農作業は、種をまくそばからカラスに食べられてしまうほどで、近隣の農家の笑いものになっていた。
それでもあきらめず懸命に農業を続けた権兵衛は、やがて村一番の農家になっていたという。
権兵衛は狩猟の腕にも秀でており、その評判は紀州藩主・徳川宗直の耳に届くほど。宗直の前で見事3発の弾を標的に命中。宗直が褒美に田を与えようとしたところ、権兵衛はこれを辞退し、代わりに村人の年貢を免じてもらって村人から喜ばれた。
狩猟の腕に自信の権兵衛、馬越峠(まごせとうげ)に大蛇が出ると聞くと、大蛇を退治するべく猟銃を持って山に入った。
見事大蛇を仕留めたものの、彼自身も大蛇の毒液を浴びてしまい、村人の介抱もむなしく1736年(元文元年)12月26日に死去した。(ウィキペディアより)
お話に出てくる権兵衛が大蛇を退治したのが馬越峠というわけです。
この権兵衛さんは、ことわざにもなっています。
「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」 - (まいた種をカラスに食べられてしまうことから)努力が実らないこと、無駄なことの意。人が苦労してやったことを他の人がぶち壊してしまいせっかくの骨折りが無駄になること。
そして、民謡にもなっているのですが、民謡だけでなく黒人霊歌の替え歌にもなっている??
まずは民謡。お座敷ずんべら。
権兵衛が種まきゃ からすがほじくる
三度に一度は 追はずばなるまい
ずんべら すんべら ずんべら
こちらは藤原義江版。民謡ともまた違う趣です。美しいテノールのずんべらずんべら。
墨田男性合唱団のコーラスがこちら。これが黒人霊歌の替え歌だそうですが、民謡とは当然ながら全く違う曲です。が、内容的には同じ権兵衛さん?
ごんべが、たねまく、パラパラ、からすが、あとから、ほじくる
ずんべらってどんな意味なんでしょう?














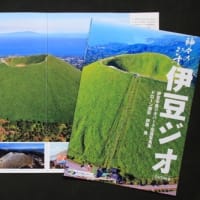






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます